◇六章 審判は満月の夜に(1)
◇六章 審判は満月の夜に(1)
フォルカー皇太子殿下が倒れたという凶報が宮殿を走ったのは、十三夜のこと。
アレクサンドラとの結婚式を翌月に控えた夜だった。



顔色も悪く手足も氷のように冷たい。身体がまともに動かず、とても起き上がれない状態です。原因は全く分かりませんが、今は絶対安静が必要です


宮廷医師の言葉によって、フォルカーの寝室には警備が敷かれ面会謝絶となった。
次期皇帝が突然原因不明の病に伏せったことは、宮殿だけではなく帝国中を不安にどよめかせた。



そんな……皇太子殿下がもう治らない病かも知れないだなんて





治らないどころかお命すら危ういそうよ





ああ、この国はどうなってしまうんだ!


不安と混乱が人々の間を駆け抜けた後、次に皆が口にするのは――罪深い憶測だった。



やっぱり皇太子さまは化け物にとり憑かれたのよ!





間違いない。今までお元気であられた皇太子さまが急に病に伏せるなんて、それ意外に考えられない





きっと寵姫は魔女か悪魔よ! 火炙りして命を絶てばきっと皇太子さまは助かるわ!


まだ世に悪魔や魔女が信じられ恐れられていた時代、それらを粛清しようという流れは当然で、リーゼロッテを処刑せよという声はあっという間に広まった。



わ……私は化け物じゃないし、皇太子さまに憑りついてなんかいません!


翌朝。リーゼロッテの部屋にやって来たのは近衛兵を引きつれた宮廷大臣だった。



お前が世にも恐ろしい化け物だと、民衆だけでなく神に仕える司教さまも言っておられる。言い訳は無用だ


大臣はリーゼロッテの反論も聞かず、近衛兵たちに彼女を捕らえ牢に閉じ込めるよう命令する。
そして鎧の男たちに捕まり悲しげにうなだれる少女の後ろ姿を見ながら、おおげさに身体を震わせた。



なんだ、あの髪の色は。肌だって真っ白で、まるで幽霊じゃないか


けれど、一瞬振り返ったリーゼロッテの顔を見ると動揺したように目を逸らし、



そ、その女にはフードを被せておけ。綺麗な顔をして人を惑わそうとするサキュバスかも知れん。髪も顔も見えないようにしておけ


と、兵士たちに命じた。
リーゼロッテは地下の牢獄に閉じ込められた。
カビ臭く薄暗い牢屋の中は、ずっと幽閉されていた地下室を思い出す。
冷たい石の床に座り込みながら、リーゼロッテは膝を抱えジッと運命の時が来るのを待った。



フォルカーさま、ご無事かしら……


牢に閉じ込められた己の身を案じるより、愛しいフォルカーの方が気掛かりでたまらない。
窓のない牢では今が昼か夜かも分からず、どれぐらいの時間が経ったかも分からなかった。
ディーダーは必ず助けると言っていたけれど、もしこのまま彼が来なかったらリーゼロッテは数日のうちに処刑になるだろう。
アレクサンドラの言った『化け物は火炙りにすればいい』の台詞が蘇り、リーゼロッテは身体をブルリと震わせる。
自分は本当に火炙りにならずに済むのだろうか。そして何より、フォルカーは無事なのだろうか。
暗く冷たい牢の中で、リーゼロッテは神に祈るような気持ちでひたすらに時が過ぎるのを待った。
けれど。
助けると約束したディーダーより早く、処刑の日はやって来た。
来月に結婚式を控えていたこともあって、一刻も早くリーゼロッテを処刑しフォルカーを回復させるべきだという声が国中からあがったのだ。
リーゼロッテが捕まってから、わずか三日後のことである。
異端尋問もされずいきなり処刑台に送られるなど前代未聞だが、それを後押ししたのは他でもないバルバラとアレクサンドラだった。



わたくしはあの娘と会ったことがありますけど、それはそれは恐ろしい娘でした。青白い肌と髪でまるで死神です。まちがいありません、皇太子に憑りついてるのはあの化け物です


大切な息子が奇病に伏せり、最愛の妻にそう助言されて、皇帝は頭からその話を信じてしまった。
フォルカーの見舞いと称してやってきたアレクサンドラも、婚約者が憑りつかれたことを嘆き悲しんで見せ、自らリーゼロッテの火刑に日を投げ込むことまで約束した。
そうして異例の速さで決まったリーゼロッテの処刑は、宮殿前の大広場にて日が沈む夕刻に行われることとなった。
目深にフードを被せられ、豪胆な兵士に縄で引っ張られながら、リーゼロッテは処刑場所まで歩かされた。



……ディーダーさま……どうして助けに来ないの……? フォルカーさまは一体どうなってしまったのかしら……


裸足で一歩一歩処刑場まで歩かされるたびに、リーゼロッテの胸は恐怖と不安で爆発しそうに高鳴る。
そうして処刑場である広場に姿を現したとき、彼女は嵐のような非難の声と目に曝され、全身を震わせながら足を竦ませた。
広場は入り切らないほどの人で埋め尽くされていた。街中、いや、国中からリーゼロッテを憎み皇太子の回復を願う人々が集まってきている。
広場の外にも入りきらなかった人々が声をあげ、ものすごい数の国民が集まっていることが分かった。
その全ての瞳がリーゼロッテを射ぬかんばかりに睨み、誰もが「化け物を殺せ」と叫んでいる。
あまりに強大な敵意に曝されて、リーゼロッテは心が壊れそうになるのを感じた。



何千……何万という人が私を化け物と罵って、私が死ぬことを願ってる……


たったひとりの少女に向けられたその恐怖は計り知れない。



どうして……どうしてディーダーさまは助けに来ないの? フォルカーさまは……?


絶望で目の前が真っ白になっていく。足が震えぬるい汗が背中を滑っていくと同時に、血の気が引いていく感覚がした。



……ああ、やっぱり私は忌み子なんだ。お父さまの言う通り、不吉で不幸をもたらす呪われた子。……生まれてきちゃいけない子だったんだ


忌み嫌われ続けてきた17年間が蘇り、リーゼロッテの瞼を熱く濡らした。
ディーダーに拾われ、救われたと思ったのは間違いだったのか。結局どこに行っても自分は忌まわしく死を願われる存在でしかないのか。
そんな悲しい思いが胸をいっぱいにし、涙がとめどなく流れた。
俯かせた顔からポトポトと涙を落とし、人々の怒号が渦巻く処刑場の中心まで足を進めたときだった。
リーゼロッテはふと、自分の足元に影が落ちていることに気付く。
見上げてみればいつのまにか空にはぽっかりと月が浮かび、優しい光を煌々と彼女に降り注いでいた。



……満月だ……


リーゼロッテは天を仰いで呟いた。
白銀に輝く月は神秘的で、まるでリーゼロッテとこの場に居る者を全て見守っているようだった。
その加護を受けて、リーゼロッテの胸が落ち着いていく。
耳から喧騒が遠ざかり、脳裏に蘇るのは月下でフォルカーと踊り幸せな時間を過ごした思い出だ。
目に溜まっていた涙の最後のひとしずくが、彼女の輪郭を滑って落ちていった。
月光に照らされたリーゼロッテの顔はもう絶望の色を浮かべてなどいない。



……間違いじゃない。こんな私でも、フォルカーさまは愛してくれた。私を抱き寄せ、撫でて、愛しいと言ってくれた





例えこのまま火炙りにされても、私はこの宮殿へ来て良かったと思う


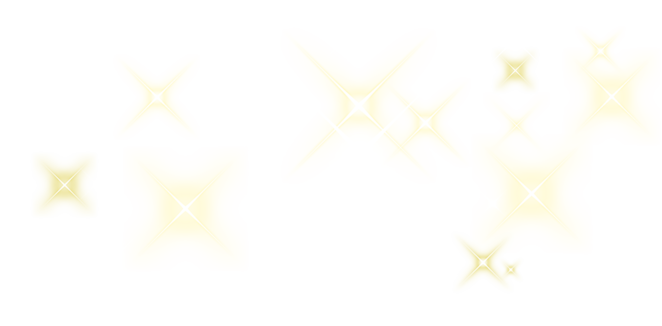



フォルカーさまと出会えて……恋を知れたから。私は生まれてきて良かったと思える


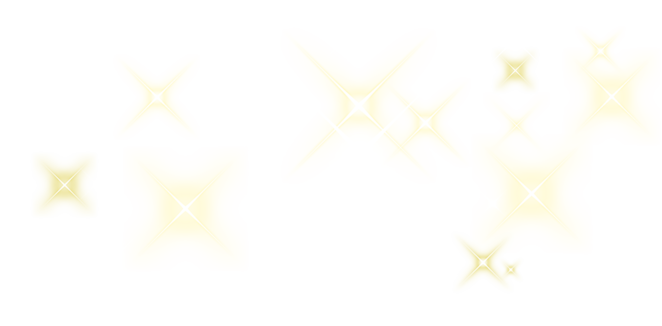
リーゼロッテは微笑んだ。なんの悔いもない心から満ち足りた笑顔で。
フードを目深に被っていたのでその表情は民衆からは見えなかったが、すぐ近くにいた兵士たちだけが気付いて、彼女に釘付けとなった。火炙りを前にして、こんなに美しい顔で微笑む人間がいるのかと――まるで、慈悲の神に対峙したように。
兵士たちが処刑の準備の手を止めてしまったことに、金切り声の叱咤が飛んだ。



何をやってるのです! 早くその女を十字架に縛り付けなさい!


驚いてリーゼロッテが声の方を見やると、処刑台が見下ろせる観覧席からアレクサンドラが身を乗り出して叫んでいた。
その隣にはバルバラとディードリヒ、それにアドルフもいる。
リーゼロッテに化け物のレッテルを貼ってここまで追い詰めたアレクサンドラとバルバラの姿を見つけ、再び身体中に悪寒が走った。
叱咤された兵士たちがハッと我を取り戻し、リーゼロッテを十字架に貼り付けようと準備を始める。
それを眺めて、アレクサンドラとバルバラは満足そうに口元を歪めて笑った。



なあ。どうしてあの女はフードを被ってるんだ? せっかくの化け物の顔が見られないじゃないか


皇族用の特設の観覧席に座りながら、アドルフはつまらなさそうに呟く。



おそろしいことを言うんじゃありません。化け物の顔を見たら呪いをかけられるのですよ。さっきの兵士たちを見たでしょう? きっと化け物が呪いをかけようとしたに違いないわ


大げさに恐ろしがって見せる母の言葉を「ふーん」と聞き流し、アドルフは席から身を乗り出してなんとか化け物の顔が見られないかと首を傾ける。



本当にあいつを処刑したら兄上の病は良くなるのか?


アドルフが今度は不思議そうに尋ねると、バルバラは口元を扇で隠しながら「そうねえ……」と呟いた。



皇太子殿下はもう私たちでさえ面会出来ないほど病状が進んでしまっているから、どうなるかは神さまのみが知ることでしょうね


処刑場に注目していたアドルフとディードリヒの目には映らなかった。バルバラがそう話しながらアレクサンドラと目配せをし合い、隠した口元を歪に微笑ませた姿が。



お、ついに張り付けられたぞ。いよいよだな


処刑場ではリーゼロッテの小柄な身体が鬱蒼とした十字架に縛り付けられ、その前に司教が進み出てきたところだった。



宮殿を陥れようとする化け物め。地獄に落ちるがいい!


そう言って司教は経典を開き悪魔祓いの呪文を唱え出した。そして十字架をリーゼロッテの前に突きつけながら、ニヤリと醜悪な笑いを浮かべて最後に呟く。



お前を宮殿に引き込んだディーダーも、見つかり次第すぐに地獄へ送ってやるからな





……見つかり次第? じゃあ今、ディーダーさまは今どこに……?


ディーダーが助けにこないのは、もしかしたら彼も捕まってしまったのではないか。そう思っていたリーゼロッテは疑問に思い顔を上げた。
――そのとき。
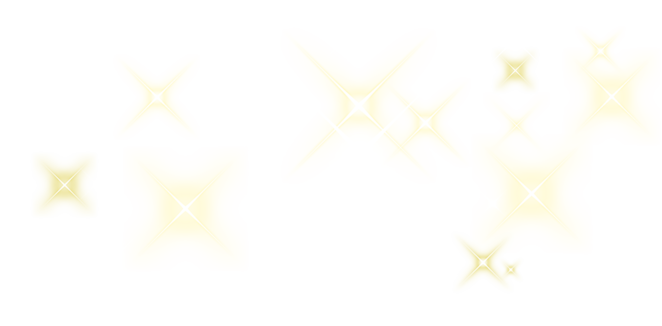
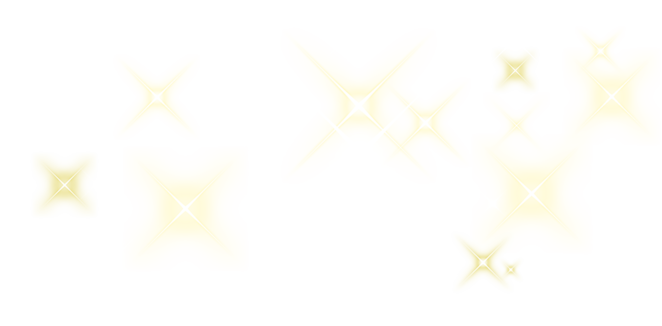
夜風が処刑台を吹きぬけ、リーゼロッテのフードをはためかせた。
フードが外れ、まるで月光が溢れたかのように彼女の白銀の髪がなびく。
その煌めく美しさに轟音のように怒声の飛び交っていた広場が一瞬で静まり返った。
そこにいた何千人という人間が、月下に輝くリーゼロッテに見惚れた。



……ニ、ニンフ?





化け物どころか……まるで女神さまじゃねえか……





なんて綺麗な少女なんだ……


惚けるような声が広場から上がりはじめたとき――。



ほーんと、こんな綺麗な子を捕まえて「化け物」は酷いですよねえ。わざわざフードまで被せて顔を見せないようにして。さすが宮殿一狡猾な皇后さま、計算高い


広場に響く声で飄々と言いながら処刑台に上がってきた者がいた。



……ディーダーさま!


フードを目深に被って姿を現した男はディーダーだった。呆気にとられる兵士たちの間を悠々と歩き、彼はリーゼロッテに近付こうとする。



ディーダーさま……! やっぱり助けに来てくれた!


けれど、司教は彼を睨みつけるとすぐさま兵士たちに命令を叫んだ。



何をしている! ディーダーは化け物を宮殿に引き入れた張本人だ! こいつもひっ捕らえろ!


司教に叱咤されディーダーをも捕らえようとした兵士たちだったが――。



黙れ、司教。ディーダーに手を出すことは俺が許さん。そしてリーゼロッテにもな


もうひとり、フードを目深に被った男が処刑台に上がってきて、場は大きくどよめいた。
なぜなら――彼が外套ごとフードを脱ぎ捨てるとその下からは、陽光のように黄金に輝く髪とこの国で誰もが敬うべく存在の凛々しい面立ちが現れたのだから。
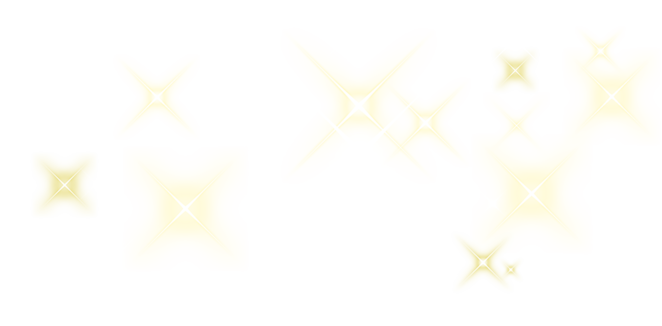



……フォルカー……さま……





すまない、遅くなったな。リーゼロッテ


約束を違えず守りに来てくれた最愛の人の姿に、リーゼロッテの瞳から真珠のような涙が零れて落ちた。
役者の揃った処刑台は、まるで戯曲に踊る舞台だ。
月はそんな彼らを照らしながら、空高く運命を見守っている――。
【つづく】
