◇第三章 禁じられた初恋(2)
◇第三章 禁じられた初恋(2)
フォルカーとリーゼロッテは市場の端から露店を見て回った。
紫色や橙色のビビットな色の青果も、見たこともない文字で綴られている革表紙の本も、華やかな柄がプリントされている更紗も、リーゼロッテの瞳に映る全てのものが新鮮で感動的だ。
フォルカーにとってはそこまで目新しい光景ではないが、リーゼロッテが好奇心に目を輝かせ、感嘆の溜息を吐き、驚きに頬を紅潮させる姿が楽しくて、頬が緩みっぱなしになってしまう。
コロコロと表情を変える彼女は愛らしく、見ていていつまでも飽きない。フォルカーは息抜きで時々身分を隠して街に出ることはあったけど、こんなに楽しい外出は今日が初めてだと思った。
けれど。



リーゼロッテ、欲しい物はないのか? なんでも買ってやるぞ。ほら、この首飾りなんかどうだ? 翠玉のついた靴もいいな


リーゼロッテを喜ばせたくてフォルカーは何か贈り物をしようとするが、彼女は曖昧にはにかんで首を横に振るだけだった。
ディーダーに「物を強請るな」と入れ知恵でもされているのだろうかと思い、フォルカーはわずかに眉根を寄せる。



俺は業突張りな者は嫌いだが、あまり遠慮をし過ぎる者も好きじゃない。お前らしく素直で自然なままでいてくれた方が嬉しい


そのように諌められてしまい、リーゼロッテは困ってしまってオロオロとする。



す、すみません。でも……





でも、なんだ?





綺麗なものも素敵なものも、自分のものにしたいとは思えないのです。こうしてフォルカーさまと一緒に眺めただけで充分、私の心は満たされましたから


リーゼロッテには所有欲というものがない。彼女はずっと何も持たずに生きてきたからだ。
地下に幽閉されていた頃、ささやかな楽しみだった夜の満月も、美しい虫の歌声も、決して彼女のものではなかった。
それでもリーゼロッテは美しい月光を浴びられたことに、虫の音色を楽しめたことに、心から感謝した。神様の娯楽を、ほんの一時分け与えてもらえたような気がして。
偽善ではなく純粋な気持ちで告げたリーゼロッテに、フォルカーは複雑な想いを抱く。
ここまで欲のない人間がいるのかと感動する気持ちもあるけれど、年頃の少女に相応しくない無欲さが哀れにも思える。
フォルカーはこの国で二番目に権力を手にしている男だ。彼が望めば手に入らないものなど、ほとんどないだろう。
男として力を誇示し愛しい女を飾り立ててやるのは、この時代身分のある者にとって当然の愛し方だった。
この愛しい少女に何かを与えてやりたい、いっそここにある全てを買い取って贈ってやりたい。フォルカーにそんな馬鹿げた衝動が湧いてくるのも仕方ないといえよう。
フォルカーはしばらく難しい表情を浮かべたあと、ふいに露店を見回すと一軒の花屋へと向かった。
そこで真っ白なマドンナリリーを一輪だけ購入すると、周りから見えないようリーゼロッテのフードに手を差し入れ、彼女の髪にそれをそっと差した。
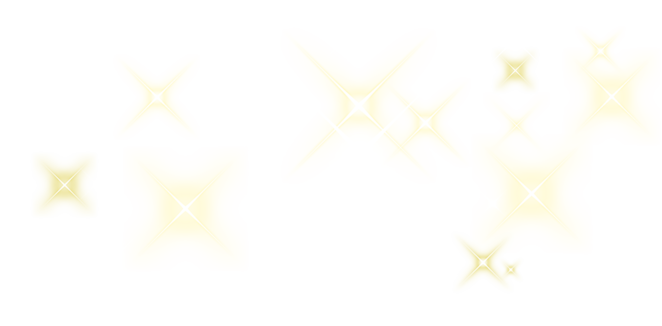

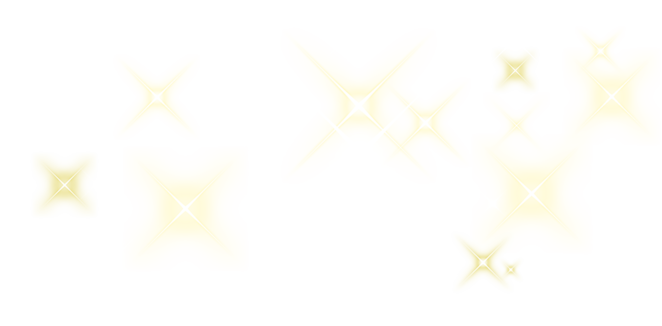



お前の無欲な想いは汲みたいと思う。けど、これだけは受けとってくれ。贈り物をして女性に気持ちを伝えるのは、男の喜びでもあるんだ


目深に被ったフードのせいでフォルカーにしか見えなかったけれど、純白のユリはプラチナ色のリーゼロッテの髪によく似合った。
その姿を見て満足そうに目を細めたフォルカーの笑顔に、リーゼロッテの鼓動が高鳴っていく。



……ありがとうございます、フォルカーさま。私、心の籠もった贈り物がこんなに嬉しいだなんて、初めて知りました。きっと一生忘れません


それは単に物をもらう嬉しさではなく、彼に愛されていると感じられた瞬間だったからだ。
恋という知識のないリーゼロッテには、この感情をどう表してどう彼に告げればいいか分からない。
けれど、琥珀の瞳に浮かぶのは恋慕の色で、抑え切れない想いは切なさと喜びを同居させた表情にありありと表れていた。
そしてそれはどんな言葉よりもフォルカーの胸を熱く満たすものだった。
少しだけ陽の沈みかけた海は、水面をキラキラと虹色に輝かせていた。
あまりの眩さにリーゼロッテは驚き、フードを目深にかぶり直す。
市場を巡り終えたフォルカーたちは今度は同じ街にある港へと来ていた。
海を初めて見るリーゼロッテには、地面が途切れ延々と見えなくなるまで水が広がっていく景色も、街に並ぶ店が幾つも入ってしまいそうな巨大な貨物船も、琥珀の瞳をゴシゴシ擦って見直してしまうほど衝撃だった。
大量の人と荷物を積み込む船は大きくて、首を真上に傾げるほど高いマストがそびえている。どうしてこんな大きなものが水に浮いているのか、リーゼロッテは不思議でたまらなかった。
初めて見る水平線はもっと不思議で、どれだけ遠くを見ても陸がないだなんて、まるで神さまに悪戯で騙されてる気さえする。



……こんな大きな乗り物、いったい誰が作ってここまで運んで浮かべたのかしら。あんなにどこまでも水ばかり広がって、いったいどこから湧いて出てるのかしら……


呆然としながら口にすれば、隣に並ぶフォルカーはクス、と小さく笑って優しく説いてくれた。



ここを北に20マイルほど昇ったところに造船所がある。船はそこで作った。沢山の投資家、設計士、工員たちの手によってな。そして川を下らせて港まで運ぶんだ。海の水がどこから湧いてるかは、まだ世界中の誰も解明していない。けれど、湧いてるのではなく降った雨が水を絶えさせないと考えるのが一般的らしいぞ





……はあー…………。すごい、フォルカーさまは物知りでいらっしゃるのね


自分が1年考えても出ないであろう疑問の答えを、あっさり出してくれたフォルカーにリーゼロッテは心から感服し尊敬する。
けれど、たとえ皇帝でなくとも普通に暮らしていれば常識として皆持ってる知識を感心されてしまい、フォルカーは苦笑いに顔をほころばせた。



お前にもっともっと色んなものを見せてやりたいな、リーゼロッテ。世界中を旅して、船に乗り馬に乗り、海も砂丘も山の峰も、すべて見せてやりたい





きっと楽しいだろうな。ふたりで色々な国を巡って、こんな風にお忍びで街へ出るんだ。北の国の毛皮を着て、東洋の音楽を聴き、南の島のダンスを踊るんだ。異国の言葉で喋り、原住民の料理を食べよう。ああ、考えただけでワクワクする


興奮気味に語るフォルカーを、リーゼロッテはうっとりと見つめた。
まるで少年のように瞳を輝かせ饒舌に喋る彼は、いつもの威厳ある皇太子とはまた別の顔だ。
そんなフォルカーの一面が見られたことが嬉しくて、リーゼロッテの胸にはまたひとつ甘いときめきが降り積もる。



フォルカーさま。私もフォルカーさまと一緒に旅が出来たら幸せだと思います。昼も夜もこうしてふたりで歩いて、ずっと一緒で、沢山のお話をするの。きっと、すごく幸せだと思います


頬を染めはにかむように言ったリーゼロッテに、フォルカーの胸もまた甘く疼いた。
けれど――そのときめきは、すぐさま胸をしめつける苦しさに変わる。



……フォルカーさま?


悲しげに眉根を寄せてしまったフォルカーの顔を覗きこみ、リーゼロッテは心配そうに小首を傾げた。



……今度、お前に異国の本を贈ろう。沢山の知識が載っている。きっと旅したような気分になれるぞ


フォルカーは無理矢理に口角を上げて笑うと、リーゼロッテにそう約束した。
リーゼロッテはそれに素直に喜び礼を述べたが、フォルカーの胸には自分を責める痛みがキリキリと走る。



一緒に世界を旅したいなどと、出来もしない夢を抱かせてしまった。……どうかしているな、俺は


リーゼロッテはただの『友達』だ。お忍びで近隣の街へ連れてくるぐらいは容易いが、当然一緒に世界を巡るなど出来るはずがない。
フォルカーが海外旅行をするには皇太子として公式に訪国しなくてはならないし、それに付き添えるのは家族と侍従たちだけだ。なんの身分も肩書きもない少女など連れて歩けるはずがない。



……公妾ならば、休暇中に別荘へ招くぐらいは……。いや、俺は何を考えているんだ


けれど一度描いてしまった夢は簡単には消せず、フォルカーの頭にはうっかりと意思に反した考えが浮かぶ。
そして小さくかぶりを振って頭の中を晴らしてから顔を上げると、明かりの灯った灯台を珍しそうに眺めているリーゼロッテを見つめた。



…………もしも俺が皇太子でなければ、彼女を正妃に娶ったのに


橙色の西日に目を眇めながら、フォルカーは切ない想いをひとり抱く。
皇太子として生まれ、時にそのプレッシャーに辟易したこともあったけれど、己の身分を嘆いたのは初めてだった。
何千万という民の上に立ちながらそんな願いを持つことは皇太子としての裏切りだと、フォルカーは自省する。
けれど、琥珀を閉じ込めた水晶の瞳に夕日を輝かせ、あどけない表情で灯台を眺めるリーゼロッテの姿に、フォルカーはどうしても芽生えた願望を摘むことが出来なかった。
【つづく】
