◇二章 秘密の逢瀬(2)
◇二章 秘密の逢瀬(2)



フォルカーさまが? 私に?


眠りから目覚めたリーゼロッテはゼルマから皇太子の言付けを聞き、驚きと戸惑いをあらわにした。
先日、初めて挨拶をしたと思ったらフォルカーはとても怒ってしまった。リーゼロッテはいまだに彼が何故あんなに怒ったのかが分からない。
ディーダーに聞いても「私の作戦ミスでした。あなたは悪くないですよ」と言うばかりで、理由を説明してもらえなかった。



ゼルマ、フォルカーさまはどうして私を庭へ呼び出したのかしら。それもディーダーさまに内緒でだなんて。もしかしたら私を厳しく叱責されるおつもりかしら


フォルカーを怒らせた自覚のあるリーゼロッテは、泣き出しそうな顔をしてゼルマを見上げる。
地下に居た頃、褒められることはなくても叱られて折檻された経験は何度もあるリーゼロッテは、そのときのことを思い出して震えた。
「もっと外で遊びたい」とわがままを言ったとき、ミルクをうっかり服に零してしまったとき、彼女を嫌っていた父はひどく罵って鞭で叩くときもあった。



私が悪い子だから、フォルカーさまはきっと怒ってらっしゃるのよ……鞭で叩かれるかも知れない


琥珀の瞳に不安をいっぱいに浮かべる少女を見て、ゼルマは母親のように優しい笑みを浮かべるとそっと頭を撫でた。



大丈夫ですよ。フォルカー殿下はそんな酷いことをなさるお方じゃありません。それに、殿下はリーゼロッテさまのことを怒ってなんかいらっしゃいませんよ。きっと、リーゼロッテさまともっと仲良くなりたいんだと思います





私と? 仲良く?


大きな瞳をパチパチッと瞬いた少女を見て、ゼルマは微笑んで頷いた。
眠っているリーゼロッテを愛しげに見つめ頬を染めていたフォルカーの姿を見ていれば、彼が何故リーゼロッテを呼び出したのかなんて答えは明白だった。



じゃあどうしてディーダーさまには内緒なのかしら


さらに不思議そうにリーゼロッテが尋ねると、ゼルマはクスリと小さく笑って人差し指を唇に当てて教えてくれた。



皇太子殿下は真面目で純情なお方なのです。だからディーダーさまに恋をからかわれるのが嫌なのですよ


と。
指定された時間になり、リーゼロッテはゼルマに身支度を整えてもらうと南側の庭園へと案内してもらった。
この宮殿の庭園は東西南北に分かれており、南側は『水の庭園』呼ばれている。羽ばたく白鳥の彫像がデザインされた大きな噴水が特徴だからだ。モッコウバラで出来た生垣の間を噴水から引かれた水路が走っており、いつでもサラサラと水の流れる音がする場所だ。
今日もみごとな月が空には浮かんでおり、庭を明るく照らし出してくれている。
噴水の前でリーゼロッテがソワソワと立っていると8時を知らせる鐘が鳴り、間もなくしてひとりの人影が静かにこちらへ歩いてきた。



フォ、フォルカーさま。ご、御機嫌うるわしゅう


緊張したリーゼロッテがたどたどしく挨拶をすると、フォルカーは頬をかすかに染めて柔らかに微笑んだ。



とつぜん呼び出して悪かったな。お前と少し話がしたかったが、ディーダーの邪魔が入ると面倒なんでな。ヤツにはまだたっぷりと公務を与えてあるからしばらくは探しにも来れまい


リーゼロッテの正面に立ってそう言うと、フォルカーは1時間後にリーゼロッテを迎えに来るようにとゼルマに申しつけ、人払いをした。
フォルカーとふたりきりになってしまったことで、リーゼロッテはますます緊張をする。そんな彼女を見てフォルカーは少しだけ困った表情を浮かべると、気まずそうに頭を掻きながら言った。



このあいだは、その……すまなかった。木偶人形などと酷いことを言って。ディーダーの過ぎたおせっかいについイライラしてしまってな。あの言葉は取り消すし、心から詫びたいと思う


フォルカーの話を聞いて、リーゼロッテは驚きのあまり大きな目をさらに大きく見開いてしまった。
ディーダーに与えられた知識に寄ればフォルカーはこの国で2番目に偉い人だ。そんな方が非礼を自分に詫びたのだ。
てっきりフォルカーに嫌われ、今日も叱責されるのではとビクビクしていたリーゼロッテは、安心すると共にひたすら驚いてしまってキョトンとするばかりだ。
リーゼロッテの反応にフォルカーもしばらくは戸惑っていたけれど、噴水の縁に腰掛けると彼女にも隣に座るよう促した。
そうしてしばらく隣り合って座ったまま、月空の下で水の流れる音だけを楽しんだ。やがて、リーゼロッテのようすが落ち着いてきた頃、フォルカーは静かに声を掛ける。



リーゼロッテ。お前の好きなものはなんだ?





す、好きなもの、ですか?


とつぜん聞かれたリーゼロッテは一生懸命に考える。そうして頭に浮かんだ幾つかのことをまとめてから、たどたどしく口を開いた。



ダンスとお月さまが好きです。ダンスは踊っていてとても気持ちいいし、お月さまはいつだって明るく照らしてくれるから





そうか。だから昨夜も踊っていたのだな


リーゼロッテの答えを聞いたフォルカーは目もとを和らげ、楽しそうに微笑む。
月明かりに照らされたその笑顔はとても優しく清廉に見えて、リーゼロッテは生まれて初めて異性の魅力というものに捕らえられた。



フォルカーさまは優しい笑顔をなさるのね。……もっと見ていたいな


そんなことを思いながらポーっと彼に魅入ってると、すっと手を差し伸べられた。



良かったら一曲踊ってはもらえないか? あいにく楽団はいないけれど、水の音を舞曲にしよう


まさかこんな所でダンスを申し込まれるとは思いもしなかったリーゼロッテだが、殿方にダンスに誘われたときの礼儀作法はしっかり教え込まれている。



よ、よろこんで


白く華奢な手をフォルカーの手の上に滑り込ませると、リーゼロッテは立ち上がってドレスの裾をつまみ一礼をした。
ディーダー以外の人と踊るのは初めてだったが、好きでたくさん練習した甲斐があって足はみごとに捌けた。
フォルカーは小柄なリーゼロッテの背を優しく支え、ナチュラルターンから鮮やかにコントラチェックの動きへと導く。
すぐ側で揺れるフォルカーの蜜色の髪を、リーゼロッテは麗しいと思った。自分をじっと見つめてくる端整な顔を、凛々しく優艶だと甘い気持ちで眺めた。
大きくてしなやかな手が優しくリードしてくれて、ヒンジラインのポーズをとれば逞しい腕が身体を支えてくれた。
練習に付き合ってくれたディーダーもダンスの腕前は相当だったが、フォルカーのスマートで逞しいリードはリーゼロッテの胸を疼かせた。
月光の下で好きなダンスをこんなに優雅に、それも麗しい皇太子と踊れて、リーゼロッテの顔には夢心地のような恍惚の表情が浮かぶ。
そしてそれは、フォルカーもまた同じであった。



リーゼロッテ……まるでニンフと踊っているみたいだ。俺はもっとお前が知りたい。聞かせておくれ、他に好きなものはなんだ? どうすればお前の笑顔が見られる?


フォルカーの胸に抱かれて踊りながら、リーゼロッテは頬を染めて答える。



歌うことも大好きです。まだ少ししか歌を知らないのですけども。あとは苺が好きです。このあいだディーダーさまが初めて苺の香りがするお茶を飲ませてくれて、すごく美味しかったから3杯もおかわりしてしまったの。ゼルマには笑われてしまったけれど





ははは、そうか。ならば明日、お前の部屋にたくさんの苺を届けさせよう。苺の紅茶も菓子もだ。それから歌の本も。たくさんの歌を覚えて、そのコマドリのような声で俺のために歌ってくれないか?





よろこんで! フォルカーさまはお優しいのね。私に歌を歌って欲しいなんて言ってくれた方は初めてだもの


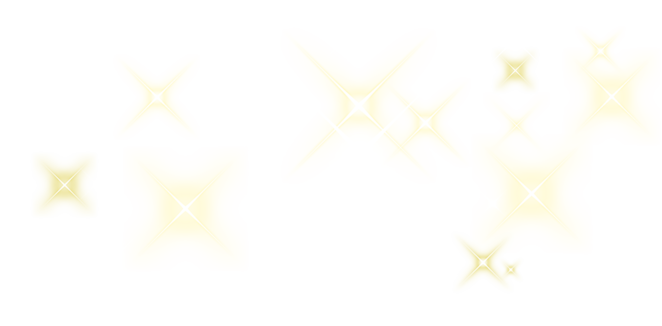
ふたりは優美なステップを踏みながら、互いを知りたくて言葉を交わす。
フォルカーはリーゼロッテの美しさだけでなく、驚くほど素直であどけない心にも惹かれていった。
宮殿で彼に艶めいた眼差しを送る女たちは、いかに自分を良く見せようかということに躍起になり、欺瞞に満ちている。
おべっかや下心の籠もった賞賛などもはや聞きたくもないと思っていたけれど、リーゼロッテが素直に褒めてくれた「優しい」という言葉は、フォルカーの胸を熱く震わせた。
今まで出会ってきたどの女よりも、いや、比べ物にならないほどリーゼロッテの何もかもが純真だと思った。



リーゼロッテ、明日も会ってくれないか? 同じ時間に、またこの場所で





はい! 明日もフォルカーさまにお会いできるなんて、とても嬉しいです。是非また一緒にダンスを踊ってください





ああ、約束しよう。明日もまた、この月下のダンスフロアで


ふたりは息が弾むまでダンスを踊ると、再び噴水の縁に座り休憩をした。そして9時の鐘が鳴るとフォルカーは、



また明日


と、リーゼロッテの指先にキスを残し、ゼルマが迎えに来るのを見届けてから庭園から去っていった。
颯爽と歩いていく後姿を見つめながら、リーゼロッテはいつまでも夢心地で立ち尽くした。
“呪われた子”と忌まれて育った17年間、こんな素晴らしい世界があるだなんて夢にも思わなかった。
誰かの美しさに、逞しさに、優しさに、胸がこんなに疼いてドキドキと苦しくなるだなんて。
もっとあの方に触れたい、話をして、もっともっと知りたいと甘い欲求が心に溢れ返る日が来るだなんて、誰も教えてくれなかった。
いつまでも熱に浮かされたようなこの状態が“恋”というもので、人生を最も輝かせる希望だということを知らないまま、リーゼロッテは恋に堕ちた。
無垢な少女から恋を知った乙女に変わろうとしているリーゼロッテを、月は今日も優しい光で儚く美しく照らし出している。
【つづく】
