◇二章 秘密の逢瀬(1)
◇二章 秘密の逢瀬(1)



うーん、どうやって仕切り直しましょうかねえ……


フォルカーにリーゼロッテを紹介する作戦が大失敗した次の日の夜。ディーダーはいつものように自室の長椅子に座り頭を悩ませていた。
テーブルを挟んだ向かいの椅子では、リーゼロッテが言われた通りにおとなしく本を読んでいる。
命令を素直に聞き、勤勉で一生懸命ディーダーの教えることを覚えようとするリーゼロッテの姿はなんとも健気だ。
ディーダーは主であるフォルカーはもちろんのこと、この哀れで美しい娘のこともなんとか幸せにしてやりたいと思う。
そのためにはやはりリーゼロッテがフォルカーに愛されるようになるのが一番なのだが……。ただでさえ公妾を拒んできた上に、馬鹿にされたと勘違いした皇太子の怒りは深刻だった。
何せ今日の政務中、フォルカーは一度たりともディーダーに声をかけることをしなかったのだから。侍従次長の彼が皇太子に無視されるなど前代未聞の事態である。
ただし、ディーダーの調子に乗りすぎる性格と、幼い頃からそんな教育係に振り回されている皇太子の関係を知っているものは、『ああ、またディーダーが何かやらかしたな』と察して口出しをしなかったけれど。



ディーダーさま、本を読み終わったのでテラスに出てもいいですか?


声を掛けられ、ディーダーは悩ませていた頭をハッと上げる。
だいぶ時間が経っていたようで、リーゼロッテは与えられた本を読み終えていた。
窓から見える月を横目で眺めソワソワとする彼女に、ディーダーは思わず笑みを零し



いいですよ、いってらっしゃい。ただし静かにね


と許可を出す。
リーゼロッテは元気よく返事をするとソファーから立ち上がり、テラスに繋がる窓へ向かっていった。
扉のように大きな窓をそうっと開けると、夜の匂いがする風が頬を撫でる。
まるでリーゼロッテのために用意されたスポットライトのようにキラキラと光を降らせる月を見上げながら、彼女は静かな足取りでテラスへと出た。
幾何学模様のタイルが敷き詰められたテラスはまるで小さなダンスフロアだ。リーゼロッテはディーダーに教わったワルツのステップでひとり、優雅に舞を舞い始めた。
リーゼロッテはダンスの練習が好きだった。音楽に合わせ身体を動かすことは楽しい。教えられたメヌエットもパスピエもフォルラーヌも、彼女はあっというまに覚えてしまった。
リーゼロッテはローブの裾をふわふわと揺らし、月明かりの下でしなやかに可憐に踊った。



月の妖精はみなもで踊る♪ それを真似して犬がドボン♪


ダンスにあわせて口ずさむのは、彼女が唯一知っている童謡だ。地下で暮らしていたとき、時々外で遊ぶ子供の歌声が聞こえてきて覚えたのだ。
歌も好きなリーゼロッテはそれを繰り返し繰り返し歌い、風に舞う花弁のように軽やかに踊る。
たったひとりのダンスフロア。見ているのは空に浮かぶ月だけ――のはずだった。



あの女は……


ディーダーの部屋を斜め下に見下ろせる西翼の四階。そこはフォルカー皇太子の寝室だった。
フォルカーは珍しくテラスへ夜風を浴びに出ていた。普段はあまりテラスへ出ることはないのだが、この夜は月明かりがあまりにも眩く、彼はいざなわれるように表へ出た。



月にこんなに惹かれるようになったのは――あの女のせいかも知れない


ディーダーのくだらない企みに憤慨していたフォルカーだが、気持ちとは裏腹にリーゼロッテの美しい姿があれから目に焼きついて離れなくなっていた。
まるで幻覚だったのではと思える儚い姿は、彼にあれが現実だったことをもう一度確かめたくさせる。
だからそんな想いを抱えた彼が、リーゼロッテのプラチナブロンドを思わせる月明かりに心惹かれテラスの出たのは不思議なことではなかった。
けれど、まさかその明かりの下で燦然たる少女を見つけたのは予想外だった。
フォルカーは、踊るには狭過ぎるテラスで器用にステップを踏みながら優美に舞う少女に釘付けになる。
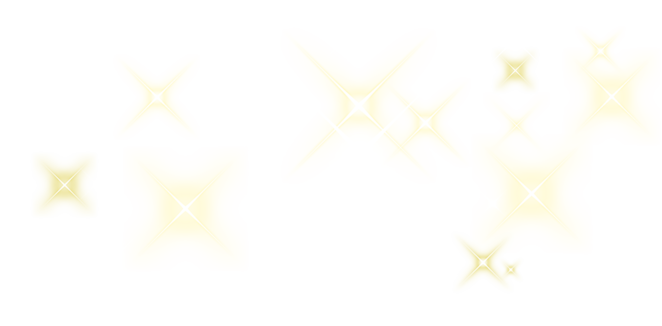



……ネズミもチウチウ真似してドボン♪ お月さまはひとりぼっち♪


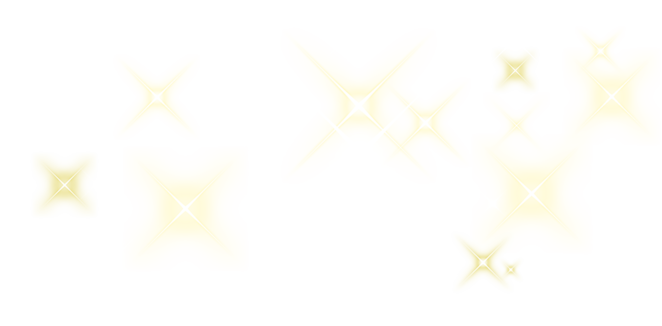
時々風に乗って流れてくる歌声が、ますます彼女を神秘的に魅せた。
華麗なダンスには似つかわしくない幼稚な童謡であるはずなのに、それがまるで永遠の少女である妖精を思わせる。
鈴の鳴るような声で楽しそうに歌いながら月明かりをプラチナの髪にキラキラと反射させて踊るリーゼロッテの姿にフォルカーはいつまでも見惚れ、彼女が踊り疲れ部屋に戻っていくと、知らず知らずに詰めていた息をホゥッと大きく吐き出した。
――翌日。
昼の政務の合間を見て、フォルカーは人目を忍びながらコッソリと宮廷の西翼に来ていた。
しかし向かうのは四階の自室ではない。二階にある侍従たちの部屋だ。
そこでフォルカーはコッソリと少女用のローブを運んでいたゼルマを見つけ、声を掛けた。



お前は確かディーダーの補佐をしている侍女だったな。聞きたいことがある。ディーダーの隠している少女は今どこにいる?





フォ、フォルカーさま……!


尋ねられてゼルマは困ってしまった。リーゼロッテのことはディーダーから固く口止めされているのだ。
けれど皇太子殿下の言うことを聞かない訳にはいかない。ゼルマは少し逡巡したけれど、フォルカーをディーダーの部屋へ連れていくと、使われていなかった衣裳部屋の鍵を開ける。
あまり広くはない部屋には本の詰まれた学習用の机と休憩用の長椅子、それにベッドが置かれ、リーゼロッテは小さな身体を丸めスヤスヤと寝床に収まっていた。
再びリーゼロッテを目にすることが出来て、フォルカーの心臓が心地好く跳ね上がる。
けれど、寝巻き姿で熟睡している彼女のようすに不思議そうに眉をしかめた。



何故この少女は寝ているんだ? まだ昼過ぎだぞ





リーゼロッテさまは日光に弱い体質なので、昼間はこうしてカーテンを閉めた部屋でお休みされ、月の登る夜になってから活動されるのです


ゼルマの説明に、フォルカーはまたひとつ衝撃を受けた。



本当にこの少女は不思議だ……。妖精でないのなら、神が間違えて地上に産み落とした月の申し子だとしか思えない


そんなことを思いながら、フォルカーは穏やかに眠る彼女の顔をジッと眺める。
煌めく琥珀の瞳は閉じられていたけれど長い睫毛が下瞼に影を落とし、起きているときよりも色香を感じた。
乱れのない寝息を繰り返す少女の姿はあどけない無防備さがたまらなく扇情的で、ネグリジェから出た白い肩やなめらかな鎖骨が呼吸に合わせて揺れるたび、フォルカーの中にはゾクゾクとした劣情が湧き上がった。
カーテンの隙間から差し込む細い光がリーゼロッテの髪に反射し、あの夜に触れた手触りを思い出させる。



――触れてみたい


ふと心に浮かんだ欲求は、夢うつつのようにフォルカーを従わせた。
壊れ物を扱うように手を伸ばし、フォルカーはそっと絹の手触りの髪に触れる。
スルスルとした感触に指先が心地好さを覚えずにはいられなかった。
何度かゆうるりと髪を梳くと、フォルカーはたまらなくなって今度は彼女の頬に触れてみる。



……柔らかい……


子供の肌のようなつるりとした手触り。けれど女性らしい柔らかさと瑞々しさも有しており、あまりの触り心地の良さに指先だけではなく掌全体で包んでみた。
くすぐったかったのか僅かに身じろぎしたものの、熟睡中のリーゼロッテは目覚めない。
けれどそのなまめかしい動きに劣情を煽られたフォルカーは、胸を高鳴らせながら今度は指先でそうっと唇を綴る。
しっとりとした吸いつくような水気。熟れ頃の果実のように健康的な弾力があり、フォルカーは夢中になって繰り返しその輪郭をなぞった。



……口付けたい……


初めて知る身体が熱くなるような衝動に、フォルカーは思わずゴクリと唾を飲みこんだ。
けれど、背後に控えるゼルマの存在を思い出しハッと我を取り戻す。
そして屈めていた姿勢を立ち上がらせ直すと、振り返りゼルマに告げた。



リーゼロッテに伝えてくれ。夜の8時、南の庭園に来いと。決してディーダーには言わず、お前が案内してくるように。頼んだぞ





は……はあ


それだけ言い残すとフォルカーはさっさと踵を返し大股で部屋から出ていった。
指先にはまだ柔らかな感触が残っており、それを掌に閉じ込めるように固く握りしめる。
その拳を、フォルカーは早鐘を打つ心臓に重ねるように当てた。芽生えた想いが何か、自分の心に問いかけるように。
【つづく】
