どれだけの時が経っただろうか……。
撫子をカフェで休ませたフェインリーヴは、それからも彼女を連れまわし、夕方になっても、柔らかなオレンジの世界に影が落ちても、その足が帰路を歩む事はなかった。
そして、馬に乗せられ連れて来られたのが……、王都から一時間ほど離れた場所に佇む、『ルナティアの森』。
普段、撫子が薬草採取で向かう小さな森とは違い、まだ立ち入った事もなかった未知の場所。
どれだけの時が経っただろうか……。
撫子をカフェで休ませたフェインリーヴは、それからも彼女を連れまわし、夕方になっても、柔らかなオレンジの世界に影が落ちても、その足が帰路を歩む事はなかった。
そして、馬に乗せられ連れて来られたのが……、王都から一時間ほど離れた場所に佇む、『ルナティアの森』。
普段、撫子が薬草採取で向かう小さな森とは違い、まだ立ち入った事もなかった未知の場所。



あ、あの……、お。お師匠様……。もう夜ですよ? こんな場所に何の用が。





もう少しの辛抱だ。恐れずについて来い。





は、はぁ……。


フェインリーヴの前を照らす魔術による淡い光。
それを頼りに迷いのない足取りで進むお師匠様の姿に、撫子は恐怖心を抱く事なく進めているのだが……。
案内なしに入ればすぐに迷ってしまいそうな森の深さは、初めて来た撫子でもわかるものだった。
夜という事もあり、景色の違いを見定める事も難しい。それに……、ここに連れて来たフェインリーヴの意図がわからず、若干……、戸惑ってもいる。



ここは……。





女子供が好みそうな場所だろう? まぁ、俺としては誰にも邪魔されずに話せる場所に来ただけなんだが……。


撫子の視界いっぱいに広がる淑やかな花の褥。
降り注ぐ月と星の光に抱かれたその場所は、確かに女性や子供が嬉々として好みそうな場所だ。
撫子も、幻想的な光景を前に自然と胸を高鳴らせてしまう。
だが、……花畑の中へと歩みだしたフェインリーヴの背中に、撫子は読み切れない哀愁のようなものを感じ取ってしまった。
ただ、弟子である自分を楽しませる為にこの場所に連れて来たわけではない気配。
本人も話があると口にした。



お師匠様……、何のお話、なんでしょうか。


また、癒義の巫女としての自分を否定されるのか。
凶獄の九尾を探す事を諦めろと諭すのか。
何度言われても返す答えは決まっているが、恐る恐る追い付いてきた撫子は、立ち止まったフェインリーヴが振り返ったその時に彼の胸へとぶつかってしまった。



撫子……、お前に頼みがある。断らずに、どうか受け入れてくれ。





お師匠様……?





凶獄の九尾……。お前の話では、巨大な狐の姿をした大妖という話だったな。人の世を蹂躙し、全てを喰らう者……。


その通りだ。凶獄の九尾は撫子の住んでいた当時の国を乱し、沢山の命を屠り踏み荒らした存在……。
フェインリーヴにもその話は何度かしているが、何故今ここでそんな確認をしてくる必要があるのだろう。



では……、この話は知っているか? 九尾が元々、――癒義の巫女を守る為に、狂った存在だと。





え……?





皮肉な話だが、あの劇と似たようなものだ。後の世で癒義の巫女と呼ばれるようになった娘を守る為、九尾は強大な力を持つ妖とその眷属を喰らい、……その負荷に耐え切れず、自身が災いの象徴となり果てた。





な、なに言ってるんですか……。伝承には、そんな事、なにも。





人間側からすれば、九尾の事情など知る由もなかったんだろう……。初代癒義の巫女も、それを知っていたかどうかはわからん。たとえ九尾の事情を承知していたとしても、後世に正しく伝わる可能性は低い。


遥か昔……、確かに九尾は世を荒らす妖として生きていた。人の命など何とも思わない冷酷非道な悪。
その悪行に偽りはなかったが、一人の娘の手によって九尾は情を得た。いや、取り戻した、というべきか。術師として能力の高い娘、後の世で癒義の巫女と呼ばれるようになった人物と想いを交し合うようになった九尾は、初めて幸福というものを手に入れた。



どんなに世界の在り方が違おうと、心を抱く命である限り、他者へ抱く情は当たり前に芽生える本能と言っていいだろう……。九尾もまた、誰かを特別に想う事で、目を覚ました。





ちょ、ちょっと待ってくださいっ。な、なんで、お師匠様がそんな事を知っているんですかっ。





あの小さな狐の妖、あぁ、名をタマというそうだが、タマに洗いざらい吐かせた。雑魚ではあるが、昔から九尾の傍で可愛がられていたようでな。


九尾の愛玩動物的扱いを受けていたというわけか……。無慈悲に命を奪う大妖のくせに、変なところで気まぐれな存在だ、九尾。
撫子はそんな感想を抱きつつも、自分の宿敵である存在が癒義の巫女を守る為に狂ったという経緯を前に、どう受け止めて良いものかと迷う。
真実だという証がどこにある?
タマが撫子達の心を揺さぶる為に吐いた嘘かもしれない。そう言えば、対峙する際に有利になると、そう考えているのかもしれないではないか。
けれど、そう疑ってしまう撫子に、フェインリーヴはその両肩を掴み、こう言った。



嘘じゃない。俺の調合した自白剤の成果だからな……。だが、問題はそこじゃない。





ま、まだ何かあるんですか?





撫子……、もうお前が九尾を追う必要も、責任を担う必要も、ない。


背を屈めて撫子の頭を撫でたフェインリーヴが、目線を合わせながら静かに言葉を紡ぐ。



凶獄の九尾は……、妖などではない。結果的には多くの妖を喰らい、それとなった存在ではあるが、元々は、――この世界の魔族だ。





ま、魔族……? あの九尾が? どうして別世界の存在が……っ。大体、どうしてそんな事がわかるんですかっ。タマが言っていたんですか?





話を聞いている内に色々出てきた情報から、この可能性が成り立っただけの話だ。それに……、九尾が狂う前の姿に関する特徴に、覚えがあったからな。





……。


どこまであの小さな妖の言っていた事を信じられるのか……。
フェインリーヴの自白薬がどこまで効いていたのか、腕の良い薬学術師である事はわかっているが、それでも、撫子には受け入れ難い事実ばかりが紡がれてゆく。
九尾が本来はこの異世界の魔族?
だから、撫子や向こうの世界の住人達に討伐の責任はない?
はい、そうですか。……なんて、馬鹿正直に受け取る事が出来る程、撫子は考えなしではない。
癒義の巫女という立場を背負い続けてきた者の誇りと責任故か、撫子は手のひらをきつく握り締めて反論に出た。



お師匠様のお言葉を疑うわけじゃないですけど、それが事実だという証はどこにもありません。九尾があのタマに仕掛けた罠だったとしたら……。





信じられないお前の気持ちはわかるつもりだ。……だが、それでもこれは事実だ。念の為、タマの記憶も読んでおいたからな。何か細工をされていれば、俺にはすぐわかる。





で、でもっ!!





事実だ!! 凶獄の九尾はこの世界の元魔族であり、遥か昔にお前の世界へと飛ばされた者!!





――っ。だ、だから……、もう、諦めろ、って、そう言うんですか?


あんな恐ろしい化け物をこの世界に放置して、手ぶらで帰れと……。
今は身を潜めていても、いつこの世界の者達に牙を剥くかわからない九尾。
たとえ、初代の巫女と愛し合った存在でも、彼女を守る為に狂った犠牲者だとしても……、自分は。
それに、異世界であった事を話したとしても、きっと一族の者や民は信じてはくれないだろう。
討伐した躯の一部か、封じた証となるような地でも示さねば、当代の癒義の巫女は責務を果たさず、おめおめと逃げ帰ってきた、と……、そう断じられてしまう。



私がどう思われるかなんてどうでもいい……。だけど、私が責務を果たせなければ、癒義の巫女を筆頭に栄えている一族が、帝や権力者達からの信頼を失ってしまう。


いや、あの時、九尾と共に消えてしまった事自体が、向こうの世界でどう扱われ、思われているのか……。姉や家族の者達は帝に咎を責められてはいないだろうか? 撫子の心はそればかりを常に胸の奥で心配している。



お師匠様……。





責任が、こちらに返ってきただけの話だ……。あとはこの世界の者で始末をつける。だから、撫子……、もう普通の娘に戻れ。自分の幸せを、見つけるんだ。





私は……、本家に引き取られてから、癒義の巫女としての在り方を義務付けられてきました。凶獄の九尾が目覚めた万が一の時、彼(か)の存在を封じる事が出来るように……、いざとなれば、贄として、皆を守れるように。


震える細い手で自分の後ろ髪から何かを外した撫子が、それをフェインリーヴの目に映るように差し出した。向こうの世界で、桜と呼ばれる木の花びらが集まった姿をイメージした、宝玉付きの簪。
それは、代々の癒義の巫女が受け継ぐ、初代の形見。



これは……。





初代様の形見です。万が一、九尾にその力が及ばない時は、これに封じられた初代の力を解き放つようにと、そう言い伝えられています。


可愛らしい桃色の装飾が施された簪の中心に嵌め込まれている青い石を、フェインリーヴがそっと指先でなぞってくる。
何かを思い出しているかのように、懐かしんでいるような気配が伝わってくるのは何故なのだろうか。



九尾は……、幸せだったのかもしれないな。





お師匠様?





この簪に嵌め込まれている宝玉は、魔族達の間では、『幸福』を象徴する石と呼ばれている。おそらく……、九尾が初代の巫女に授け、それを加工して作った物なんだろう。


そう小さく呟くと、フェインリーヴは自分の左側の髪をよけ、耳にしている青色のイヤリングを見せた。
簪に嵌め込まれているそれと、同じ輝きの石……。



魔族達は、自身の愛しい者……、つまり、伴侶となる者へ渡す物として扱っている。どこにでも売られているわけではなく、魔族が自分の力を集めて創り出す、命と願いが込められた石。





命……?





言葉通り、その魔族の命の一部が魔力と共に注ぎ込まれ、かなりの守護力を発揮する。唯一人……、愛を捧げた存在だけが、それを使う事が出来る。


――そして、自身を殺す刃でもある、と、フェインリーヴが語ったその時、撫子は悟った。
凶悪な大妖……、数多の妖を取り込んだ九尾を、初代の巫女が封じる事が出来たのは。



その簪を使った、から……、封じる事が出来た、という事なんですね。





そうだ……。殺す事も出来たのだろうが、その魔族が初代の巫女に使い方を教えていたかはわからん。だが、巫女の強い想いに簪の宝玉が応え、九尾を封じる事が出来たのは確かな事だろうな。





この簪に、まだ力は残っているんですか?


初めて簪を受け取ったあの日、撫子が感じたのは強大な力でもなんでもなく、心が落ち着くような優しいぬくもりだけだった。
修行を積んで触れてみても、ただの簪にしか思えず……、九尾の一部とは到底思えなかったのに。



この簪に残っているのは……、巫女と九尾の愛だけだ。力を失っても、互いに想い合った証だけは消えず、形となってお前達に受け継がれた。





そんな……。じゃ、じゃあ、九尾と戦っても、この簪は……。





役に立つかと問われれば……、微妙なところだな。唯一人と愛し合った記憶の証、狂った九尾の目を覚まさせるには有効かもしれないが……。


代々の癒義の巫女達は、万が一の時に備えて、決してこの簪を手放す事はなかった。
だが、フェインリーヴの話が本当であれば、これはただの簪……。あまりあてには出来ない代物というわけか。
けれど、……この簪をそれでも手放したくないと思ってしまうのは、初代の巫女と九尾の想い合った証が何かを訴えかけてくるからなのか……。
簪をぎゅっと胸に抱き締めた撫子は、劇場で感じた悲恋の二人を見た時と同じ切なさを胸に抱いた。
一族の今や未来を心配する気持ちはまだ胸の中にある。何を知っても、九尾が敵である事は間違いなく……、倒すか封じるか、その二つしかない事も。



恐らく……、この世界に戻ってきた時の衝撃か何かで、九尾は自我を取り戻しているかもしれない。お前に伝言を届けに来たタマが言っていただろう? 元の世界に戻るか、自分の事を忘れてこの世界で生きるか、と。狂っている者がそんな選択肢を示すわけがない……。





じゃ、じゃあ、九尾は、元の正常な状態に戻っているという事なんですか?





どうだろうな……。一時的なものなのか、身の内の妖達を御する事が出来るようになったのか……、もしくは。


狂気の衝動と闘いながら自我を保っているか。
フェインリーヴは冷静にそう分析した。
もし正気に戻っているのであれば、ほっとするべきなのだろう。初代の巫女が願っていただろう、彼の無事を。けれど、それは同時に撫子の役目や立場の存在意義が全て崩壊する事を意味している。
いずれにせよ、一度九尾に会わなくては。
そう懇願してくる撫子に、フェインリーヴは緩やかに首を振ってみせる。



やめておけ。万が一、身の内の狂気に取り込まれている状態の九尾と出会えば、お前程度の術師は一瞬で命を落とす。





でもっ、会わなきゃいけないんです!! 諦めるにしろ、戦うにしろ、私にはけじめが必要なんです!!


もしも、九尾が自我を取り戻し、贖罪の為に生きるというのであれば、元の世界に戻る方法を探しながら、一族が不利な立場に追い込まれないように上手い言い訳や誤魔化す手段を考えるつもりだ。
それに、……両手の中にある簪が、恋しい人に会いたいと、泣いているように思えるから。



撫子……。まったく、……仕方のない弟子だな。お前程俺を困らせてくれる存在はそういないぞ? ……アイツ以外には。


ふぅ、……と疲労感たっぷりの溜息を零したフェインリーヴに簪を奪われ、撫子は後ろにまわったお師匠様に優しく頭を撫でられる。
ボソリと何かを小さく呟いたような気もするが、それは形にならず撫子の耳を擽っただけだった。



仕方ないから許してやる。だが、一人では行くなよ。必ず保護者同伴だ。





あの……、お師匠様。





なんだ?





九尾との事を許してくださったのは有難いんですが……、あの。さっき、魔族の人達が簪に嵌め込まれている石を作れるって、そう言ってましたよね。





ああ……。魔族だけが作る事の出来る石だ。かなりのレア品だぞ。


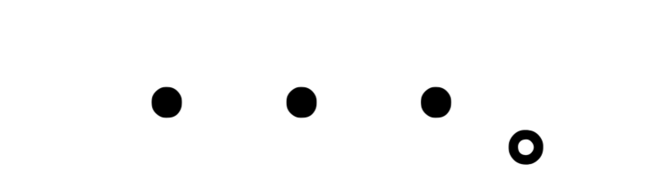



それってつまり……、お師匠様も魔族って事なんじゃ……。





……あ。


撫子からの当然の指摘に、背後でフェインリーヴが間抜けな声を出して固まった。
気まずい沈黙がずしんと落ちてくる。



……魔族なんです、よね? お師匠様。





あ~……、え~と……。


くるりと顔だけを振り向かせた撫子に、フェインリーヴは視線を宙に彷徨わせて口ごもる。
いや、もしかしたら……、魔族ではなく、魔族の女性からその装飾品として加工された石を貰った立場なのかもしれない。
そう思い当たると、撫子は何故だかまた……、チクリと不快な痛みを胸に覚えた。



逆ですか? 魔族の恋人がいらして、それで……。





そんなもんおらんわ!!!!!





えぇ……。じゃ、じゃあ、恋人とか、じゃなくて、奥さん、とか、ですか? 一度弟子としてご挨拶した方が良いですか?






ど・く・し・ん、だ!!





本当に……?





だあああああっ!! この馬鹿弟子がぁあああっ!! 勝手に人を所帯持ちにするんじゃない!! 大体、この石はちゃんと自家製だ!!





……。


あれ? という事は、やっぱり……。
問題点が最初のところへと戻り、ぜぇぜぇと息を切らすフェインリーヴの目が、はっと我に返った。
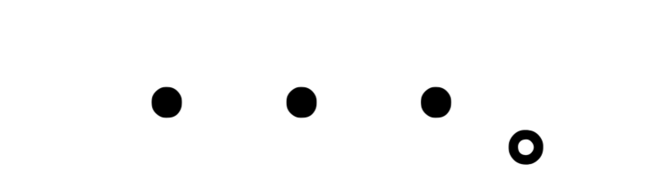



別に隠さなくても良いんじゃないですか?





か、隠していたわけじゃない……。余計な騒動を起こさないように気をつけているだけだ。





お師匠様、そこまで動揺しなくても……。別に、私は気にしませんよ? 妖の類みたいな異形を見慣れてますし。


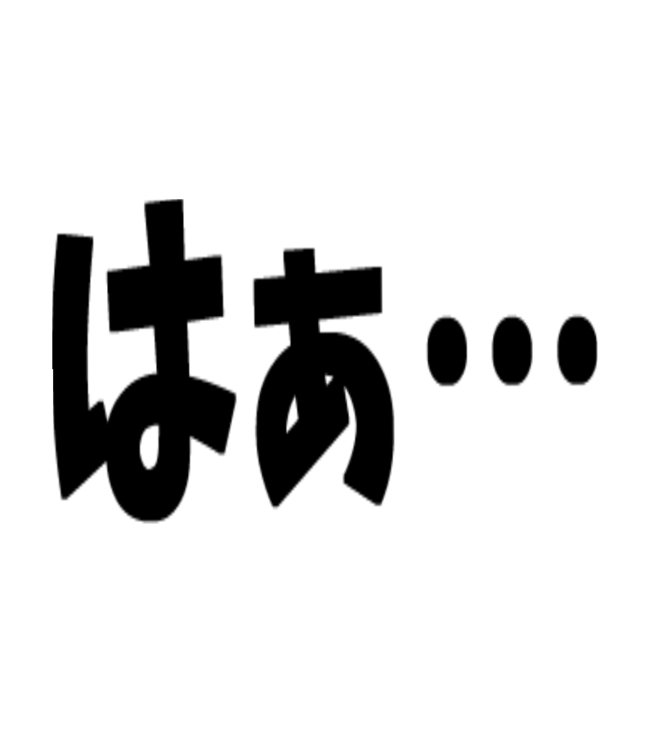



俺達魔族と妖や魔物を同列に扱うな……。うぅっ。





ご、ごめんなさい……。


けれど、……フェインリーヴが魔族であった事よりも、特定の相手がいない事に安堵を教えてしまった撫子は、何故かトクトクと忙しくなった鼓動に疑問を感じながらも、小さな笑いを零した。
どんな種族でも、フェインリーヴが自分の保護者であり、頼れる存在であるお師匠様である事に変わりはない。だから、正体がバレてしまった事でぷるぷると打ち震えまくっているお師匠様を観察しながらニッコリと微笑む。



でも、魔族ってお師匠様が初めてですけど、意外に人と変わらないものなんですね~。王宮の図書館で見た資料には、怖い事がいっぱい書いてあったんですけど。


それに、千年ほど前には人間の世界に侵攻までしてきた種族だ。今は比較的友好関係にあると書かれてあったが、フェインリーヴを見る限り……、どうにも警戒心というものが湧き起こらない。
そんな弟子の言葉に眉根を寄せたフェインリーヴは、また残念極まりない溜息を落とす。



一応言っとくが、どの種族も悪い奴ってのはいるんだぞ? 俺だって、本気で怒れば人間の害となる事もある。





全然想像出来ませんねぇ……。あ、でも、怒った時のお師匠様は確かにちょっと怖いです。昼間の女の子達を追い払う物言いも怖かったですし。





……気を付ける。


ようやく簪を着け終わったのか、フェインリーヴは困惑顔で頬をほんのりと薄桃色に染め、彼女の手に温もりを伸ばした。
そろそろ帰ろう、優しい、あったかな……、お師匠様の低い声。
撫子はそれに頷くと、長い一日の終わりを感じたのだった。
