この日は九時に駅前に待ち合わせる予定だ。確か寝坊して遅刻ギリギリで自転車を飛ばしていったから、八時五〇分頃に家を出ただろうか。約束の時間には間に合ったから少しくらい早く出てもいいかもしれない。
この日は九時に駅前に待ち合わせる予定だ。確か寝坊して遅刻ギリギリで自転車を飛ばしていったから、八時五〇分頃に家を出ただろうか。約束の時間には間に合ったから少しくらい早く出てもいいかもしれない。
僕は遅刻どころか早すぎるくらいの時間に目を覚まし、部屋の中で机に向かっていた。あの日記帳に今日の予定を書き記すためだ。



今日は四人でプールに行って、それから


僕は、この世界での僕は初めて彼女に出会う。そうだ、秋彦の計画はこの時から始まっていたのだ。プールで秋彦と松原さんが二人きりになれば、当然僕と彼女は二人で取り残されることになる。あいつの狙いは始めからこっちのことだったのだ。
今更気付いたところでどうしようもない。僕は前に経験したことをそのまま再現することしか許されていない。でももしも因果律を傷つけないでいられるなら、まだ結果の決まっていない未来をつくれるのだとしたら、僕は、僕はどうすればいいのだろうか。
以前の僕がそうしたようにプールに行く準備を整えて、僕は愛用の自転車にまたがった。時間には余裕がある。下手に飛ばしていく必要もない。水着も新品を買ってきた。恥ずかしさを堪えて店員さんに相談して決めた一品だった。
駅の自転車置き場で人目につかないように時間を潰し、約束の九時一分前に走りこむように駅前で待っていた秋彦たちの元に駆け寄る。



悪い。でもギリギリセーフだよな?





ちょうど九時。確かにセーフだ


秋彦がスマートフォンの画面を見ながら言った。僕にだけ見えるようにほっとした表情で息を吐く。



間に合ってよかったよ。あ、初めましてだね? 松原春香です。今日はお誘いありがとう


ピンク色のワンピース姿の松原さんが控えめに僕にお辞儀をした。それだけ言うと、また一歩下がって僕らから距離を置く。松原さんはたった二クラスしかない僕らの学年でも知らないくらいに目立たない人だった。引っ込み思案でとにかく目立つことが苦手でいつも顔を隠すように教科書を読んでいる娘だと秋彦に聞いてようやく思い出したほどだった。
今も両手で口元を隠して周囲の視線を気にするようにそわそわしている。隣のクラスでも長い間浮いた存在だったらしい。



間に合ったらそれでいいということはありませんわ。常に余裕を持った行動こそ優雅に立ち振る舞う秘訣なのですから





なんだよ、いきなり





あ、あの今日一緒にプールに行ってくれるお友達の美冬ちゃんです





さぁ、計画はすでにギリギリです。自己紹介は後ほどしますわ


美冬はそう言って僕たちを急かしながら改札の方に歩いていく。松原さんは頬を掻きながらゴメンね、と小さく言った。その言葉を聞いて僕たちも美冬の後をついていく。
楠美冬(くすのきみふゆ)は、一言で言うなら高慢なお嬢様かぶれだ。やたらと丁寧な語調と人間離れした透明感のせいで僕はこうして出会うまでどこかのお嬢様だと勝手に誤解していた。僕はこの後知ることになるのだが、美冬はなんでもないうちの学校の近くにある高層マンションの一室に住んでいる普通の女の子だ。
性格の方はマンガから出てきたようなお嬢様ぶりそのままで、わがままかつ世界が自分の思うとおりに動いていると思っているような奴だ。そう思っていた。
見えない糸に引かれるように美冬を先頭に僕たちは連なってレジャーシーズンの電車に乗り込んだ。目的地が同じと思われる家族連れや学生の集団も見える。



それでいつも一人でいる春香が可哀想で、私がお友達になってさしあげたのです





なってやった、って


僕は心苦しくなりながら、美冬の自慢話のような松原さんと知り合った経緯にケチをつけた。まるで優秀な自分が報われない少女を救ってあげたような壮大な話。それを僕は尾鰭を付け過ぎだと不平を漏らしたのだ。



何か言いたいことがおありですか?





なんでもないよ


美冬の鋭い視線に僕は気にも留めない風を装って片手を払う。それ以上美冬は何も言わなかった。
レジャープールは当然の超満員で水面が見えなくなるほどの人が浮かんだり泳いだりしているのが見える。プールサイドも貸し出しのベンチやブルーシートを広げているせいで地域最大級などと広告を掲げているところなのにまっすぐ歩けそうもない。



適当に広そうな場所探すしかないか


貴重品はロッカーに預けてきたし、四人分遊ぶスペースがあればそれでいい。とはいえこの状況ではかなり強欲な願いかもしれないけど。
施設の中心にある大きな丸型のプールに向かおうとして、誰かが、いや振り向かなくてもわかる、美冬が僕の手首を掴んで引き留めた。



な、なんだよ?


胸元にレースがあしらわれた水色のビキニ。凹凸がはっきりとした美冬の体はきっと自分が目指す理想を体現するために努力を重ねた結果だ。以前の僕は気にしていなかったけど、今は美冬の胸の膨らみに視線を外そうとすればするほど、そこに吸い込まれていく。



プールに来たらまずは準備運動から。ケガしても私は助けてあげませんわよ





はいはい


思わず顔を背けると、その先で秋彦がにやにやと笑って僕を見ている。そんな顔をしていると僕に計画がバレてしまうぞ。既に僕は知っていることだけれど。
美冬の長い準備運動に付き合い、四人で水の中に飛び込んだ。適温に保たれた水が体を包む。消毒剤の塩素の匂いが鼻先をくすぐった。



うりゃ!





やめろ! 飛びつくな、秋彦


肩に巻きつくように飛びかかった秋彦が僕を巻き添えにするようにいっしょにプールの底へと沈み込む。逃げるように水面に這い出すと、松原さんと美冬が大笑いで迎えてくれた。周りから見ればまさしく青春している学生の一ページ。さらにあわよくばダブルデートにも見えなくないか。
海の家ほどの趣はないが、砂も飛ばないプールサイドのフードコートで昼食をとり、丸テーブルを囲む。美冬はさも当然のように僕の隣に座り、こちらの顔を窺っていた。



それじゃ、そろそろ行くか


ここぞとばかりに僕は立ち上がり、右手を掲げて指差した。



え、行くのか。あれに?


僕の言葉に秋彦が嫌そうな声で答えた。僕の指差した方角にはこのレジャープール一番の目玉、日本最速(自称)のウォータースライダーがある。あまりに速すぎるので安全のため小さなゴムボートに乗って滑るタイプのものだ。僕自身久しぶりに乗りたいという気持ちもあったけど、それ以上にこの提案は秋彦から頼まれたものだった。



当然だろ。何しに来たって言うんだよ





プールで泳ぎに来たんだけど





なんだよ、まだ高いところ苦手なのか?


渋るように顔を歪める秋彦に僕は怪訝そうに聞き返した。もちろん秋彦は高いところなんて怖くもない。ただ松原さんの方は絶叫マシーンみたいなのがまったくダメらしいのだ。



あ、あの、皆行ってきてもいいよ。私は下で待ってるから





お、俺も遠慮する。春香ちゃん一人にするわけにもいかないし


後は僕が美冬を連れて行けば、二人きりの空間は発生するというわけだ。多少強引だが、今日プールに来た目的は表向きでは秋彦と松原さんをくっつける足がかりにすること。僕の役目はその手助けだ。



何だよ。楠は来るよな?





え、私ですか?





まさか高いところ苦手とか言わないよな?


体を跳ね上げた美冬に畳み掛けるように煽る。プライドの高い美冬はこの一言に応じるしかない。



もちろんですっ! あなたこそ階段を上りきってから、やっぱりやめよう、なんて言わないことですわね


いってらっしゃい、と秋彦と松原さんに見送られて、僕は美冬を連れてウォータースライダーに続く階段へと向かった。
長い長い階段には一番人気のアトラクションということもあって人の列が延々と続いていた。その最後尾にはただいま一〇分待ち、という看板があがっている。夏休み中ということを考えればこれでもラッキーな方だろう。



あなたはこういうの平気ですの?


落ち着かないように手を擦りながら美冬は不安そうに僕に問いかけた。



あぁ、俺は平気だけど。もしかして怖い?





い、いえ、そんなことあるはずないじゃありませんか!


顔を真っ赤にして反論した美冬に思わず僕は可愛いと思ってしまう。今はまだ、今の僕は美冬のことを嫌いでいなくちゃいけない。高慢で人を小馬鹿にしたような鼻持ちならない奴だと。
一段、また一段と階段を上がるたび、下のプールで遊んでいる人が小さくなっていく。もう秋彦がどこにいるのかもわからない。ウォータースライダーの水流の音と先を行く誰かの悲鳴が一定の間隔で聞こえてくる。
美冬はだんだんと順番が近付いて怖くなってきたのか、時々肩を擦りながら、僕の横顔をチラリと時々盗み見ていた。僕は知っている。美冬は怖いものは苦手なのだ。それを無理やりこうしてついてきている。



それでは次のお客様


最前列に並んでいた僕が呼ばれる。係員が抑えているゴムボートの端から激流が飛沫を上げて流れ落ちていた。



あ、はーい


滑り止めが利いたザラザラのタイルを進もうとした時、僕の後ろから大きな声が上がった。



ふ、二人です。二人乗りで!


美冬だった。僕はこうなることがわかっていたのに、普段からは想像できない動転して裏返った声で叫んだ美冬に振り返る。真っ赤な顔を隠すように美冬は俯いていた。



あ、カップルの方でしたか。失礼しました


水流からゴムボートが上げられ、二人乗りの一回り大きいものに変わる。子供の頃に来たときはこれに乗って父さんと何度も滑ったっけ。
僕が先にボートに乗り込むと、その前側に美冬が膝を抱えて座り込んだ。僕のふくらはぎに美冬の背中が当たっている。



はーい、それではもっとお二人ボートの中心に寄って下さい。くっついちゃって





こ、これ以上ですか!?





中心に寄らないと投げ出されてしまう危険性がありますから


投げ出される、というワードが美冬に刺さったようで、一度体を浮かせた後に、彼女は開いた僕の股にぐいと体を寄せた。今度は太ももの辺りに美冬の柔らかい感触がある。膝の上に彼女の二の腕が乗せられて、伸びた手がゴムボートの持ち手をしっかりと握っている。



準備はいいですか? それではいってらっしゃい!


係員が支えていた手を離す。激しい水流と重力に引かれて、僕らの乗ったゴムボードは怒涛の勢いで流されていく。美冬の体がさらに密着して、僕はもう速さも景色も恐怖も知覚出来ないほどにのぼせ上がっていた。




きぃやあああぁぁぁ!


美冬の絶叫をざまあみろ、と聞いていた前の僕はすっかりどこかに消えてしまったらしい。

一〇分かけて上った階段の高さから数十秒で下り、勢い良く着地用のプールに飛び出した。荒い息でボートから降りると、お疲れ様でしたー、と係員がてきぱきとした動きでゴムボートを回収していく。



昔はそんなに怖くなかったんだけどな


この後調べたら、数年前に改装されて速度も長さもパワーアップしていたらしい。何でも昔の考えで乗るものじゃない。



あ、あ、あ、あらそんなに疲れた顔をして。情けないですわね


水着と良い勝負が出来そうなほど青い顔をして美冬は僕に言ってくるが、蒼白な顔を浮かべて震えた声では苛立ちすら起こりもしない。下で待っている、と言った秋彦と松原さんの姿は見えなかった。どこか場所を間違えたか、と辺りを見回す。



そっか。これか


思わず僕はやれやれと息を吐いた。思い出したように秋彦たちのいる方へと目を向ける。そこではタトゥーを掘り込んだ男二人に秋彦たちが絡まれているところだった。



またあれやらなきゃいけないのか


結果はわかっているとはいえ、やっぱり怖い。だが、そうも言っていられない。やらなければ秋彦がどうなるかわからないし、何より因果律が崩れてしまうかもしれない。



どうかしましたの?





楠、警備員の人探してきてくれるか?


秋彦たちの方を指差すと、美冬は無言で頷いた。



よし


気合を入れて咳払いをして、僕は体を奮い立たせて、ゆっくりと歩きながら秋彦たちのところに近付いていく。



おい、なにやってんだてめぇ





なんだぁ? チビに用はねぇんだよ、消えろ


睨みを利かせる焦げた肌のタトゥー男が吼える。それににひるまないように目元が引き攣るほどに力を込めて睨み返した。




俺のダチだ。何か文句あんのかよ





やる気か、てめぇ


拳を振り上げた男を僕は変わらず見つめている。その凄みに男は一瞬たじろいだ。



こら、何やってる!


後ろから知らない男の声。美冬が連れてきた警備員の声だ。



やべぇ、逃げるぞ


拳をほどき、男たちは脱兎のごとくプールサイドを走っていくが、滑りやすいところでそんなことは命取り。すぐに転んで警備員のお兄さんに捕まえれて事務室の方へと連れて行かれた。



助かったよ


秋彦は僕の背中を叩いて安堵したようにその場に座り込んだ。



全くだ。ありがとうな、楠





いえ、誰かを助けるのが私の務めですから


腕を組んで口を尖らせて美冬は横にを逸らした。



でも、すごいね。あんな怖い人に立ち向かえるなんて





夏生は中学の時演劇部だったからな。凄みだけなら部内で一番だったんだよな





おかげで回ってくる役はいつもチンピラAだったよ


小道具がメインだったけど、悪役の時だけはそういう理由で舞台に立たされるのだ。本当は主役をやってみたかったが、それは結局叶わないままだった。
帰りの電車に乗り込む頃には四人とも遊び疲れて、人の数が少ないのをいいことに足を通路の方に投げ出して空いた席に座っていた。松原さんは小さく寝息すら立てている。その隣をきっちりと秋彦がキープして、そこから二つ離れた席に僕は座っていた。少し二人に気を遣ったつもりだったのだ。
僕の隣に美冬が静かに腰を下ろす。



今日は、楽しかったですわ。誘っていただいてありがとうございます





いや、誘ったのは秋彦の方だよ。俺は付き添い





いえ、それでも嬉しいですわ。きっと一人ではあのウォータースライダーなんて乗れなかったですし


夕陽が差し込む車内で、美冬は子供のように笑った。いや、僕らは子供だ。自分の気持ちに整理もつけられず、理解すら完全ではなく、それを表現するのにも苦労する。



まぁ、楠が楽しかったなら良かったよ。ぼ、俺も楽しかったし





その楠、と呼ぶのやめていただけません? 私たちあんなに肌を重ね合った仲ではありませんか





お前、誤解されるような言い方するなよ。ウォータースライダーでくっついただけだろ


何かおかしいですか、という表情の美冬に、僕は思わず顔を赤らめた。自分の考えが勝手にそっちにいっているのが悪いのだ。



わかったよ。じゃあ、美冬、今日はありがとう





はい、こちらこそありがとうございましたわ。夏生


曇に遮られ、強く差し込んでいた西日が車内から消える。僕の真正面に映った美冬の無邪気な笑顔は、それまで僕が持っていた美冬のイメージを粉々に砕いてしまうほどに純粋で綺麗な笑顔だった。
駅前でバスに乗るという三人と別れ、僕は自転車置き場に向かった。このくらいの距離なんでもないと思っていたが、一日遊んだ体には一漕ぎが重い。朝余裕を持ってバスで来たという三人の先見には感心させられる。
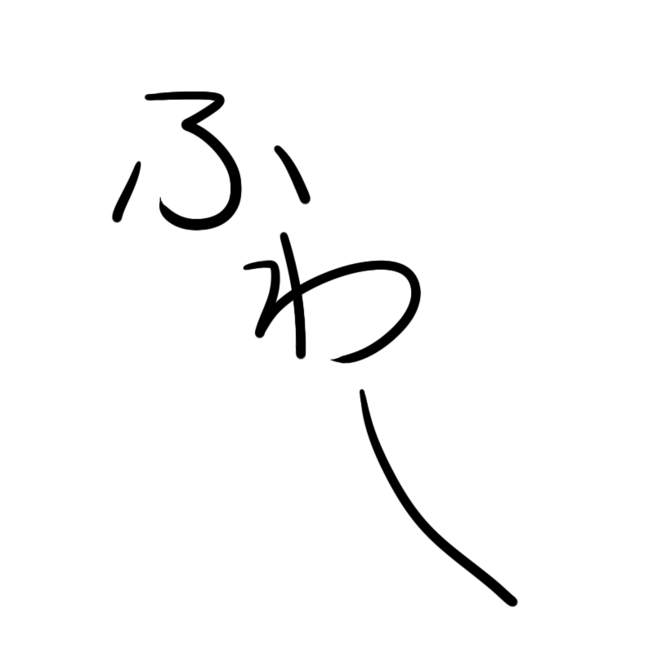



よお、プールは楽しかったか?





猛虎、お前どこに行ってたんだよ?





どこって。ちゃーんとプールまでついていっとったで。おかげでべっぴんなお姉ちゃんよーけ見れたわ。眼福眼福





お前なぁ


自転車のペダルを震える足で踏み込みながら、朝は一〇分で駆け抜けた道をゆっくりと走っている。



まぁ、見とらんでもうまいことやっとるやないか。その調子で頑張りや





わかってるさ、わかってる


すぐにあの日はやってくる。僕を取り巻く因果の渦で、一際大きなそれが僕を取り込んで動けなくする。どうにか外に出ようともがいてしまえば、周りまで巻き込んで世界は崩壊の道を歩んでいく。それでも僕は、こうしてもう一度やり直すことができるのなら。



変なことは考えんときや


僕の心を読み取ったように猛虎が耳元で呟いた。その言葉に僕は返事ができなかった。
その日の夜、秋彦からメールが届いた。



八月一六日に夏祭りがあるからそこにまた四人で行こうって話になった。お前も来てくれるよな?


了解、とだけ返事をして僕は携帯を枕元に投げる。



……美冬


僕は本当にこのままでいいんだろうか。猛虎もこの心の中の呟きは読み取れなかったようで、無言のまま僕の本棚から勝手に取り出したマンガを読み続けていた。
