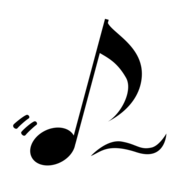立て付けの余り良くない引き戸を、勢いをつけて開ける。
立て付けの余り良くない引き戸を、勢いをつけて開ける。
半透明の硝子が嵌め込まれた扉が柱にぶつかる派手な音が辺りに響き渡ったが、それでも、家からは誰も出て来なかった。



……やはり


「今日の夕方に帰る」と昨夜の内に連絡したはずなのに、誰も居ないとは。溜め息以前に肩を竦める。
祖父母も両親も、まだ家に残っている兄弟達も皆、何処かに行っているのだろうか? 誰も居ないのに玄関の鍵を閉めないなんて、不用心過ぎる。そう思いながら、勁次郎は慣れた感じで家の中に入り、肩に掛けていた大きめのスポーツバッグを居間の隅に置いた。
家族なのに何処か他人のような余所余所しさは、昔からのこと。だから今更、久しぶりに実家に顔を出した勁次郎を出迎えない家族のことをとやかく言うつもりは、無い。
重いスポーツバッグを掛けていた所為で少し痛くなった左肩をぐるぐると回しながら、人気の無い居間と台所を抜ける。その向こうにあるのは、板敷きの広々とした部屋。勁次郎の家には空手と柔道と合気道を組み合わせたようなよく分からない我流の武術が伝わっており、父親はその武術を教える為の道場を副業として営んでいる。勁次郎自身も、この場所で、祖父から厳しく手ほどきを受けた。
道場の正面に飾られた、簡素な神棚に手を合わせてから、その前の床にあぐらをかく。そして勁次郎は、ただ静かに目を閉じた。聞こえるのは、既に九月だというのにまだ諦めきれずに鳴いている蝉の声のみ。
工学を学ぶ為に都会の大学へ進む前は、毎日毎晩、この道場で飽きもせず様々な武術訓練を行っていた。そのことが、大学で実学よりも理論を学ぶ方が面白くなり、誰にも相談せずに大学院に進んだ今となってはとても懐かしく、また奇妙にも思えた。
武術が嫌いになったわけではない。帝華大学という、この国でも有数の大学の大学院に進学し、普通とは少しずれた、強靭で傷付き易い心を持つ人々と行動を共にするようになってからは、尚更、この道場で育んだ感覚が役に立っているのを感じている。武術よりも大切に思う人や物事に出会ってしまったから、結果的に、武術自体からは距離を置くことになってしまったのだろう。瞑想の中で、勁次郎はそう、考えた。
と。
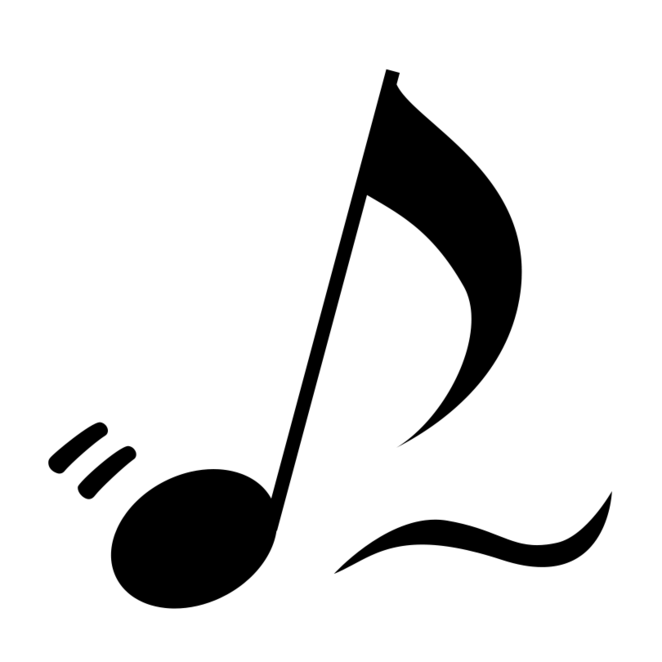
不意に、蝉の声にピアノの音が混ざる。この、音は。勁次郎はかっと目を見開くなり立ち上がった。この道場から、塀と小道と小川を挟んだ向こう側には、かつて勁次郎も通っていた高校がある。だからピアノの音が聞こえてきても、不思議ではない、のだが。……だが、この音、は。でも、まさか。
道場から直接庭に出る。確かに、すぐ近くからピアノの音が聞こえて来る。勁次郎は庭用の古いサンダルを足に引っ掛けたまま、実家の外玄関を出た。
昔と同じように、小道と小川の向こうに金網のフェンスとプレハブの平屋が見える。ピアノの音は、確かに、プレハブ平屋の、黒いカーテンが風に揺れている部屋から聞こえてきていた。あの部屋は、第二音楽室。高校の定員が多かった時代に作られたが、勁次郎が高校に通っていた時には殆ど使われていなかった部屋、だ。勿論、少子化が進んでいる現在では言わずもがな。その音楽室から、勁次郎が昔聞き知った旋律が聞こえてきている。その曲を、弾いているのは。



まさか
……いや、あり得ない


小川を超えてフェンスに飛びかかる為に、足に力を込める。だがすぐに、勁次郎はフェンスの上に鉄条網が設えられていることに気付いた。勁次郎が高校に通っていた頃には無かったものだ。サンダル履きは勁次郎の運動能力を損ねない。だが鉄条網は、服が破けてしまう恐れがある。仕方が無い、正門に回るか。逸る心を抑えつつ、勁次郎はサンダル履きのまま左を向いた。