勁次郎が家の横にある高校に進学することを決めたのは、偏に武術修行の為だった。
勁次郎が家の横にある高校に進学することを決めたのは、偏に武術修行の為だった。
公立で、それなりの由緒がある高等学校。一応進学校だが校風は自由気侭、制服は有って無きが如し、勉学にも部活にもあまり力が入っていない学校だったから、武術に打ち込みたい勁次郎には丁度良い学校であった。
朝、ギリギリまで道場で過ごしてから、始業のチャイムが鳴る頃に道場着のままフェンスをよじ上るのは日常茶飯事。昼食も、朝とは逆方向にフェンスを乗り越え、自宅に帰って食べていた。その後、午後の授業が始まる直前までまた道場で修行し、午後の授業が終われば即刻帰宅。そのような生活を飽きもせず、続けていた。高校の他の生徒や先生とは必要最低限の話をするのみ。それで良いと当時は思っていた。
だが。
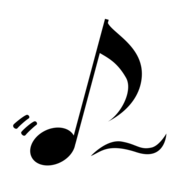
道場での修行中に、ピアノの音を耳にするようになったのは、高校一年の秋頃。勁次郎が道場に居るのを見計らったかのように、耳障りな旋律が響き渡るようになったのだ。



何だ? この音は?


最初は、偶然だと思った。だが、その調子外れの演奏が二週間も続けば、家族の中では温厚で通っている勁次郎でもむっとする。実害も有った。ピアノの音の所為で武術修行に集中できないのだ。



どんな状況でも集中できるようにならねば、真の武術者とはいえない


血の繋がった家族である以前に師匠である祖父からそう言われ、勁次郎はその音を気にしないよう努めた。
勁次郎の努力が実ったのか、その内、修行中でもピアノの音は気にならなくなった。



良かった


勁次郎はほっと胸を撫で下ろした。
だが。
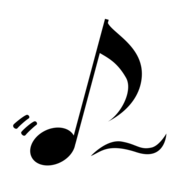



また、だ……


勁次郎がその音に慣れた頃を見計らったかのように、旋律が変わる。途端に、勁次郎は修行に身が入らなくなった。
何度も気にしないように努めても、気にならなくなった頃に旋律が変わる。そのパターンの繰り返しに、とうとう勁次郎の怒りは頂点に達した。
誰が弾いているのか分からないが、一言言いたい。音楽を奏でるのも、武術に集中するのも、それぞれの勝手だと、分かってはいるが。
だから勁次郎は、冬のある日、第二音楽室に乗り込んだ。
プレハブの校舎だからか、第二音楽室に続く廊下も、プレハブ校舎自体も、普通の校舎以上に空気が凍り付いているように感じる。寒さにかじかんだ手を息で温めてから、勁次郎は、微かに音が漏れる第二音楽室の冷たい引き戸を引き開けた。途端に、いつもの旋律が大きく響いて耳に入る。勁次郎に背を向けているので、一心不乱にピアノを弾いている人の顔は見えない。だが、その真剣な背中に、何か自分と共通しているものを感じ、勁次郎は文句を言おうとした口を途中で止めた。



あら


不意に、音が止む。振り向いて勁次郎に笑いかけたのは、生徒ではなかった。



今日は道場に居なかったのね、平林君


長い髪を掻き揚げて、整った顔が笑う。勁次郎も一週間に二時間ほどお世話になっている生物のまだ若い女教師、坂口先生だと、すぐに分かった。



此処から見えるから、邪魔してやろうと思って


勁次郎の問いに、坂口先生はあっさりとした表情で答え、指を窓の方へ示した。その細い指の先に視線を移す。確かに、黒いカーテンの向こうに、見慣れた道場がある。こんなに近くから、見られていたのか。何故か、羞恥心で身体が熱くなる。だから、でもないのだが。



別に、気にならない


口から出て来たのは、強がりの言葉。それだけ言うと、勁次郎は先生に背を向けた。
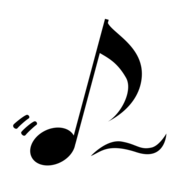
それからもずっと、ピアノの音は勁次郎の武術修行を嘲笑うかのように毎日響いた。



毎日弾いてて飽きないのか?


気になって、再び第二音楽室を訪れ、尋ねる。勁次郎の不躾な問いに、坂口先生は再び整った唇を綻ばせた。



することが無いからね


この高校は、勉学も日々の生活も生徒の自主性に委ねられている。教員は生徒の言動に口を出さないし、生徒も先生の授業方針に口を出さない。勉強したい者は勝手に勉強し、遊びたい者は遊ぶ。他人のことには口出ししない。そういう高校だった。
勿論、坂口先生も、生徒が生物という学問をきちんと理解することができるように授業方法を工夫している。だが、校風が自由過ぎるからだろうか、この学校の生徒は諦めが早く、張り合いが無いのが正直な所。そう、先生は勁次郎に話した。



だからかな
道場で一生懸命な平林君を見ると、更に負荷を掛けたくなった


性格が、捻曲がっている。心の中で先生をそう評価する。それでも、一応褒められてはいるのだろう。先生の口調から、勁次郎はそう判断した。だから、先生がピアノを弾いて勁次郎を邪魔することを、勁次郎は咎めなかった。
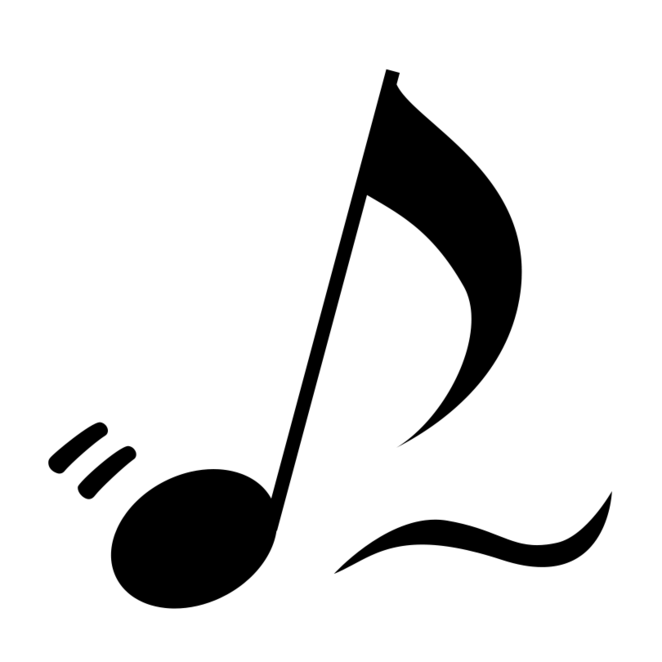
……その邪魔が、勁次郎が高校を卒業するまで続くとは、流石に思わなかったが。
卒業式の、前日。
もう一度、第二音楽室に足を運ぶ。
勁次郎の予想通り、坂口先生は火の気も無い極寒の音楽室のピアノの前で勁次郎を待っていた。



とうとう、最後ね


静かな声で、それだけ言い、笑う先生。三年間ずっと邪魔され続けた恨みと、良くも飽きずに続けていたなという半ば呆れたような感覚が、勁次郎の顔に微笑みを作った。



道場、離れるのね


おそらく職員室で聞いたのだろう、勁次郎の進路を、口にする。



止めるの?


先生の問いに、勁次郎は首を横に振った。



止めない


幼い頃からずっと、武術修行は勁次郎と共にあった。遠くの大学へ行くとはいえ、身体と心に染み付いたその感覚から、離れられるわけが無いではないか。



じゃ、私も、邪魔するのを止めない


不意に、先生の顔が勁次郎の1センチ前に現れる。いつの間に。戸惑う間もなく、後頭部が押され、一瞬だけ、先生の唇が勁次郎の唇に重なった。



じゃ、また


突然のことに、呆然と立ち尽くしてしまう。
その勁次郎に向かって微笑むと、そのまま、坂口先生は、勁次郎を音楽室に残して立ち去った。
