「悩ましい顔をしているな、少女」
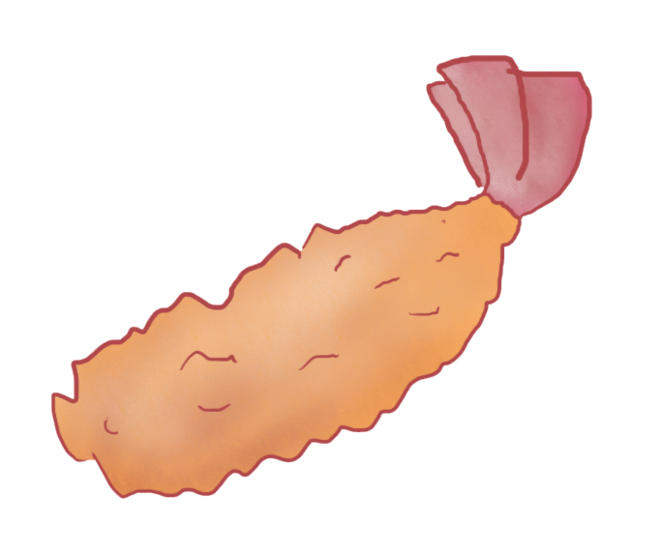
「悩ましい顔をしているな、少女」
朝日の差し込む明るい部屋で突然それは話しかけてきた。当然のように私を呼び止めるのは白い皿にぽつりと乗せられた海老を衣に包んで揚げた食べ物だ。
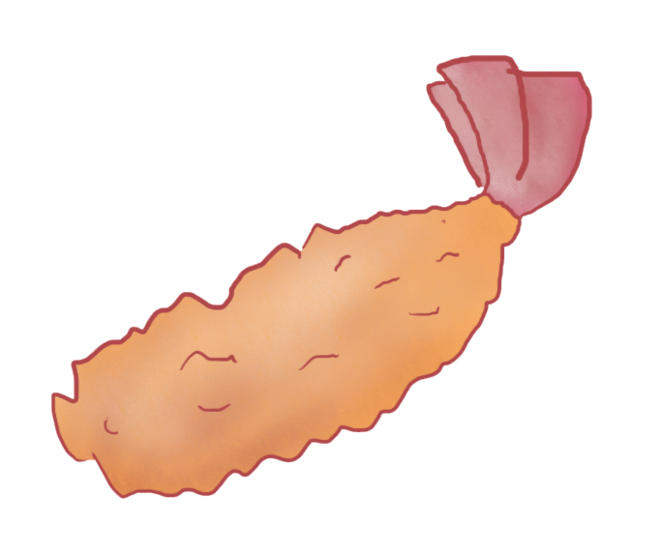
「私でよければ話してごらん」
優しい言葉を吐きだすのは落ち着いた低い声だ。心なしか皿の上のそれは私を心配しているように見える。ふと思い立ってそれを突いてみるとそれは呻くような声を上げた。突かれるのは嫌だそうだ。
気づいたら私はそれと会話していた。勉強が難しくてついていきづらいこと、これからが不安だということと、気になる先輩がいること。それから家族のこととご飯のことも話した。
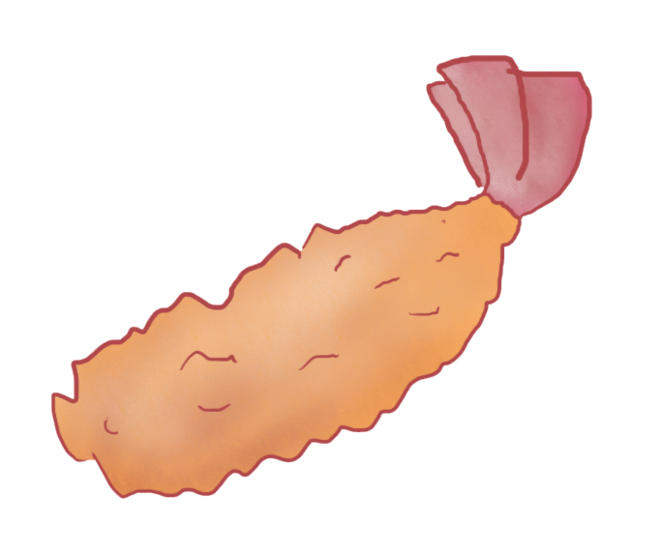
「君は随分と悩み事が多いみたいだね。可哀想に。その小さな体は重荷で今にも潰れそうなんだ。君は優しい子だからね」
それはとても安易に私の欲しい言葉を吐き出した。衣からはみ出た赤い尻尾を摘まむと落ち着いた低い声が止めるよう促してきた。
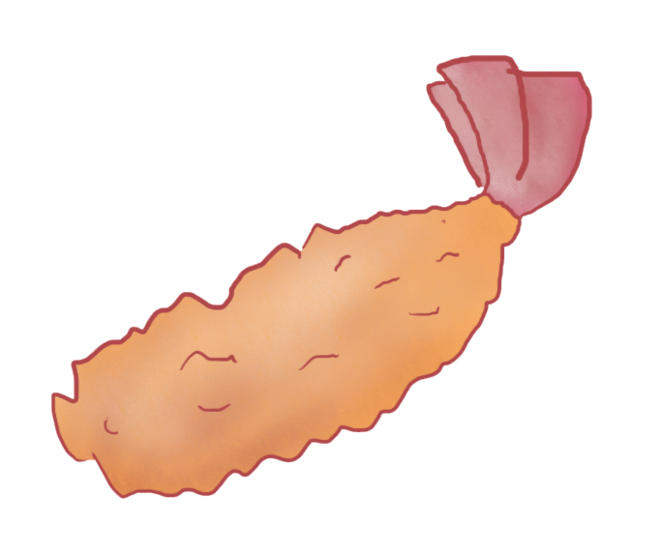
「さぁ、泣かないで。君は考えすぎなんだよ。お腹が空いてるんだろう。ご飯をお食べ。お腹がいっぱいになったらきっと悲しいこともなくなるだろうよ」
一体何を根拠にそんなことを言っているのかはわからないが、確かにお腹が空くと人は暴力的になるし悲観的にもなる。一理あるのかもしれない。
そして誰もが予想した通り、私は彼を食べたのだ。
