第2話
第2話



成る程ですねー


俺の話をひとしきり聞くと、正面のオフィスチェアに座る医師は、傍らの机上に置いたカルテに、何やら走り書きをした。



わんにゃん大パニック、と





先生?


猜疑心丸出しで咎めると、しかし相手は「ノーノーノーノー!」と大声を出しながら、俺に向けた両手をブルブルと振り、ニカッと笑った。



最初に言った通り、私のことは『ドクター・ヤブ』と。ドゥユーアンダスタン?





ヘイ、リピート、アフターミー! 『ドクター』





ヤブ





オーケーオーケー、なに、病気なんてもんは大概の場合、大声出せば何とかなるもんさ





私もね、子供の頃はよくインフルエンザにかかったもんだけど、家の中で『天城越え』を熱唱してる内に綺麗サッパリ! 親が私に何て言ったか分かる?





『石川さゆりに治療費払わないと』っすか?





惜しい、『やっぱりクール・ジャパンは最高ね』さ! ね、ジョークのセンス、凄くない?


悪い方にな、と俺は思った。そして、今更ながら後悔し始めていた。もっとちゃんと病院を選ぶべきだった、と。
ジョイさんの会社から出た俺は、猫と化した先輩に、有無を言わさぬ勢いで早退の願いを告げた。そして、猫先輩から頂いた「今すぐにでも病院に行け」という金言に従い、近くの心療内科を探した結果、この病院に駆け込んだのだ。
だが、結果がコレだ。患者に向かって「わんにゃん大パニック」とは何事だ。失敗した。せめて『ヤブメンタルクリニック』という名前について、もう少々しっかりと考えるべきだった。
ここで一つ断っておこう。何も俺は、全国の薮という名のドクター諸兄に喧嘩を売っているワケではない。むしろ、皆様が名医の誉れ高い、確かな知識と経験と技術をお持ちの人格者であらせられることは疑いようもない。
が、目の前の、診察室に入るなり「ようこそいらっしゃいましたハッハッハー!」と大声を上げて俺を出迎えた、四十歳手前と思しきアフリカ系パンチパーマ野郎だけは話が別だ、と俺は推測する。何故か。



ちなみに、この病院の名前の由来って分かる?





『ヤブって名前だったら自動的にヤブ医者になっちゃうじゃん、日本ってスゲー。面白いからヤブって名前にしちゃえ』





オゥ、素晴らしい! ワンダフル! アナタもジョークのセンスがある! うちのマミー程じゃないけど


やはりである。ノリと勢いで生きるタイプだ。おまけに偽名を使っていることまで露呈するとは。
パンパンと手を叩いて盛大に笑うドクター・ヤブの姿に、俺はセカンドオピニオンの決意を固めた。こういう、自分の中のワケの分からんツボにハマり続ける奴には、得てしてロクな奴がいない。



さて、ジョークは一旦、ここいらで戸棚の奧にしまっておいて、だよ





ジョーク飛ばしてる余裕なんかないんすけどね、こっちは。やっぱ脳外科の方が良かったかな





それ。そういうのだよキミ、えーっと……井出くん? ミスターイデ?


馴れ馴れしくもタメ口である。が、こちらの白けた視線などどこ吹く風で、ドクター・ヤブは話を続けた。



もっとおおらかな気持ちが大事。オーケー? なんでも効率で考えない。無駄こそが人生の美徳。日本人はいつだって難しいこと考えてるでしょ?





そんなことじゃあねぇ、体も心も保たないように出来てるの、人間の体は! 最近無理してるな~って感じたことない?





無くはないっすけど





ホウ! そりゃ良かった。自分が無理してることすら気づけない人も居るのよなァたまに。そういう意味ではキミはまだ大丈夫な方。オーケー?





リピートアフターミー、『キミはまだ』……





大丈夫な方。……ちょっと待って。もしかしてこれが治療とか言うんじゃないでしょうね


尋ねると、ドクター・ヤブは口を魚のように突き出し、目をパチパチと瞬かせた。そうじゃなければなんなのよ、とでも言わんばかりに。



いいですかヤブ医者





ノーノーノーノー、私のことはドクタ――





このままじゃあ俺は、今後も商談の席で犬と談笑したり、猫に仕事の報告しなきゃいけないんだ





いや、そうじゃねえや。つまりだ、俺は自分の頭がどうかしちまったんじゃないかって、そう思ってるワケだよヤブ医者!





刺激的で楽しいと思うけどなァ、そんな幻覚。ホラ、ドクター・ドリトルみたいで





冗談じゃねぇよ!





わーかったわかった、わかりましたので。ひとまず席に着きましょう? オーケー? ほら、コーヒーも入りました。インスタントだけどね


アッハッハッハッハ、と何が面白いのか、ドクター・ヤブはゲラゲラと笑った。また怒鳴りかけたが、彼の机の端、俺の手が届く場所にコーヒーを置いてくれた看護師の女性が、実に冷ややかな目でこちらを見ていたので、何となくバツが悪くなり、俺は再びキャスター付きのスツールに腰を下ろした。



さて、ではまとめるとだよ、ミスター・イデ。キミはこう言いたいわけだ





自分に起きているものと合致する精神的な病気は無いか? もしくはこのような症状に対する特効薬や治療法は無いか?





なんだ……分かってるじゃないですか


少しほっとして、差し出されたコーヒーを口に含んだが、そうしてから俺はハッと気づいた。分かっていながらおちょくられていた、ということなのでは。



結論から言うとそんな病気は無いし、そもそもこころの病に特効薬なんてものは存在しませーん! ハッハー! おっとこいつは失礼


こういう時は生まれつきの目つきの悪さが良い方に働くものだ、と、ドクター・ヤブを睨んでやりながら思った。が、口をつぐんだのは一瞬で、ドクター・ヤブはすぐにまた、やかましい調子で口を開く。



つまりだよ、私が言いたいのはだね、焦っても一切解決しないってことだよ





それよりも、無理をしないでいられる空間を探し、メリハリをつけてそれを利用すべきだと私は思うね。治したいなら尚更さ





要するに、しばらくは犬猫が見えるまま我慢しろって?





そゆこと。あ、どこ行っても似たようなこと言われると思うよ。そんな怖い顔されてもどうしようもなーい、これはキミのこころのもんだーい。オーケー?


カルテにさらさらと何やら走り書きしながら、ドクター・ヤブは慣れた調子でそう言った。どうしてもアレならしばらく休むことも考えた方がいいね、とも。



そう言われてもなぁ……働かねえと生きていけないし





じゃあホラ、ミスター・イデ。キミ、何か趣味とかは? もしくは『これをしてたら楽しい』みたいなもの


えらく曖昧な質問が飛んできた。要するに、そういうことでストレスを発散しろ、ということなのだろう。俺はしばらく考えた。趣味……は特には無い。楽しいもの。合コン?



……あ、そう言えば





So言えば?





明日、中学の同窓会がある。えっと、つまり、大勢で飲むのは好きかな





んー、そうそう、そういうのよミスター・イデ。キミの症状がストレスから来るものだったとしても、それを溜めない様に、と考えるのはNo! 無理だからねそんなの! ま、差し障りのないお薬は出しておくので


そう言うと、ドクター・ヤブは白い歯を見せ、ニカっと笑った。



犬猫の幻覚なんて気にならないくらい、楽しんで来なさいよ


『ヤブメンタルクリニック』での顛末は以上だ。思い返せば全くの時間の無駄だったような気もするが、一方でそれなりに良い助言を与えてもらったような気もしないでもない。『焦らないでいればそのうち治るよ』という前向きな診断を貰った、と捉えようと思う。
そこで翌日、俺はドクター・ヤブに告げた通り、中学校の同窓会に参加するため、夕方頃に家を出た。先日のジョイさん訪問あたりで完全に頭から抜け落ちていたが、元々ずっと楽しみにしていたのだ。
持論だが、こういった集まりの楽しみには三つあると思う。
一つは、旧友の近況を知れるということ。二つは、酒が飲めるということ。そして三つ目が、失われた過去からの、思いがけぬロマンスの到来である。特に三つ目は大きい。彼女の居ない俺にとって非常に大きい。とにかく大きいのだ。
思い起こせば、中学校時代の俺は大変な馬鹿者だった。甘酸っぱい青春の思い出が殆どないのだ。一度気になる女の子にアタックして玉砕してからは、その悲しみを記憶のゴミ箱に投げ捨てんか如く、野郎どもと終始アホなことをして騒いでいた。
何とまぁ愚かしいことか。もっとリビドーの赴くままに片っ端から声を掛けまくれば良かったというのに。
今晩はかなりの参加者が居ると聞いている。それ即ち、ロマンスの獲得率も高いということだ。この機を逃す手は無い。例え幻覚が俺を襲っていても。
往路の電車で何人か犬の顔をした婦人や猫の顔をしたサラリーマンなどを目撃したが、そんなことも吹き飛ぶくらい、俺はとにかくワクワクしていた。期待に胸は震え、微かなロマンスの香りも逃してやるものかという意気込みは、俺を熟練のハンターのような目つきにしていたことだろう。
だから、気が付いていなかったのだ。
俺の身に起きた事柄のすべてが、『幻覚』や『こころの病気』で片付く訳が無いことに。
自宅から電車に揺られ三十分、繁華街の駅前にある居酒屋にて、同窓会は催された。懐かしい野郎どもとの再開を喜び、集まってくる垢抜けた女性陣にロマンスのかぐわしさを堪能しながら、やがて通された座敷にて、俺はいつそのロマンスを刈り取りに行こうかそわそわしていた。ちょうどその時だ。



おうい、我らが恩師のご到着だぞー!


幹事が威勢よく、座敷中によく響く声でそう告げると、そこかしこで盛大な拍手が巻き起こった。そうして、頭を掻き掻き部屋に入ってきたのは、恩師どころかスーツ姿のウサギだった。



ん、どうした井出。顔色悪いぞ





どうしたもこうしたも……


隣に座る幹事に返しながら、俺は上座へ進む二足歩行のウサギを、ウンザリした面持ちで眺めていた。もう勘弁して欲しい。犬猫を忘れるどころか、更に新しいのがお出ましとは。
旧友たちはと言うと、ケラケラ笑いながらウサギのもとへ集まっている。頭を触って「相変わらず触り心地いいですね」なんて言っている女の子もいる位だ。俺の記憶じゃあ、恩師の頭は不毛の荒野だった筈なのに。畜生、羨ましい。いやそうじゃなくて。
頭に手を当て、俺は今更ながら、ジョイさんとのやり取りを思い出していた。ジョイさんは自身を、ネギが苦手な『種族』だと言っていた。それはつまり、いま見ている光景がストレスによる幻覚なのではなく、現実に犬人間が居るという、何よりの証左では無かったか。



なぁ、先生ってさ……





全ッ然変わってねぇよな! いいよなぁ、ハゲる心配なくて


そういう問題では無い。呆れて見つめていると、幹事は幹事で「あ、違う、別に俺が薄くなってきたとかじゃない」などと言い出す始末だ。それはそれで気の毒だが、今この場においては、お前が不毛の荒野を突き進んでいることなど至極どうでもいい。こっちはもっとエライ目にあっているのだ。
俺は溜め息をつき、ただただ上座のウサギと、それに群がる友人達を眺めていた。悪夢なら覚めてくれ、なんて虚しい独り言を呟きながら。
……と、その時。ふと、とある人物が目に留まった。
座敷には背の低い長テーブルが六つ配置されていて、俺は出口に最も近い下座の、そしてその人物はウサギがいる上座の――要するに、ウサギのすぐ傍、座敷の対角線上に座っていた。そして――何よりも重要なのは――彼女は、傍のウサギを、呆気に取られたかのように見つめていたのだ。
それは沸き立つこの場において、明らかに異質な反応だった。懐かしいウサギの姿に、皆は実にニコヤカである。ところが、彼女はどうだ。まるで亡霊や悪霊を見ているかのようにウサギを見つめている。――俺と同じように。
彼女は青い顔をして立ち上がり、傍の出口を通って部屋を出ていった。確信に突き動かされるまま、俺はその後を追った。



種本!


狭い居酒屋の廊下で名を呼ぶと、彼女はビクリと体を震わせ、立ち止まった。木製の廊下は冷たく、足元から寒気が這い上がってくる。
振り返った彼女は、ただ一言、「井出君」と俺の名を呼んだ。傍の座敷の喧騒はどこか遠くに消え去り、俺と彼女は暫く見つめ合っていた。
さて、勘違いなさらぬよう、ここで注釈を入れておこう。この時、俺はかつてのクラスメイトとのロマンスを感じていた……ワケでは無かった。何故か?
先に述べた『俺が告白して玉砕した』相手こそが、紛れも無い彼女だったからである。



久しぶり


青い顔で、何となく苦々しく彼女は言った。俺も俺で、振り返る彼女の姿にフラれた瞬間を思い出してしまい、「久しぶり」という返事はひどくぎこちなかった。
今でも、だ。今でも、鮮明に想い出せる。彼女は俺をこう言ってフッたのだ。「井出君って何だか軽いから」。



井出君は、あんまり変わってないね


そう言うと、廊下の先の彼女は苦笑いをした。それはつまり、まだ『軽い』ということだろうか。畜生め。



種本はアレだな。昔より落ち着いた感じだ


内心の動揺を隠すように、俺はついつい洋画の登場人物のような、気取った調子でそう笑った。種本も「何それ」などと返しつつ、つられて笑う。そしてまた、気まずい沈黙が流れた。
と、そこで思った。
こんな安っぽい恋愛ドラマみたいなことしてる場合じゃねえ。



ごめんね、井出君。あたし、ちょっと体調が良くなくって――





オーケー、分かった、分かってる、ちょっと待って!


そそくさと通路奧のトイレへ逃げ込もうとする種本の肩を、俺は慌てて掴んだ。逃してなるものか。こちとら、自分がオカシイか世界がオカシイかの瀬戸際である。それを確かめられるのは、間違いなくこの場しか無い。
よっぽどの剣幕だったのだろう。強引に肩を掴まれた種本は、酷く驚いた――怯えた?――目で俺を見返した。そんな彼女に、俺は早口に、ただ一言を投げかけた。



先生がウサギっておかしくねえ?


――嗚呼、その直後の彼女の反応を、俺は未来永劫忘れないだろう。彼女は一瞬、ピタリと静止して――まるで再生中の映像に一時停止をかけたようだった――そして、次の瞬間。



おかしいよ!


一言叫び、ぐい、と近づいて、彼女は肩を掴む俺の手を思い切り掴み返してきた。次は俺が彼女の剣幕に驚く番だった。



良かった、分かってくれる人が居て! 最近職場の先輩がセキエイインコになっちゃって、しかも街を歩いたらそこかしこで犬とか猫とかが服着て歩いてるし! 昨日なんて豚にナンパされて、もうあたし何が何だか――





その豚ってのはアレ? 俗にいう横に長い体格の方ではなく――





違う、正真正銘本物の豚! 哺乳綱鯨偶蹄目イノシシ科の動物のこと! でも二足歩行なの!





これっておかしいよね!? なんでみんな平然としてるの!?


なるほど、と思った。彼女はどうも俺のように素直に病院に行くこともなく、異常事態に数日間一人で耐えていたようだ。その精神力は驚嘆に値する。
が、それよりもまず、俺よりも頭一つほど身長の低い彼女が、泣きそうな目でこちらを見上げ密着している、というこの状況は、精神衛生上非常に喜ばし……じゃなくて。



よーしわかった種本、はいどーどーどー。とりあえず落ち着こう。な? お互い、この状態は第三者に見られると困るはず。多分


ほんのり伝わってくる彼女の温もりに名残惜しさを感じながら言ってやると、彼女はハッと我に返り、すぐさま俺の手をリリースした。数歩後ろに下がり、バツが悪そうに「ごめん」と謝ってくる。くそう。



ちなみに、俺のところの先輩は猫に変わった。目の前で





猫に……そっか、井出君も大変だったんだね


まさか人生でこんなやり取りを真剣に行う日が来ようとは、誰が予想できただろうか。そんなことを考える俺の目の前で、種本はうんうんと何度も頷いている。話の分かる人間の存在が、これ以上ない安心を彼女に与えたようだ。



ねぇ、色々話したいんだけど大丈夫かな? 井出君はいつ頃から――





おい、そろそろ始めるぞ! 中に入ってくれよ


種本が勢い込んで尋ねようとしたところで、空気の読めない薄毛幹事が、廊下の俺たちへと声を掛けた。「悪い、すぐ行く」と返してから、再び種本に向き直る。



なぁ、話は同窓会が終わってからにしないか? 話し始めるとかなり長引きそうだし





俺としては、ひとまず自分が狂ってるんじゃない、って分かっただけでも安心したよ





そうだね……その方がいいかも


かなり名残惜しそうに、ではあるが、それでも彼女は納得したようだった。それから、「終わったら帰らないでね。あとお酒も飲みすぎないで」と釘を刺すように告げてくる。
その段階になって、俺はようやく、この事態に一筋の光明を見た。そう、即ち、種本とのロマンスである。
俺は大声で猫先輩とジョイさんに御礼を申し上げたくなった。よもや、このような形で学生時代の恋が再燃しようとは。終わったら帰らないで? オーケー、望むところだ。積もる話をゆっくりしよう。そんな思惑のまま種本の言葉に頷いた、ちょうどその時だ。
不意に、強い耳鳴りが俺を襲った。
それは近くを飛び回る羽虫の羽ばたきのようであり、深夜の冷蔵庫から響く重低音のようでもあった。または猛スピードで走り過ぎる車のモーター音のようでも、雑踏に澱む喧噪のようでもあった。つまりは、例のよく分からない耳鳴りが容赦ない頭痛を生み出して、俺は思わず、傍の壁に手をついた。



……種本、大丈夫か?


しばらくして痛みは引いた。傍で小さく、苦しげに呻く種本の声に、恐らくは相手にも同じ症状が出ていたのであろうことを予想しながら、俺は彼女へと視線を戻した。
途端。俺の全身は、極寒の海に投げ出されたが如く、凝り固まった。
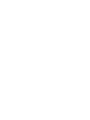


うん……何とか。
最近、よく耳鳴りと頭痛がして……
井出君も?





え、ああ、うん


言いながら、俺の頭の中は、ただ一つの疑問に占領されていた。そう、ただ一つ。
『どっち』だ?
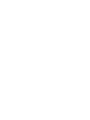


井出君?


俺の様子がおかしいことに気づいたのだろう。種本は怪訝そうに尋ねた。が、その後すぐ、聡明な彼女は、俺の視線の『意味』を考えてしまったらしい。
種本は自らの頬に手を当てた。それから、猛然とした勢いで提げていた小さなバッグを開き、手鏡を取り出して、自らの姿を確かめた。
彼女は呆然と呟いた。



ヤモリ


なるほど、イモリじゃなかったか。そんな呑気な考えが現実逃避気味に脳裏をよぎった途端、二足歩行のヤモリと化した種本は、自身の変わり果てた姿に、そのまま廊下へ倒れ込んだ。
