死に別れた両親が目の前に立っている。
そして、自分を見つめている。
ありえない奇跡を前に、ルイは茫然と立ち尽くしていた。




……っっ





……





……


死に別れた両親が目の前に立っている。
そして、自分を見つめている。
ありえない奇跡を前に、ルイは茫然と立ち尽くしていた。



………


エルカの目から見ても、彼の両親は優しそうな人たちだ。
自分の両親のような、『何を考えているのかわからない』表情ではない。
二人が投げかけるのは、我が子を慈しむような視線。
春の木漏れ日のような温かさが、彼と彼らの間に流れている。
親子の会話を聞いてはいけない。
ここから先は彼のプライベートな時間だ。
そう思って離れようとしたが、握り合う手をルイが離してくれなかった。



………





………


心なしか、握り合う手に力が込められたような気がする。
ルイが強く手を握るから、エルカはその場を離れるわけにもいかなくなった。
視線を動かすと、グランとマースは彼らから距離を取って見守っていた。



エルカ、邪魔をしてはいけないよ。これは最後の再会になるのだから





(………)





(離れられないのなら、黙ってなさい)





(これは彼らにとって、最後の再会だ)





(………そうだね)





(だから……離して欲しい)





………


だけど、ルイは手を離してはくれなかった。
離して欲しいと目で訴えても、彼はこちらを見てくれない。
仕方がないので、エルカは俯いて目を閉じる。
耳も覆いたかったけれど、残念ながら片耳しか抑えられない。



(仕方ない……よね)


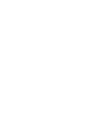


(それまでは空気になろう)


そして、ルイは顔を上げる。
時間が、ゆっくりと流れていた。
ここまでルイは、魔法による奇跡を次々と見せられている。
これ以上、おかしなことが起きても動じないつもりでいた。
彼女の手を握っていなければ、叫んでしまいそうだ。
エルカが離れたそうにしている。




………っっ





……


何度も視線を向けられていることに気付いていた。
申し訳ないと思いつつルイは、彼女の手を離したくなかった。
自分を落ち着けるために、気付かないフリをして彼女の手を握りしめた。

乱れる呼吸を整えて、目の前で起きていることを考える。
黒い双眸に、信じられない光景が映っていた。
これは夢だろうか。
先ほどのように、過去の記憶が映像として浮かび上がっているのだろうか。
手を伸ばしても触れられないのかもしれない。
声をかけても届かないのかもしれない。
目を凝らす。
半年前に喪われた人たちが、そこに立っている。
怖くて声をかけられない。
声をかけたら、目の前から消えてしまいそうで怖くなる。
ルイが最後に彼らを見たのは一瞬。
叔父のバラトが咄嗟に引き戻したので、詳細を見てはいない。
赤い血の海。
横たわる二人。
じっくり見たわけではない。
あの一瞬だけで、ルイはアレが目の前の二人だと理解できた。
その時の二人がどんな顔をしていたのかはわからない。
二人の顔を思い出そうとしても、その日の朝の表情しか思い出せなかった。
父親は眉間にしわを寄せて怒っていた。
ああ、怒っている顔しか思い出せない。
母親は眉根を寄せていた。
どうしよう、困っている顔しか思い出せない。
あれが、最後の朝で、最後の会話になるなんて思ってもいなかった。
後で謝罪しようとは思っていた。
せっかく用意してもらった朝食を食べないで飛び出してしまった。
だから、明日は朝食を食べようと思っていた。
『後で』なんて、
『明日』なんて、



(その瞬間が、永遠に来ないなんて想像できるわけがないだろ)


だけど……



(僕が彼らと再び会うことはできない)





(あれは、夢でした……なんてことにはならない)


二人は息絶え、ルイは遺された。



(これが、現実だった)


ルイの両親は帰れない場所へ旅立ってしまった。
手の届かない場所に行ってしまった。
ケンカをしたまま、朝食を食べられないままに、その日は永遠に失われた。
この後悔を引きずって、今までもこれからも生きていくのだ。



(そう思っていた)





(それを受け入れていた)


だけど、目の前に彼らがいた。
再会できるはずのなかった、両親が目の前にいる。



……





………


握り合う彼女の気配を感じる。
自分と彼女がやらなければいけないこと。
そんなの、わかっていた。
それは、死に別れた家族との対話。
ルイも彼女も肉親と死に別れ、そこに未練を遺している。
自分には自分の、彼女には彼女のやるべきことがあるのに……
ルイは彼女の手を握っていたかった。
この不安を抑えて欲しかった。




(僕は臆病だ)





(最初の言葉が出せない)


茫然として言葉を失っていたルイに向けて、母親が口を開く。
いつもそうだった。
父親とケンカをしたとき、頑固な男たちは口を結んだままだった。
そんな時は、いつも母親が間に入って声をかけてくれた。
穏やかで優しい声が、とても心地よくて懐かしかった。



ルイ……久しぶりね。元気にしていた?





は、はい


母親の声に、ルイはぎこちない表情と声で答える。



ほら、あなたも





久しぶり……だな


そして、同じようにぎこちない声がかけられた。
父親は気難しそうな表情を浮かべていた。
顔を合わせればケンカばかりだった。
反抗期のルイは、二人に対して無愛想な表情で応じていた。
いつもは、眉間にしわをよせて怒鳴っていた父親。
それが、今は眉根を寄せて困ったような表情を浮かべる。
ルイはどんな表情を浮かべて良いのかわからなかった。
自分がどんな表情を浮かべているのかわからなかった。

