26 後悔の追憶2
26 後悔の追憶2
数日おきにルイが訪れる。
それを、渋面を浮かべながらナイトが応じる。
そんな日々がしばらく続いた。
ノートは手作りのものだ。
紙をまとめて糸で縫い合わせる手間をかけてルイはそれを作っていた。
受け取るかどうかもわからないエルカの為に。
いつものようにノートを渡して、頭を下げて立ち去ろうとするルイをナイトの声が引き止めた。



ちょっと良いか?





はい?


ルイは表情を強張らせながら振り返った。
何か怒らせるようなことをしたのだろうか。
ついに殴られるのだろうか。
時間をかけてナイトを見上げる。



それで、具体的には何があったんだ? あいつは教えてくれなかったんだけどさ……





え?





お前たちが仲違いした理由だよ。もちろん学校側から話は聞いている。だけど、あれは連中が作り上げた噂話だろ。





事実じゃない。あいつからは何も聞いていない。何故かは分からないが教えてくれないんだ。頼む、本当のことを教えてくれないか?


それは妹を気に掛ける兄の表情だった。
それに気が付くと、それまで怖いと思っていた鋭い視線も柔らかく見える。



あれは……ちょっとしたすれ違いでした。すみません。彼女が言えないことを僕の口からは言えません





そっか……いや……そうだよな。あいつの意思を尊重するとそうなるよな





すみません





まぁ、いいさ。それと、あんまり無理はするなよ。お前だって子供なんだ





……はい





親御さんだって、きっと心配しているだろうよ。何かあったらきちんと話すべきだ。まぁ、オレが言うことじゃないけどな





………はい





(親……か……)


家族とは今朝も喧嘩していた。
不登校になってからは、前にも増して会話する時間が減っていた。
それが良くないことは理解していた。
ナイトに見抜かれている気がして表情が固くなってしまう。
ルイはエルカが羨ましかった。
両親が側にいなくても、こうして心配してくれる家族がいるのだから。
ルイには両親が側にいる。
だけど、ナイトのように心配してくれる様子はなかった。
何より先に世間体を気にする人たちだ。
不登校になったことを恥だと言われて、朝も夜も喧嘩している。



一度、家族会議するぞ。いいな!


今朝も怒鳴るような父の言葉にルイは曖昧に頷いていた。
家族会議なんかしても、喧嘩になるだけだ。
そう思って、ろくに会話をしないまま、食事もせずに家を飛び出していた。
ルイはエルカの家にノートを届けた後、自宅には帰らなかった。
学校の隣の森に足を向ける。
女王様たちは彼女の本を教室の窓から森に投げ捨てた。
ここは生徒はもちろん教師も立ち入りを禁じられている場所。
だが、学校と関わるつもりのないルイには、もう関係のない話。
これは日課になっていた。
ルイは立入禁止の看板に目もくれずに足を踏み込んだ。
目的はただひとつ、失くした本を探す為。
探すと約束した。
あれは一方的な約束。
けれど、必ず守らなければならないものだ。どんなに時間がかかっても見つけるつもりだった。



今日も……見つからなかったか


月明りの道をのんびり歩いていた。
予定より遅くなってしまったようだ。
住宅街は暗く、静寂に包まれている。
殆どの住人たちは眠りについている時間だろう。
家族会議をすると言われたのに、こんな遅い時間に帰れば会議どころじゃない。
頭に血がのぼった父親に殴られるかもしれない。



叔父さんのところに行こうかな


不登校になってからは、顔を合わせば父親と喧嘩の日々だった。
それが嫌で叔父の住むアパートに逃げ込む日もあった。
叔父は理由を追求せずに、黙って家出少年を受け入れてくれていた。
翌日には、鬼の形相の父親が迎えに来るのだが……。
僅かな時間でも、安らげる場所だった。
叔父のアパートを見上げて肩をすくめる。
そこは、灯がついていなかった。
寝てしまったのか、もしくは不在なのだろう。
そうなると、自宅に帰る選択肢しかない。
気が重くなる。



こんな時間に帰ったらまた喧嘩だろうな


脳裏に浮かぶのは眉間に皺を寄せた父と、呆れ顔を浮かべる母の姿。
今朝、別れたときと同じ両親の顔。
静かな街路を重い足を引きずって自宅に向かう。

気味が悪いほど静かだ。
人の話し声も、風の音も、虫の声も聞こえない。
聞こえるのは自分の足音と鼓動。
自宅に近付くにつれて、ドクンドクンと鼓動が早鐘を打つ。
何で?
どうしてなのかは分からない。
ゆっくりと歩いていた、足が早まる。

先ほどまでは、あれほど帰りたくなかったのに。
早く帰らなければという気持ちが背中を強く押していた。
気が付くと、走っていた。

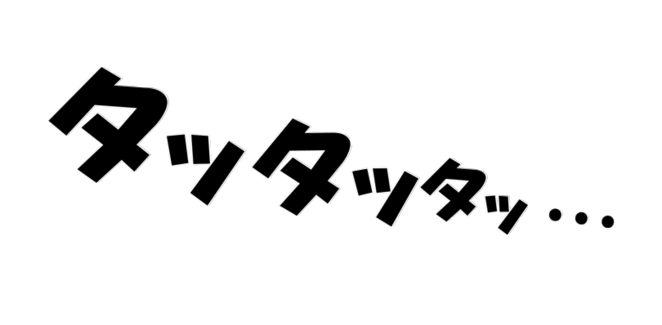
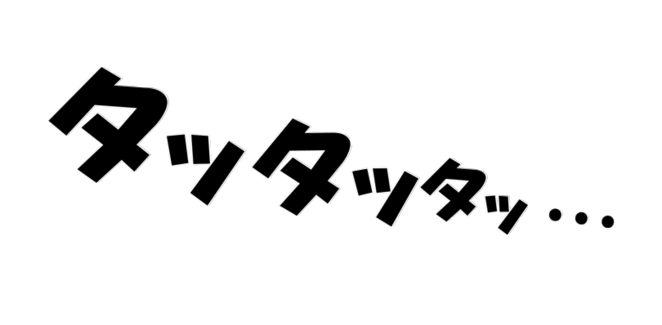



ハァハァ




息を切らせて、ようやく辿り着いた自宅。
まるで、他人の家のような気がした。
灯はついている。
他の家は暗いのに、ルイの家だけが明るかった。
それに違和感を抱く。
玄関の扉を開けた瞬間、父親の怒号が待っているような気がした。
それを、期待していた。
そうであって欲しい。
きっと、怒鳴り散らされて、殴られる。
身構えておいたほうが良いだろうとか、考えていた。
玄関の扉の前で立ち止まる。
ドクンドクンと、鼓動が鳴りやまない。
その扉は開けない。
開いてはいけないような気がする。



……っ


突然、扉が開いた。
玄関の扉が開くことは、それは何もおかしいことではない。
どうして驚く必要があるのだろう。
こんな夜遅くに帰ってきた息子を咎める為に、父親が飛び出てきたのだろう。
でも、違っていた。
現れたのは両親ではなかった。

