06 本の檻
06 本の檻
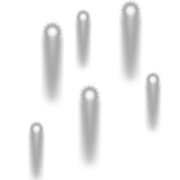
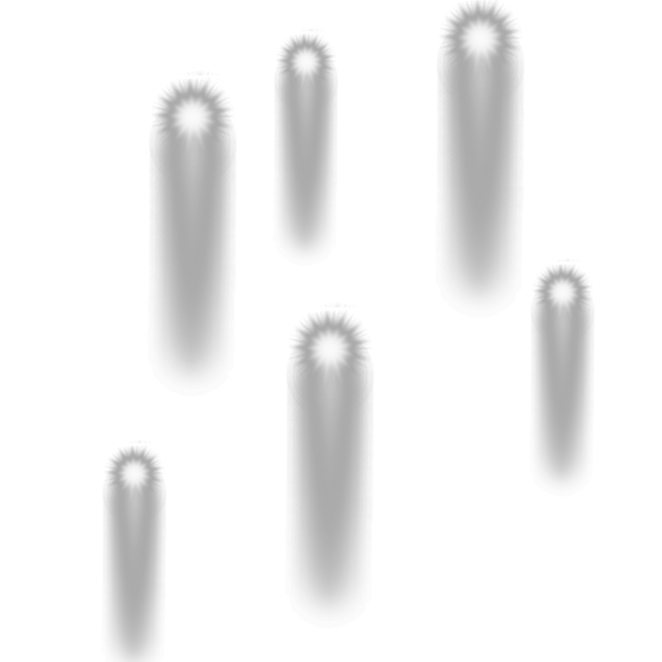
背中から落下していく。
まるで寝心地良いベッドで寝ている気分だった。ふわふわとした優しい感覚が全身に流れてくる。とても気分が良かった。
この疾走感に身を委ねてしまいたい。
どこまでも落ちていたいと思わせてくれる。
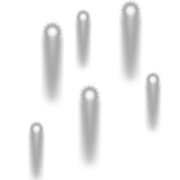



?


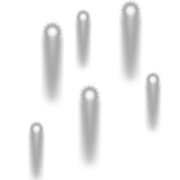
まどろみに沈みたかったのに、意識を無理矢理こじ開けられる。
どうやら、ソルをゆっくり休ませるつもりはないようだ。
何もかも忘れて虚無の底に沈みたかった。
しかしそれは許されないのだろう。



っ………


ようやく漏れ出た声は、情けない音を響かせる。
ここは何処だろうか。
視界がぼやけている。
何も見えない。
声が出てこない。
何かを忘れてしまったような気がする。
目を瞬かせながらソルは頭の中を整理する。
確か、エルカと共に図書棺を訪れて……本を探したところまでは覚えていた。
その後、何かが起きて自分は背中から落下したらしい。何が起きれば背中から落下するような事態になるのだろうか。思い出せなかった。
こうして思考を巡らせている間も、優しく緩やかな速度で落下している。
不思議なことに恐怖は感じられなかった。
そこまで考えると、突然視界に光が注がれる。
仰向けになって落下していたはずなのに、いつの間にやらソルは両足を地面につけて立っていた。地面に降り立った感覚はなかった。
眩しさに目が慣れてくると、正面に人影が確認できた。



ようこそ、本の檻《おり》に


それは聞き覚えのある声だった。
しかし、初めて聞く声のようにも思えた。
その見た目に反した妖艶で不気味で、それでいて親し気な笑みを浮かべた。幼女に見えるが、幼女ではない。
魔女だ。
咄嗟に、その言葉が脳裏に浮かんだ。
言葉にしなくとも、彼女には届いたのだろう。
口端を上げて、ニヤリと笑う。
その笑みは、いかにも悪い魔女らしい何かを企んでいるような笑みだった。



本の檻《おり》?


聞きなれない言葉が口から洩れる。
しかし、周囲を見渡せばすぐに理解できた。
それは確かに檻だった。
先ほどまでいた図書棺とは別の場所らしい。
四方を囲む本棚は檻のようにソルを捕らえている。扉らしきものは何処にも見当たらない。ソルはここから逃れることができないだろう。
目に見えない檻の中にソルは立っていた。



は じ め ま し て





私の名前はコレットよ。よろしくね


コレットと名乗る幼い魔女は愛らしい笑みを投げかけた。その姿と、その名前に聞き覚えがあるが、思い出せなかった。
記憶の中で黒いインクで塗りつぶされていている部分が思い出せない。
とても、すぐ最近のことだったはずなのに思い出すことが出来なった。
周囲を眺めて、ソルは自分が法廷の証言台のような場所に立っていることに気が付く。
裁判席からかかるプレッシャーがズキズキとソルを突き刺していく。
まるで裁判を受けている気分になってきて、生唾をのみこんだ。
しだいに、自分を取り囲むように並ぶ本棚が傍聴席のようにも見えてきた。
本棚に納められた一冊一冊、それぞれがニンゲンのように思える。ニンゲンはそこにいないのに、視線が一点に、自分に向けられている。
ケラケラ、クスクス
そんな笑い声も聞こえてきた。
そんな気がする。
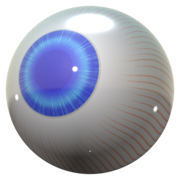
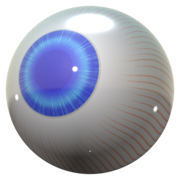
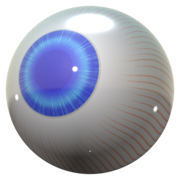
じっくり見ると、本棚の本から無数の目玉が浮かび上がる。
それらがソルを見ていたので、ギョッとして身体を仰け反らせた。
しかし逃げることは不可能だ。
ソルの両足は鎖のようなものでしっかりと固定されているのだから。



な………んだよ


鎖の拘束によって足は自由に動かすことが出来なかった。
足の付け根までが氷漬けにされたかのように動かない。
ソルが一人で、唸っていると。裁判長のコレットがトントンとガベルを叩く。

その音に喧騒に包まれていた空間が静寂に包まれた。



皆様、どうか静粛に。さぁ、ソル………証言台の上を御覧なさい


コレットに促され視線を動かす。証言台の上には一冊の本。
違う、それは日記帳。



オレの……日記


ザザッとノイズのようなものが脳裏に走る。
聞こえるのは、懐かしい声。



『何を書けとは言わない、書きたいものを書けばいい。その叫びを文字に起こせばよい。文字の勉強にもなるだろう。お前だけのお前の心をここにしまいなさい』


それは、エルカの祖父グランから貰った日記帳。
優しい人だった。
悪ガキだったソルのことも褒めてくれて、叱ってくれた人。
あの、くしゃっとした笑顔が脳裏に浮かんでいた。



……これに日記なのに日記らしいことは殆ど書いていなかったな。書いてあるのは罵詈雑言なかりで


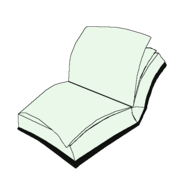
静かにページを捲る。
捲るごとに昔の光景が蘇る。
嫌なことが、哀しいことが、流れ込んできて息が苦しくなる。
呼吸が出来ない。
目を閉じたソルの視界には裁判長席に君臨する幼女の姿をした魔女がいた。
どうやら、目を閉ざすことも許されないらしい。目を開いても、閉じていても、見えるものは変わらない。
魔女が立っている。
感情のない瞳がジッとソルを見ていた。

