25 二人の孤独な時間
25 二人の孤独な時間
エルカはゆっくりと足音を立てないように廊下を進む。
物音を立てないようにに、慎重に目の前の扉を開いた。
周囲に誰もいないことを確認してから図書室の中に入る。
入る時も、音が出ないように息を飲みこみながら。そして再度、周囲に気配がないことを確認。
更に秘密の部屋に足を踏み入れた。
この部屋での行動は王子やナイトには気づかれてはいけない。
そんな風にエルカは考えている。
何だか、悪いことをしているような気がして、足を踏み出すたびに鼓動が跳ねる。
目的のテーブルまで辿り着いてから深呼吸をした。ここまでこれば、もう大丈夫だというのに、ページを開くまで緊張の糸を張り巡らす。
本を手に取って、パラパラと適当なページを開く。文字なんて見えないのだから、ページは何処でも良いはずだ。



(ソル、お願いだから気づいて……)


チリン
期待をこめて鈴を鳴らした。
その音は小さくて儚くて頼りない。
本当に、この音がソルに届くのだろうか。
二人は仲が良かったわけではない。
むしろ、エルカはソルが怖かった。
だけど、今は違っていた。
彼の声が聞きたかった。
早く、聞きたかった。
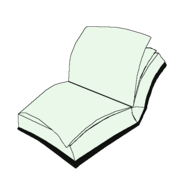



ソル?





………………ああ





よかった! 気付いてくれて、ありがとう





………………そんなことで、礼を言うなよ


声が返って来た。
ただ、それだけなのに嬉しく思う。
だけど、違和感を抱く。
返って来たソルの声には覇気がなかった。
返事をすることが面倒なのかもしれないが、元気がないように感じられた。
眉根を寄せて、本のページを撫でていた。
そうすることに意味はあまりないけど、そうしたかったのだ。



………どうしたの? 元気ないけど、何かあった?





あ、何でもないよ。そっちは進展あったか?





うん、王子にプリンを食べさせたら、凄く喜んだよ。物語は進んでいる





……そっか





でも、この先は思い出せないの。これは、きっとハジマリでしかないから。プリンを食べて笑顔になった。それで終わりってわけじゃない。現に私たちの状況は変わらないから……


エルカは本を抱きしめていた。
壁に背を当てて、そのままストンと床にしゃがみ込むと、抱きしめた本に額を押し付けた。
物語は進んでいる。順調に事は運んでいるはずなのに、言いようのない不安に襲われる。
思い出せないのが怖かった。
同時に思い出すことも怖くなる。
エルカが物語を思い出せば、過去のことも思い出してしまう気がする。
それは、見たくないものが見えてくるということ。
前向きになろうとしても、心の不安は深まるばかりだ。
正しいことをやっているはずなのに、胸の奥に痛みを覚える。



…………喜んだ王子は、それでどうしたんだ?





え?


エルカが黙り込んでしまったからだろうか、突然ソルが問いかける。
目の前にいないのに、口を結んで視線を横に反らしながら話す、彼の姿が想像できた。
戸惑うエルカに彼は言葉続きを口にする。



プリン王子は満足しなかったんだろ?





そうだね、喜んで笑顔になった……でも、これだけじゃダメだった。だから、どうしたんだろう……





………お前ってさ、食べなかったよな





ん?





昔の話だよ





え?


ソルの方から話を切り出すとは思わなかった。
だから、エルカは目を見開いて本を凝視する。別に彼の顔がそこにあるわけではないのに。
少し照れたような彼の横顔が浮かんだような気がした。



ガキの頃、おやつに食べてたプリン。全部、オレに渡していたよな





…………うん


それはプリンをソルにあげないと怒るからだ。
逆にプリンをあげれば、怒らなかった。だから、エルカのプリンはいつも彼にあげていた。
彼を笑顔にするために。その為なら、自分がプリンを食べれなくても構わなかった。
エルカが我慢するだけで、少しだけでも穏やかになるのなら。



オレが欲しがるからだったよな。あの時は悪かった





それは……気にしてないよ。私がやりたくて、やっていたのだから





だけどさ…………一度だけ……一緒に食べたよな





……………ああ、そうだったね





……………あれが、さ…………





ソル?


ソルの様子がおかしい。
言いたくないことを口にするような、そんな雰囲気が伝わってくる。
周囲の空気が震えている。
風もないのに、冷たい風が頬を撫でるのを感じた。
そして、意を決したように彼は告げる。



…………あの……プリンが…………一番美味しかった気がするんだ





…………だって、あれは、ソルが作ったんだから…………


エルカは思い出した。
欠けていたパズルのピースがピタリと嵌め込まれた気持ちになる。
なぜ忘れていたのだろうかと、エルカは苦笑を浮かべる。
あんな衝撃的な出来事は忘れられないのに。
兄や祖父ではなく、ソルがプリンを作ったことがあったのだ。
正確にはエルカとソル、二人で作った。
その、たった一度きりの思い出がよみがえる。あの日のプリンはエルカも食べている。
とても美味しかったという記憶も思い出している。ただ、それだけではなかった。
見なくていい、見せなくていい。
耳を覆っても、目を閉ざしても無理だった。
その思い出はエルカの目の前に突きつけられる。

