この世界は不公平
不条理で優しくない世界
こんな世界から逃げたかった
この世界は不公平
不条理で優しくない世界
こんな世界から逃げたかった
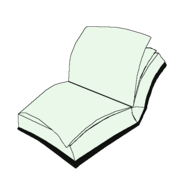
小さな日記帳に、わたしはそんな言葉を書き連ねる。
それは、どこにも届かないわたしの心の闇。
声に出して訴えることが出来ない臆病なわたしは、日記帳にペンを走らせて、歪んだ心を吐き出す。
日記帳は鍵をかけて、机の中に押し込むから誰の目にも止まらないの。
誰も知らない、わたしの闇。
第1幕
少女の物語
prologue
真っ暗な廊下に、わたしはいた。
わたしは息を殺して、足音を立てないように歩いていた。
自分の小さな身体を抱きしめるように、歩き続けていた。



………



これは風が窓を叩く音。
そう理解していても、反射的にビクリと身体が震える。
もしかすると、これは風の音ではないのかもしれない。
何者かが中に入ろうと、乱暴に窓を叩く音なのかもしれない。
その窓から見える空は、闇色に染まっていた。
なんて、不気味な色だろう。
そういえば、嵐が近付いているのだっけ。
誰かがそんな噂話をしていたことを思い出す。
隙間風がビュービューと家の中に入り込む。
これは、隙間風なんかじゃなくて、何者かが侵入する音なのかもしれない。
わたしの脳裏に浮かんだのは黒い影。
その何者かは窓の隙間から侵入してきた。
そして、家中の空気と一体化すると、私の周囲を急激に冷やす。
月が厚い雲に隠されていて、空は闇の色を深くする。




………っ


ああ、窓が割れるのではないだろうか。
そう思うと、恐怖心が全身に走った。
この窓が割れて、ガラスが飛び散ったら……きっと痛いだろう。
わたしはその痛みを想像する。
パラパラと舞い散るガラスの破片が、己に降りかかる様子を想像する。
それは痛いだけでは済まされない、赤い血が飛び散りそうだ。
自分の部屋に引き返そうかと考えて……首を横に振る。
戻るということは、同じ道を引き返すということ。
同じ恐怖をまた味わうのだ。
それでは、何も変わらない。
ギュッと唇を噛みしめて、小さな歩幅で前に踏み出す。
ようやく辿り着いた扉の前で、わたしは安堵のため息を零した。
傷とシミだらけのボロボロの古い扉。
それが、とても頼もしくも思えた。
わたしは小さな手を握りしめて、控えめに扉を叩く。
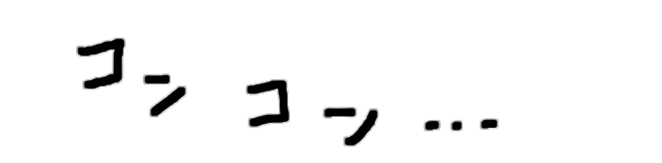
程なくして、鈍い音と共に扉が開かれた。
眩い光が視界一杯に広がり、目を細める。
扉の隙間から微笑んだのは初老の男。
わたしのお爺様だった。



おや、エルカ


お爺様の穏やかな声で名前を呼ばれる。ただそれだけで、今までの恐怖心が一瞬にして消え去ってしまったみたいだ。
わたしは、満面の笑みを彼に向けた。



こんばんは、お爺様





こんな夜更けにどうしたんだい?





本が読みたいの





嵐が怖いのかい?





うん。怖いから、本を読んで欲しいな





やれやれ……仕方ないなぁ。おや? カンテラも持たずに来たのかい


わたしは、こんな真夜中に手元を照らすカンテラを持たずに来たのだ。
呆れ顔のお爺様に、わたしは胸を張って説明する。これには、ちゃんとした理由があるのだから。



カンテラなんて持っていたら、魔王に見つかってしまうの。ロウソクの炎に色んなモノが集まってしまうの。とても悪い何かが。





ほら、お爺様の部屋の灯だって危ないわ。扉を開いたままだと魔王に見つかってしまうのよ





それは大変だな。散らかっているけれど、おいで


招き入れられた部屋。そこは彼の書斎であった。
書斎というよりも、書庫と読んだ方が正しいのかもしれない。わたしは、地下書庫と読んでいた。
壁一面に本棚が並び、隙間なく本が詰め込まれている。机の上にも本が積み重ねられている。
机の下にも、棚があって本が並んである。ベッドがあった場所も本が散乱していている。だから寝床になっているのはソファーだった。でも、そのソファーにも本が置かれていた。
どれもこれも古い本で、わたしには読めないものもあった。文字のようなデザインのような、よくわからないものが描かれている。
わたしは、この書斎なのか書庫なのか分からない、お爺様の部屋が大好きだった。
紙やインクの匂いは心を安らかにしてくれるのだから。
椅子に身を委ねているお爺様の膝の上。
そこが、わたしの定位置だった。




子供は眠らないといけない時間だというのに、困った子だな





だって、眠れないの





何かあったのかい?


お爺様は魔法使い。
だから、わたしが何も言わなくても分かるのだ。わたしが、心の中に不安を抱いていることなんかお見通し。
お爺様は膝の上に座ったわたしのエメラルド色の髪を撫でまわしながら尋ねる。
数年前に出ていった母親譲りの繊細な髪は、お爺様は好きらしいけど、わたしは好きじゃない。
わたしは記憶を呼び起こしながら説明をした。



お昼ぐらいだったかな……家の前を歩いている人たちが、この家には魔王が住んでいるって言っていたの


古い屋敷で、至るところには蜘蛛の巣。雑草は生え放題。玄関先にはゴミが散らかっている。
到底、人が住んでいるような雰囲気は、この家にはなかった。
街の住人なら、ここに誰かが住んでいることは知っている。だから噂話は外部の人間のものだろう。

ここには、心霊スポットのような感覚で訪れる者も少なくはなかった。
彼らは住人がいる屋敷の前で話をしていた。
住人がいるとは思っていないのだ。
隙間だらけの家の中には外の会話が良く聞こえてくる。
だから聞きたくもないような下賎な話が耳に入る。
わたしにとって、それは怖い話だった。
自分が住む屋敷に見知らぬ何者かが住んでいる、そんなことを言われたのだから。




魔王? おお……じじぃは魔王だったのか……知らなかったなぁ





違うよ、お爺様は魔王じゃないよ。だから、私が知らないだけで、魔王が住んでいるかもしれないの。





一人で寝ていたら食べられちゃうかもしれない。この嵐だって、魔王が呼んだのかもしれない


この嵐を呼んだ魔王が、わたしを恐怖で追い詰めて食べてしまうのだ。
そういえば、子供の方が美味しいのだっけ?、絵本の中の魔王はそう言っていた。



魔王などおらんよ。この屋敷の主であるじじぃが断言する





だけど、冷たい空気と一緒に家の中に何かが入って来たわ。きっと、魔王の部下なの





家の中に入って来たそいつは、エルカに何もしていないだろ?





うん





そいつはなぁ……じじぃの結界魔法で消えてなくなったのだよ





すごいわ!


わたしは目を見開いてお爺様を見上げた。
彼は胸を張って、ドヤ顔で続ける。



じじぃの魔法がこの屋敷を守っている。だから魔王も魔王の部下も入ってはこれないから、安心なさい





………本当に?





本当だ……いいかい? 噂話に耳を傾けてはいけないよ





どうして?





噂話は真実ではないからだ。真実は違うだろ? ここに住んでいるのは、じじぃとその家族だ





うん……





噂話に耳を傾けても、不安になるだけだ





不安って、怖いことだよね。怖いのは嫌だよ





そうだな。だから、耳を傾けないように





……うん



お爺様の大きな手がわたしのの耳を塞ぐ。
わたしは目と耳をギュッと閉じる。

風が窓を叩く音が遠くで聞こえていた。
ここは地下だから窓なんてなかった。
それなのに、聞こえてくる。
やっぱり、魔王がそこまで来ているのかもしれない。
お爺様には大丈夫だと言われたが……
それでもわたしは彼の腕にしがみ付いていた。しだいに、瞼が重くなる。とろけるような意識の中、お爺様が呟いていた。



エルカ、人はいつか【本】になるのだよ





(…………え?)


わたしは、お爺様にそれはどういうことなのか、尋ねることが出来なかった。
すぐそばにいるのに、遠くに聞こえるお爺様の声。それに、耳を傾ける。
激しい睡魔が押し寄せてくるけど、お爺様が何かを伝えている間は眠りたくなかった。



その本は、この世とあの世の狭間にある巨大な図書館に納められるのだよ。人の人生は様々だ。十人十色の物語がそこにある





(何て素敵なの! わたし、いつか絶対にその図書館に行こうと思うの)


この言葉はお爺様に届いただろうか。



(図書館に着いたら初めにお爺様の本を探そうと思うのよ。だって、お爺様の本を読めば寂しくないのだから)


そして、わたしの意識はまどろみに沈んでいった。



……夢、か


瞬きをしながら身を起こす私は、もう幼い女の子ではなかった。
本を読んでいるうちに、いつの間にかソファーで眠っていたらしい。
開いたままの本が、サイドテーブルに置かれていた。
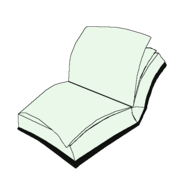
読書に没頭して現実逃避をしたまま眠ってしまうのは私の日常だった。
物語の非現実的な世界は私を傷つけない。
物語の登場人物たちは与えられた運命に向かって流れていくだけで、私に危害を加えることはないのだから。
私は、その世界を空の上から見守る。
読み手は見守るだけで、何もしない。
登場人物が死のうが生きようが、その顛末を見守るだけ。
その末路に泣いたり、笑ったり、呆れたり……そうやって、他人の人生を傍観していた。
祖父の地下書庫には、大量の本が収められている。
埃がかぶった本を開いて、私はその世界観に浸っていた。
私は着替えを済ませると、鏡を見ながら淡いエメラルド色の髪を両サイドに結い上げる。
昔は嫌いだったこの髪も、今は嫌いではない。
外出なんてしないけれど、身だしなみだけは整えたかった。



さて、今日はどれを読もうかな?


私は書棚を見渡す。
ここには古い物語も新しい物語もある。
生きている内に、これを読み切ることが出来たら素晴らしいだろう。
適当に取り出した一冊を手に、再びソファーに身体を預ける。

大きな音に私は眉を寄せた。
これは何処かで風が窓を叩いている音だ。
物心つく頃には壊れかけていた窓。
そのうち壊れるだろうと思っていたが、まだ現役だ。
なかなか、しぶとい……私はそう思いながら本に目を落とす。

この地下にまで聞こえてくるのは厄介だと思った。
読書に集中できなかった。
だからと言って新しい窓を取り付ける余裕なんか、この家にはないのだ。
大きな屋敷ではあるが、生活は苦しい。
出来れば、もう暫くは壊れないで欲しいと私は願う。

数年前までは、これが魔王が窓を叩く音だと思っていた。
少しばかり恥ずかしい話である。
今でも、この音は嫌いだった。
何か恐怖心を掻き立てる音だ。
私は読んでいた本を閉じ、ワインレッドの瞳を細める。
視線の先……木製の椅子に座っていた主は、もう何処にもいない。
怖がる私を優しく包んでくれた祖父は、ここにはいなかった。
二年前に遠い空に旅立ってしまったのだから。

