広げた新聞を意味もなく眺めながら、野口は呟いた。
くわえた駄菓子が唇の動きに合わせて、ぐらぐらと揺れる。
そのまま、こぼれそうになった欠伸を噛み殺そうとして、ふいに野口は刺さるような視線を感じた。



世を儚む作家の飛び降り、ね。
まあ、聞かない話じゃあないが


広げた新聞を意味もなく眺めながら、野口は呟いた。
くわえた駄菓子が唇の動きに合わせて、ぐらぐらと揺れる。
そのまま、こぼれそうになった欠伸を噛み殺そうとして、ふいに野口は刺さるような視線を感じた。



先生をそこらの奴と一緒くたにしないでくれる


冷え冷えとした声に顔をあげれば、すがめられた金色の瞳が鋭い光を放っている。
唾液を吸ってもろくなっていた菓子が、ぼきりと折れた。
思わず、何度か目をしばたいてしまう。



意外だな。
もう少しは冗談の通じる奴かと思ってたんだが





へえ、冗談か


寝室へ続くドアに背を預けたまま、微動だにすることなく、男は言った。



不謹慎だと言われないかい?





さてねえ、どうだったか


にやりと笑い、軽く挑発をしてみる。
すると、おもしろいくらいに男の顔が歪んだ。
どうやら、本当にこの男は「あれ」に弱いらしい。
眉間に寄った深いしわを見て、野口はくつくつと喉を鳴らした。
その男は常人離れした身体能力を持ち、耳を通さずに相手に意思を伝える――いわば、テレパシーのような、奇妙な力を持っている。
駅前で女子高生と話しているところを何度か目撃されており、名前は「カヲル」というらしい――
目撃情報にあった女子高生から話を聞くまで、野口は男について、それ以上のことを知らなかった。
仕事で使うありとあらゆる伝手でも、このカヲルという男に関する情報は得られなかった。
もっとも、女子高生のほうも、多くの情報を持っていたわけではない。
短いやりとりの中でわかったのは、カヲルが「都々楽ツユリ」を探しているということだけだった。
これに、野口が違和感を覚えなかったわけではない。
しかし、野口は女子高生――佐倉ゆかりに、ひとつの頼みごとをしたのである。



もし偶然にも、そいつとまた会うことがあったら、今度ある都々楽ツユリのサイン会に誘ってみちゃくれないか


半ば、賭けのようなものだった。
上手くいくという保証など、どこにもなかった。
けれど、野口が目をつけた少女は、見事なダークホースだった。



彼に、会いました


電話口に、そう報せてきた佐倉ゆかりの声は、かすかにふるえていた。
それを訝しく思えど、野口は追求をしなかった。
努めて明るい普段の態度で応対し、電話を切った。
そうして、会場であるショッピングモールへと向かい、再びカヲルと相見えたのである。
――もっとも、その再会の場には、想定外の真実が横たわっていたのだが。



で?





お前さんの『先生』とやらの容態はどうなんだ?


デスクに新聞を放り投げ、回転椅子ごとカヲルに向き直る。



あんたも探偵なら、
俺がここにいる時点でわかるだろ





そりゃ、推測ならいくらでもできるさ。
それこそ、何千何万通りのね。
だが、それだけじゃあ意味がない





――それくらいわかるだろ?


頬杖をついて、にんまりと笑う。
とたん、舌打ちが返った。



……峠は越えた。
もう命に別状はないよ





へえ、大したもんだな。
あんな悲惨な――





…………





おおっと、そんな恐い顔するなよ。
生きてるんだから別にいいだろうが





俺は生きた心地がしないね


ため息とともに金色の目を伏せ、カヲルは背を浮かせた。
それまで、決して動こうとしなかったドアの前から離れ、その足は玄関へと向かう。
野口は片眉をあげた。



なんだ。どこか行くのか





やかましい口のないところに





言うねえ。
大事な大事な『先生』をほっぽってっていいのかい?





何かあったら、
あんたの臓器を移植するさ


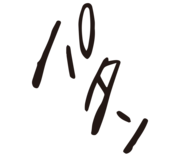
それは、「あれ」に妙な真似をしたら生かしてはおかないという脅しなのか。
はたまた、散々からかった野口へ対する仕返しだったのか。
カヲルの姿が宵闇に消えた今となっては、野口があずかり知ることではない。
けれど、背筋には自然と冷や汗が伝っていた。



まあ、僕も死人を出したいわけじゃないからねえ……


駄菓子の入った箱を作務衣のポケットに押しこみ、野口は寝室へと向かう。
そうして、ノブをひねってドアを開けた瞬間。
ベッドの上の人物と目が合った。



え


互いに目を丸くして硬直すること、しばし。
いち早く我に返った少女が、あわてたようすで、はだけたシャツの前を掻き合わせた。
これに野口はさらに目を丸くし、それから、ふきだすようにして笑った。



はっはっはっはっは!





まあ、お嬢さん。
そうあわてなさんな――僕は女だ





は?


そう間抜けな声を発して、少女――佐倉ゆかりは固まったのである。
