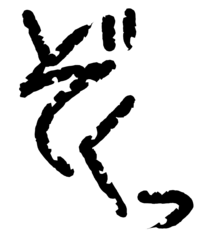ゆかりは、死んだはずだった。
立体駐車場の屋上から落ち、アスファルトに叩きつけられ、そうして「あれ」が望むように命を落としたはずだった。
屋上から地面までの高さを考えたのなら、ほぼ即死。
生存確率は、絶望的だった。
だのに、目覚めたとき、ゆかりがいたのは、私立探偵である野口有紀の自宅兼事務所だった。
彼――否、彼女というべきか。
野口は、目覚めたゆかりに対して、何も言わなかった。
好物だという棒状の駄菓子を始終くわえたままで、彼女が口にしたことといえば、自分が女であるということと、ゆかりが未だ息をしてそこにいる理由と――身に覚えのない事実だけ。