タラトは口元の血を大雑把にリストバンドで拭く。舌を口元の傷に這わせ、鉄分の味を吟味したように見える。シャセツの攻撃に驚いたらしく、拳を握りこまない平拳や掌底を自分の手で作っている。
タラトは口元の血を大雑把にリストバンドで拭く。舌を口元の傷に這わせ、鉄分の味を吟味したように見える。シャセツの攻撃に驚いたらしく、拳を握りこまない平拳や掌底を自分の手で作っている。
そんなタラトにシャセツは正対する。表情は至って冷静だが、どこかイラつきが見える。連撃を受け、傷を負えども、平気に立ち上がってきたタラトが気に入らないのだ。



素直に寝ていれば良いものを。





お、まえ……つおい。





ジジイとは俺がやる。
貴様は今度にしろ。





オレ……
つおいな、な……いい。


片言ながら、タラトの言葉は伝わってくる。タラトは強い相手と戦いたいだけ。それが場長とは違う強い者でも何の問題もないのだ。純粋な戦いの欲求であり、他の余計な感情は一切見受けられない。
場長への挑戦者がいると集まってきた野次馬達だったが、相対した二人を中心に盛り上がっている。誰もが強者の戦いを目の当たりにしたいと、目が釘付けの状態だ。
歓声を割るように動いたのはシャセツ。あっという間に距離を詰めて上下に打ち分ける連打。タラトが拳を振り回した時には、既に離れて届かない位置に移動している。



ガァッ!


空を切るタラトの攻撃は、当たれば無事では済まない勢いだ。その間にも、シャセツの攻撃は止まらなかった。



遅い!


タラトの反撃に合わせたシャセツの攻撃は、タラトの視力を一時的に奪う手刀だった。



ゥグッ!


流石のタラトも、慣れない刺激で顔を天に向ける。その瞬間、シャセツはタラトの背後に回り込み、隙だらけの後頭部に大振りの手刀を振りかぶる!



な、に……!?


シャセツの腹部には、タラトの平拳が刺さっていた。
シャセツの腹部に痛覚が走る。息が止まる箇所への打撃。これは先程シャセツがタラトに繰り出した攻撃。ここまで繊細な攻撃をしてくるなんて、シャセツは想定していなかった。それに何故、視覚を奪われた状態で自分の攻撃が分かったのか?
シャセツの顎をとらえたのは、タラトの掌底。まさにシャセツが使用した連撃を、タラトがすぐにやってのけたのだ。



い、ぎ……ぐぃぃ……


しかしタラトは初めて使った掌底に慣れずに、当て所が悪く手首を痛めてしまった。



くっ、っつぅ……
小癪な。


当たり損ないだったとしても、がら空きの顎に打ち付けられたダメージは重く、シャセツの足元はフラフラになっている。



おーおー、やっぱり
学習能力はピカイチじゃのう。
それに鼻も効く。


場長の言葉から察するに、『勘違い』と言っていたのは、タラトの学習能力のことだろう。



見とったらこっちまで
うずうずしてきたけぇ。


肩をぐるぐる回して参戦の意志を表す場長。最高潮に賑わう野次馬達。ハルは更にもみくちゃにされているが、徐々に前列に進んでいる。



ジジイ……
初めからそう言え!


即座に場長との距離を詰めるシャセツ。悠然と立つ場長に下段回し蹴りを放つ。が、それはフェイントで、場長の懐に踏み込むものだった。その右足を軸足にして、逆の脚での膝蹴り。場長の腹部に直撃。すかさず斜め上からの右肘を顔面に落とす。返す外から巻き込むような左掌底も顔面。続いて左上段蹴りも頭部に直撃した。



ほんまわやするけぇ。





ジジイ、くたばれ!





場長の胸板にシャセツの後ろ蹴りがめり込んだ。鋭く重いその攻撃からは、手加減などという言葉は見受けられない。



ほんま元気じゃのう。


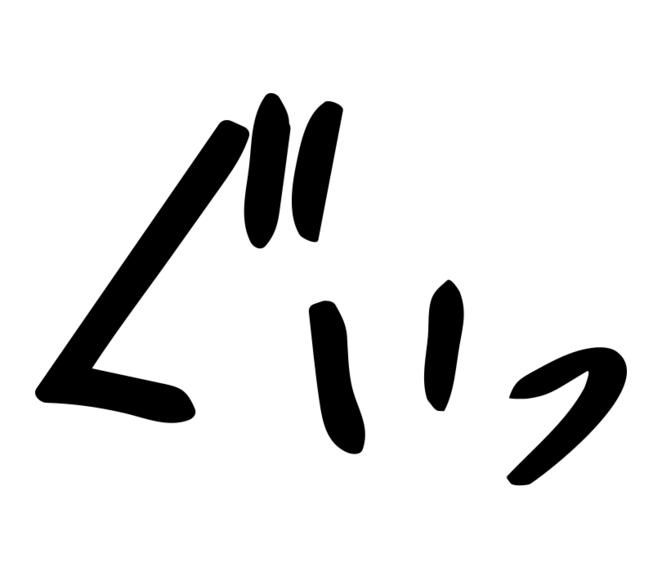
シャセツの足首は掴まれていた。
そして抗うシャセツを嘲笑うように粗雑にぶん投げる。



ぷっはぁ~、
やっと前列にこれたっ……
すびゃぁあーー!!





なななな、何すか、一体?


シャセツの投げられた先にハルが居て、巻き込んで倒れる。他の野次馬訓練生も巻き添えになっている。
ふと場長の方に目をやると、タラトの胸板に正拳突きを繰り出していた。



ぷぎゃあーー!!





ぐっ、何で貴様まで
飛んでくる。


タラトまでぶっ飛ばされ、更に野次馬達を巻き込み倒れる。後ろに居たメナとエノクの視界が一気に広がった。



やっぱりワシが一番強いのぉ。






いい加減にして下さい。





げ!!


声の主はリーベだった。エノクとメナの後方から、場長に冷たい視線を送っている。



場長。
この訓練場のルール。
ご存知ですよね。


いつも通りの冷静な口ぶり。しかし、底辺にある怒気が滲み出ているように見える。




な、何だったかのぉ?





訓練中その他の時間含めて
無関係な訓練生に
迷惑を掛けないことです。





そーそー、
そーゆールールじゃ。





貴方が暴れ回るから
新設されたルールですよ。





あ!
ほうじゃった。
今日は特別メニューの料理が……


場長は一人小芝居の後、逃げるように場を去っていった。
リーベは逃げる場長の背中に声を飛ばす。どこか二人の関係が近しく思える。リーベの神秘的な雰囲気の下地にある、人間的な部分が垣間見えたような光景だった。


