晴紘は呼び鈴を押した。
記憶のままの硬い感触。
記憶のままの硬い音。
知らないで終わるはずのものが
記憶にあるというのも
おかしなことだ。
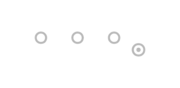
しかし返事は返ってこない。



さて、どうしたものか


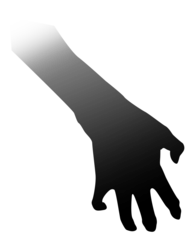

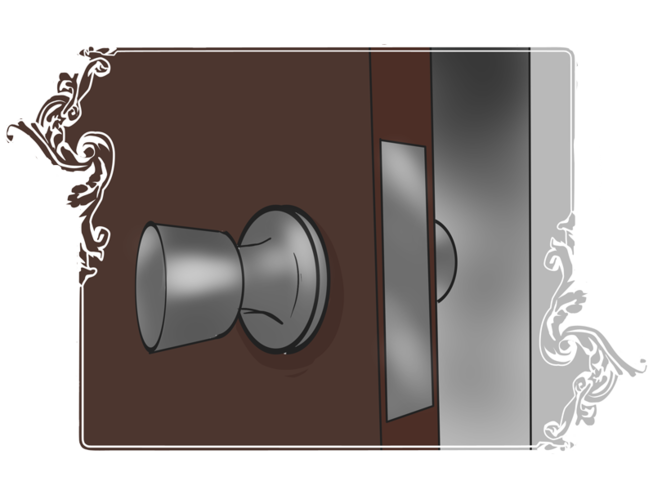
ドアノブを回すと扉が開いた。
鍵はかかっていなかったらしい。




こういうところだけは同じなんだな


有難いが、
不用心さに頭を抱えたくなる。
が、そうも言っていられない。
晴紘は
扉の先へ足を踏み入れた。
扉の先にあったのは
これまた見慣れた廊下。
廊下の右扉は居間、
左扉は食堂、
真っ直ぐ行けば灯里の工房、
階段を上がれば晴紘の部屋、
そんな見取り図まで
しっかり頭の中に入っている。
いつもなら
紫季が眉間に皺を寄せつつも
出迎えてくれるのだが
今は、人の気配はない。



ただいまって言うのも、おかしいよな


ここに住んでいるのが
灯里や紫季ならまだいい。
しかし違ったら。
住んでいるのが面識のない
「灯里の父親」だったなら
どう言い訳をすればいいのだろう。



自分の家と間違えた、なんて通用するはずがないし


それに
父親と母親が健在ということは
この世界の灯里はまだ子供。
晴紘の同級生ではないどころか
面識もない。
いくら未来の級友だと言ったって
そんなもの誰が信じるものか。
黙って入れば不法侵入。
でも



どうせ鐘が鳴るまでのことだ


別の十一月六日に飛ばされることを
悪用している気がしなくもないが



戻りたいのでしょう?


