懐かしい香りで大翔は目を覚ました。いや、正確に言えば眠りに落ちたのだが。チョークの粉が舞っている粉っぽい空気。清潔とはいいがたい共同空間でありながら、どこか落ち着く心地がする。
懐かしい香りで大翔は目を覚ました。いや、正確に言えば眠りに落ちたのだが。チョークの粉が舞っている粉っぽい空気。清潔とはいいがたい共同空間でありながら、どこか落ち着く心地がする。



また中学校か


大翔は教師になったかのように教壇に両手をついて立っていた。しかし誰かに教えられることなど何もない。それを証明するかのように後ろにある黒板にはバツ印の代わりに十字に亀裂が入っていた。
学級崩壊と呼ぶにはあまりにも物理的過ぎる教室内は昨夜見た景色とたいして変わることなく、物が散乱していて外へ出るにも一苦労ありそうだ。
とりあえず床が見えるところを踏んでなんとか扉まで辿り着く。途中で折れてしまった机の足を手にとり、しっかりと握った。
まずはこれで不意打ちの一撃。今までならば頼りなさ過ぎると思っていたが、今夜は別だ。少しでもひるめばその隙に触角をへし折る。その隙さえできてくれればいいというのなら、小回りが利いて取り回しいのいい武器が役に立つ。一人ではかなり不安があるが、なんとかなるはずだ。
軋む扉は大翔を外に出すのを嫌がるように固く開くことを拒んでいた。音が鳴ればカベサーダを引き寄せることになるが、今なら少しくらいは気持ちに余裕があった。



おりゃあ!



気合も上乗せして重い扉をこじ開ける。歪んだ扉はレールと擦れて野生動物の断末魔のような声を上げた。
甲高い音が誰もいない廊下に響く。それが開始の合図のように爪が床を叩く音が聞こえた。



いきなり来たか


昨日までなら息を潜め、物陰に隠れ、こちらにこないでくれと願うことしかできなかった相手。だが、今は違う。手に持った武器と冷静な行動さえできれば戦えない相手ではないはずだ。大翔は手に握った中空の軽いパイプを確認して、廊下に顔を出した。
全てがうかつな行動に見える。実際に大翔のやっていることは異常だと言えた。心臓を突き刺せばライオンも死ぬと知っていたところで、わざわざ野生のライオンとケンカしにいく人間などまずいない。



逃げるに越したことはないんだけどな


言葉ではそう言いながら、大翔は腹の底からふつふつと湧き上がってくる感情に身を任せている。
まだカベサーダの姿は見えない。誰かと合流してから相手をしたほうが安全なことは大翔にもわかっていた。ただ大翔にもやりきれない思いはある。多くの人間を見捨ててここまで生き残ってきたという思いは、敵を討つ理由には十分すぎた。目の前にありながら拾い上げることのできなかった命さえある。
開いた扉の隙間から体をすり抜けさせ、教室内と同じく物が散らかった廊下に出る。教科書を蹴り飛ばし、戦えるだけのスペースを作る。



来いよ。やってやる


自分自身を奮い立たせるように大翔は呟いた。
乃愛のように格闘の心得があるわけでもなければ、尊臣のように優れた体格を持つわけでもない。光のように頭も回らない。ただ大翔にあるのは衛士や顔も名前も知らない誰かを見捨てたという自己嫌悪だけだ。
背中の方で爪の音が響く。大翔はすぐさまその音の方へと振り返った。



来たか?



カベサーダは大翔の方に向かってまっすぐ全力で走りこんでくる。床に散らばったものが激しい走りに巻き込まれて方々へと散っていった。



だりゃあああ!


走りこんでくるカベサーダの頭に向かって持っていたパイプを叩きつけた。大きく突き出た額を打ったが、あまり効果はないらしく、カベサーダは構わず大翔に飛びかかろうとする。



ちっ、なら!


早くも少し曲がってしまったパイプをカベサーダの触角に向けて大きく横に薙ぐ。
カベサーダは頭を低く落として、大翔の一撃を避けた。
そう、避けたのだ。
今までどんな攻撃にもプロレスのように避けなかったカベサーダが、大翔の一閃を嫌って身を翻したのだ。その事実が大翔の頭にどれほどの興奮を与えるだろうか。
殺せる。
自分が目の前の敵より上に立った瞬間。全身をアドレナリンが高速で巡っていく。目が血走り、全身が血の赤色に染まってきていることを大翔はまったく気がつかない。
その結論を胸に抱いて、大翔はカベサーダの触手に手を伸ばした。
脳内麻薬に犯された体は羽のように軽い。頭を下げたカベサーダの触角に指をかけると、折り取るように手首を返した。




どうだ?


この世界でヒーローになれるかもしれないという高揚感が大翔を包んでいた。欲しいのは名声ではない。ただ自分以外の誰も傷つかないで済むかもしれないという期待があった。
カベサーダは声を上げることはなかった。人が苦しむようなうめき声も悲鳴のような叫びもしなかった。ただ無言のままふらふらと数歩歩いた後、操り人形の糸が切れるようにその場に倒れて動かなくなった。
それが大翔には逆に不気味だった。
仇討ちのつもりで戦ったはずなのに、まるでただ道具を壊しただけのような感覚。物足りないなどと言うつもりはないが、あまりのあっけなさと自分の高揚感の落差に大翔は折った触角を倒れたカベサーダの上に投げ捨てた。
倒した、という慢心が警戒心を鈍らせる。
倒れた亡骸を見下ろしていた大翔の前からもう一匹。仲間が殺されたことに怒っているのか、それともただ本能のままに獲物を捉えたと思っているのか。やはり大翔に向かって猛然と飛びかかってくる。
咄嗟に手元の曲がったパイプを振り回すが、緩く握ったパイプは遠心力に引かれて大翔の手元からするりと逃げていった。勢いのまま振るった拳がカベサーダの顔に当たって大翔の拳に鈍痛が走った。こんなに固かったのかと冷静さを取り戻してきた頭から痛みを排除しようとするが、我慢でなんとかなるものでもない。コンクリートの柱でも殴ったような痛みだ。
体を強張らせた大翔にもカベサーダは容赦などしてくれるはずもない。強引な接近を簡単に許してしまった大翔はやすやすと両肩を掴まれて、事切れたカベサーダの隣に並ぶように大翔の体が廊下に押し付けられた。




まだ


既に弱点はわかっている。首筋に噛み付こうと顔を近づければ、その瞬間にその触角を折ってやればいい。
自分の左腕を伸ばそうとして、大翔の肩に鋭い痛みが走った。
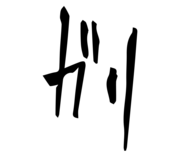



くそっ。だからこいつら、こうやって


両肩を掴むカベサーダの両腕。爪がじりじりと大翔の肩に傷をつけていく。肩の付け根を押さえられては腕が満足に動かない。



何も考えてなさそうなクセして


なんとか片腕でも伸ばせれば、と大翔は必死に身をよじる。
そこに今度は乾いた足音が駆け寄ってきた。
