大きなため息をつく少女の名は日輪 みう。近隣の小学校に通う十歳の女の子である。
彼女はいま憂鬱であった。望まぬ労働を強いられているからだ。
本来ならば、今頃録画していたアニメ『プリティドラゴン』を見ている筈だったのだが、母親である日輪 綾に見つかったことが運の尽き。
母曰く、



はぁ~……せっかくの日曜日なのにすっごく憂鬱だよぅ……


大きなため息をつく少女の名は日輪 みう。近隣の小学校に通う十歳の女の子である。
彼女はいま憂鬱であった。望まぬ労働を強いられているからだ。
本来ならば、今頃録画していたアニメ『プリティドラゴン』を見ている筈だったのだが、母親である日輪 綾に見つかったことが運の尽き。
母曰く、



みう? あんた今日暇でしょう?
だったら裏の物置小屋の掃除してきなさいよ。あとでパパも手伝いに来るから


とのことである。
一見、当たり前に見えるかもしれないが、これは日輪家における絶対命令である。仮に言いつけを聞かなかった暁には脳天に拳骨が飛び、嵐のようなお説教が一時間は続く。



怒ったママは怖いけど、できることをやったら褒めてくれるし、お小遣いとかくれるし……
できないようなことは絶対に言わない……よね?


語尾に自信がない。
それもそのはず。日輪家の物置小屋は自分の個室よりも広い木造の庭小屋であり、重たいバイクの部品やよくわからない鎖など、危険なものが所狭しと詰められている。
十歳の女の子一人に任せるにはやや危険な場所である。



やっぱり無理だよぅ……


みうは弱音を吐いてしまう。それでもなお、自分にできる範囲のことを探し始めた。
やらなかった時の罰が怖いからだ。
まずは安全に掃除ができるよう、小さい物、軽い物を選んで小屋の外に出した。
次に、自分の持ち運べる範囲で重たい物を頑張って運んだ。
重い物は埃っぽくて油臭い物が多く、必然的に手のひらが真っ黒になる。
汚くて、大変で、全く楽しくない。



ああん! もう! 臭くて汚くて重い! こんなのやりたくないよぅ!
こんな時に『レオ』みたいに魔法が使えたら良いのになぁ……


彼女の言う『レオ』とは、アニメ『プリティ・ドラゴン』に登場するヒロインである。勇敢で優しく、どんな悪にも恐れずに立ち向かう魔法使いの女の子。彼女が大好きなキャラクターである。
もしも大好きな『レオ』と同じ魔法が使えたら、きっと掃除も楽にできるのに……。
あまり有意義とは言えない妄想であったが、そうした愚痴でも言わないと、まともにやってられなかった。



……ラジカル・パレッタ・マッサクゥルゥ~♪
次はこれ…かな?


アニメでお馴染みの魔法の呪文を唱えながら仕事をしているうちに、みうは奇妙な物体を見つけた。
それは鎖でがんじがらめにされた木造の箱だった。蛍光灯が三本は入りそうな大きさであり、何やら物々しい模様が描かれている。



ママが暴走族やってたっていうときに使ってたものかな?
何が入っているんだろう?


みうは箱を手に取った。
次の瞬間、
ガタガタガタガタガタッ!
ガタガタガタガタガタッ!
箱は激しく振動したのだ。



きゃあっ!


予想だにしていなかった出来事に、みうは思わず手を離し、箱を放り投げてしまう。
箱は床に落ちてなお振動を続けた。
ガタガタガタガタガタッ!
ガタガタガタガタガタッ!
箱は間隔をあけて止まり、止まっては動いた。
不規則な動きをする奇怪な箱に、みうは思考が困難になる程の恐怖を覚えた。



なによ……これ……?


ガタガタガタガタガタッ!
ガタガタガタガタガタ……
ガタガタ……ガタガタ……
やがて、激しかった振動は徐々に弱くなっていき、数十秒後には箱は完全に沈黙した。
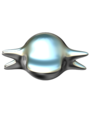


……ここは、どこだ?
綾、君が近くにいるのか?
頼む、俺の声に応えてくれ!





ひ……ッ! 喋った!


なんと驚くことに箱がしゃべり出した。
男の声で流暢な言葉を語ったのである。
加えて、彼(?)は母の知り合いであるらしく、「綾」と軽々しく呼んだ。
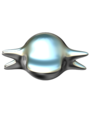


む? 綾じゃない? 声質がやや幼い……。ということは、彼女の娘か、はたまた孫か……。
すまない、そこの君。落ち着いて俺の話を聞いてほしい。突然の超常現象を目の当たりにして落ち着けというのは無理があるかもしれないが、決してパニックにならないでくれ。いいね?


箱から聞こえる男の声は誠実さを感じさせるものがあり、同時にみうに対する気づかいが見られた。言葉の端々からにじみ出る知性的な面もまた、みうの中にあった恐怖を和らげさせた。
かなり怪しい存在であるものの、自分に危害を与えるつもりはないようである。



あなたは……何?
ママの知り合い?


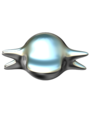


俺は自律思考型……いや、やめておこう。
そうだな……俺は君のお母さんに使われていた道具だ。





道具?


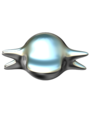


そうだ。
俺は一種のロボットみたいなもので、君のお母さんが若いころに疎ましがられて、この箱らしきものにしまわれてしまったんだ。
俺はどうしても外に出たい。出る必要がある。
勿論、協力してくれたら俺は必ず恩を返す。約束しよう。


男の声は切実だった。
しかし、相手は喋る箱で、母の道具を自称するロボット。荒唐無稽で、信用に足る程の証拠はどこにもない。
だからといって、困っていると主張するそれを放っておけるほど、日輪 みうという少女は冷酷にはなれなかった。



う、うん……。分かった。


みうはおそるおそる鎖を解いた。
鎖は簡単にほどけて、箱もいともたやすく開いた。そして、中に封じられていた彼が姿を現した。
それはおよそ80cmほどの杖だった。白を基調としたプラスチックのような無機質でできていおり、杖の頭にはルビーのような宝石を思わせる半透明な赤い球体が乗っていた。
下になればなる程徐々に細くなっており、まるで逆さまにしたガゼルの角を細長く引き伸ばしたような形をしている。



魔法の杖みたい……


杖は、まるで腹筋運動をするかのように真ん中をぐにゃりと曲げ、人間が起き上がるような動作と共に箱の中から出てた。
箱から出た杖は、みうと同じ目線まで浮かぶと、再び真ん中をぐにゃりと曲げた。赤い球体を頭であると仮定するならば、45度相当に曲がったそれは、丁寧なお辞儀に見えた。
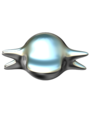


ありがとう。君のおかげで俺は外に出ることが出来た。
本当に感謝している。
では、改めて自己紹介をしよう。
俺は自律思考型エネルギー増幅デバイス及び出力補助装置、グランパだ。
君の名前を教えてくれ。





みう……日輪 みう。えっと、小学4年生、です……。


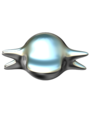


みう、か……。優しそうな名前だ。
はじめまして、みう。
今日から俺は君の道具だ。


こうして、魔法の杖と普通の女の子が邂逅を果たしたのであった。
