ああ、そうだ。
犯人が目撃者を消そうとするのは
当然のことだ。
それがたとえ級友でも。
いや、級友ではあるけれど
そこにどんな抑止力があると
言えるだろう。
この世界の誰よりも
灯里と言葉を交わしているのは
自分だという自負はあるが、
彼がどう思っているかは知らない。
たまたま縁あって
同居するようにはなったが、
それだって別に
彼が望んだことではない。
彼自身としては
次の借家が見つかるまでの短期間なら、
という考えだったのではないだろうか。
現に、友人と言ったって
それらしいことはしていない。
食事時に同席すれば話もするが
それ以外の日常では全く接点がないし、
その唯一の食事時だって
会えないことのほうが多い。
その程度の存在だ。

殺してしまっても
なにも感じない程度の。






!


振り下ろされたナイフを
ぎりぎりで避ける。
左腕の袖が裂けた。
避けたつもりだったが、かすったらしい。

ひりひりと
焼けるような痛みが走る。
だが痛がっている暇はない。
目の前の彼は
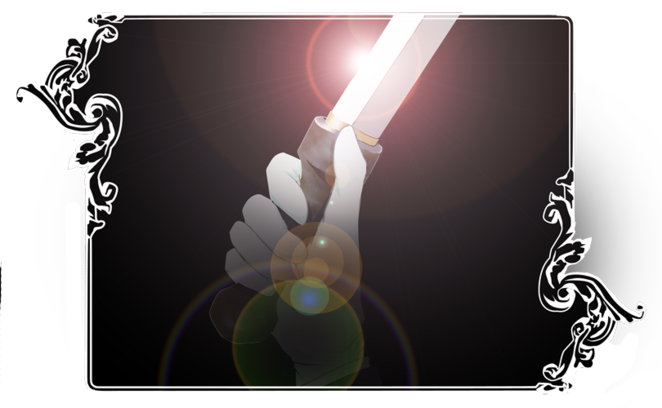
ナイフを構え直している。



待ってくれ! それは、本当に木下さんの足なのか!?



彼は答えない。



何故、彼女を、


もっと優秀な足は
他にいくらでもあるだろうに。
黙っていた彼の顔に
妖艶な笑みが浮かんだ。



彼女は晴紘と仲がいいから





は?


そんな理由で?
そんな理由で木下女史は
選ばれたと言うのか?
そんな、
それでは彼女が死んだのは
自分のせいなのか?



……って言ったら?


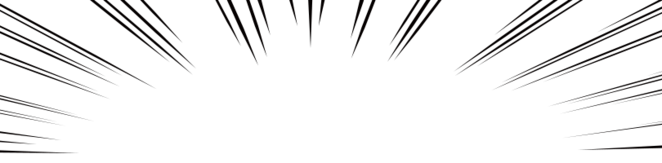

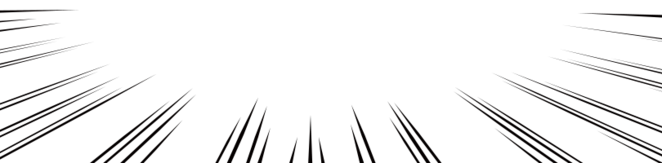
刹那、彼の足が地を蹴った。
至近距離まで詰め寄り、
ナイフを真横に振り払う。
のけ反って避けたものの、
そのまま重心を崩して

晴紘は転倒した。
これが
引き籠って人形を作っている者の
動きだろうか。
慣れている。
ナイフを使うのに、
人を傷つけることに慣れている。



灯里、


