洋館の大きな窓から、朝日が射し込む。
俺は、目を開け、ゆっくり起き上がる、
いつも最後に起きるのは俺だった。



んっ……


洋館の大きな窓から、朝日が射し込む。
俺は、目を開け、ゆっくり起き上がる、
いつも最後に起きるのは俺だった。
下の階から、おいしそうな匂いがしてくる。
姉が先に起きて、朝食の準備をしてくれているのだろう。
姉妹に引き取られてからもいうもの、俺の暮らしは見違えるように変わった。
さっきまで寝ていたベッドも、孤児院の頃とは比べ物にならない位ふかふかだった。
姉が作る料理は非常においしく、レパートリーが豊富で、いつもお腹いっぱい食べることができた。
それに、小腹が空いてキッチンに降りていくと、姉がすぐにできたてのパイを作ってくれる。



どう?美味しい?


なにより、俺と目が合うと、ニコッと笑ってくれる。
思わず、こっちが赤くなるほどに。
孤児院のおばさん達は、子供達(特に俺達名前が無い子)を基本的に無視していた。
子供をほうっておいて話す内容と言えば、政府の助成金がまた上がったとか、うちの孤児院は他より優遇されているとか、どうでもいい話題ばかりだった。



そういえば、うちって政府のお偉いさんの訪問多くないかしら?





バカね、愚痴るよりチャンスだと思わなくちゃ。お役人様の前で愛想よく振る舞っていれば、あっという間に玉の輿に乗れるのよ





そうそう、前に来たお役人様も、ここは他とは違うっておっしゃられていたじゃない?きっと、私達は他の孤児院より優秀だってことなのよ!



……なんてことを、目の前で例のカースト制度による暴力が行われているのに一切気付かずに話していた。
子供の喧嘩も、かなりエスカレートしない限りは止めようともしなかった。
それに比べて、姉は本当に優しかった。
いつも俺に微笑んでくれた。
あなたは独りじゃないと、そう言いたげに。




…………


掃除と洗濯は、妹の仕事だった。
とはいえ、ただでさえ広い洋館の全てを1日で掃除するのは不可能なため、右半分と左半分で1日おきで掃除している。
それでもかなり大変そうだったため、俺が自分から名乗り出て掃除を手伝うことになった。
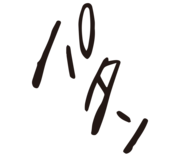
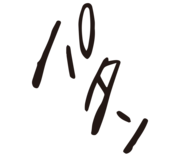
妹は、掃除や洗濯が終わると趣味である機織りをよくしていた。。
その時間を、大切にしてほしかった。
そして、妹も俺と目が合うと笑ってくれる。



…………


普段はあまり感情を表には出さないけど、それでも時折見せる笑顔はとても綺麗だった。



…………はぁ~っ


そして、俺は――何もすることがなかった。
ここに来た翌日、姉から言われたのだ。



あなたはこれで自由。元々名前がない私達は誰よりも自由なんだから。だけど、絶対にこの洋館から出てはダメよ。とても危険だから


大丈夫だよ今まで何回も外に出たこともあるからへっちゃらだよって言っても、姉は首を縦に振らなかった。
寧ろ、孤児院時代に外に出たことを怒られた。
あの時はただただ面食らっていたけど、よく考えてみると、さすがに過保護すぎではないだろうか。
それに、この洋館内なら何していてもいいと言われても、一緒に遊ぶ友達が誰もいない。
孤児院の友達を連れてくることを、姉妹は頑として頷かなかった。
遊びたい盛りの13歳が、ただ広いだけの洋館に飽きるのには1ヶ月もかからなかった。
それに、洋館の右半分は入ることを禁止されていた。
1度だけこっそり行ったこともあるが、恐いくらい静かな空間に耐えられなくてすぐに戻ってきた。
妹に掃除の手伝いを申し込んだのも、退屈な時間の使い方に困ったからだった。
そのため、俺の日常は、良くも悪くも見違えるように変わってしまったのだ。
ある日
午後の静かな時間に、ぶらぶらと洋館の中を歩いていた俺は偶然ある客間の前を通った。
すると、中から知らない誰かの声が聞こえた。
驚いて耳を扉に近づけると、姉の声が聞こえてきた。



……その話は、無かったことにしてちょうだい





貴様、本気で言ってるのか?


これは、男の声だ。



本当よ。私はあの子を一生かけて守るって誓ったの。そのためなら全てを犠牲にしてもかまわないって





……あの子の将来を決める権利は、俺にもあるはずだ!





いいえ、あなたにはないわ。あの子は私の……


ダンッと、机を叩く音がする。



何故貴様はそんなに非常になれるんだ!貴様のせいで、俺は……俺の家族は……名前を失ったんだぞ!!





えっ………?


ゾクリと
背筋を何かが駆け上がったような気がした。
姉の冷たい声が響く。



それが何?私は名前を失っても12年間ずっと顔を上げて生きてきた。この国が滅んでも、私はあの子と2人で生きていければそれでいいの





そんな自己満足のために…………!!





そろそろお帰りいただけないかしら?
夕食の準備をしたいの


有無を言わさない口調に、相手は押し黙ったようだ。
俺は、その隙をついて、急いでその場から逃げるように離れた。



……どうしたの?


妹の部屋。
俺は何も言わずに部屋に入ると、妹が何を言うのも聞かずに機織機の側でうずくまった。
機織機の前には、できかけの布。
きっと、今日完成させると決めていたのだろう。
とびら越しに聞こえた音が、とてもリズミカルだったから。
それを止めてまで、妹は俺を心配してくれる。
優しい。
……優しすぎる。



…………ねぇ


ポツリと、ふと思ったことを聞いてみた。



なに?





それの名は何?


指さしたのは、機織機の上のできかけの布。
否、布になりきれてないもの。
それはとても長く、まるでマントでも織ってるみたいだった。
だけど、作りかけ。
糸とも布ともマントとも呼べないできかけのそれを、俺はなぜか気になった。
妹は、意外そうな顔をしたが、やがてゆっくり笑みを作る。



あの布は……名の無い布なの。今は……まだね





……どういうこと?


妹は、機織機をそっと撫でた。



見ての通り、これはまだ完成していない。今のままだと、糸の塊とも布とも何とも呼べない状態になってる。未完成の何か、としか呼べない





だけど、それでいいんだと思う。大事なのは名前に縛られることじゃなくて、どういう名前をつけたいかじゃないかな。未完成だからこそ、素敵に見えることもきっとある。それこそ、完成したものよりも、ずっと素敵に見えることだって





この名前のないものは、いつかは絶対に完成されるもの。それは、名前がついてしまうから。だけど、もし未完成の頃に輝くことができたら、たとえ名前がついても色あせることはないと思うな。そして、それにもしまだ名前がなかったら、きっと……素敵な名前がつくんじゃない?


陽が落ちてきた。
夕陽が、優しい笑みを浮かべる妹を包む。
後ろから抱きしめるように。
ろくに勉強もできない俺には、何を言いたいのかさっぱりだったけど、その言葉が、まるで妹が自分自身に言い聞かせているように見えた。
遠くの方で、姉が夕食を知らせる声がした。
