頭も体も限界まで疲労していた。今すぐ眠りたいと思ってしまうと同時に、もう二度と眠りたくないという正反対の思いが浮かんでくる。



助かったか


頭も体も限界まで疲労していた。今すぐ眠りたいと思ってしまうと同時に、もう二度と眠りたくないという正反対の思いが浮かんでくる。
両の掌にはいくつもの豆が潰れていたが、大翔はそれが誇らしかった。諦めることなく光を守ったというなによりの証でもあった。



でも、あの子誰だったんだ?


カベサーダを膝蹴り一つで倒した少女。あの場所にいたということは大翔の中学校の後輩なのだろうか。あれは彼女の夢だったのだろうか。
大翔が夢の世界で出会った人間の多くは高校生から大学生くらいの若い男がほとんどだった。ニュースで流れる不審死の被害者もたいていがそのくらいの年齢だったはずだ。そこに少女が混じってきた、というのは夢の世界が拡張してきているのと同じく新たな変化の兆しと言える。



中学のことか。あんまり思い出したくもなかったんだけど


大翔はベッドに座ったまま、ちょうど部屋の反対側に置いた本棚に目をやった。一番下にはもう何年も開いていない百科事典。その上の段は卒業証書やアルバム。あとはほとんどがマンガか昔の教科書が片付けないままささっている。
その一番上。



あれももうどっかにしまったほうがいいかな


金色に輝く表彰楯に小さなトロフィー、ホコリをかぶったカップ。全て中学時代に陸上の大会で大翔がもらってきたものだ。大翔は全国トップとは言わずとも地方大会なら最上位、全国大会で入賞の経験も一度だけある。
それでも高校に入ってからは一度も本気で走ったことはない。いや、夢の中でカベサーダから逃げるときはさすがに全力だっただろう、と大翔は思い直す。
真由が入学して間もない頃にしきりに陸上部へ誘ってきていた理由もこれだった。そして大翔が陸上をやめようと思った理由もまた、このトロフィーたちが原因だった。
考えていても仕方がない。これから片付けるには時間がなさ過ぎる。大翔は重い体を引きずるようにベッドから出ると、痛む体を労わるように陸上部でやっていた柔軟体操を始めた。



ふあああ


教室に入ると同時に大翔は大きなあくびをした。眠い。明らかに体が重い。夢が恐怖の対象になってから二日。外から見れば休んでいるように見えても、大翔自身は少しも気が休まるときはない。高校生という若さを振り回していても、二夜も続けて徹夜をすればどこかに支障は起きるものだ。大翔の状態はそれに近い。今すぐ目を閉じれば立ったままでも深く眠りに落ちていくだろうと思う。



どしたの? 徹夜?





まぁ、そんなところだ


自分の席に向かう足取りすら危うい大翔に声をかけたのは真由だった。



千早がいたらまた怒られてるところだよ?





別にいつものことだろ


遅い歩みの大翔の前に立ち塞がった真由にあくびを漏らしながら答える。千早のおかんむりなど聞き慣れている。今さら言われたところで変えるつもりなど大翔にはさらさらなかった。



ねぇ、神代ってマゾ?


降って湧いた真由の質問に大翔は半分閉じていた目を見開いて真由の方を見た。聞き違いではなかったらしく、真由はいつものようにいたずらっぽい瞳で大翔の答えを待っている。



なんでそんなこと聞いた?





いや、そうなのかなって。純粋な疑問





純粋な奴がクラスメイトがマゾかなんて聞くかよ


真由の横を通り抜けて、大翔は自分の席へと向かう。眠らなくとも体勢を楽に休めるようにして体力を保っていなければ、本当に寝てしまいそうだ。



えー、だって神代って千早に怒られてるとき、いつも嬉しそうだし





そんなことねぇよ





私の知らないところで何かありそうじゃん?


何もない、ということはない。千早が大翔に怒るのはそれが一番大翔にとって楽だからと知っているからだ。それを真由は知らない。だから大翔と千早の関係が奇妙に映るというだけの話だ。



別に。大したことねぇよ





あぁ、もうズルい。私も千早と同じ中学がいい





またそれかよ。過去なんだから諦めろ





じゃあ、中学の頃の千早の話してよ。夢の中で千早との楽しい中学生活送るから





……それは虚しくないか?


夢、という単語が大翔の耳にひっかかって答えに詰まった。夢を見たいと思えるということは真由はあの世界には落とされていないということなんだろう。それに大翔は安堵した。できることなら見知った顔にはあの夢の中では出会いたくはない。あの恐怖を味わうのは自分だけで十分だ。



ほら、そろそろ予鈴だろ。あいつがまた何か言い出すぞ


と大翔は期待を込めて千早の声を待つ。
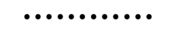
しかし、今日に限ってはいつもの可愛らしい怒声が少しも聞こえてこなかった。



あれ? 今日休み?





誰のこと?


とぼけたように真由が教室の中を見渡す。



誰って、堂本に決まってるだろ





ふーん。決まってるんだ





うるせぇな


話の流れでわかるだろ、とは言えない。真由もわかった上で言っているのだ。ここで大翔がそう言ってしまったら、千早がいないことを寂しがっていることになる。
それだけ悩んで口を閉ざしていれば、大翔が何を考えているかなど、付き合いの短い真由にでも手に取るようにわかってしまう。男の思考回路はとても単純にできている人間がほとんどだ。



今日は千早、お休みみたい。誰かさんが心配かけすぎなんじゃないの?





俺のせいかよ





自覚があるんなら少しくらい優しくしてあげたら?


真由は答えも聞かずに大翔に道を譲って、そのまま他の女子に話しかける。こうなると大翔は簡単には声をかけられない。真由は大翔がそういう性格だとわかっている。たった数ヶ月でそんなことまで理解しているなんてまったくもって嫌なことだ。
大翔は自分の席につくと、誰も座っていない千早の席に目をやった。まだ始業には時間はあるから遅刻ではないものの、千早が大翔より遅く教室に入ってくる姿を大翔は見たことがなかった。どれほど早くに来ているかを大翔は知らないが、とにかく朝教室に行くと、決まって待ち構えたように大翔に言いがかりのように文句をつけるのが、千早の日課のようなものだった。
それがないというだけで、大翔はなんとなく朝から気力が削がれるような気がしてくる。口うるさい小姑がいなくて平和そのものだ、と心の中で嘘を並べてもやる気はまっさかさまに落ちていくだけだ。
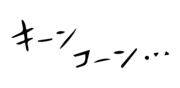
授業が始まっても大翔の視線の半分は空になった千早の席に向かっていた。千早がいないということはそれだけで大翔の緊張の糸をすっぱりと切り落とすだけの刀になった。
黒板がぐらぐらと歪み、視界に暗転が混じる。



あぁ、助かった


大翔は反射的に教室の中心で小さく言葉を漏らす。もはやこの光景は大翔にとって安心の合図だ。あの恐ろしい夢から覚めるときに見る世界が切り替わる瞬間。だが、今は現実にいる。つまり夢の世界に落ちる瞬間に見る風景でもあった。
