数は、一匹。ただ時間をかけるとまた部屋でふらついていた方がやってくるかもしれない。最初から喉には噛みついてこない。今までの経験ではそうだ。押し倒してくるというならそれに合わせてカウンターを入れる。一か八かにしては分の悪い賭けになりそうだ。
数は、一匹。ただ時間をかけるとまた部屋でふらついていた方がやってくるかもしれない。最初から喉には噛みついてこない。今までの経験ではそうだ。押し倒してくるというならそれに合わせてカウンターを入れる。一か八かにしては分の悪い賭けになりそうだ。



その役目は俺がやろう


首筋から垂れる赤い血を拭って衛士が大翔と同じようにスタンドライトを握っていた。



そんなむちゃくちゃな





それは君も同じだろ? あんなのにこんなもので挑むなんて


話している間に近付いてきたカベサーダに向かって衛士が先に飛び出した。



あ!


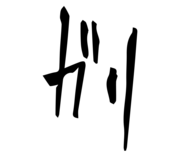
衛士とカベサーダが交錯する。外から見ても結果は明らかだった。
大きく隆起した額に阻まれたライトが砕け散る。それでもその突進は止まらない。



よし


押し倒された衛士が小さく呟いた。



さぁ、今のうちに逃げろ





何言って


昨夜の大翔と同じだ。少し違うのは大翔が言った時にはただのやけっぱちだったが、衛士にはそれなりの考えがあったということだ。



首の傷、感覚がないんだ。たぶん助からない



血の量が明らかに増していた。さっきの部屋で助けた時はそれほど大きな傷には見えなかったのに。
大翔の考えを察したように衛士は言葉を続ける。



歳をとれば君もいろいろなことを覚えるものさ。血の止め方。それからこういうときに激しい運動をすると血が出やすくなるとか、ね


割れたライトスタンドをカベサーダの顎に押し込みながら、衛士は確かににやりと笑った。震える手がじりじりと下がっていく。時間はそれほど残っていないのが見てとれる。大翔の選択は決まっていた。
持っていたスタンドライトをカベサーダの頭に振り下ろす。

一撃、二撃、三撃。
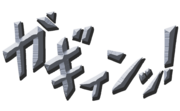
離れろ、ひるめ、苦しめ。

百の怨嗟を込めて攻撃を振り落とすが、カベサーダの動きは少しも止まらない。



あああああ!


気合というよりは悲鳴に近かった。
徐々に衛士の首筋に近付いていくカベサーダの口元から赤く汚れた牙が見えた。
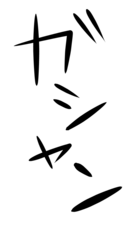
やがて先に耐えられなくなったライトスタンドが半分に折れ、大翔の手からは血が滴り落ちていく。
やめてくれ、と大翔が願ったとき、ぐらりと視界が揺れた。昨夜も感じたこの光景、この感覚を大翔は覚えている。
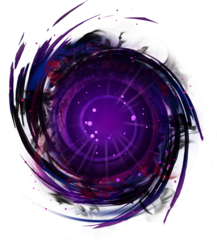



ありがとう


拳を握り、振るったか弱い暴力は赤い瞳をすり抜けて消えた。
頭の中ではまだこだまのように声が響いていた。もう夢ではない。現実世界だと理解すると、遠く離れていくように声は消えていった。



朝か。朝が近かったのか


それがわかっていたならば、その瞬間まで大翔が囮になったり、大声を出してカベサーダを誘ったりとやりようはいくらでもあったはずだ。人を超えた速度で襲ってくるあの恐怖でも現実世界にまではその牙を向けることはできない。



くっそ


柔らかいベッドの端を叩く。安いベッドのアルミ枠が小さな音を立てるが、すぐに小さく消えていった。
まずは地図を作る。そう言った尊臣の言葉に従って、枕元に置いておいたメモ用紙に触れることもせず、大翔は起き上がる。全身が重い。まるで休んだ気持ちがしない。徹夜していたほうがよっぽど楽なのではないかと思えてしまう。
衛士は助かっただろうか。大翔が目覚めたということは同じように衛士もすんでのところで死を免れたかもしれない。



おはよう





今日も起きてきた。いったいどうしたの?


朝食の準備をしていた晴美がわざとらしく驚いた。



遅刻しないことに驚くのはやめてくれよ。部活行ってたときはもっと早く起きてたんだからさ





人間っていうものはやらなくなると知らずしらずに衰えていくものだぞ


既に直食をとり終わったらしい洋介がコーヒーをすすっている。今日は家を出るのが早いらしい。
毎日同じ時間に出られない父はどうやってその体調を管理しているのか、大翔にはよくわからない。以前それとなく聞いてみたのだが、気合とやる気、という納得のいかない答えが返ってきただけだった。
もしも、起きる時間を完全にコントロールできるのなら、あの世界で命の危機に瀕した瞬間に目覚めてしまえばいい。それができれば他の人を救うことができる。



どうしたの、調子が悪いの?





顔洗ってくる


晴美の質問に答えないまま、大翔は洗面台に向かった。冷たい水で顔を洗うと、ようやく今は危険ではないということがはっきりしてくる。
顔を拭いて鏡に映った自分を見ると、少し太ったように思えた。あの時から自分はグラウンドに近付かないようにしている。アイツは今、どんな気持ちでいるんだろうか。
リビングに戻ると、朝のニュース番組では昨日に続いて不審死事件の続報が流されていた。昨日は死者が二人だったものが、今日は一気に十人と増加していて、警察は事件だけではなく奇病の可能性もあるとして、専門家と連携している、というものだった。
死者の顔写真が画面上に映し出されると、大翔は俯くように画面から目を逸らした。
氷室衛士の顔はその中にあった。



助けられない? わかってるさ


それでもまた自分は何もできないままでただ立ち尽くしていたのだ。



やっぱり具合が悪いなら病院に





いや、なんでもない。大丈夫だよ


心配そうに駆け寄った晴美を大翔は片手で追い払った。
誰も自分を咎めない。むしろ優しく励ましてくれる。それが大翔にとっては何よりも重くのしかかっていた。
