もう一度言おうとした大翔の頭に尊臣のげんこつが落ちる。今までよりも少しキツイ一撃に大翔は思わず床にうずくまった。



やっぱり





あほう



もう一度言おうとした大翔の頭に尊臣のげんこつが落ちる。今までよりも少しキツイ一撃に大翔は思わず床にうずくまった。



命あっての物種じゃ





でも、何か役に立てるかもしれないだろ





立てるならワシも逃げるやこ言わんわ


苛立つように尊臣がこぼす。光はそれを横目に逃げてきた人をまとめていた。



さぁ、できるだけ奥に逃げ込もう


倒れた人を肩に担いで、光は少しでも遠いところに、とあの階段の部屋を抜けた先、フードコートの方にまで行こうと提案した。疲れで床に倒れ込んでいた人たちもカベサーダの恐怖には敵わないらしく、ふらつく足で光の背中を追い始める。
本当にこれでいいだろうか。
助かるにはそれが一番いい。そんなことは誰に聞いたってわかることだ。



おら、はよせい


背中の方で尊臣が荒っぽく大翔のことを呼んでいる。もう通路の周りに残っている人はいなかった。誰もがこの先で起こっている事実を終わったもの、あるいは自分とは関係ないものと思っている。



俺は行くよ


それだけ言うと、大翔は少し前に通ったホテルへの狭い通路に潜り込んだ。



待て、あほう!


大翔を追いかけて通路に入ろうとした尊臣だったが、狭い通路には簡単には潜り込めない。手を伸ばして大翔の足首を捉えようとしたものの、先を急ぐ大翔の姿はすぐに遠くなっていく。



ごめん、でもやっぱり見捨てるっていうのは


できない。ヒーローになりたいわけじゃない。死にたいと願っているわけじゃない。ただ誰かが犠牲になることを黙ってみていることができないだけだ。
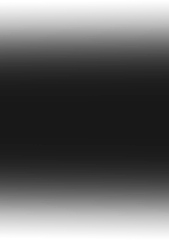
通路の先に辿り着き、通路を塞ぐソファの隙間からホテルの中の様子を窺う。誰もいない、声も聞こえない。しかし、ソファの隙間を縫って外に出るのは簡単なことではなさそうだ。下手に当たって崩れでもしたら、身動きの取れない状態でカベサーダに襲われる可能性もある。
ゆっくりと蛇のように体をくねらせながら、大翔はホテルのフロント横に這い出した。床に敷かれた絨毯には赤い血の斑点が列を成していた。それを追いかけるようにカベサーダの爪が絨毯を毛羽立たせた跡もある。状況があまりよくないことは明らかだった。
何か武器を、と大翔は周囲を見渡してスタンドライトを手に掴んだ。
策はある。カベサーダは不意打ちに弱い。後ろから思い切り殴りつければ少しくらいは時間が稼げる。その間にあの通路を抜けていく。尊臣ほどではないにせよカベサーダもあの細い通路を通るにはそれなりに苦労するはずだ。



よし


落ち着け、と自分に言い聞かせ、大翔は血の列を追いかけ始めた。
一階のロビーの奥。ホテルの部屋が並ぶ廊下どの部屋もしっかりと扉が閉まっている。ひとつひとつの部屋が開くのかを調べるつもりにもなれない。
血の跡を追いかけて、大翔は何部屋目かもわからないところで足を止めた。ショッピングモールもおかしかったのだから、延々と続く廊下があっても不思議には思わない。大翔が足を止めたのは血の跡が部屋の中へ入っていったからだった。

息を飲み、部屋の扉を開ける。
四つんばいで何かに覆いかぶさっている黒い影に持っていたスタンドライトを振り下ろした。



おらあああ!



大声は恐怖を振り払うため。目を閉じたのは人の形をしたものを傷つけるのを見ないため。
ガラスが割れる音がして、少し遅れて何かが床に倒れ落ちる音が続く。それを聞いてから大翔は目を開けた。



今のうちに、逃げましょう!


不意打ちの効果はあったようだ。昨夜の尊臣ほどではないが、明らかにカベサーダの動きは鈍くなっている。



君は、さっきの


首筋を押さえ苦悶の表情を浮かべた衛士の顔を見て、大翔は少しだけ安堵した。まだ生きている。それならば助かる可能性があるはずだ。
衛士がカベサーダから離れるように立ち上がり、大翔が助け起こそうと手を伸ばす。目の前の危険が少しだけ遠ざかって二人の気持ちは緩んでいたのかもしれない。互いに知っていたはずのことが頭から抜け落ちていた。
カベサーダは二匹いた。
わずか数分前に聞いた情報。もっとも覚えておかねばならない敵の数。衛士の顔が驚愕の色を帯び、何かを伝えようと口が動くが、声は出てこなかった。




があぁぁ


大翔の背中に何かがのしかかる。
昨夜の痛みを思い出す。肩を抑えられてはまた抜けられなくなる。大翔は体を捻り、後ろから飛びかかったカベサーダの体を横に落とすと、衛士を引き上げた勢いのまま部屋を飛び出した。
追ってきた血の跡を逆に辿ってホテルのロビーを、その先にある通路を目指す。一匹はまだしっかりと意識がある。すぐに追いつかれてしまうだろう。



ここでなんとかしないと


延々と続く廊下がどれほどの長さかはわからないが、アスリート級の足の速さを持つカベサーダから逃げられるものではない。もう一撃。どうにかして動きを鈍らせなければ食われてしまうだけだ。
持ってきたスタンドライトは部屋に捨ててきたが、ありがたいことにホテルの廊下には同じものが等間隔で並んでいる。大翔は一つを握って後ろを振り返った。
