家に帰るときは、誰にも気づかれないように門を開く。
帰宅時間が遅くなっても咎められることはない。家族や使用人に会いたくないから忍び足で屋敷の中を歩いていた。

家に帰るときは、誰にも気づかれないように門を開く。
帰宅時間が遅くなっても咎められることはない。家族や使用人に会いたくないから忍び足で屋敷の中を歩いていた。



こんなにも容易く侵入できるなんて、この家の警備は甘すぎるよね


そんなことをぼやきながら廊下を歩いていた。
向かうのは、殺風景な自室ではない。静寂に包まれた中庭だ。この中庭は好きだ。ここだけが昔と変わらない。暖かい空気に包まれていた。
月明りに照らされた薔薇に見とれていると、
―――坊ちゃん
と、背中に声がかかる。
振り返ると………………メイドが無表情で立っていた。若いけれど古株で、確か父親付のメイドだったと思う。このメイドとは直接会話することは初めてだった。
メイドは猫を抱いて立ち尽くしている姿を見て、不審に思ったのだろう。



坊ちゃん、どうされたのですか?





この猫、拾って来た


どう言えば良いか悩んだが嘘をついても仕方がない。そう考えて、抱いていた猫を見せる。



まぁ、汚い猫


まるで生ゴミでも見るような目でメイドは言う。
想像通りの反応に嬉しくて笑みが溢れる。



汚い猫だから拾ったんだよ。綺麗な猫だと父さんに盗られちゃうからね


父親の仕事など知らなかった。劇場を経営しているんだっけ、素晴らしい演劇を作る為だからって、有名な俳優たちと酒を交わす。父親は仕事に没頭して母親に愛想をつかれた。
だけど世間体とかいうものがあるから二人は離婚していない。もうずっと、昔から母親の愛情が向けられたのは夫でもなければ息子ではなく、新しい恋人だった。
父親の愛情が向けられるのは美しい動物たちの死体と自分の演出する舞台。
二人の愛の結晶であったはずの息子など、目もくれない。
だから、お蔭で自由に動ける。



さて、遊ぶか


夜遅くに薔薇園の中で猫と遊ぶ。
そんな行為すら咎められない。
だけど、今夜はこのメイドが何かとうるさく絡んで来た。



坊ちゃん、洗ってあげては?





ダメだよ。父さんが欲しくなる





確かに旦那様は坊ちゃんが拾って来た犬も鳥も剥製にしましたね


思い出すだけで吐き気がする。
大事な動物たちが、知らない間に物言わぬ剥製に姿を変えていた。
あの犬はもう足にすり寄ってこない、あの小鳥の囀りはもう聞けない。



酷いことをされたよ





そうでしょうか? 友達がいつまでも美しいって嬉しいことなのでは?





君は狂っている。笑わない、動かない、そうなったら彼らは……友達とは呼べなくなってしまう……って、何持っているの?


ふいに彼女を見上げる。使用人なんて見るつもりがなかったのに。メイドの右手にはスコップが握られている。左手には鉈。それを睨みつける。何のための道具なのかを思案すると。
メイドはニコリと笑いながら、それを背中に隠す。



旦那様から花壇の草むしりを仰せつかったのですよ





へぇ、こんな時間にね


月明りが照らす夜だ。
本当にそれだけなのか、怪しいと思った。



美しくない者は生きる価値がありませんから、雑草も虫も排除します。


そう言って微笑む、彼女はぞっとするほど冷たい目をしていた。



……





あと枯れた花も棄てなければなりませんね。美しくない者は美しさを保つ必要ありませんよ


メイドは微笑んで頭を下げると、奥のずっと奥の方に歩いて行った。
その笑みが怖くて、でも、気になって、気が付くとその背中を追っていた。
辿り付いたのは豪華な庭の一画。
隅の方の暗い場所で、花も咲いていない。
メイドは小兎と向かい合っていた。
あの小兎は確か父親が持ってきた商品だった気がする。
小兎を前に、メイドが光のない目を浮かべていた。
そして、
その鉈が、
小兎を潰した。

か細い断末魔の声に、ゾッとする。自然と猫の身体を抱きしめていた。



ニャ





!!


抱きしめられたのが驚いたのか、猫が声を上げる。
しまった。



坊ちゃん?


メイドが振り返った、見られてはいけない場面を見られた彼女は蒼白だった。
それと、同時だったと思う。見てはいけない場面を見てしまったと、それに気づいてしまって……

声は一瞬だけ。
先ほどの小兎のものと変わらないだろう。
目の前にうつ伏せに倒れる女がいた。
どうして、ここは赤いのだろう。
理解出来なかった。
今すぐ、ここから離れたくて走り出す。



悪くない、
悪くないぞ、
悪くないよな?





…………


誰も答えない。 答えられるはずがない。だって、そこには自分しかいないのだから。
いや、違う。
見ていた。



…


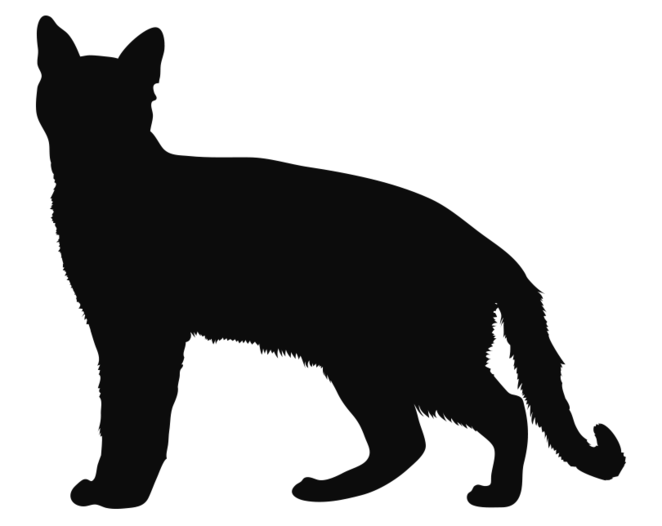
二つの眼がこちらを見ている。
拾って来た猫がジッと見ている。


