脂汗が滲んだ額を拭って大翔は息をついた。




夢か、夢だよ、そうだよな


脂汗が滲んだ額を拭って大翔は息をついた。
朝起きたばかりだというのに全身が妙に気だるい。頭の中でしか走っていないはずなのに本当にマラソンでも走り抜けてきたような気分だ。開け放したままの窓から吹き込んでくる風が大翔の汗ばんだ頬を撫でて身を震わせた。



それにしてもなんだったんだ、あの夢


自由に動けるのなら世界も作れてしまえばいいのに。そうすれば自分だってゲームの主人公のような大立ち回りだって出来るはずだ。それなのに実際のところはどうだろうか。夢の中の自分が立っているのは、いつも薄暗い廃墟のような場所ばかり。やっと見つけたと思った人間は目の前で息絶え、黒い肌の怪物に襲われた。
一緒に逃げてくれるのは可愛い女の子ではなく、筋骨隆々の大男でさらに自分が活躍するどころか逆に助けられてしまう情けなさだ。
夢の中でくらいヒーローになってみたかった。これは自分の想像力が足りないからなんだろうか。
そんなことを考えながら、まだ鳴るべき時を待っていた目覚まし時計の仕事をキャンセルして、大翔は制服を着替えようと起き上がった。




痛っ


着ていた半袖のティーシャツが擦れると肩に激痛が走る。歯を食いしばって痛みに耐えながらシャツを脱ぎ、調子に乗って買ったはいいもののすっかりオブジェと化した姿見の前に立ってみる。



なんだよ、これ。あれは夢だったんだろ?


鏡に映る自分に問いかけたところで返事はない。
その代わりに大翔の両肩には爪でひっかかれたような跡が赤く残っていた。血は止まっているが、表皮が擦り取られたように腫れ上がっている。夢の中で味わった激痛と比べれば大したことはない。そう思いながら軽く傷跡に触れてみる。



くあぁぁ


言葉に表せない痛みが大翔の両肩を襲って、その場に膝をついてうずくまった。まさしく夢の通りの痛み。慌てて脱いだティーシャツを見ると、肩の部分が真っ赤に色を変えていた。



あいつに押し倒された時の


昨夜に見た夢を思い出す。いや、あれは本当に夢だっただろうか。大翔の中で疑念が渦巻いていくが、考え込んでいても答えは出てこない。部屋の本棚の上に置きっぱなしになっていた救急箱からワセリンを取り出して塗りつけておいた。部活をやめてから必要ないと思いつつもとっておいて助かった、と大翔は制服に手を伸ばす。
昨日あの怪物に襲われた結果ついたのがこの傷だとしたら、もし襲われてあの男のように首を噛み切られたら。白いステージが真っ赤に染まるほどに血が流れたとしたら。
そんなことあるはずがない。考えれば考えるほど悪い方向に転がっていく思考を振り払うように大翔は荒々しく部屋の扉を開けた。
大翔がダイニングに顔を出すと、母親の晴美が信じられないという顔で大翔を見た。



おはよう





どうしたの、熱でもある?


過剰なリアクションはいつものことだ。母親なりのスキンシップなのだろうが、いい加減大翔にもワンパターンに感じられて反応に困ってしまう。



ないよ





もう、そんな仏頂面してると女の子も寄ってこないでしょう





余計なお世話だよ


朝、キッチンに母親がいる。毎日見慣れている当たり前の状況にこれほど心が休まるなんてやはりどうかしている。
冷蔵庫から牛乳を取り出してコップに移し、大翔はそれを一気に飲み干した。神代家の朝食は和食と決まっている。ご飯と一緒に牛乳を飲むのは嫌いだった。
そうしているうちにもコーティングで光を反射するテーブルにご飯、味噌汁、玉子焼きと朝食が並べられていく。父、洋介は今日は遅番だろうか、食卓には大翔の分しか並んでいない。



冷めちゃわないうちに食べてね





はーい


箸を取って玉子焼きを口に運ぶ。砂糖入りの甘い玉子焼きは洋介の好物だ。
行儀悪く咀嚼したままテーブルの端に置かれたリモコンをとってテレビをつけると、ニュース番組のキャスターが淡々と原稿を読んでいるところだった。
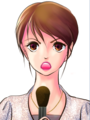


『……死亡した少年は十七歳の高校生で、今朝未明、部屋から臭いがするのを不審に思った父親が部屋に入ると、少年が首から血を流して死亡していたということです。警察では事件と自殺の両面から捜査を続けています』





あら、怖いわね


お茶を持ってきた晴美が画面を見ながら小さく言った。



大翔は悩みとかないの?





別にないよ





小さなことでもいいから、何でも言うのよ。私は母親なんだから





わかってるよ


今まさに両肩の傷を隠している大翔は晴美から視線を外して答える。
テレビには生前の少年の写真が映し出されていた。特別特徴のある人間には見えなかった。写真一枚で人柄がわかるというものではないが、それでもいじめられるほど気弱だとか、トラブルを起こしていそうなやんちゃさは感じられない。
普段ならすぐに忘れてしまいそうな顔だったが、モザイクのかかった仲間に囲まれて笑う少年を見て、大翔は持っていた箸を落とした。




こいつ、嘘だろ?


他人の空似だとも思った。しかし大翔の勘が、今朝の傷が、直感が、正しいと告げている。画面いっぱいにズームされた少年の顔は、昨夜大翔が見た怪物に襲われて死んだあの男の顔と同じだ、と。
薄暗くてよく見えなかったせいだ。見下ろした先立ったから十数メートルは離れていた。そうやって言い訳を並べてみるが、どれも大翔の不安を拭うには足りない。



大翔、何か顔色悪くない?





大丈夫だよ


不審そうに近付く晴美を手を振って追い払い、大翔はテーブルに落ちた箸を拾って味噌汁に口をつける。濃いカツオだしがよく目立つ晴美の味噌汁が、今日は味気なく感じられた。



昨日の夢、あれはいったいなんなんだ?


晴美に話したところで、冗談と思われるだろうか。もしかしたら気が触れたかと心配されるかもしれない。あの時に大翔が塞ぎがちになってしまったことを晴美は今でもきっと気にしているに違いないのだから。
大翔は平静を取り戻して、朝食を機械的に口に放り込みながら、昨夜の夢に出てきたもう一人の男のことを思い出していた。
