がくん、と膝から崩れ落ちる。
恐る恐る手を伸ばしてその身体に触れる。




あ……あ……ああああ……!


がくん、と膝から崩れ落ちる。
恐る恐る手を伸ばしてその身体に触れる。
ぬるりと血液で濡れた肌はまだ生温かい。
身体中にある傷は切創とも、擦過傷とも、刺創とも言えなかった。
ノクトビションに医学の知識はない。
しかし、血液の知識はある。
あの監獄のような研究施設から脱走するために、血液操作を利用する必要があったノクトビションにとって血液のことを知る機会などいくらでもあったわけだ。
だから、ノクトビションにはその傷がどんな風にしてできたのかを推察することができた。
その傷は血管を流れる血液が無理矢理外界に出ようとしてその表面を内側から突き破った傷。
つまり、創傷の結果としての流血ではない。
いわば、流血の結果としての創傷である。
――が、なぜそんなことが起きうるのかはノクトビションには分からない。
血液操作の暴走?
ノクトビション以外に血液操作の検体はいないと、あの科学者は言っていた。
もちろん、あの能見という胡散臭い科学者が検体であるノクトビションに真実を伝えているという保証などどこにもないのだが。
しかし、そんなことに嘘をつく意味があるのだろうか。
だとしたら……。
《自由七科》。
その実験の内容は知らないが、しかし、ノクトビションが脱走の際に忍び込んだあの部屋にあったパソコンのディスプレイにはその実験対象者リストに彼女の名前はあった。



う……誰かと思ったらお前かよ……。


虫の息でエリカはノクトビションに語り掛ける。



あ、あんた……大丈夫なのか……。





だ、い……じょうぶなわけ……ないだろうが。
もう……あたいは助からない……。それぐらい馬鹿なあたいだって分かるよ……。





な……何があった……?





さぁ……?
自分が何で死ぬかも分かんないなんて……こんな情けねぇことないよな……。
ったくよぉ。ざまぁねぇな……。





とりあえずどこか安全な場所に――。





だから……もう助からないって言ってるだろう?
それぐらいのことあんただって分かってるだろう?
だったら、取り繕わなくていい。
無理にあたいを助けようとするフリなんてしなくていいよ……。


そう。
ノクトビションには彼女と同じように、いやそれ以上に彼女が助からないことが分かってしまっている。
分かりすぎるほどに、分かっている。
しかし、かと言って、今、自身が何をすべきかが分かっているわけではないのだ。
だから助けようとしているフリをした。
それもまた、人間たらんとするノクトビションの潜在意識でもあるのかもしれないが。
だが、エリカは思わぬ形でノクトビションにその答えを示した。



殺してくれ……。





――は?





年頃の女の子にこんなセリフを何度も言わせるなよ……。
殺してくれ、と。そう言ったんだよ。





な、なんで……。





そんなことも……分からないのかよ……。
身体中の血液が……内側から噴き出して死ぬのがどれだけ辛いか、想像を絶することぐらい想像つくだろう……?
あれ、自分でも意味分かんねぇこと言ってんな……。
とにかく、これじゃあ……死にきれないけど死ぬほど辛いんだよ……。
だから……。


殺してくれ。



そ、そんなことできるわけが……。


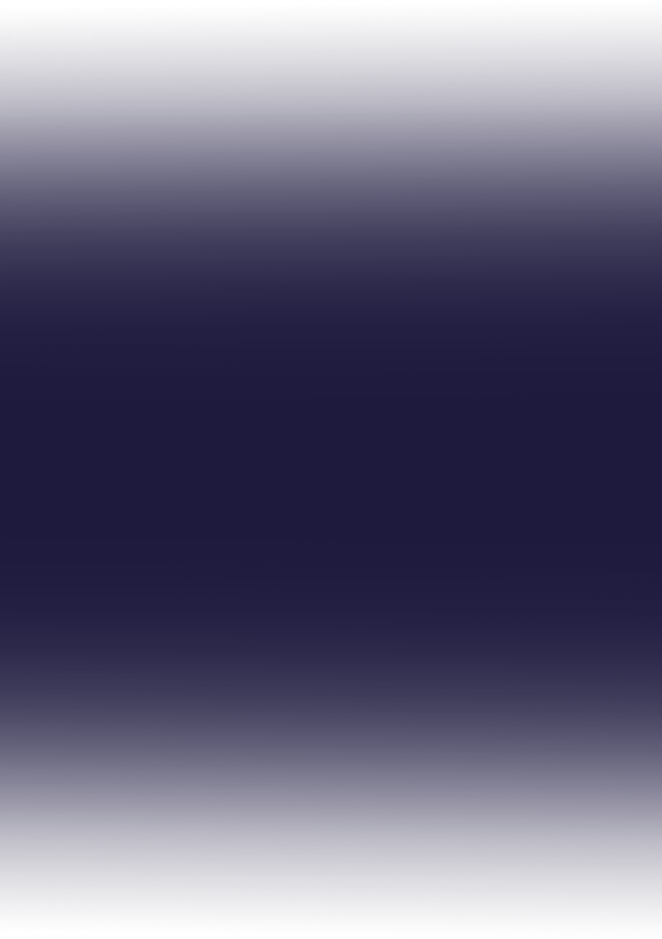
そう言いかけたとき、またあの感覚が襲う。
吸血衝動。
さっきまでは彼女の凄惨な情景に動揺していたせいで気付かなかったが、今彼女は、狂おしいほどに甘い芳香を纏っていた。
当たり前だ。
ノクトビションが、怪物としてのノクトビションがあれほど、それこそ狂うほどに飲み干したいと思った血液をその身体に滴らせているのだから。



何を迷うことがあるんだぁい……?





僕は……。





目の前の女の子が助けてくれってさぁ。
懇願しているのにぃ?
哀願しているのにぃ?
切願しているのにぃ?
嘆願しているのにぃ?
嘆願しているににぃ?
請願しているのにぃ?
それを無視するのかい?
無下にするのかい?
無為にするのかい?
無残にするのかい?
無駄にするのかい?
無情にするのかい?





僕は……人間だ!





彼女の願いを無かったことにするのが人間?





そ、それでも僕は人間だ!


ブラッドがノクトビションを抱きすくめる。
飲み込まれる感覚。
ノクトビションはそれに抗おうともがくが、彼女は一向に離れないどころか、さらに絡みつく。
彼女の冷たい、細い指がねっとりとノクトビションの輪郭をなぞる。
ぞわぞわという快感とも不快感ともつかない感覚がし痺れのようにノクトビションを襲う。



僕は……僕は……


吸血鬼だ……。



そう、吸血鬼。怪物。
だから……。


本能のゆくまま、
この者の血を飲み干せ。

ゴクッ
