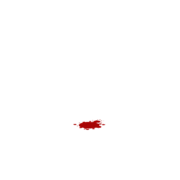ここ数日、町が賑わってきていると聞いて山を下りてみれば、丁度、この日は七夕祭りが開かれていた。
家々の前には短冊などで飾られた笹が揺れ、大通りの両脇には多くの商人が店を広げてあの手この手を使って客寄せをしている。中には、幼い子供が大人顔負けの迫力で呼び込みをしていたり、可愛い動物が手招きをしていたりする店もあり、眺めているだけで楽しい気分になってくる。普段から流通が盛んで賑わっている町だが、今日は祭ということもあり一段と活気が溢れていた。
七燈は人混みにうまく溶け込んで大通りを散策していた。喧しいのは嫌いだが、祭の賑やかさは昔から好きで胸が躍ってしまう。どこからか聞こえてくる囃子の音がそれに拍車をかけているようだ。