七燈の亡骸を前に夕鶴は呆然としていた。目の前で起こったことがあまりにも唐突だったため、脳が理解しきれないでいるのだ。
どうして、七燈は自害をしたのか。
夕鶴を好きだと言ったのは、嘘だったのか。
なぜ、彼が死ななければならなかったのか。
夕鶴には理解できないことばかりだった。
七燈の亡骸を前に夕鶴は呆然としていた。目の前で起こったことがあまりにも唐突だったため、脳が理解しきれないでいるのだ。
どうして、七燈は自害をしたのか。
夕鶴を好きだと言ったのは、嘘だったのか。
なぜ、彼が死ななければならなかったのか。
夕鶴には理解できないことばかりだった。



なな、ひ……さま……


空虚が胸に広がっていく。彼女はいまにもそれに飲み込まれてしまいそうだった。
それでも彼女を突き動かしたのは愛しい人への想いで、夕鶴は力の入らない足を引きずりながら七燈のもとへ這った。



……


まだ少しだけ温かい彼の体に触れて悲痛な面持ちを浮かべる。彼の髪を、頬を、短刀の刺さった喉を震える指で撫で――――最後に、大好きだった手に触れたときだった。
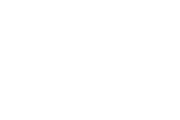



ッ――――!?


七燈の、これまでの記憶が夕鶴の中に流れ込んできたのだ。それは彼が七十五回も繰り返し夕鶴と出会い、彼女を助けるために、彼女と生きるために、運命に抗った記憶だった。
あらゆる手を尽くし、それでも結局、運命を変えることはできないと知った彼は、とうとう夕鶴と生きることを諦めてここに果ててしまった。
それが夕鶴の幸せだと、それだけを願って、身勝手に。



ひどいひとです、七燈さまは……っ


込み上げてくる感情を抑えることはせず、夕鶴は涙を零した。彼への想いは泉のように滾々と湧いて尽きることがない。もうこんなにも好きなのに、今更他の誰かと幸せになんてなれるわけがない。



わたしは七燈さまと幸せになりたかったのっ……七燈さまのいない世界に、わたしの幸せなんてないのよ……


本当に勝手なひとだ。最愛の人が死ぬことで残された者が幸せになれるなんて、これを悲劇と呼ばずに何と呼ぶのか。



わたしのためを思うのなら、生きて……二人で幸せになれる道を探しましょう、七燈さま。今度はわたしも一緒に考えますから……


夕鶴は七燈に向かって微笑みかけ、彼の喉に刺さった短刀を引き抜いた。七燈の血で真っ赤に染まったそれを怖いとは微塵も思わなかった。それよりもこの先、彼のいない世界で生きていくことの方が怖くて、寂しかった。




名前も知らない世界樹さん……
今度はわたしが七燈さまを守ってみせます。
必ず、二人で幸せになると誓います。
だから、どうか……わたし達をもう一度、あの日へ――――


鮮血が雨となって大樹に降りかかる。汚れた思いは血をも濁らせるが、夕鶴の純粋な思いは雪解けの水のように澄んでいて、朽ち果てるだけだった大樹の力を少しだけ回復させた。
事切れた二人の亡骸の前で、この地に顔を出した世界樹の一部は、最後の力を振り絞り二人のためにしくしくと泣いた。
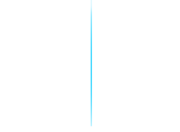
ここ数日、町が賑わってきていると聞いて七燈は山を下りた。丁度、この日は七夕祭りが開かれており、家々の前には短冊などで飾られた笹が揺れ、大通りの両脇には多くの商人が店を広げていた。
それらを冷やかし程度に眺めて大通りをぶらぶらと歩いていた彼の前に、長い黒髪を背に流した一人の女が現れる。




七燈さま!





……っは、なんで……


満面の笑みを浮かべて胸の中に飛び込んできた女を、七燈はずっと前から知っていた。
女もずっと前から七燈のことを知っていた。
二人が恋に落ちたのは、必然だった。



今度はわたしが七燈さまをお守りします。だから、もう勝手に諦めないでくださいね





ッ……ああくそ、わけわかんねえ! けどっ


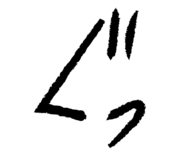
七燈は夕鶴を抱きしめた。夕鶴も七燈をぎゅっと、ぎゅーっと抱きしめた。
今度こそ、失わないために。



好きだ、夕鶴!
俺と一緒に生きてくれ!





はい! わたしも七燈さまが大好きです!
今度こそ、ずっと一緒です!


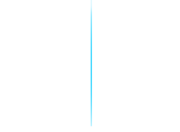
――――今度こそ、彼らが幸福であらんことを。

