デスタン家の夜会に行ってからというものの、母親の様子がおかしいことにエリゼは気づいていた。
前々から母親は機嫌が良いとエリゼを人形のように可愛がるものの、機嫌が悪いとヒステリーを起こすことがあった。




ママ?


デスタン家の夜会に行ってからというものの、母親の様子がおかしいことにエリゼは気づいていた。
前々から母親は機嫌が良いとエリゼを人形のように可愛がるものの、機嫌が悪いとヒステリーを起こすことがあった。

花瓶の破片が頬を掠めた。
エリゼはゴクリと生唾を飲み込みきるや否や、母親は歳のわりに小綺麗な顔を年老いた魔女のような顔に変え、声を荒げた。



あの、アイリスとかいう女……不愉快だわ。一番綺麗なのは、エリゼなのに。そう、私の娘が一番美しくて才女なのよ





ママ……


ああ、あのアイリスとかいう歌姫が現れたせいか。
確かに銀細工のように美しい女性で、披露した歌もそれはそれは心をとろけさせるほどの旋律であった。と、エリゼはそのくらいにしか認識していなかったが、どうやら母親は違ったらしい。
美に執着のある母親は何かに取り憑かれたように、蒼白な顔でエリゼを見た。



エリゼ、エリゼ。
貴方は美しくて何もかもが完璧でなくてはならないの。分かるでしょう?


ズシンと重石が乗ってくる感覚に反して、長年の練習のせいか取り繕うように顔がほころぶ。



分かるわ、ママ。わたしはそのためにママの娘として生まれたんだもの


心のなかのエリゼは泣いているのに、エリゼ自身それに気づいていないようだった。
だが、エリゼは母親を見捨てることができない理由があった。
いつもいつも、ママは可哀想な人だから自分が救わないといけないという使命感を忘れることがなかった。
エリゼは一生、この美しくて窮屈な鳥かごの中で生きていく覚悟はできていたのだ。



ママ。私はママの夢を辿るからね。あいつとは違う、安心して。そのためにあんな不気味な人形屋敷から飛び出してきたんだもの





そう、そうね。ふふ、そうよ。
ああ、お母様も人形もアリシアも嫌い嫌い嫌い! エリゼ、あなただけ愛してるわ


狂乱状態の母親は割れた花瓶の欠片を踏み潰しながらそう言った。
あいつ――アリシアとは違う。そう、あいつなんかとは違うんだから! エリゼは血が沸騰しそうなくらいの怒りを押し殺して、目を閉じた。
もうアリシアは覚えていないだろう。
昔、コルマールの川で溺れてから幼い時の記憶を手放したのだから、当然といえば当然だ。溺れた事実ですら覚えていない彼女は、母親とエリゼの気持ちに気づくことは金輪際ないだろうと思われていた。
エリゼは誰にも聞こえない声で、アリシアに対する呪いの言葉を吐き捨てた。



あの時、死んでいれば良かったのに


エリゼはことごとく、アリシアを水の中に沈めたがる。セーヌ川のほとりに呼び出して押したのも、遠い昔、川で溺れて戻ってきてほしくなかったからという深層心理が働いたのだろう。
そうだ、今度あいつのいる屋根裏部屋にこっそり乗り込んで、大切にしていそうなものを根こそぎ奪ってやろう。エリゼの企みは毒々しく胸内で花を咲かせていた。
アベルの叫び声が聞こえた。事が起きたのは、パサージュのドーム下にたどり着いたちょうどその時のことだった。
パラパラと氷の欠片のようなものが落ちてきたかと思いきや、上から落ちてきたのは金のプリマ――セレスティーヌさんだった。



お嬢さん!


背後からオズウェルさんの止める声が聞こえたが、わたしの体は真っ直ぐセレスティーヌさんの方へ引き寄せられていた。
刹那、肩と腹部に例えようのない衝撃が走る。私の意識はそこでプツンと切れた。
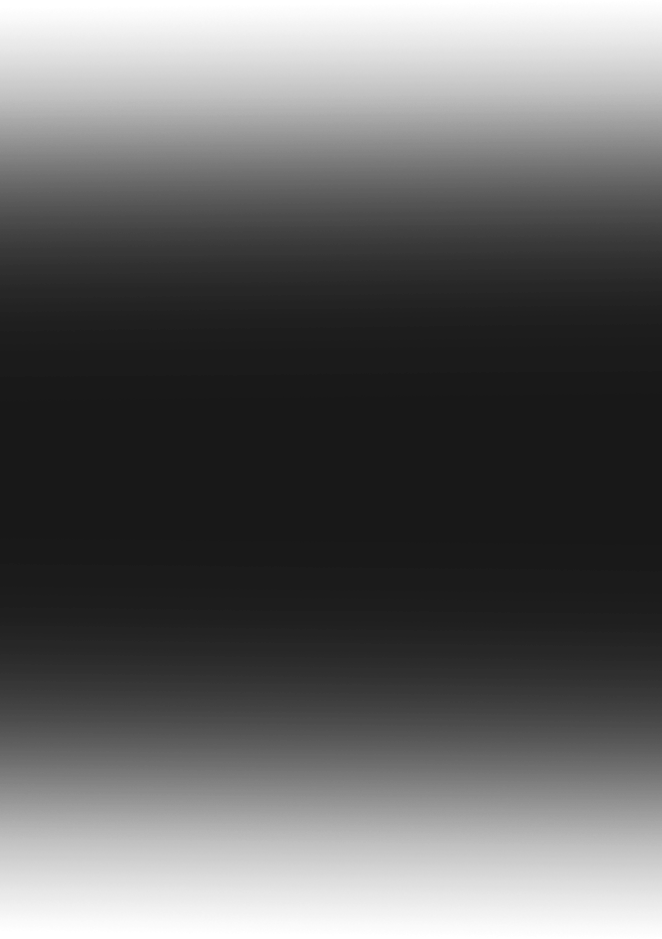
あれ、ここは――?
見覚えのある、時計仕掛けの世界。
中央の時計塔の針は4時44分で止まったまま、というよりか若干針を前後にさせながらカチッカチッと動いている。その周りには、忙しなく動く歯車の音ばかりで、啜り泣く声が混ざっていた。



あなた、本当に馬鹿ね


それは、スカートの短い黒髪の少女の言葉だった。彼女は時計塔の前で、顔を手で覆いながらしゃくりあげていた。
嗚咽混じりの声にど肝を抜かれていると、相変わらず真顔を保っている緑髪の少女が同意した。



庇わなくていい、価値のない人間を庇うなんてね。呆れたボランティア精神だわ


言い返そうとしたが刹那、黒髪の少女が頷きながら少し荒々しい声を発した。



セレスティーヌはね、あの転落で死ぬ予定の人間だったの。
ああ、せっかく収束しそうだった未来が、また分裂した


セレスティーヌが、死ぬ予定だった……? 全身粟立ち、少しよろめいた。



まあ、今までもアリシアは困難に打ち勝ってきたんだから、きっと修正できるだろうけど
気をつけなさい、アリシア
貴方を邪魔してくる存在すら、味方にしてしまいなさいよ





そう……そうよね。頑張っていらっしゃい、アリシア
貴方は全ての起点、イヴなのだから





え?





”Mors certa, hora incerta”<死は確実、時は不確実>よ。死は確実にやってくるけど、それがいつ来るか誰にも分からない。
アリシア、あなたの行動次第でどうなるか変わっていくわ


あのラテン語は、そういう意味だったのか。頭にそのことを刻みつけていると、黒髪の少女は天井を見上げ、ふふっと笑った。



あらま、愛しの彼が呼んでるみたいよ。
でも、彼に溺れすぎちゃあ駄目よ。砂糖はおやつの時間だけにするのがちょうどいいのよ、アリシア。
じゃあね~! また会いましょう!


わけが分からず戸惑っていると、黒髪の少女はずいずいと私を時計台の淵に追いやり、とんっと押した。
視界がふいにぼやけ、黒髪の少女が手を振る姿が闇に溶けていった。
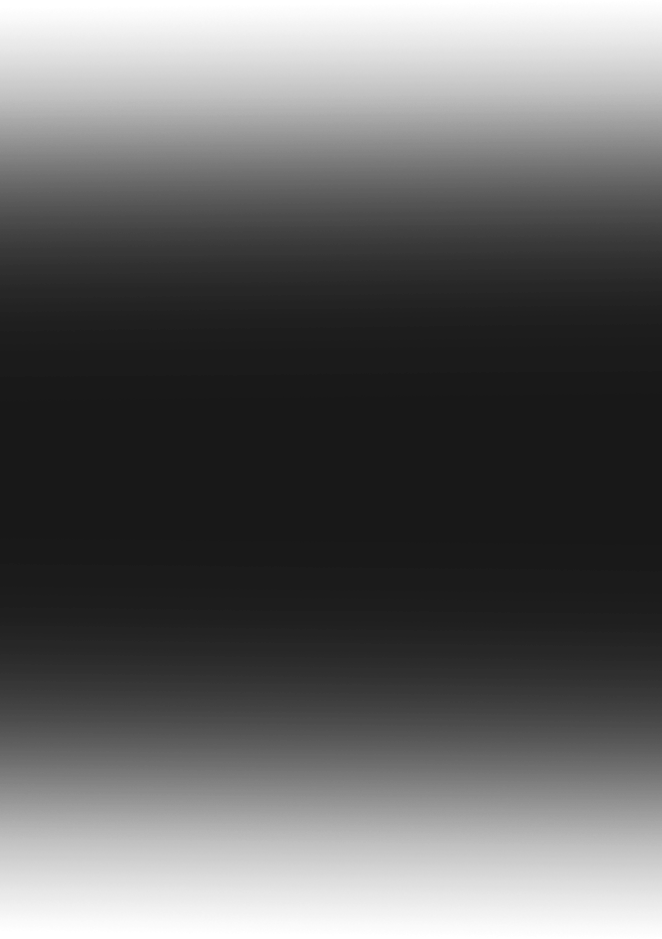



お前はとんでもなく大馬鹿野郎だ


次に意識が覚醒した時、視界いっぱいにアベルの端正な顔が映っていた。そこで吐き捨てられた言葉はとても弱弱しいものだった。



……わた、し……?





お前、覚えてないとか言わねぇよな? 落ちてきたセレスティーヌを庇ったんだよ


そういえば、全身針が刺すような痛みがじくじくと広がっている。少々痙攣する手をアベルの顔に伸ばすと、その手は切り傷だらけだった。きっとガラスの破片で切ったのだろう。



セレスティーヌさんは? 無事?


アベルはわたしの手を掴むと、それをじっと見た。



あんまり無理に話すな。
――ああ、あいつはお前が庇ったお陰でなんとか生きながらえてる。
こんなに傷までつくって……どうしてお前はいつも、考えるより先に行動する


そうだね、確かにわたしはそういうところがある。毛布の中で身動ぎしつつ、毛布で顔の下半分を隠した。



ご、ごめんなさい。でも、後悔はしていないんです


例えセレスティーヌさんがあの時死ぬ予定だった人間、だとしても。
あの時、アベルはきっとセレスティーヌさんを助けようとしたはずだ。それを代わりにわたしがやってのけたのなら、それは誇らしいことだ。それに――。



セレスティーヌさんは、昔わたしに夢を与えてくれた人なんです。オペラ女優になるという夢を


彼女がいなかったら、わたしは灰に埋もれた世界で生きていたことだろう。窒息死しそうだったわたしを救い出してくれたのが彼女だった。わたしにとっては一縷の希望だったといっても過言ではない。
今はどうであれ過去の彼女は今でも尊敬しているし、わたしの目標に違いない。



なんでお前が泣いてるんだ。理解に苦しむ


アベルは立ち上がり、乱暴にもうひとつの毛布をわたしの顔に被せた。



幸い、骨は折れてねぇってさ。取りあえず泣いてる暇があったら寝てろ





……はい


乱暴なくせに、少し優しさを見せるアベルに顔が緩んだのは秘密だ。



優しいのね





――そんなことない。それに、俺はいつだって無力だ


帽子をかぶり直したアベルは長いまつげを伏せてわたしを一瞥すると、部屋から出て行こうと扉を開けた。
駄目だ、このままアベルが出て行ってしまったら一生戻ってこないかもしれない。そんな得体も知れない恐怖感が喉にまでせり上がり、毛布をぎゅっと握りしめた。



そ、そんなことない。そんなことないからね!
わたし、貴方に救われてるのよ、アベル!!
ずっとずっと生きながらに死んだ心で生きていたわたしを、生き返らせてくれたじゃない……っ。無力だなんて、言わないでよ……


無理矢理上半身を持ち上げると骨の奥で激痛が走り、そのままベッドから崩れ落ちた。
ビタンと頬に床があたれども、構わず顔をあげて手を伸ばした。



アリシア、お前……! なにしてんだよ


寝てろって言っただろう! と語気を強めながらこちらへ戻り、倒れたわたしを支えあげようとした。 しかしその手をひしと掴み、首を振った。



アベル、行かないで。わたし、貴方のことがす……


ハッとして、我に返る。わたし、今「好き」と言おうとした?
それは彼にとっては呪いの言葉だから、絶対に口にしてはいけない。例え死のうとも、心に押しとどめて膿んでしまっても。
今まで他の女性は、アベルに「好き」と言ってきただろう。
でもそれは、アベルの心よりも自分の心を優先させている証だ。わたしは、そうしたくない。アベルが苦しむくらいなら、自分が二倍苦しんだほうがいい。
ゴクリと飲み込む。
針のような心の疼きさえ、彼には気づかれぬよう温めておけばいい。この熱は、彼が必要とした時にのみ活かせばいいんだ。



言葉って難しいね、アベル。思考の中に収まらなくて、どうも言い表せないの


まっすぐと彼のブルートパーズの瞳に訴えかけた。空のような瞳で、それこそ空の視点から人間や流れる時代を見てきた彼に、わたしの言葉はあまりにも拙すぎる。



もう、なにも言わなくていい。黙ってろよ


言葉は乱暴なのに、彼はわたしの手を解くと、わたしの額に自身の額をコツンと当てた。
いよいよ彼との距離が睫毛の距離になり、観客は窓の外から除く満月だけになった。
心臓が大きく鼓動していることを、額越しに伝わってしまいそうで怖くなる。
闇夜の海に浮かび上がる夜光虫のように青白く光る瞳に、吸い込まれそうになった。それでいて、心奥まで突き刺さる強靭な視線。なるほど、今まで数えきれないほどの多くの女性がアベルに惹きつけられたのも会得がいく。



言葉は万能じゃない。どうしても言葉で伝えられないことは、俺でもあるんだ。
それに、だてに長年人間を見てきていない。お前の視線と鼓動で、抱いてる感情は大体分かる





め、迷惑じゃ、ありませんか……? この、感情は。
あの、押し付けるつもりは、ないんですけど……


あ、また緊張して敬語になってしまった。頬に熱が集中して下唇を噛み締めていると、アベルは額をパッと離し、呻くような声で呟いた。



それを呪いに変えないなら、別に迷惑じゃねぇよ


アベルのその言葉に、わたしは心踊るほど嬉しくなる。わたしってなんて単純なんだろう。
このまま幸せでいたい、これ以上の幸せは望まない。そう、思っていた――。
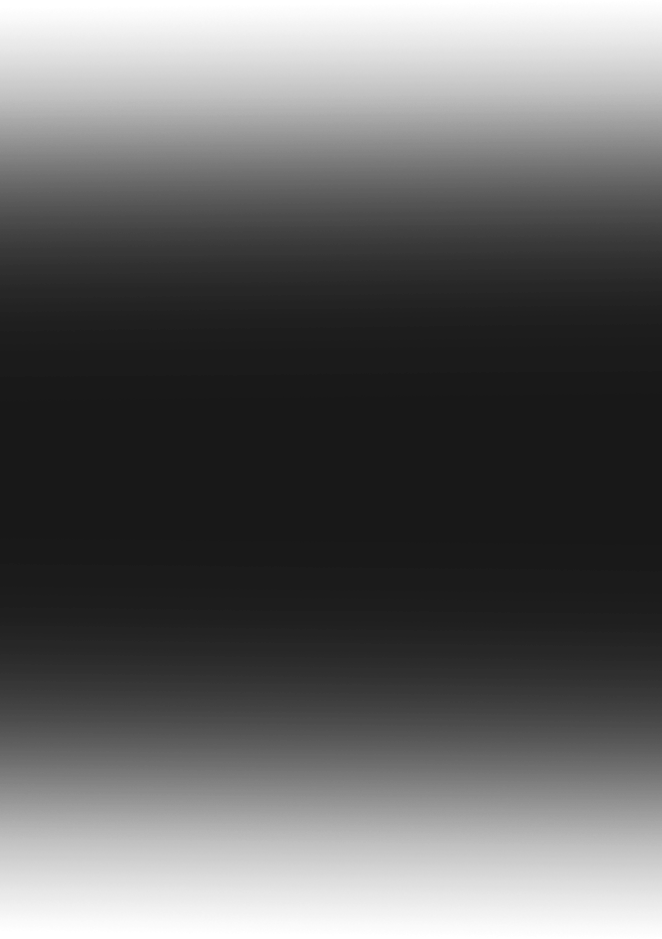



アベル、お前変わったなぁ





なんだよエリオ。別に俺は過去も今も、ずっとこんな調子だ


アベルは仏頂面でそう答えると、その声は天井の高いセレナーデの図書館の隅々まで反響した。亡者たちの湧き上がるうめき声に勝る反響は、アベルの動揺具合を表しているように思えた。
今、図書館にはアベルとエリオしかいない。
アベルはエリオが苦手だった。チャラチャラと深く考えていないように見えて、意外とその裏面では熟慮している食わせ物だからだ。
エリオはにんまりと笑いながら、二階のイーゼル越しにこちらを見下ろした。が、すぐに絵画へ目を向ける。左手に筆で塗りつつ、右手は指揮者のように動かしながら、エリオは熱弁した。



まるで恋する乙女のようなアンニュイな瞳……!
ぷっ、アベルをこんな表情にさせる悪い子猫ちゃんは誰だろうなぁ!





別に恋してねぇし。若造が調子にのるなよ、エリオ





ふふん、アベルー


エリオは指揮棒をくいっと動かすように右手を動かすと、首を傾げてカンバスから顔を離した。



自分に素直に生きねぇと、とんでもない後悔をしちまうぞ


態度が一変。軟派な口調から押しつぶすような重い口調に変わった。アベルは眉根を上げ、エリオを睨みつけた。
こいつは23歳ではない。
そもそも、このセレナーデのメンバーであること自体、「普通の人」ではない。
アベルはエリオの心境を探るようにじっと表情を窺ったが、やはり読めなかった。



お前、本当の歳を言わねぇけど実は歳食ってるだろ?





あれ、バレちまったかー!
流石アベル、セレナーデの年長者なだけあるなぁ。尊敬するよ!


エリオは喜色の絵の具で顔面を塗りつぶし、本当の感情を隠してきた。
社会になじまざるを得ない芸術家たるもの、一般人と溶け合えない感情を隠すことは必須事項なのだ。



アベルほどじゃないけど、それなりに生きてきたよ。でも、
君とは違う。
俺の場合は、記憶がなくなっていくんだ。だからずっと若々しく、苦しみもまっさらにして生きていける。
……君は気の毒だと思うよ、アベル。忘れたくても、忘れることができないんだからね!





…………





あれれ、図星? あはっ、嬉しいなぁ。いつもはアベルが一枚上手なのに、弱点を突いたらあのアベルに、舌戦で勝っちゃったってか?





黙れよ、エリオ





黙らないよ


今まで聞いたことのない、地を這うようなエリオの声にアベルは流石に目を丸くさせた。
まるで、葉叢(はむら)に隠れていた獣が姿を現したよう。
エリオを見上げると、エリオはもう笑っていなかった。真顔で、陰をさした瞳でこちらを見下ろしていた。



君はずるいよ、アベル。
いつも不意に、思いつめた顔をしてさぁ。そんでもって知らず知らずのうちに人の心を掴んでいく。
永く生きていようが短く生きていようが、誰もが心の出血を抑えながら平気な顔をして生きてるんだ


エリオは筆についた紅色の塗料を指ですくいとると、それを大切そうに握りしめた。



セレスティーヌの時だってそうだった。
アベル、君はずかずかとあいつの心に入り込んでいった。けど、好きになられたら困るから退ける。それはおかしいだろ?
それなら最初から入り込まなかったら良かったじゃないか、俺みたいに


握りしめた手を開くと、紅色の塗料で右手が赤く染まっていた。それが血のようだったが、エリオは愉しげにそれを照明に当てて眺めていた。



勝手な奴だ、そう言いたいのか?





ああ。あの子……アリシアも犠牲になるんだと思うと、不憫でね。俺はこう見えて、情の深い芸術家なんだぜ


にこっと好青年のようなほほ笑みを浮かべるエリオだが、もうそれはただの繕いのようにしか見えなかった。
アベルはアリシアの話が出てギクリとした。エリオに、自分とアリシアの関係を口出されたくない。そう思ったアベルは酷く棘のある口調でぴしゃりと言い放った。



俺とアリシアとの関係は、お前には関係ない話だ





いーや、関係あるね! 君のせいで、彼女は銀からくすんだ灰に変わってしまう。





……あの子に、君はふさわしくない


エリオは二階の手すりに肘をつき、唇に弧を描かせた。



アベル、君がまた今までのようにアリシアを誑かすつもりなら――俺が奪っちゃおうかなぁ


アベルは再確認した。やはり、エリオは苦手だ。否、スケル・トーンとはまた違った意味で、それ以上の存在だと。
ちょうどそんな時。タイミングを見計らったように、天井から四角い床が降ってきた。オズウェルとスケル・トーンが帰ってきたらしい。
黒猫姿のオズウェルは綺麗に着地したが、足首をくじいたスケル・トーンは



骨が折れたー!!


とその場で悶えていた。もちろん、皆無視をした。
オズウェルは華麗に人間の紳士姿に戻ると、穏やかな表情で首をかしげた。



驚いた。合理主義哲学者と鬼才の芸術家はウマが合わないとはね。この題材でいい詩がつくれそうだ





オズウェル、聞いてくれよー!
俺はアベルと仲良くしたいんだけどさ、アベルは俺のこと毛嫌いしてるみたいなんだ。寂しいなぁ


コロコロと玉虫色のように態度を変えるエリオに吐き気がした。アベルは無言のまま、ひたすらエリオの弱点を見透かそうとしていたが、エリオはやはり仮面を貼り付けたままだった。
誰にも心を許さない。自分と似ているようで、自分以上に厄介な奴だ。



あ、そうだ。
オズウェル、この間の賭けの件だけど負けを認めるよ。50フランなんて、くれてやる!


ハラハラと50フラン分の紙幣が二階から降り注ぐ。
オズウェルはそれを拾うことはせず、ただただ天変地異に立ち会ったかのように、モノクル越しからぱちぱちと不自然に瞬きを繰り返した。



賭けの件って、お前、お嬢さんに――?


オズウェルが続きを言いそうになった瞬間、エリオは目を細めて言葉を被せた。



現実に、俺が追い求めてた銀色の色素が現れたんだ。
ピトレスク(絵画的な美)を求める俺が、見逃すとでも?


エリオのそれは明らかに、アベルに向けた挑発であった。
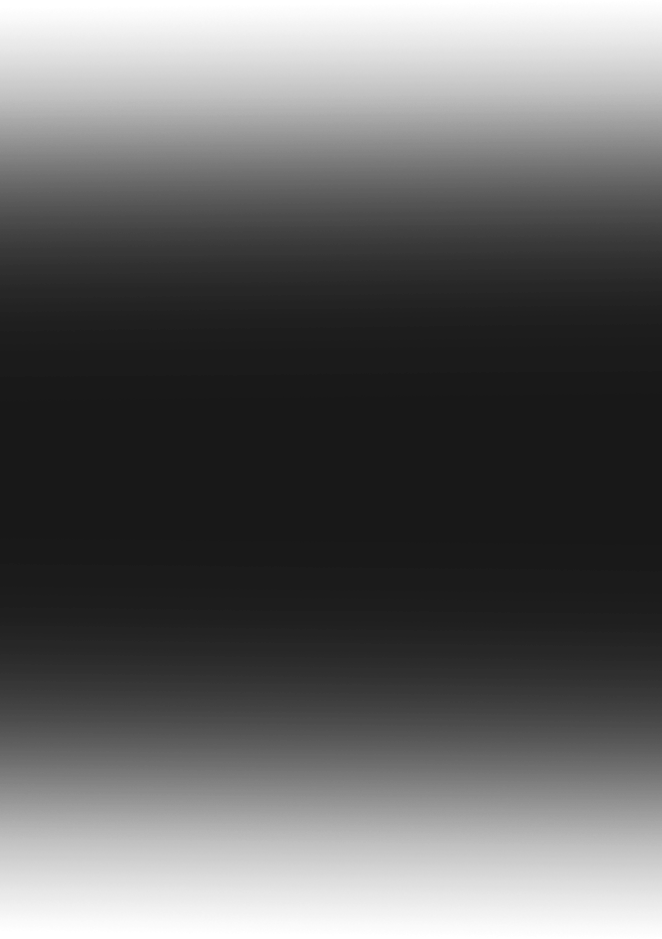
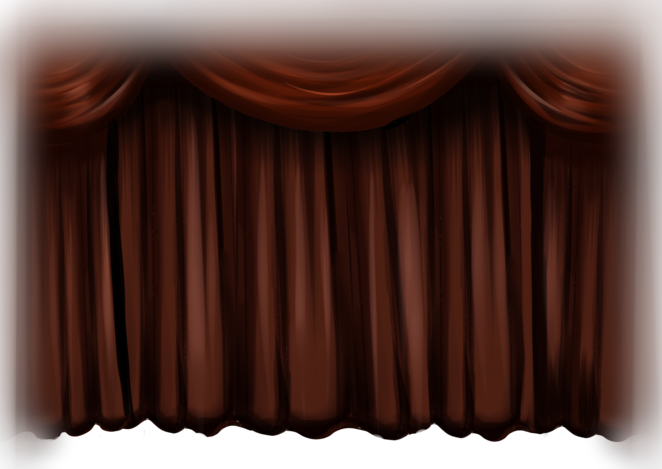

聖花さん、20幕までおめでとうございます!
エリゼの考え、これからのアベル、エリオ、アリシアの関係性が気になります。
続きを楽しみに気長にお待ちしておりますので、どうぞ無理なさらずに聖花さんのペースでやっていってくださいね(o^^o)これからも応援しております!
今回の話もとても良かったです!
アリシアはアベルに思いを伝えたいのに、伝えると嫌われ、離れてしまう。そう思って伝えようにも伝えられないもどかしさ…胸が痛いです。でも、きっといつかアリシアはアベルに思いを伝えられるって、思ってます!
そして身を呈してセレスティーヌを守るアリシアが健気で優しくて…とてもいい子なんだな、と伝わります!エリオも表面上はチャラチャラしていますが、きっと重く深い過去を抱えているのでは、と私は思います。全員が全員ハッピーエンドになる訳では無いかもしれませんが、それでも全員の幸せを願います
エリゼも、親の期待にいつか潰されないかと心配です。きっとエリゼ自身は母の為にと思っているのでしょうが、それはきっと身を潰すだけなのだと思います。エリゼが、そして母が今の自分達は間違っていると気づいてくれたらいいな、と思います。
たくさんの想いが交錯した20幕目でしたな!
そしてこれからがまた楽しみな!
エリオの正体が分かりそうでまだ少し足りなくて、アベルとエリオの駆け引きもハラハラしました。エリオはオズウェルさんとの賭けに負けたって自覚したかー、そうかー。うふふ。
陳腐な恋愛小説ではない感じが好きです。
◆いつも「ああぁああああ!」って所で終るこの歌劇…。個人的にはエリザの心情が気になりますね。このまま母の操り人形で生きていくのか、はたまた目覚めるのか。結構嫌いじゃないキャラです。
聖花様、20幕おめでとうございます(◍•ᴗ•◍)
いつも楽しく読ませていただいています!
アリシアの気持ち、アベルの気持ち、エリオの気持ち、そしてエリザのアリシアに対する気持ち…
全てが気になりすぎてます…!
そして、アリシアとエリザ、お互いの思いの内を話せて笑いあえたらどんなに素敵か…!
とは思いましたが、お互いの気持ちを考えると難しいんだろうな…と少し悲しくなりました。
これからどうストーリが進んでいくのかとても楽しみです!
長文失礼いたしました。