わたしの人生の譜面にはいつも、不協和音が染み付いていた。わたしはそのことに気が付かず、指揮者もいない独り舞台に立ち、ずっと嗄声(させい)で歌っていたんだ。
もう、古傷に悶え苦しむ自分とはおさらばしたい。わたしが歌いたいのは、歪んだ不協和音じゃない。美しい協和音なのよ。

わたしの人生の譜面にはいつも、不協和音が染み付いていた。わたしはそのことに気が付かず、指揮者もいない独り舞台に立ち、ずっと嗄声(させい)で歌っていたんだ。
もう、古傷に悶え苦しむ自分とはおさらばしたい。わたしが歌いたいのは、歪んだ不協和音じゃない。美しい協和音なのよ。
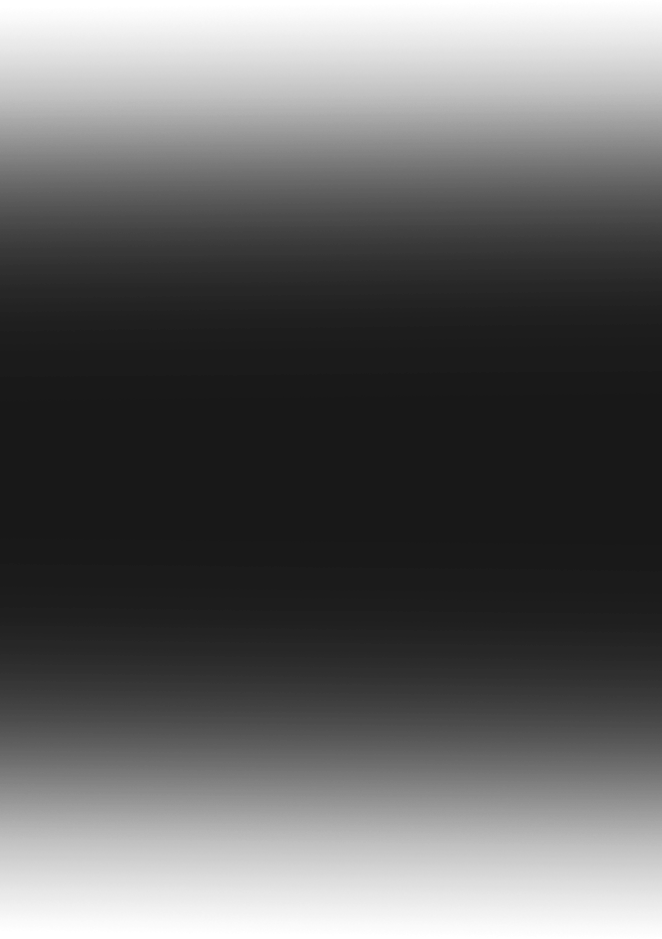
窓ガラスにふきつける、細かい雨。
窓の高いところにかたつむりが二匹身を寄せあっていて、どことなく微笑ましい。番(つがい)かしらと思いつつ出窓で肘をついて眺めていると、背後から風情もない言葉が投げかけられた。



プチ・グリがこんなところにいるとはな。ブルゴーニュ風にして食ってやれば?





い、いくら食用のかたつむりだからって、可哀想よ……


プチ・グリという種のかたつむりは食用で、古代ローマ人がよく好んで食べていたらしい。
今ではフランスの名物として、よく白ワインを飲みながら前菜として食べられる。
でも、わたしはどうしてもかたつむりが食べられなかった。
殻がなくては生きられない生き物なのに、無理矢理そんな殻から引き出して食べるなんて酷いにも程がある。そう思いながら、心のどこかで殻から出てこれない自分とかたつむりを同一視していたのかもしれない。



ねぇ、アベル





あ?





わたし、殻から抜けだしてみようかなって、思ってるの


解放をもとめる心根を丸出しにしてみた。アベルのページを捲る音がピタリと止まり、古びた屋根裏部屋には雨が殴りつける音に満たされた。
ぴちょん、ぴちょんと雨漏りした雫がバケツの中に落ちていく。もうすぐで水が溢れそうだと思いながら眺めていると、本をパタンと閉じる音が聞こえた。



いいんじゃねぇの。
この前、派手なドレス姿で帰ってきてからお前、変わってきたみてぇだな? どうした、恋でもしたのかぁ?


険のある瞳がわたしを見かえす。わたしはどうにかアベルに心境の変化を伝えるべく、咄嗟に思ってもないことを言ってしまった。



そ、そうよ


あ、違う! と思っても後悔先に立たず。
アベルは瞼を落として、そうかそうかと軽く受け流した。
え、それだけ? もう少し、こう――「誰に?」とか、「どういうことがあった?」とか聞いてくれはしないんだ、と思ってしまう自分がいた。
わたしはアベルに興味を抱いていたとしても、アベルはわたしに興味をもってくれない。何だろう、この温度差は。
陰鬱な気持ちになりながら、ふとバケツに満ち満ちた水の中に指を入れると、水面がバケツの縁に到達してしまった。



言っておくがアリシア。お前の嘘はわかりやすい


アベルの言葉が降ってきた途端、大きな雨雫がポチャンと派手に落ちてきた。
表面張力をゆうに超えたバケツの水が、そしてわたしの感情が、同時に溢れでた。



あなたに何が分かるの。わたしの、何が


知っている。アベルはわたしよりずっと永い時間を生きてきて、人の死だって見てきただろう。人形とはいえ、色んな経験をしてきたはず。
そんな彼からしてみれば、わたしの拙い嘘なんて見破られるだろうし、必死に感情を表現してもぎこちなさのあまり鼻で笑うレベルに違いない。
それでもわたしは必死に背伸びをして、他人に関心がなかったのにアベルを知ろうとしているのに。
いつもアベルはそんなわたしを俯瞰して、観客席から眺めているばかりだ。舞台に立って必死にわたしが求める声をあげていても、高みの観客席から降りてくれない。



わたしをこんな気持ちにさせるアベルなんて、


嫌いよ、と言いかけたがぐっと堪える。その時バケツの水面に映るわたしの憎悪に歪んだその顔は、異形より醜かった。



……アベル。どうして、そんな顔を?


ふとアベルを見やると、アベルはなにかに恐怖するような表情でわたしを見ていた。人間であったなら、血の気の引いた顔、と言ったら妥当だろう。



嫌いになればいいさ。嫌いになってくれたほうが、俺は楽だからな





……酷い人ね





人じゃない、人形だから当たり前だ





そう言いつつも、どうしてそんな目でわたしを見るの?


ベッドに腰掛けたアベルに歩み寄り、控えめにアベルの服の袖を引っ張る。
アベルの左目が揺れていることを見逃すはずがない。強気な態度で一見分かりづらかったけども、きっとアベルには恐怖心があるんだと確信した。



お前がどんどん『探し人』に似ていく……なぜだ?


アベルに手を引っ張られ、わたしは仰向けにベッドに転んだ。天井とアベルの憎悪の滲んだ表情が視界に映る。手首を強い力で握られ、骨が悲鳴をあげそうになっていた。



教えてやるよ、アリシア。
俺の『探し人』はな、感情のままに無責任な言葉を吐き出す愚かな人間だったんだ。言葉巧みに人の心を紡いで操り、いらなくなったらその糸を無感情に切ってしまう。
俺はそいつに呪いをかけられたんだ。『好き』やら『愛してる』やら、『完璧じゃなくても、貴方を見捨てない』って、何度も何度も何度も。
散々愛玩人形の扱いを受けた後、そいつは俺を切った。そう、容赦なくな!
そいつは遠距離恋愛中の恋人と子どもをつくり、俺の前から姿を消した


語気を強めて奥歯を噛みしめるアベル。感情を露わにした姿をはじめて見て、わたしはただただ眼の前の出来事が信じられなくて言葉が出なかった。
胸が締め付けられるように痛くて、無意識にアベルの首の後ろに腕を回していた。アベルはびっくりしたように体をよじらせたが、構わずそのままわたしは抱きしめた。しばらくして諦めたのか、アベルの体重がこちらへ寄りかかった。



予め言っておくが……同情なんていらないからな





同情じゃない、です。共感です


押し殺していたアベルの感情、少しでも受け止められたら良いのに。そう思うと、抱きしめる腕の力が強くなる。
首あたりにアベルの柔らかな髪がくすぐり、やっと自分から抱きしめてしまっていることに気づいて心拍数が上がるが、ここで腕を離してしまったら一生アベルを離してしまうことになりそうでぐっと耐えた。



わたしは、そのかけられた呪いからあなたを解放したいのだと思います


首に僅かにかかっていたアベルの呼気が止まった。



無理だ。根が深いからな





無理じゃない、です。
できる気が、するんです。
それで、その『探し人』を見つけたら、言ってやりたいんです。「よくもアベルを苦しめましたね」って、ビンタしてやるんです





……ぷっ。お前、そんなことができるほど勇気ねぇだろーが


肩を震わせて笑い出すアベルに、ほっと安心して息が漏れた。馬鹿野郎と言いながら起き上がるアベルは、いつもに増して愉しそうだった。



その前に、お前をオペラ女優にしてやらねぇといけない。人の生って短いから大変だ





――なれるかしら?





お前が『探し人』にビンタするよりは、高い確率でなれるだろうな。
頑張れば、だが。
上には上がいるから、今度オペラ・コミック座で観てみようじゃねぇか


アベルはいつもどおりの自信満々な表情で腕を組んだ。
アベルは正直、まだまだ秘めている事実や感情があると思う。それこそ、先ほどの吐露は氷山の一角にすぎないはずだ。
それでもわたしは、この人と――人形と一緒に歩んでみたいと思ってしまった。わたしは本当の意味でアベルを受け入れ、わたし自身をも受け入れ、ちいさなちいさな一歩を踏み出したのだ。
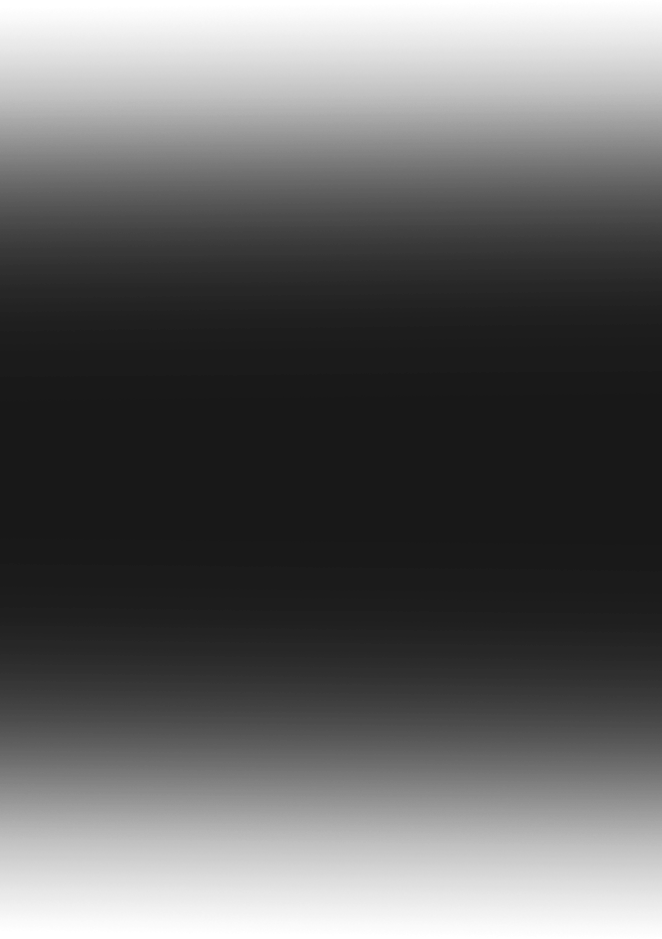
パリの雨はすぐに止む。わたしは今の嬉しい気持ちを真っ先にニナに聞いてほしくて、水たまりを気にせず走った。
雲の隙間から太陽がのぞいてきて、光のカーテンがパリを包み込む。
こじんまりとした木造のキヨスクで『イリュストラシオン』が売られ、エリオさんが仕上げたであろう精緻な版画絵が視界の隅に映る。
高貴な黒猫が横切り、オズウェルさんを彷彿とさせる。
怪しげな露店で古臭い人形が売られている。アベルと同じ匂いがする。
ああ、パリってこんなにも肌で感じる「身近な息吹」があったんだ。
わたしは視ようとしなかっただけで、ずっと存在していたのね。新たな感覚を身につける度に、わたしは生まれ変わっているのだ。
背筋を伸ばして大きく空気を吸い込む。そして、右目にかかる邪魔な前髪を払いのけた。今まで視界を遮っていた右目が光をとらえた。
「光の都市・パリ」は生と死が混在した異様な街。
裏を返せば、生だけでなく死でさえも受け入れる街。わたしはむしろこの街だから、今まで生きてこれたのだと痛感した。



がんばろう、わたし


そう決意をこめて頷いた直後、背後から鈴の音がシャランと聞こえた。柔かすぎる音が、パリには合わない。
けたたましい雑音の中際立つその音に意識を集中させていると、カラン、カランと不思議なくぐもった靴音がこちらへ近づいてくるのを感じ取った。
ドキドキと足を止めるや否や、視界の隅に変わった靴が入ってきた。何だろう、木でできたこの靴は。



すみません


じっとそれを見ていると、今まで聞いたことのない柔らかい発音がその人物の口から発せられた。



すみません。巴里は広すぎるものだから、少し道に迷ってしまって……お助けいただけますか?


そこには、目を疑うほどに神秘的な東洋人が佇んでいた。思わず呼吸の仕方を忘れ、まじまじと魅入ってしまう。



申し遅れました。私、鈴花(すずか)と申します。
はるか遠くにある日出づる国、日本からやって参りました


雨上がりの空には虹がかかっており、その下にはサクラを彷彿とさせる少女。
周りから色んな意味で浮いているその少女は真夜中の空を体現したような髪を靡かせ、幼い顔立ちには似合わない妖艶な微笑みをつくった。
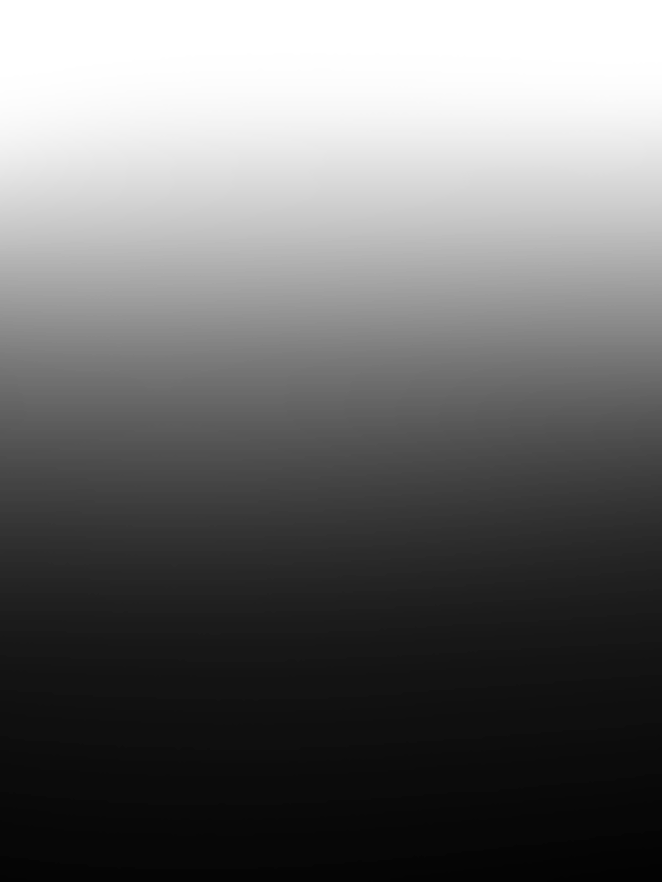
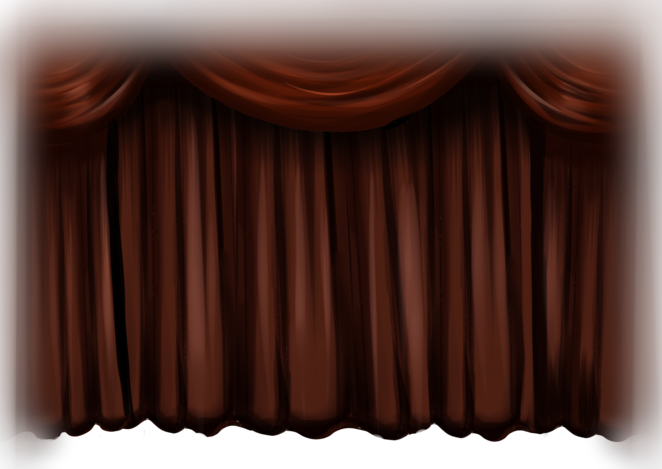

今回の2人の間のやり取りとても好きです…!上辺だけの恋愛感情だけでなく思いを吐露した中で混ざり合うアリシアの感情とアベルの複雑なる過去。無意識に無自覚に(?)強く前を向きつつあるアリシアが見る今までとは違う景色。本当惹き付けられます。そして鈴花ちゃん登場!!カワイイ!w文字数
遂にアベルがアリシアに甘えた…!?よく見る恋愛モノと違う切なくも美しい恋愛?描写に胸がきゅんきゅんします!そして…鈴花ちゃんきたー!!!本格的な活躍を楽しみにしています!!これからも機械仕掛けの世界展に小説にイラストに…応援しています!!頑張ってください!!!
アリシアたんとアベルのやり取りがすごく印象的でした。
アベルはきっと穏やかに感情を殺しつつ、でも殺しきれずに吐露してしまうのかな、とか。
今後の2人に期待、と思ったところで鈴花ちゃんきたーーー!この出会いからアリシアたんはまた変わるのね、ワクワク!
アリシアとアベルの関係性が、私のときめきを蘇らせてくれました。なんともいえない、もどかしくはがゆい…しかし、1つずつ感情が剥がれていくアリシアとアベルが本当に素敵です(*^^*)
鈴花ちゃんも麗しくて、これからの展開に期待が高まります!
聖花さんの話、気長にお待ちしております。