その日は、雪の降る夜だった。
その日は、雪の降る夜だった。
《俺》は。
ただ、震慄(ふる)えていた。
怯えるように。
憤るように。
《あいつ》は。
縋るように。
逃げるように。
ただ、慟哭(な)いていた。
吐く息は、白く。
眼前には、赤。
指先で肌に触れると、
それは氷と紛うほどに冷たくて。
そこからは、
一切の温もりを感じ取る事ができずに。
思考は止まり。
感情は冷えきり。
身体は竦んで。
もはや、何も、動かない。
紅白に染まった視界の中。
《俺》は声に出さず、だれかに尋ねた。
『どうすれば、この地獄に居続けられますか?』
2.咎人
歴史とは、犯罪と災難の記録にすぎない。
History is only the register of crimes
and misfortunes.
高校一年生の二学期末。
本格的な冬が到来し、朝夕の冷え込みが増す時期。
この半月ばかり解けては積もってを繰り返していた雪が、やっとといった様子でなだらかに積もり始めている。
路面には氷が薄く張り、歩行者も車両もこぞって《冬用の足》に履き替え始める、そんな時節。
世間では既にクリスマスに向けてのムード作りが着々と進められており、街中が色めきだった雰囲気で賑わいを見せる中――俺はキリと連れ立って、我が部のお稲荷様ことてんこが坐す、荒廃した名もない神社に足を運んでいた。
学生には貴重な放課後の自由時間を使ってまで、寒風吹きすさぶ寂れた社へ赴いた理由はただ一つ。



はあ、嘆かわしい。只々、嘆かわしい


神様のご神託――というか、お説教を受ける為だった。
てんこはいつもの朽ちた賽銭箱の上に座ったまま、眼を閉じて慨嘆する。



今回は偶々処置が間に合ったから良かったものの。下手を打てばお主ら、昨日で死んでおったんじゃぞ? 本当に。全く危機感が足りん


器用にも言葉の端々に溜息を差し込みながら、てんこはぐちぐちと小言を続けている。
発端は、先週から調査を続けていたあるミームの霊障によるものだった。
俺とキリは、今年の春から《meme研究部》の活動を行っている。
が、現在我が部には俺達二人しか部員が存在しない。
場馴れした人間のいない中手探りで続ける調査活動には、常に危険がつきまとう。今回もそのご多分に漏れず、俺達の不注意によって危機を呼び込んでしまい、それをいつも通りてんこに助けてもらった――ということだった。



お主ら、この半年で何度死にかけたか憶えておるか。吾輩は憶えておらんぞ。もう少しばかり、命を尊ぶ事を覚えよ


と言って嘆息した。
ううむ。一理ある。



そうは言うけどさ。これでも、アタシらも割と精一杯やってんのよ?


ね、的? とこちらに同意を求めるキリ。



んまーな。当然。命懸かってるワケだからそりゃ必死ですよ


同調してみた。
が、てんこはじろり、とこちらを睨みつけながら言った。



じゃから、その懸命さが足りんと言っておる。……はあ、何とも遣る瀬無い


てんこはふるふると頭(かぶり)を振り、続けて言った。



お主らに撫子子ほどの力を期待している訳では無い。では無いが、それでも撫子子のおらぬ今、自衛くらいはある程度こなせるようになってもらわねばならん。……特に的、お主はな





名指しかよ。そりゃ、《俺》には篁さんやキリみたいな戦う力は無えけどさ――





そういう意味ではない。解っておるじゃろう?





…………


少しだけいたわるような目を俺に向けて、てんこは続けた。



……今更言うまでもないが。《お主》が持つ性質は、常人の其れとは全く異なる。撫子子のような《強さ》とも違う。謂うなれば、《妖しさ》じゃ


妖しさ。
怪しさ。
異しさ。



お主の其れは、吾輩の知りうる誰よりも妖しく、そして――佼(うつく)しい。其れは凡百の霊や妖にとってはまさに《麻薬》であり、同時に《劇薬》となるじゃろう。……まあ何にせよ、其れがお主にとって危険を呼びこむものである以上、自衛の手段くらいは確保せよという話じゃ


言うとてんこは目線を俺から逸し、ぼんやりと宙を見やる。



しかし《下犬目》、か。全く厄介な血筋を持ったな


と、さも曰くありげな口ぶりで、てんこは吐き捨てた。
血筋。
いや――血統か。
下犬目という血統は、世間的にはいわゆる名家として通っている。
が。
その隆盛の裏には、公にはされない陰惨な歴史がひた隠しにされている――
――下犬目の家系は、代々霊能者の血統として知られている。
その能力でもって、占術師や祈祷師といった生業を営み、今日まで続く繁栄を築いてきた――というのが表向きの顔。
だが。
実際には、《下犬目家の者には、いわゆる霊能者としての力は、無い》。
いや、正確には全くの無能力というわけではない。一般人のそれと比べれば、適性は確かに有る。
が、その程度。
その程度だ。
霊的存在に対する直接的な解決手段を持ち合わせている訳でも、未来を正確に見通す千里眼を持っている訳でもない。
そんな下犬目家が今日まで栄華を保っていられた理由が、てんこの言う《魂の特性》。
俺自身にも、しかと継がれている、この特性。
それは、てんこの説明通り――霊的存在に対する《麻薬》と《劇薬》の役割を果たすというもの。
あるいは、《餌》と《毒》。
《囮》と《罠》。
《罪》と、《罰》。
餌とは文字通り、俺達の持つその稀有な魂の波長――てんこの言うところの《妖しさ》――が、必要以上に怪異を惹きつけてしまうというものだ。
霊を、妖を、時には神でさえも、呼び込んでしまう。
それはやっぱり必要以上であって必要以上でしかなかったが、俺の先祖はこれを必要悪に転換した。
つまり、その特性を利用して――あるいは利用されて、下犬目家は成り上がりを図ったのだ。
詮ずる所、人柱。
生け贄。代価。捨て石。犠牲。人身御供。殉教。
そんな存在として、子を、兄弟を、時には自身を差し出すことで。
提供することで。
例えば、荒ぶる御霊を鎮めるための供物として。
例えば、豊作や雨天を祈願するための贄として。
例えば、強力な呪詛をかけるための代償として。
例えば。例えば。例えば。例えば。例えば。例えば。
削られ、奪われ、捨てられ、割かれ、抉られ、侵され、
補い、与え、授け、聞き入れ、許し、捧げ。
悦んで、差し出して。
そうすることで――
下犬目家は世間に時代に取り入り、ひとつの地位を築いた。
これが、下犬目の《罪》。
その罪は連鎖し、やがて怨嗟となる。
罪重なって、罰を生む。
捨てられた石は、
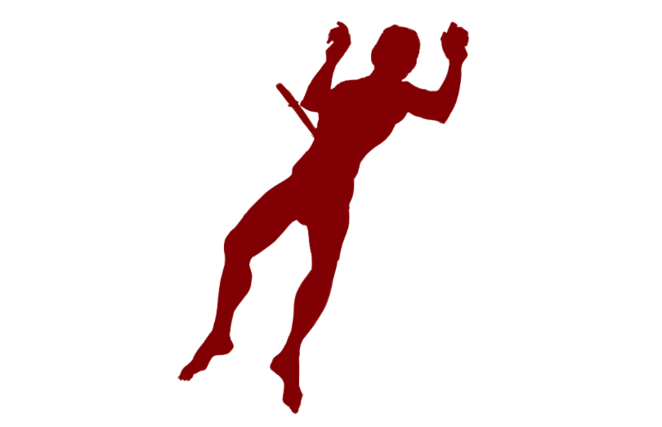
当てられた馬は、

噛みつかれた犬は。

その不条理を呪い、不合理を呪い、不道理を呪い、
世界に呪いを振りまき、
振りまき、振りまき、振りまき、
振りまいて。
孤独に死んで――蠱毒を生んだ。
長い年月を経て、毒としてこれ以上ない程に完成(だらく)した下犬目の《血》は。
《呪い》は。《業》は。
遂に、霊を、妖を、神すらを。
《殺す》までに、行き着いた。
あるいは、死に着いた。
《下犬目の血を取り込んだ怪異は、
力の大小を問わず、その業に飲まれる。》
《下犬目の血を取り込んだ怪異は、
その代償として命を、存在を喪失する。》
これが、下犬目の《罰》。
もしくは、世界への《罰》。
だから、そこからあるのは、負の連鎖。
時には、荒神を討ち滅ぼすための贄として消費され。
その無念は、呪いに形を変える。
時には、血に引き寄せられた怪異によって消費され。
その絶望は、呪いに形を変える。
罠を磨き、罪を重ね、毒を強める。
それはもはや、千日手。とんだマッチポンプ。狐と狸の化かし合いだ。
終わることのない、罪と罰の螺旋構造。
詰まる所、下犬目とは、《消費物》の血統なのだ。
どうしようもなく壊れていて、例えようもなく完成されている、消費物としての生。
その中でも、《俺》は――



おい、的


はっ、と顔を上げる。
……どうやら、随分長い間考え込んでしまったらしい。



……すまぬ、少々軽率じゃったな


そんな風に真摯に詫び入ると、息を全部吐き出してからてんこは続けた。



しかしこれは、お主らの身を案じて言っていることでもある。……解っておるとは、思うがの





……ああ。解ってるよ、有難うな





まあ、そもそもお主らの身の安全を最大限保証するのは契約の内じゃからの。じゃが、それを抜きにしてもお主の性質(それ)に関しては、出来うる限り何とかしてやりたいと考えておる


其れが吾輩の贖罪でもあるしな、とてんこは自嘲気味に言う。
それを受け、キリが眉をひそめながら聞き返した。



……どういうこと? 的の性質は《血》によるものなのよね? てんこに関係あるの?





うむ……。それは――





てんこ





――む。……すまんな娘御。悪いが、吾輩の口からは何とも云えぬ





ん、そっか。立ち入ったことだったかな、ゴメンね


キリはすぐに表情を切り替え、あっけらかんとした様子で言う。



悪い。もう少し整理できたら、必ず話すから





謝んないでよー。こっちが余計申し訳なくなるっつーの。いーよ。気が向いたら教えて


はにかんだような笑みを浮かべながら、キリは頭の後ろで手を組んだ。



どうする? アタシちょっと外そうか?





いや、大丈夫。てんこももういいよな?





ああ。話はもう良い。……が、再三にはなるがの、やはり自衛の策は必要じゃ。――娘御、あれは持って来ておるな?





あ、油揚げ? 持ってきてるよー。今食べる?





違う。ああいや、欲しい。それは欲しいのじゃが、違う。《羽々斬(はばきり)》の事じゃ


ああ、と言ってキリは拝殿の中、社の壁に立て掛けてあった刀袋の方に歩み寄った。そのまま刀袋を掴み上げるとすぐに房紐の結びを解き、中の木刀を一息に抜き出す。
――木刀《羽々斬》。全長約三尺九寸程の、桐製の大刀。
その外観は極めてシンプル。鍔を持たず、一切の装飾類が施されていないその木刀は、もし柄巻が無ければ遠目に見て一本の木材と見紛うほどに簡素なものだ。
そしてその素朴さに比例するように、《拍子抜けするほど軽い》。
軽量化の限界を極めたかのようなその刀は、柄巻込の総重量にして一六〇グラム以下というとんでもない軽さを誇る。
これは、訓練用の木刀を想定して羽々斬を持ち上げようとしたら、その重さのギャップで《ぎっくり腰になる》かもしれない程の軽さだ――と言うと少し大げさかもしれないが、そこまで言ってしまいたくなるくらいには、規格外に軽い。
この木刀は、剣道場を営むキリの家系に代々伝わる《稽古用木刀》らしい。
キリ曰く、「軽い刀を重く振る」という、天之流の剣技に欠かせない技術を養う為に用いられているようだ。
で、そんな羽々斬を何故てんこが気に掛けるかというと――



……うむ。やはり、この刀は素晴らしい。神籬(ひもろぎ)としてこれ以上のものは中々見当たらんじゃろう


と、差し出されたその刀を見て満足気にてんこが言った。
神籬とは、神がその力や存在を宿すための依代のような物、と俺は認識している。話によるとこの羽々斬、元来神依木として扱われていた桐の木を切り出して作られているらしい。
つまり御神木が刀を象ったもの、とも言えるこの羽々斬は、てんこからしても扱いやすいようで、その通力を宿す上でお誂え向きの依代となるようだ。



しかし――やはり、ここ最近の連戦で此れに込められた通力も幾分弱まっておるようじゃ。……どれ、数分貸せ


と言い切ると、てんこは口で受け取った木刀を器用に賽銭箱の上に置き、刀身を見つめながら何やら呟いた。
その声に呼応して、刀を発生源とした燐光がふわりと浮き上がり、境内を淡く照らしはじめる。
地面を覆い隠すように積もった雪がその光を反射して、ある種の幻想的な雰囲気を作り出していた。



おお……。雪が積もってっと、いつもよりキレイだな。これで夜ならもっと良かったぜ、きっと





うん、そうだね


キリはさほど興味無さそうに相づちた。



あれ。キリ、こういうの好きじゃなかったか?





いやー普段なら喜んで写真撮ってたと思うんだけど、ちょっと今複雑なキブン





と言いますと?





……てんこ、アタシの名前憶えてないのに、羽々斬は憶えてんだ、ってね……





ああ、成程……


無情だ……南無。



――ねえ、ちょっと聞いていい?


てんこの通力が生みだす光景にしばし見入っていた俺に、探るようにしてキリが声をかける。



ん?





さっきの、《血》の話。答えたくない事だったら無視して





ああ……わかった。なんだ?





うん。えっと、アタシなんとなくしか把握してないからちょっとおさらいしておきたいんだけど。的の持つ特性って、要は《血によってミームが引き寄せられちゃう》、って事だったよね? で、《ついつい食べたくなっちゃう》と





随分ざっくりだな……、だけどまあ、そういうことだな。そして、あの家は永いことそれを――餌とされる事を、是としてきた。消費される事に、本懐を見出した。胸クソ悪い需要と供給だよ


吐き捨てるように言って、キリに視線を向けた。



でも俺は本家を出た人間だ。そんな消費される人生は真っ平ゴメンだし、その辺のミームに喰われるつもりも毛頭ない。……とはいえ、その逃避も一人じゃ満足に出来ないんだから救えないよ。お前にも、随分迷惑かけてるな


実際のところ、俺に出来る事は極めて少ない。以前は篁さん、今はキリに頼りっぱなしになってしまっている。
我ながら――不甲斐なさに、虫酸が走る。



いや、そういうのは別にいいんだけどね


俺の感傷はバッサリ切り捨てられた。



お、お前なあ……





でまあ何が聞きたいかというと。その、ミームの側からして『こいつ、食べたらヤバい!』みたいなのって分からないもんなのかな? ってこと。程度の差はあれ、どんな存在でもやっぱり死にたくはないんじゃないの?


ああ、成程。



……俺も詳しく知っている訳じゃないけど


一度言葉を切って、大きく息をしてから続きを言う。



主にこういう理由だと思う。一つは、単純にそのミームに明確な自意識が存在しない場合。もう一つは、自意識があったとしても、リスク回避を行う為の知識や感覚が欠けている場合。この二つの場合は、まあ説明不要だろ。旨そうだから喰う、綺麗だから襲う。そんな感覚なんじゃないか


自分で言って、気分が悪くなる。



――で。あと一つが、自意識があって、リスク回避の思考も出来るのに襲ってくる場合。推測だけど、こいつらに関しては『ヤバいって解ってても自制心が効かない』、みたいなことなんじゃないかな。多分これが、てんこの言ってた《麻薬》って意味なんだと思う


早口に言い終え、残った息を溜息に変えて吐き出した。
やっぱり、自分を餌として見た時の考察なんてのは、気持ちいいもんじゃないな……。



うん、なるほどね。あ、じゃあ――





待たせたの、終わりじゃ


とそこでてんこから声がかかった。



通力は羽々斬に行き渡った。これでまた暫くは問題無いじゃろう


そう言ったてんこは控えめに見てもかなり疲弊している。毎回の事ではあるが、通力を使う度に激しく消耗するてんこを見ると申し訳無さが募る。



お疲れ。いつも助かるよ





ふん。早う持っていけ


言うとてんこは木刀を咥え、キリに差し出した。



ありがと。うーん、やっぱり違いは見た目にはわかんないわねー


そう言ってキリは暫し刀身を見つめていたが、やがてそれを刀袋に仕舞いこんだ。



――少々疲れた。吾輩は眠る……が、その前に一つ忠告じゃ


いつも言っておることじゃがの、と前置きしたうえでてんこは話し始めた。



その羽々斬、凡百の怪異――お主らの言うところのミームには負けはせん。吾輩は腐っても神じゃからの。格が違う。その吾輩の力が宿っておる以上、有象無象には負けぬ道理じゃ


平然と言うてんこ。
いや。
当然か。
てんこにしてみれば、言葉通り生物としての格が違う。例えるなら、蟻と象を通り越えて、蟻と竜ほどの差があるんだろう。
まさに、竜の鬚を蟻が狙うがごとしだ。



とはいえ、同格の存在――つまり神じゃな。若しくは、其れに匹敵する格の持ち主。此れに敵うかは、正直判らん。一口に神と云っても玉石混交じゃ。衰えた今の吾輩より弱い者も居れば、当然強い者もおる


そこまで言い切ると、てんこはやや声音を低めて続けた。



まあそもそも、神と相対する機会などそうないとは思うが。だがもし、万一対峙せねばならない時が来た場合。既に何度も言っておるが――《必ず逃げろ》。戦うな。あまりにも、勝算が薄すぎる





……うん。大丈夫、覚えてるよ。……篁センパイの件もあるしね





…………





――そうか、ならよい。ではあともう一つ……、その刀で対象を斬った場合の話じゃ


てんこは、キリが抱えている刀袋に視線を向けた。



羽々斬によって対象を滅した場合、そのミームは《存在を失う》。吾輩が捕食した場合と一緒じゃ。成仏させるでも地獄に送るでもない。三千世界の何処にも属さぬ、完全な消滅じゃ。輪廻の枠からも外れ、再び生を受ける事は無くなる。……脅すつもりではないが、其れで斬るという事はそういう行いなのだと、改めて認識しておけ


そう忠告するてんこの目は、これ以上ない程に真剣だった。
……多分てんこは、言外にこう告げている。
――認識しておけ。
――其れで斬るという事は。
――人を殺すという事よりも、
尚重い行為なのだと云う事を。



……わかった。でも


キリは覚悟を込めた表情で、てんこに告げた。



今生きてる人間に被害が出るなら、アタシは斬るよ





――そうか。いや、割り切っているのであれば問題はない


その会話を最後に、てんこは「眠い」と言って休眠の体勢に入った。
俺達は、これ以上の長居は眠りの妨げになると判断し、油揚げを手渡してさっさと神社を出た。神社にいた時間は短かったから時間的にはまだ余裕があったが、どことなく重い空気が漂う中何をする気にもならず、その場ですぐにキリと別れた。
帰途の折、考え事をしながら歩いていると、歩道上の堆積された雪にうっかり右足を突っ込んでしまい、心中で一人毒づく。
時節柄か、踏み抜いた雪には水気が多く、固まりきってはいなかった。
足下をしとどに濡らす不定形なその雪が、黒く凝った俺の慙愧に似ているようで――苦し紛れに、足を引き抜くと同時に雪を前方に蹴り飛ばしたが、奥の奥まで染み込んだそれは、乾くには暫く時間を要しそうだった。
雪は、まだまだ解けそうにない。
