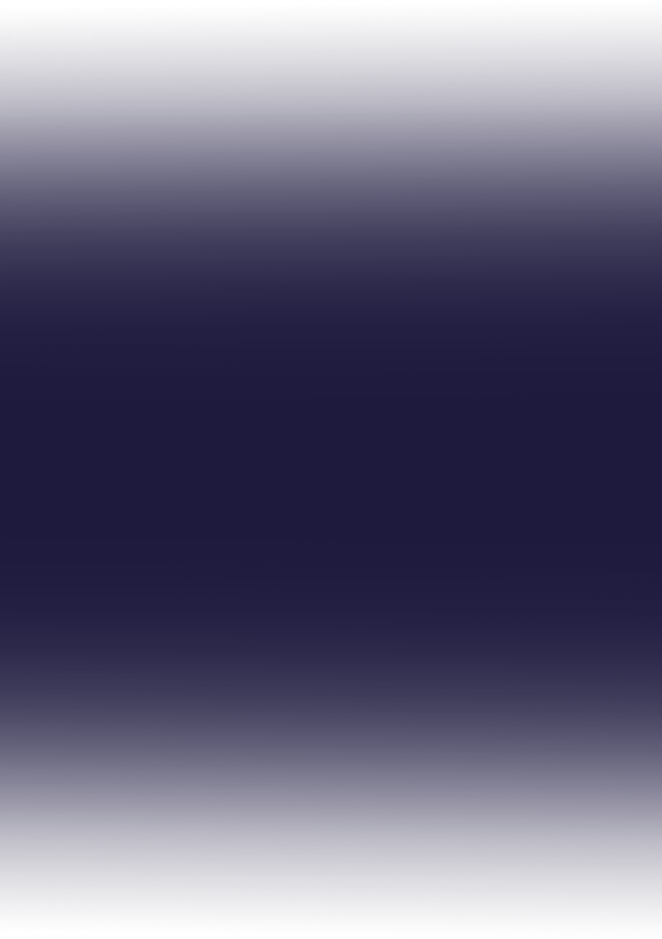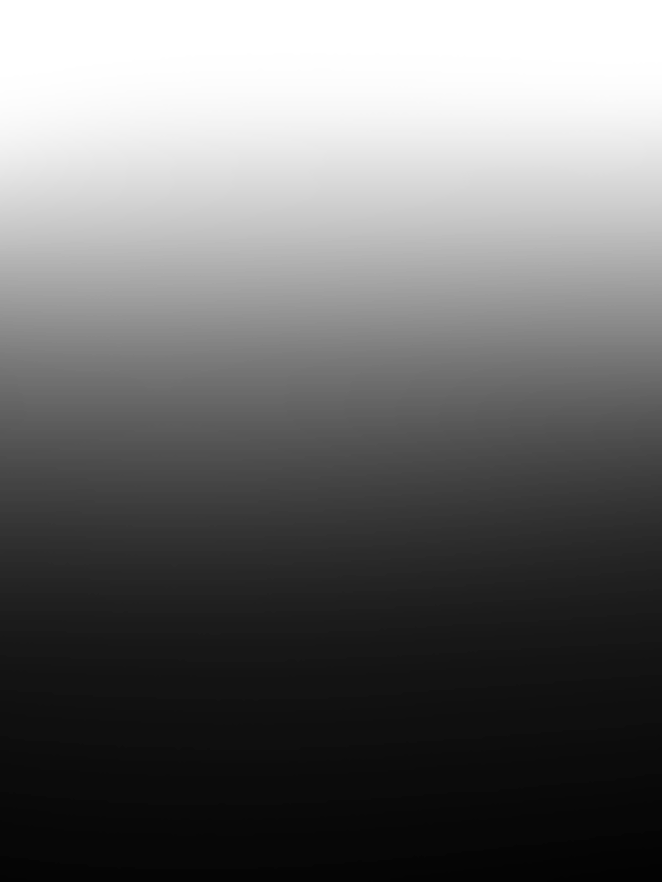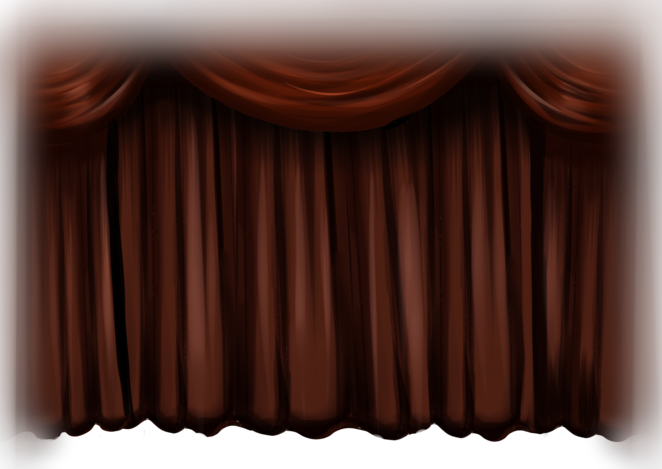わたしの声がほしい……?
アベルはわたしの首を絞めながら、突拍子もなくわたしの声がほしいと言った。冷たくて硬い指が首に食い込み、まるでわたしを殺しにかかっているようだ。抗おうにも上手く力が入らない。
とうとう意識が虚ろとなり、本気でアベルを怖いと思ってしまった時、ぱっとアベルの手が離れた。
ゲホッ ゲホッ。
勢いよく咳き込むと、オズウェルさんが優しく背中を撫でながらアベルを咎める。
しかしアベルはただただ押し黙ってこちらを凝視していた。 その目は凍てつく冷たさを宿し、でもどこか憎悪の炎が奥に漲っているようにも見え、その視線から逃れようとした。