チリンと鈴の音を立てながら、ニナの帽子を咥えて逃げまわる黒猫。なんてやんちゃな猫なんだ。黒猫は、走る速度の遅いわたしを気遣うように立ち止まっては、走っての繰り返しでむしろ止まってほしいと切に願った。
猫の毛に埋もれつつある金の眼が夕陽よりも眩しい。猫のわりに知性の宿る瞳がアイコンタクトをとるようにじっとこちらを見ては、迷いなく人混みを避けて道を進む。

チリンと鈴の音を立てながら、ニナの帽子を咥えて逃げまわる黒猫。なんてやんちゃな猫なんだ。黒猫は、走る速度の遅いわたしを気遣うように立ち止まっては、走っての繰り返しでむしろ止まってほしいと切に願った。
猫の毛に埋もれつつある金の眼が夕陽よりも眩しい。猫のわりに知性の宿る瞳がアイコンタクトをとるようにじっとこちらを見ては、迷いなく人混みを避けて道を進む。



猫さん、はや……い……


走っているはずなのに、おかしいことに早歩きするパリジャンに追いぬかれていく。猫の走りにさえ追いつけないわたしってもしかして、かなりの運動音痴ではなかろうか? そんな疑問さえ浮かぶ中、必死に視界の隅に映る黒猫を追いかけた。



や、やっと……もう、悪さ、しちゃあいけないよ……


ぜぇぜぇと息を吐きつつ、黒猫を捕まえた。
あ、毛並みが良い。もふもふだ……ではなく、人間を弄ぶとは何て罪深い猫だ! そう思いただしながら、口に咥えてあったニナの帽子を奪って、黒猫の鼻先を人差し指でつついて「めっ」と叱りつけた。
その際、黒猫の首輪に挟まった紙に視線がいく。その紙は丁寧に丸めてあって、黒猫は逃げようとしないので興味本位でそれを引きぬく。すると、紙の近くにあった鈴がチリンと鳴った。
青空のような空色の紙に金文字で
『Lettre d'invitation de la Sérénade<セレナーデ(夜曲)への招待状>』
という走り書きがある。
しだいに紙は青空から夕空に変わり、金粒が集い出し、今度は粒同士をつなぐ金の線が浮き上がる。星座かと思いきや、それは文字であった。

「急いで!」と、書かれてある。
紙の中身が動くなんて……そんなことがあるの!? どういう仕掛けなのかしら。お金持ちにしかできない技術なのかもしれない。
ということは――もしかしたらお金持ちの家の猫で、これは夜会の招待状みたいなものかもしれない。さぁっと血の気が引く。



とんでもないことをしてしまったかも


そうだとしたら、勝手に見たらまずい!
慌てて招待状を猫の首輪に挟みなおそうとするものの、猫は素知らぬ顔でさっと避ける。
すたっと着地した場所は、教会のステンドグラスが夕陽で地面に照らされている石畳だった。黒猫は慌ただしくその場でぐるぐる回ると、石畳をカリカリとひっかき始める。
いったい全体どうしたというのか。

よく見てみると、そこには小さな穴がある。ためらいつつそこをなぞると、胸元がじりじりと熱くなる。熱くさせている正体は、アベルがくれた時計状の鍵であった。針は4:43を指している。



もしかして……


ステンドグラスの映る地面、それがまるでドアの形のようで、本来ドアノブがあるであろう場所に穴。きっとこれは、鍵穴なのだろう。形からしてみても、そうに違いない。
人間らしく胸が高鳴り、緊張していた口元が緩む。
左手には夕暮れ色の招待状とニナの帽子、右手には夕暮れ色の鍵、そして頭上には本物の夕暮れ。まるで物語の始まる条件が揃ったようだ。


恐る恐る鍵穴に鍵を入れ、回す。そして抜く。
すると、ガーゴイルを引きずるようなゴゴゴという重音が轟き、足をよけようとしたその時だった。



あれ? なんの、音?


これはおかしい、と思った時にはもう遅かった。地盤沈下したように少し下がった地面に冷や汗が流れる。



猫さん、これ……!


危なくない? そこまで言いかけた途端、自身が座り込んでいたところを中心として5m四方の地面がいきなり沈下したのだ。つまり、穴があいた状態と同じ状況である。



や、やっぱりいいい!


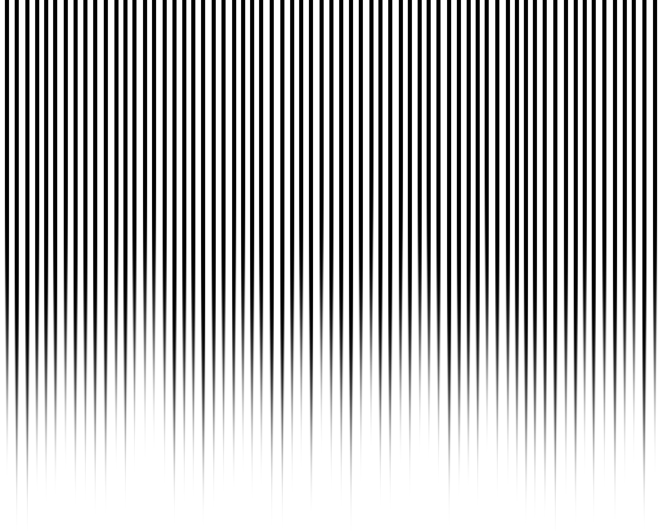
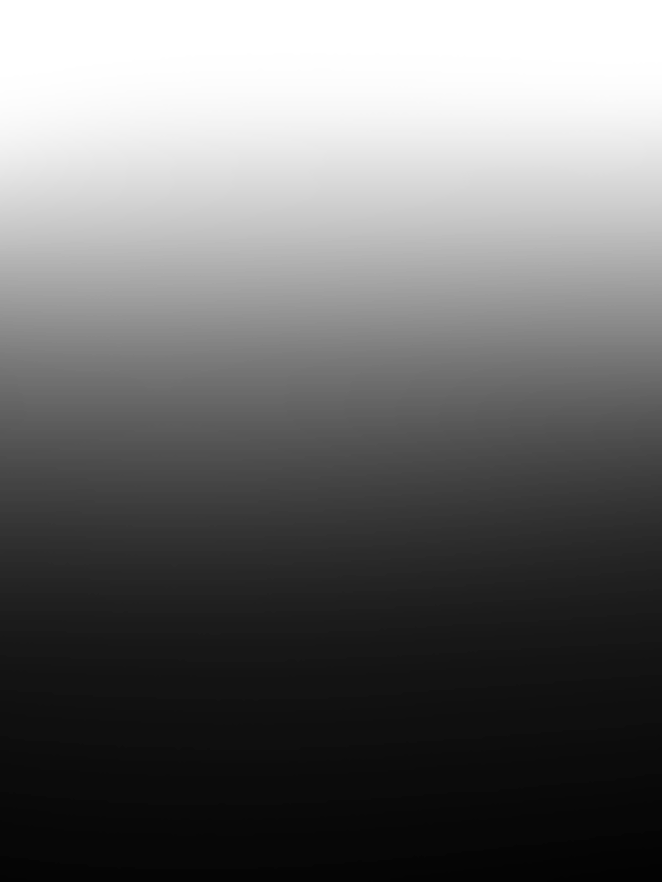
ひゅううっという冷たい風を全身に受け、深い穴へ落ちていく。
一足先に落ちていく地面を見つめながら、生まれてこの方あまり感じたことのない恐怖感を味わった。
黒猫は斜め上で同じく落下しており、慣れた表情でこちらを楽しそうに見ている。慌てて黒猫を抱き留め、せめて黒猫は助かりますようにと祈る。



神様、いらっしゃるのならお助けを!!


と十字を切りながら、敬虔なカトリック信者であることを表す。こんな時だけ敬虔な信者ぶっても仕方ないけれども、なりふり構ってはいられない。

魂を何かに預けているような不安に耐えていると、徐々に下方から淡い橙色の光が近づいていることに気が付く。
まるで最近読んだ『不思議の国のアリス』のような状況だが、運の悪いわたしがアリスのように助かる確率は低いだろう。目をぎゅっと瞑り、絶望でガクリとうなだれていると。



おわ!


唐突に視界が開かれた。まばゆい光に包まれ、ポスンと体に柔らかい衝撃が走る。どう考えても固い地面ではない。
腕の中から猫がすっとすり抜ける感覚が伝わり、恐る恐る瞼を持ち上げた。
視界に広がる広い空間――数多の本が本棚に収められていたり、床に散乱していたりしており、全体的に懐かしさを感じさせるセピア色に包まれている。
天井は高く、自分がさっき落ちてきたであろう穴が不自然にぽっかりと空いていた。落ちてきた証拠のように、穴から手放したせいで遅れて落ちてきたニナの帽子が落ちてくる。慌てて受け取ろうとするが、タイミングがあわず帽子は頭上に落ちてきた。どこまでも不運だと我ながらに思う。
下を見ると、衝撃を和らげてくれたであろう、雲のような柔らかい羽毛絨毯があった。ありえないくらいにふわふわで、自分の体重で20㎝以上も沈んでいる。
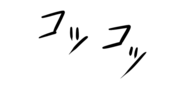
突然響いた靴音にびくっと肩を揺らす。
目線を前方に向けると、誰もいなかったはずなのに目の前には品のある美男子が立っていた。
服装は黒色のフロック・コートの下に白いシャツ、ネクタイで少し明るい色のズボンを着用している。大きめのトップ・ハットが彼を更に紳士らしく仕立て上げていた。身長の彼を見上げるには首が痛くなる。



き、れい……


自然と口から洩れた言葉にはっとして両手で口を覆う。その際、持っていた招待状をひらりと落としてしまった。
少し童顔である青年はふわりと微笑んでしゃがむと、落としてしまった招待状を拾い上げる。



お嬢さん、招待状を受け取ってくれてありがとう。歓迎するよ


艶のある黒髪を揺らし、眼鏡越しから見える金色の瞳が輝いた。思わず見惚れていると、カシャンカシャンという不気味な音が後方から聞こえる。音に誘われて振り返ると、そこには何と……。



おいオズウェル!
久しぶりに人間の女の子が来たって本当か!?


人間のように動く骸骨がいたのだ。



が、骸骨!?


驚愕してそう尋ねると、



失敬な! 俺はれっきとした英国紳士だ!


と胸――否、胸骨を張って言い切った。文字通り肉も皮もない骸骨がこちらへ歩み寄ってくる。心臓が口から出そうになっていると、オズウェルと呼ばれた美青年が呆れたような表情でたしなめた。



おいおいスケル・トーン、女性を怖がらせてはいけないよ。
少し引っ込んでてくれないかい?





ひ、ひっでぇ奴!
俺だって生前はお前より優れた容姿で……


何が何だか分からない状況で頭がパンクしそうだ。いきなり地面に穴があき、落ちたら本の世界。そして目の前で美青年と骸骨が口論を繰り広げている。
ああ神様。わたしが何をしたというの!
涙目でまた十字を切っていると、クスクスという押し殺した笑い声が斜め後ろから聞こえる。



やぁ、アリシア。今の気持ちはどうだ?


歌うような旋律で言葉を紡ぐその声に聴きおぼえがあった。



な、何でここにいるのよ。アベル!


そこには、本の山の頂上に座り、悠々と読書に耽るアベルがいたのだ。
アベルは読んでいた本を投げ捨てると、両手を広げて滑稽に笑う。わたしの質問を無視し、凛とした声で語りだす。



さあ、アリシア。
『情念論』によると、人間には驚き・愛・憎しみ・欲望・喜び・悲しみが基本情念にあるらしい。
今の気持ちはそのうちのどれかな?
もしくは、どの情念を併せ持っているかな?





……お、驚き。あと、たぶんだけど……


ちらりと周りを見渡す。すると他にもちらほらと人影(のようなもの)があって、こちらへ好奇の目を向けていた。



『たぶんだけど』、なんだ?


アベルはにぃっと怪しく微笑み、目を細める。アベルの催促に、子どもっぽく大きめの声で答えた。



よ、喜び……!


すると、アベルが待っていましたとばかりに手を叩き、カラカラと笑った。



Super!<素晴らしい>!


それにつられて周りも和やかな雰囲気となる。口元をもごもごさせながら少し微笑んでみせると、スケル・トーンと呼ばれた骸骨がわたしの手をとって立ち上がらせると、いきなり爆弾発言を口にした。



アリシア、だっけ?
お前を見てると俺の胸骨が震えるんだがどういうことなんだ……もしかして、死後初めての恋かもしれない





はい!?


その場にいた皆が口揃えてそう言う。わたしももちろんそのうちのひとりだ。
わたし、今……生まれて初めて骸骨に告白されたよ。どういうことなのかしら。
めまいを覚えていると、スケル・トーンさんの頭に重そうな本がクリーンヒットし、



いだ!


と悲鳴をあげる。今、ゴキッていったけど大丈夫かしら。



おい骸骨野郎。こいつは俺の操り人形なんだからとっとと失せろ。
その骨、犬のおやつとしてしゃぶられてもいいのか?





んだとゴラァ! ただの古臭い人形のくせに……お前は貴族のままごとにでも使われてろ!





ほーう、言うじゃないか


アベルからはフランスのスラング、スケル・トーンさんからはイギリスのスラングが飛び交い、本格的な喧嘩が始まる。
何て喧嘩っ早い人(人ではないけど)なのだろうか。
だが、オズウェルさんの咳払いひとつでシーンと静かになる。



アベルとスケル・トーンは敬遠の仲でね。あれは日常茶飯事なんだ。だから気にしなくていいよ。
それはそうとアリシアさん、だっけ?
アベルから話を聞いてるよ。
『セレナーデ(夜曲)の鍵』に魅入られた存在――とても興味深い


オズウェルさんがわたしの首にかけている鍵を指さすと、わたしの前で優雅に跪いた。



ここ――サン・ゼヴラン教会の庭は、中世の時代ではシャルニエ(死体置き場)だったんだ。
ちなみに僕は生前黒猫で、アベルはヴィスクドール、スケル・トーンは英国紳士だったんだよ


改めて紹介に預かったアベルは口をすぼめたまま肩を竦め、スケル・トーンさんは紳士という単語を聞いて背筋を伸ばした。



改めまして――ようこそ、異形が集う秘密の図書館『セレナーデ(夜曲)』へ


怪しく笑ったオズウェルさんは跪いたままわたしの手をとり、手の甲へ口づけを落とした。



な、ななな!


舌がもつれるほど動揺し、頬が熱くなる。背後からスケル・トーンさんの断末魔のような叫びが聞こえたが、オズウェルさんはしれっとした顔で何事もなかったかのように立ちあがる。その際、アベルが投げたであろう本が背後から飛ぶが、オズウェルさんは華麗にそれを避けた。



アベル、君はいつも乱暴だな。
なあに、これからセレナーデのメンバーになるだろう彼女を歓迎しただけだよ


人影からコソコソとささやき声が増し、彼らは遠巻きでわたしたちのやりとりを見守っていた。



め、メンバー?


何の話か追いつけずに首をかしげる。するとオズウェルさんは上品な微笑みをこびりつけ、両手を腰につけてわたしと鏡合わせのように首をかしげた。



そう、メンバー。君はセレナーデの鍵に魅入られた時点で、僕らメンバーに加わる運命なんだ。君の友人も絡んでいることだしね


その言葉に、ハッとした。友人といえば、一人しかいない。ニナのことだ。
オズウェルさんに詰め寄り、震え声で問う。



あ、あの、ニナのことですよね……? 彼女に、なにがあったんですか!





……彼女は少し厄介なことに巻き込まれているんだよ、お嬢さん。その話をしたくて、わざと彼女の帽子を奪うような真似をして君を呼び寄せたかったんだ


ざわざわと



本当に巻き込むつもりなのか?


とか、



人間なのに


といった不満気な声が耳朶(じだ)を打つ。



お嬢さん。今から言うことは信じられないかもしれないが、決して嘘偽りではないから聞いてほしい。
お嬢さん、パリの地下にはなにがあると思う?


その問いかけに小さく



採掘場?


と答えると、真後ろからアベルの小馬鹿にした笑い声がこだまする。



はっ、お前の頭はいつでもお花畑だな?


ひとしきり笑い終わると、打って変わって底冷えするような低い声で囁く。



――ちげーよ、カタコンベ(地下墓所)だよ。お前、知らないのか?
パリは【光の都市】と謳われているが、実態は違う。憎悪や悲哀の感情を消化できなかった哀れな死体でできあがった、腐乱都市さ


耳元で低いアベルの低い声がそう説明する。恐怖に身が竦み、そちらへ視線をやることさえできなかった。



ほら、耳をすませたら聞こえてくるだろ?


アベルの指がわたしの後ろ髪を耳にかけさせ、わたしの耳を露わにさせた。言われた通り音に集中すると、どうしたものだろう。身も心も凍えるほどの、ウォォォとかああああといった唸り声が微かに聞こえるではないか。



やつらのうめき声、怨嗟(えんさ)の声。身を焦がすような感情が白骨から突き破って、ついには亡霊となって地下から地上に這い出てきたんだ


ごくりと息をのむ。



おまえも聞いただろう? パサージュ・ショワソルでガラス窓を叩く足音。
奴らは4時44分を機に、徐々に姿が濃くなる。地獄の蓋が開くのさ。
まあ、あいつらはただ遊び足りなくて地上に出てきただけの無害な亡霊だが、もっと厄介な亡霊――いいや、怨霊がいる





も、もしかして、その怨霊が?


その先の言葉が分かってしまって、強い緊迫を感じて歯がガチガチとなり出す。



そう、お前の大切なお友達に取り憑いているんだよ


咄嗟に真横にあるアベルの顔を見る。アベルは長い睫毛を伏せ、悲哀とも興奮ともとれぬ表情でこちらを見ていた。ついその表情に魅入ってしまうが、アベルの吐いた言葉にやっと頭にたどり着く。



に、ニナが取り憑かれてる……!?


そういえば確かに今日会ったニナはいつもと違って生気を失ったような、心ここにあらずな様子だった。アベルの言うことが本当であれば、あの様子は会得がいく。
どうしてニナのような良い子が……。やるせない気持ちで胸がもやもやした。スカートの裾を握りしめ、覚悟を決める。



わ、わたし……ニナを助けたい!
なにかわたしにできることがあったら……なにか必要なものがあればなんでも言って……!


アベルの表情が変わる。一瞬、目をこれでもかというほど見開かせた後、三日月形の目に変わる。次いで、ほくそ笑むように口端を上げた。



そうかそうか、それじゃあ――。


ガッ!
と、いきなりこちらの首を締めるように両手で握ってくるアベル。あまりに唐突のことで、息がひゅっとつまる。
スケル・トーンさんが「なにしてるんだサド野郎!」と喚き散らしている。本当にそのとおりだ、なにをしているんだ……!



お前の声がほしい、アリシア・バレ





は……い……!?


アベルの瞳孔の開ききった左目が、わたしの左目の奥を覗きこんでいた。それはまるで、わたしを通して他の誰かを見ているようであった。
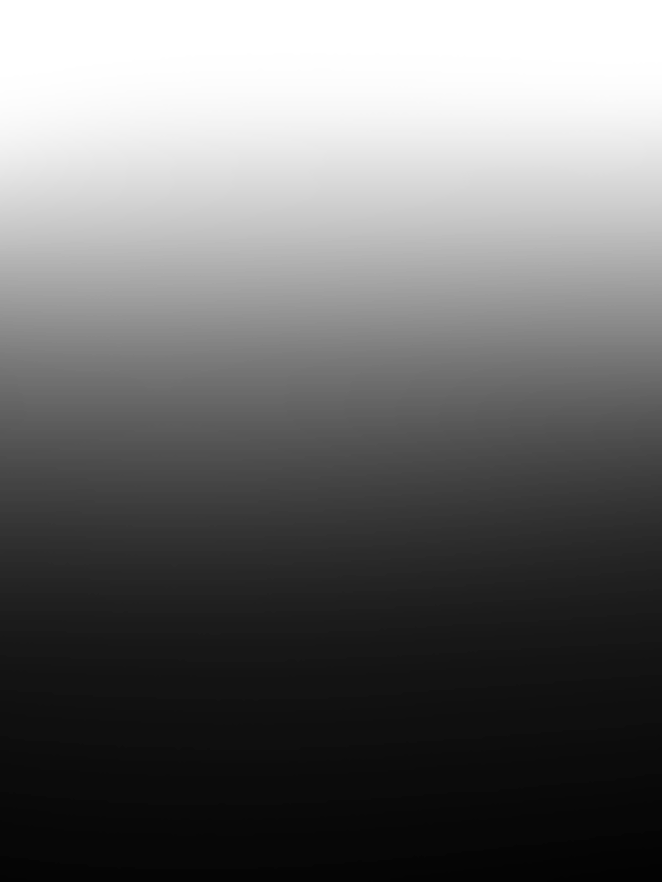
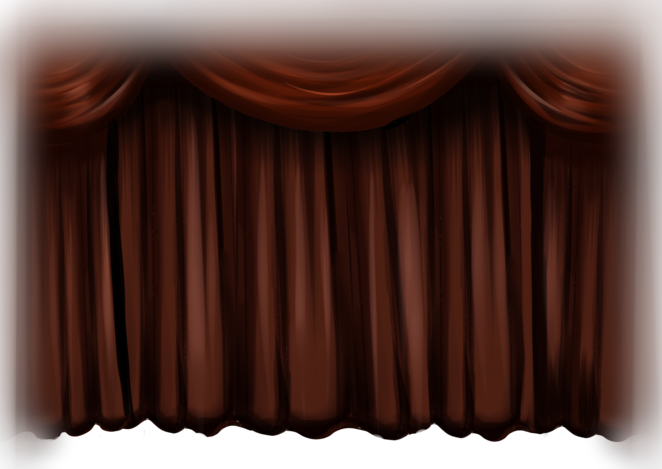

今回も読ませていただきました。ダイジェスト版ではなかった続きのお話が始まりましたね!この先どうなるのか全く予測がつきません。とても楽しみです!招待状の変化に合わせて背景も変わっていき、落下後の上を見上げて見えた景色、とても綺麗でした。登場人物もさらに増え、盛り上がってきましたね。
楽しく読ませて頂きました!
ついにオズウェルとスケル・トーンと出会ったアリシアの反応がまた可愛くてw
いつもながらに表現や描写が細かく絵や作品で想像も膨らませれてと楽しいです♪アベルの言葉がアリシアをどこに導くのか…!楽しみにしてます!
ダイジェスト版で気になってたところが、とうとう開幕しますねー((o(*゚▽゚*)o))
今回も楽しく読ませてもらいました!
続きにもうソワソワしてます♬
◆いつもまとめて拝読していますが、背景の写真と物語が合っていて、作品の中を放浪しているかのようにドキドキしながら楽しめるのがいいですね。いつもイイ所で終っているので、次回も楽しみです。アベルの謎とアリシアの変化していく様子を興味深く見守ります。
このお話が更新されるたびに、とても勇気付けられています(o^^o)アリシアの少しずつ変わっていく姿に励まされております(*^^*)アベルとアリシアの関係もドキドキです♪
やっと時間ができて通しで拝読させて頂きました。
ハンドメイド作品から感じる印象と、小説から感じる印象が同じであるのに驚きました。
重なる謎に駆け足で一気に読みました…!
続きを楽しみにしております!
やっとまとまった時間が取れて、第1幕から夢中で読んでしまいました(*´ω`*)
セレナーデの鍵が使われるところなど、聖花さんにしか作り出せない世界にワクワクが止まりません><*
これからのアリシアとアベルの関係にもドキドキしつつ、続きを楽しみにしております(っ´ω`c)♡