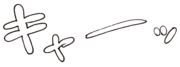あの日。
私も冬弥も仕事が早く終わり、久しぶりに二人揃って食卓を囲めることとなった。
外は雪が降っていて、とても寒い日だった。
「今日は寒いからすき焼きにしよう」
私がそう言うと、冬弥が「いいね」と答えた。
その時の冬弥の笑顔を見た時、私は幸福の絶頂だったと思う。
それは同時に不安が最高潮に達した瞬間でもあった。
冬弥の笑顔を離したくない。
ずっと彼の側にいたい。
なぜ冬弥は愛してると言ってくれないのだろう。
そう思う一方で、そんなことばかり気にしてはいけないと思う、もう一人の自分も常にいた。
私はまな板の上で鍋に入れる食材を切りながら、どうしても消せない不安を必死に振り払おうとしていた。