あの日、俺は仕事が早く終わり、美由もお昼のバイトから帰ってきて、珍しく二人揃って夕食時を過ごせることとなった。
美由はようやく目標額のお金が貯まり、四月から目的の専門学校へ通うことになっていた。
俺は二十三歳、美由は二十一歳。二月上旬のパラパラと雪が舞い落ちる寒い夜だった。
あの日、俺は仕事が早く終わり、美由もお昼のバイトから帰ってきて、珍しく二人揃って夕食時を過ごせることとなった。
美由はようやく目標額のお金が貯まり、四月から目的の専門学校へ通うことになっていた。
俺は二十三歳、美由は二十一歳。二月上旬のパラパラと雪が舞い落ちる寒い夜だった。



今日は寒いからすき焼きにしよう


美由はそう言って台所でテキパキと準備を始めた。
ザク、ザクっと野菜を切る音が聞こえる。
俺は食卓の上に置きっぱなしの調味料や箸置きを片付けて、すき焼きを楽しむ場所を確保した。
その後、美由の準備が整うまでの間に少しだけ小説を進めようと思い、パソコンの電源を入れた。
小説はもうすぐ完成するところまできていた。なのではやる気持ちを抑えきれずにいたのだ。
最近は以前より家事を怠り、小説を優先していた。
最初のうちはすまない気持ちもあったが、美由はなにも言わなかったし、俺も気にしなくなっていた。
俺は目を閉じ、大事なシーンの出だしの文章を考えた。
包丁がまな板を叩く音が、やけにうっとおしく感じた。
ガスコンロの上でグツグツ茹でる音も聞こえる。
普段は好きな音が気になってしまい、集中できずにいた。
それでもギュッと目を閉じて意識を小説の中へ移行する。
ようやく外部の音を感覚の外へ追いやり、考えがまとまりかけた時だった。
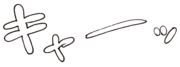
美由の叫び声とともに、ゴトンという音が聞こえてきた。
俺は妄想の中から一瞬で現実に引き戻され、何事かと美由の方を見た。



ごめんなさい。
手が滑っちゃって包丁を落としちゃった


床には包丁が転がっていたものの、美由に怪我はない様子だった。
俺は美由の無事を目で確認したことでホッと胸を撫で下ろし、再びパソコンとにらめっこした。
そして腕を組み、再び意識を小説の中へ移すため、目を閉じた時だった。
カチッという音と共に、煮えたぎった鍋の音がスーっと消えていった。
そして美由が二、三歩こちらへ近づく気配がした。
美由の方を見ると、彼女の目が俺を睨みつけていた。
美由の少し開いた口からは、感情的になるのを必死に抑えるかのように呼吸を整えているのが見て取れる。
美由の後ろでは、コンロの火が消されており、鍋の煙が蜃気楼のように揺らめいている。



私、包丁を落としたんだけど


なぜそんなことを改めて言ってくるのかわからないが、美由の静かな怒りが俺の鼓動を強めた。
これほどに怒っている美由を見るのは初めてのことだった。



怪我はないかとか、大丈夫かとか。
そういう言葉はないわけ?


その言葉で怒りの引き金が、俺の思いやりに欠ける態度にあったことは予想できた。
だが俺は美由の無事を目で確認したし、怪我がないのは美由自身が一番わかってるはずで、俺にも真っ当な言い分があると考えた。
なので俺は謝る気は起きなかったが、どう言葉を返せばいいかわからず、ただ口をあけていた。
さらには反省などしていないという主張を半笑いで表していた。



いや、でも大丈夫なんだろ?
別にどこも怪我してないじゃん





はあ?
冬弥、あたしの体のことちょっと見ただけで全部わかるわけ?
包丁落としたんだよ!
怖かったの!
足に刺さりそうになってさ!
怖かったのに!
なんで何も言ってくれないわけ?
冬弥!
私のことどう思ってるわけ?
心配じゃないの?
何事もなかったようにパソコン眺めてさ!


美由はヒートアップしていき、声のボリュームがどんどん大きくなっていった。
座ったままだとふてぶてしく見られそうで、余計に美由を怒らせてしまうと思い、俺はゆっくり立ち上がった。



いや、心配だったよ。
だからさっき、すぐに美由が無事かどうかちゃんと目で確認したんだぜ





うそだ。
そんな言い訳聞きたくない。
私なんかより小説の方が大事なんでしょ!
私のことなんかどうだっていいんでしょ!


その言葉で俺も怒りが湧いてきてしまった。
美由に勧められたとはいえ、家事の負担を押し付けて小説を書いていることに負い目を感じていたが、美由は笑ってそれを受け入れていた。
だが、本当はそんなものは俺の勘違いだった。
そう思った。



なんだそれ。
不満に思ってたんなら応援するフリなんかやめろよ。
小説ばっかり書いてないで家事を手伝えってちゃんと言えよ


俺は美由に借りを押し付けられた気分になっていった。
俺の言葉を聞いた美由は、うつむいて肩を震わせた。
ポタリ、ポタリと美由の目から涙が床に落ちていく。



ごめんなさい。
ごめんなさい冬弥。
違うの。
そうじゃないの。
私、冬弥が夢を追いかけてる姿が一番好きだよ。
ずっと冬弥の側で力になってあげられたらって……。
でも不安なの。
冬弥、今までに一度も好きだとか愛してるとか言ってくれなかった。
冬弥の気持ちがわからなくて。
だから心のどこかでいつも不安に思って。
幸せなのに、どこか不安で……怖くて


美由は震える声で、静かに言った。
愛していると言ってもらえない。
そんなことでこれほどまでに美由が追い詰められていたなど、俺には想像すらできなかった。
心に思っていることは言葉にしないと伝わらないと、俺は今まで散々耳にし、目にしてきた。
それは恋愛小説だったり、漫画の名言に込められていたり、結婚式場のCMだったり、どこかで耳にした演説、学校の先生、子供の頃に俺を補導したおまわりさん、バラエティー番組、母親。
でも実際は大事にすべき言葉ほど、信用できないのが現実だった。
母は父にプロポーズされた時に「ずっと一緒にいよう」と言われたそうだが、肝心の父は母を残してあの世へ行った。
その後も母は、性欲に駆られた男達の言葉に踊らされて振り回されて……。
美由の涙を見ていたら、母が病院で涙を堪えている顔を思い出した。
母はその時俺に言ったんだ。



冬弥、愛している


あの時の俺は、死を直前に迎えた言葉だったにも関わらず、嫌悪してしまった。
だけど母の言葉だけは偽りなどなかったはずだ。
子供の頃の、酒にまみれた母の言葉だって本物だったことくらい、わかってはいたはずなのだ。
俺の心にも偽りなどない。今まで安い言葉だと思っていたが、安いのは言葉ではなく、軽く偽る人の心の方だ。
思いは口にしないと伝わらないのなら、あの言葉を口にすることで美由が安心するというならば……。
いくらでも言ってやろう。
大嫌いだった、母の人生を振り回した嫌な思い出しかないあの言葉。
薄っぺらい、なんの意味もないと思ってきたあの言葉を……俺は、生まれて初めて口にすることを決心した。
いつの間にか入っていた肩の力を抜いて、小さく深呼吸をした。
だが、自分の過ちを正す暇すら与えず、唐突にそれは訪れた。

不意に部屋全体から小さく物が這いずる音がして、床がわずかに揺れ動いた。
その揺れに妙な不安を覚え、心臓の脈打つ音が俺の中で少しずつ大きくなり、足の裏に全神経が集中していった。
胸騒ぎというやつだと思う。
嵐の前の静けさとも言うべき無音状態が数秒ほど続いた後だ。
あらゆる方向から聞こえる爆音とともに、足の裏から全身を波のような揺れが襲った。
テーブルに置いてあった食器やコップが跳ね回って床に転がり、パソコンのモニターが激しい音と共に倒れた。


美由の叫び声も遠くに感じるほどの音が、そこら中で踊り狂っている。
やばい!
まともに立っていられる揺れじゃない!
俺は美由が心配になり、壁に手をついて美由の方へ目を向けた。
その瞬間、俺は今までに味わったことのない恐怖を感じた。
美由は床に中腰になって、なんとかバランスを保っている状態だった。
そんな美由のいる真横で、あの馬鹿でかい食器棚が斜めに傾いているのだ。

俺は無意識に叫び、がむしゃらに美由のもとへと走った。
バランスを崩して前のめりになり、一瞬宙に浮いたような感覚になった。
そのまま倒れこむように美由の体を押しのける。
後方へ倒れこむ美由の動きがゆっくりになった。
美由が驚いた顔をして俺を見ている。
その表情には、どこか悲しみも含まれているように感じた。
ごめん、そういえばまだあの言葉を言ってなかったね。
いつも心の中で思っていたあの言葉。
さっき君を抱きしめて、ちゃんと伝えようと決意したあの言葉。
口にすると美由への思いが削り取られてしまいそうで、それがたまらなく嫌だった。
本当はずっと言ってあげたいと思っていたんだ。
ちゃんと言うから。言うからさ。
そんな悲しそうな顔をしないでくれ。
