沙希はそう言って手を振った。



今日は楽しかった、ありがとね。かずくん


沙希はそう言って手を振った。
俺は彼女の家にその笑顔が吸い込まれるのを見届けたあと、自分の家には向かわずに、商店街の方へと足を向けた。
先ほど来た母からのメールのためだ。
味噌が切れたから買ってきて欲しい。
急ぎのお使いといえばそうなのだろうけど、そのメールを確認したのがデートからの帰り道。
沙希の家の方が近かったので彼女を送る方を優先した。
そういう理由で今、自宅とは逆方向の商店街。その一角にあるスーパーを目指している。
沙希に言ったら付いてきそうだったのでメールのことは話さずに彼女の家の前で別れた。
流石に今日一日中付きあわせといて、更に母のお使い程度に連れ回すのは気が引ける。
そんな言い訳じみたことを考えているうちに頭の片隅の不安に気付いてしまった。
俺は恐れているんだ。沙希に踏み込むことを。踏み込めないことを。
沙希が俺に踏み込むことを。踏み込んでこないことを。
俺は恐れているんだ。
俺と沙希は昔からそうだった。最後の一線を越えない。互いに干渉しない。
そうやって生ぬるい幼なじみという関係を続けてきた。だからこそ続いてきた。
昔から?
違う。アノ日から。
じゃあ今から。
その関係を更新することができるのか。新しい関係に、沙希と、なれるのか。
幼なじみという関係のまま十数年の月日を重ねてきた。
今さら。
そう今さらだ。だって沙希はアノ日。
オレヲキョゼツシタンダカラ
俺たちはこれからも幼なじみという役割を満たしあうだけではないだろうか。
違う、そういうことではない。気付いている。知っている。
沙希が欲しがっているのは『幼なじみ』であって『俺』ではない。
演劇みたいな、どこかに脚本でも隠されているようなセリフの応酬。タイミングを見計らったような笑顔に、コント。
それはまるで仮面みたいに、俺たちの顔に張り付いて。支配される。
だから俺は互いに踏み込むことも踏み込まないことも怖がっている。それはぜんぶ、結局は仮面の延長だから。仮面を、付け替えるだけ。
幼なじみだから、恋人になるのも自然でしょう?そう誰かに囁かれ続けている気がする。
それで、二人の関係がまったくの誤りであるような。根っから間違っているような気がして。
俺の問題だ。
でも、それが普通なんじゃないか?それが普通の人間同士の関係で、仮面越しのやりとりが普通。みんな互換可能で誰でもよくて。
つまり俺がこんなことさえ考えなければ沙希とともに、もっと先に歩んでいくこともできるんじゃないか。
俺はどうしてそれで満足できないんだ?
どうして唯一の何かで在りたいんだ?
『幼なじみ』の役割を演じきれないんだ?
『恋人』の役を。
わからない。
そんなことを考えていた。
だから気付かなかった。
その少女がそこに立っていたことに。



ねぇ


その少女は立っていた。
どこに?そこにだ。そこに少女は立っていた。
公園を通り抜けようとした、商店街への近道。
ろくな遊具もない広場の真ん中に。
彼女は立っていたんだ。



あなたは


そう、何もない広場の真ん中だ。しかし俺は声をかけられるまで一切その存在に気づかなかった。
もう一度自分に尋ねる。
彼女はどこに立っていた?
少女は俺の真正面にいた。



あなたは人を殺す側?


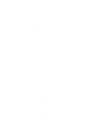


な!?





私は違う


俺はひたすらにその少女の存在に異質なものを感じていた。
その少女が自分と同じ言葉を喋りかけることが信じられない思いで見つめていた。



カガミミヨ


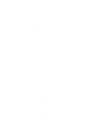


え?





あなたは?


数秒の沈黙のあとに気付く。今のは彼女の名前だったのだと。
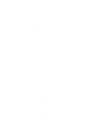


水夜?





あなたは?


なおも尋ねてくる彼女を無視するという選択肢も俺にはあったはずだった。
常識的に考えて、普通はそうする。適当にあしらって、見なかったことにする。
しかし俺は引き出されるように自分の名前を口にしてしまう。
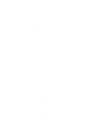


間宮夏月





カズキ


水夜は一言俺の名前をつぶやいて、俺から目を離そうとしない。俺もその瞳から目を逸らせなかった。
威圧感ではない。恐怖心でもない。ただ、見つめていたいと思ってしまう。
そんな瞳だった。
可憐というより妖美。
神秘的というより蠱惑的。



そう


ふいにそんな言葉を囁いて、彼女は視線を落とす。金縛りが解かれたような心地を受けた。息を吐く。



あなたは殺す側なのね


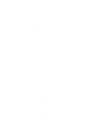


へ?


視線からは解放された。
代わりに俺は彼女の言葉と対峙しなくてはならなかった。
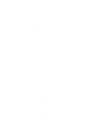


どういう意味だよ


俺が人を殺す側。
当然人を殺したことなんて俺にはない。突然そんな質問を投げかけ、いつの間にか答えを得てしまった少女は再び俺の視線を捕らえた。



これにだけは答えて


俺にどんな戯言も吐かせるつもりがないかのように、有無を言わせぬように彼女は尋ねた。



ランプをこすって何を望む?


ランプ?こするってことは魔法のランプか?何を。何を望む。俺は。
頭のなかで水夜の言葉がぐるぐると脳裏をえぐり削り。
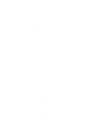


救い


気付けば答えていた。思わず。
思ってもいなかったはずのその言葉はあまりに自然と俺の口からこぼれ落ちた。



………


沈黙が辺りを満たした。
思い出したように遠くの街のざわめきが戻って来る。草木のこすれる音が息を吹き返す。
だけど水夜は俺の前に立ち続けていた。



指


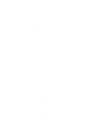


え





怪我してる


彼女の視線の先は、今朝自分で巻くことになった絆創膏。
沙希だって今日中ずっと気づかなかった噛み跡。
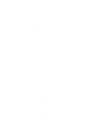


だからなんだって言うんだよ


触れてほしくなかった。思い出したくなかった。
だけど見透かされるように。



…………


現れた時と同様、唐突に彼女は踵を返した。
そのまま水夜は公園から出ていき、俺の視界から消える。
それまで俺は動けなくて、気付けば溜めていた息を吐き出してみる。
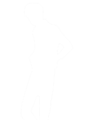


なんだったんだ、あれ


口に出してみてももう彼女はいない。
それが何だったのか、わかることは。きっと二度と、ない。
しばらく空を見上げて夕焼けの残り香が触れそうなくらいの確かな夜空に変わるのを眺めたあと、
俺は本来の用事を思い出した。
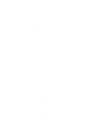


買い物行かないと


母はあんまりに俺が遅いので怒っているかもしれない。
夕飯抜きなんてのは勘弁して欲しいのだけど。
俺は何かから逃げるかのようにその場を離れ、温かな光を灯す商店街へと先を急いだ。
