授業に出席する。彼女のいる教室へ。今週も名前の思い出せない彼が隣に座った。
授業に出席する。彼女のいる教室へ。今週も名前の思い出せない彼が隣に座った。
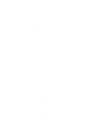


そういえばお前、川口のこと知りたがってたよな


彼女は教室の反対側で家族シネマを読んでいた。柳美里の代表作だ。戯画のような、されど本質を噛み締めようとする家族の話。
彼は尋ねてもないのに話し始める。彼女がサークルで先輩のひとりに執着して、別の女と付き合っていたその先輩を別れさせようとしたこと。
合鍵を勝手に作って、週に一回先輩のいない部屋で夕飯を作っていたこと。終いには弁護士を雇う事態になりかけて、彼女の両親が先輩に謝罪して彼女にはサークルもやめて先輩に近づかないと誓約書を書かせて。それで何とか収まったこと。
彼は本当に嬉しそうに語る。たぶん僕の彼女への憧れのようなものが崩れる様を想像しているのだろう。
でも、僕は彼の話になんとも思うことはなかった。だってそうだろう?僕はすでに彼女を手に入れた。今晩も僕は彼女の隣にいられる。僕は彼女と繋がれる。
それは僕だけの彼女であって、彼女そのものがどんな人間であろうと僕だけの彼女とは関係ない。彼女と彼の話す彼女はまったくの別物だ。僕はもう言い聞かせなくても、そう思うことができた。だから、笑顔で彼の話を受け流す。
彼は少し気味悪そうに眉をしかめた。授業が始まる。彼女が家族シネマを閉じる。
僕はそれから週に数回、彼女の元を訪ねた。幸せだった。彼女は相変わらず眠ったまま僕を迎えてくれたし、部屋の鍵はいつも開け放してあった。
毎回、ただ隣に座って少し話をするだけだったけれど、それが彼女と僕の関係で、僕はそれで満足だった。
ある日のこと。
僕はその夜も彼女の部屋にお邪魔した。そして違和感を覚えた。少し寒い。見ると、僕が毎回エーテルを換気するために開ける窓が、僕が開ける前から少し開いていた。
驚いて彼女を見る、しかし確かに眠っている。部屋の中は微かにエーテルの、化粧品のような匂いがした。
大丈夫。窓は開いていたようだけど換気はうまくいかなくて、彼女はちゃんとエーテルで眠っている。
僕はほっとして彼女の隣に座る。向こうの化粧台に蓋の開いた除光剤が見えた。
僕はいつも通りに語りかけた。返事のない彼女に。
この部屋にはマグカップが二つある。僕はそれらを借りて、ココアを二つ作って、僕と彼女の前に置いた。これも寒くなってきた最近ではいつものこと。彼女は飲まないし、僕だけが啜る。そして帰るときにはマグカップも洗って、ぜんぶ元通りにして、彼女が気付かないようにする。
でもその日は妙な味がした。エーテルの香りがやけに強く残っているせいかもしれない。
話の途中でお腹が痛くなった。僕は彼女に断ってトイレを借りた。初めてのことだったけれど、急だったので彼女も許してくれるだろうと思った。
トイレは清潔に保たれていて、微かに人工的な甘い香りがした。僕は少し緊張しながら腰を下ろす。
トイレから出たら彼女に何を話そう、と考える。考えている。
その時、目の前のドアが鈍い音を立てた。
ドアノブが壊れそうな衝撃で揺れた。僕は息が止まるほど驚いて、震えさえする鳥肌の立った手で着衣や用を足すのもそこそこに立ち上がる。
そして、躊躇う。
今の音は何だったのだろう。まともな理由が何一つ思いつかない。この部屋には彼女と僕しかいないはずなのに。そして彼女は眠っている。はず。
ありえないことばかりが想像を駆動させ、僕はそして静寂に包まれていることを自覚する。
あの大きな衝撃は一度きりだった。続く音はなく、再び換気扇が頭上で回る音だけがする。ドアに耳を当ててみた。空気の通る音。それ以外聞こえない。
ゆっくりとドアノブに手をかける。回らない。いや、重い。
僕は訝しく思いながら押し開けようとして、ドアが向こうから誰かに押さえつけられていることを知る。押しても、ほとんど動かない。
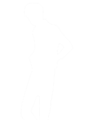


誰か、いるんですか?


僕は震える声で尋ねた。あるいは彼女が目覚めたのだろうか。別の誰かがあの部屋にはいたのだろうか。
終わりだ。僕はきっと警察に捕まる。僕は二度と彼女に会うことはできなくなる。怖い。たまらなく怖い。
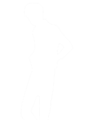


ごめんなさい、あの、理由を。そうだ、理由を聞いてください


しかし返事はない。今頃、ドアの向こうで押さえている誰かは携帯で警察に連絡をしているのかもしれない。
僕は観念した。座り込む。僕は待つ。ドアが開かれて、裁かれるその瞬間を。
・
・
・
だけど。ドアは開かれなかった。小一時間経つ。ドアの向こうの誰かはずっと立ち続けているようだった。押してみても、ドアはすぐに元の閉まった状態に戻る。
いや。
ずるずると音がして、向こうの何かが押された。ドアは閉まらない。
ようやく理解する。ドアの向こうにいたのは人じゃなくて何か重い物だったのだと。
きっと僕を閉じ込めた人間が、何かを置いて自分で押さえる代わりにしたのだと。だけどそれにしてはあまりに軽い。僕が体重をかけて押し開くだけで、僕は出られてしまう。
慎重に少しだけ開けて、様子を伺う。トイレの前には誰もいないようだった。しばらく耳を澄ませても、誰の声も聞こえない。ドアの向こう側、僕がトイレから出るのを拒んでいた物を見る。
そして僕は首を吊っている彼女を見つける。
彼女はトイレのドアノブに首を吊って死んでいた。理解できない。現実を疑い目を疑い。頭がパンクしてただ恐怖だけがじりじりと顔の表面を這い登ってくる。
つまり、僕がドア越しに押していたのは彼女の死体だった。
悲鳴を上げながら僕はリビングに転げ込む。彼女がいたはずのコタツ。手の付けられていないココア。そのカップの下に何かあった。
手紙だ。
僕の頭は勝手に現実を整理してしまう。僕は侵入者だ。でも彼女は死んだ。
ここで今、僕が自室に逃げ帰ったとしたら、彼女の死体は見つかって、証拠を残している僕はすぐに捕まってしまうに違いない。
彼女が死んでしまったことで色んなもののバランスは崩れた。僕は今とてつもない危険の中にいる。頭が白く歪む。
僕は彼女の死体のほかにこの部屋に誰もいないことを知って、手紙を開かざるを得ないことに気付く。
僕は逸る心音をやけに遠くに感じながら、手紙をもどかしく開いた。
