帰り道。電車が来た。乗り込み、自宅へと動き出す列車の中で彼女を見かける。同じ方向に住んでいたらしい。朝の彼の言葉を思い出す。
帰り道。電車が来た。乗り込み、自宅へと動き出す列車の中で彼女を見かける。同じ方向に住んでいたらしい。朝の彼の言葉を思い出す。
『だけど彼女はゴールドラッシュを読んでいた』
それは僕も読んだことがあった。救いのない父親殺しの物語。僕はそのタイトルが彼女の手元に収まる日をずっと待っていた。本の内容について話しかける口実になるから。
電車の窓の外側。空の片隅にだけ微かに夕陽の欠片が息づいてる。街灯が尾を残して一方通行に過ぎ去る。彼女の手の内側で、その物語は今日が終わるのに合わせるように、終盤に近づいていた。
彼女が今、目の前でその本を読み終わったら。きっと僕は話しかける。柳美里、いつも読んでますよね。好きなんですか。彼女は驚くだろうし不審げに眉をひそめるかもしれない。でも、それでも。
そう、変わらないのだ。僕が話しかけない限り、彼女が僕と接することは一度もない。季節が移ったら時間割は変わって。名前と顔しか知らない彼女を僕は失ってしまう。変えるには、変わらないといけない。単純なことだ。それは単純なことだ。
緊張に喉をやられる。いくら唾液を送っても息苦しく空気が通らない。何気ない声が出せるか不安だ。彼女の文庫の残りページ数が減っていく。縦に往復する目線が滑らかに僕を追い詰める。されど彼女の僕に与える手の震えは、芯の部分に微かな希望を孕んでいて僕を惹きつけてやまない。
彼女は僕に話しかけられて不快に思うだろうか。僕がいくら傷付くよりも彼女を傷付けてしまうことが怖い。なるたけ上手くやらないといけない。当たり障りなく器用に、不意に何気なく話しかけてしまったかのように。
そして彼女は文庫を閉じて。
立ち上がった。
ガラス越しにページの中身を追っていたからわかる。確かにまだ彼女は読み終わっていなかった。読み終わるより先に、駅に着いてしまったらしい。僕の脇をすり抜けて電車を降りる。
こんなのってありだろうか。運命は残酷だなんて陳腐な事実が聞きたいわけでもなく、僕はただ悲しかった。振り向く気にもならなかった。彼女が降りた駅が何処であろうと。
扉が閉まる、アナウンスにはっとする。
繰り返される駅の名前は僕の降りるべき駅だった。
僕は慌てて人を押しのけ、閉じかけた扉から無理やり電車を抜ける。人混みの少し先を彼女は歩いていた。つまり、彼女の駅は僕の駅と同じだった。
信じられない思いで、彼女の跡をふらふらと。改札を抜ける。
どうして今まで気付かなかったんだろう。きっと僕の家とも近い場所に住んでいるに違いない。
商店街を抜ける、話しかけることなんて頭から抜け落ちて、ただ着いて行く。
何かの無料配布をしていた女性に不審げな視線を向ける。自分が他人から見ていかに奇妙なことをしているかに気付いて、少し先を歩く彼女からなるべく視線を外してさり気なく歩くようにした。彼女は手渡された除光液の試作品を鞄にしまった。
そして。そう、そして。
僕の住んでいる小さなアパートにたどり着く。
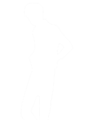


え


彼女はオートロックを外し、中へ。
郵便受けを見る。それぞれのポストと一緒に列ぶ八つの名前の中に川口の二文字があった。彼が今日教えてくれた彼女の名前。
そしてその一階の部屋は僕の隣だった。
課題をこなす。見たことのない式を教科書から探して、その一文字一文字の意味を理解して、文章に直していく。
身が入らない。ふと振り返った先に壁。彼女が向こう側にいる。僕と彼女を絶望的に遮る。壁。それは実際の厚さよりも僕と彼女を隔てる。
どうして彼女が隣に住んでいたことに、昨日まで気付かなかったのだろう。それはそれだけ僕が彼女と無関係だから。
隣に住んでいる彼女は、どうしようもなく、他人だ。例え壁一枚を隔てた、たった数メートル先で彼女が僕と似たような生活を送っていても、僕と彼女の生は交わらない。
それはつまり、僕と彼女が同じ学校に通い、同じ教室で同じ授業を受け、同じ場所で生活をしていることにだって意味は無いということだと思う。
もっと決定的な何かがない限り、僕は彼女と関わりを持つことはありえない。
話しかけてみる。昨日は簡単に乗り越えられると思えたその一線が今ではあまりに遠い。
他人が他人でなくなるというのは、この時代のこの街ではとても怖いことだと思う。
隣に誰が住んでいるのかだってわからない。友人を名乗る彼らが何を考えているかわからない。表面だけの付き合いばかりで、深入りすることは特別な相手にしかしない。
当たり前に色々なものが遮断されて、見えなくなって、その見えない先でたった今どんな歪みが生まれていたとしても見えない。それが今僕らの生きる社会だ。
そして僕の容姿や話し方はお世辞にも好青年とは言いにくい。きっと彼女は警戒するだろう。
そんな僕が同じ学校で同じ授業を受けていて、今まで隣に住んでいたことに、お互い気づかなかった。そんな偶然、気味が悪い。
万が一にも僕のような人間に一緒に学校に行こうなんて誘われたら、と僕に玄関口で話しかけられた彼女は想像するかもしれない。そして困ってしまうかもしれない。
柳美里を読むんですねなんて尋ねられたら。迷惑かもしれない。
もし仮にそうじゃないとしても、もう僕は自分のことをそう思っているから。思ってしまっているから。彼女に積極的に関わることができない。
だから、僕は彼女に話しかけたところで、きっとお隣さんという名前の、表面だけの付き合いにしかなれなくて、それに意味はないと思う。
言い訳かもしれない。けど、それでいい。僕は今までそうやって諦めてきた。僕はこれまでもこれからも何も持たない。
そう言い聞かせるように。嗚咽を押し殺す。
