ブラッドは面白そうに言ってみせた。




そもそも僕が襲われるのはお前がいるからなんだと思うんだけどな。





そうは言ってもあなたが存在するから私は存在するのよ?


ブラッドは面白そうに言ってみせた。
コードα。
それが今はルック・ワールド・ノクトビションと名乗る彼が目覚めて最初に呼称された名であった。
ノクトビションをそう呼んだ男はノウミと名乗り、そしてノクトビションの身体に宿ったものを説明した。
なんでも、不老不死のための実験、なんだそうだ。
タテシナという彼の上司が作り上げたプログラムを書き換え、自己の状態を最良に保つとプログラムされた人工血液。
そしてその実験と同時にこの精神世界が構築された。
精神世界とは、すなわちその人間の心。ゆえに誰しも持っているものだ。しかし、通常の人間にはそれを認識することができない、否する必要性がない。
なぜなら、大抵一人の人間の中には一人の人間の心のみが存在している。
自分しかいない世界というのは、誰もいない世界とほぼ変わらない。
ある偉人の言葉を借りるならば、
「存在することは知覚されるということ」
である。
まず存在させられるべきものがないのなら、知覚する必要がない。
しかし、ノクトビションは違う。
彼が体内に宿した、不老不死を実現しうる人工血液は独立意思をもつ。
その独立意思こそが今目の前でにやにやとしている囚人のような少女だった。
そしてその本体が人工血液であるがゆえに彼女の名はブラッドなのである。



もしそうだとしても、お前のせいでこっちは迷惑することの方が多いんだよ。


彼女がノクトビションにもたらすのが不老不死だけなら何もいうことはない、とまではいかないまでも、まだ我慢できよう。
血液操作の能力というのも、どちらかといえば便利なくらいだ。
しかし、もちろんそんなことはないのだ。
ブラッドが彼女にもたらしたのは、不老不死と血液操作ともう一つ。
吸血衝動である。
だが、血液なら何でもいいわけではない。
ある特定の人間にしか吸血衝動は感じない。
ノクトビションが吸血衝動を感じるのは、何か甘い香りのする人間だった。
その甘い香りというのを何かの香りに比喩して形容するのは不可能である。
ただ甘いということだけは分かる。そしてそういう人間に出会うと抗いようのない痒さが体中を駆け巡るのである。
まるで身体の中で幾億もの虫が這いずり回っているような、おぞましい痒さである。



本当にひどいことを言うなぁ。
あなたが完全になるために必要なんだよぉ?


ノクトビションが不平を言うたびにブラッドはそう返す。
何を完全と言っているのかを明言したことはない。
そして、それをまた今一度問うたところで求めているような解答を得られないことを経験則で知っているノクトビションは何も言わずに眉間あたりを押さえた。



とにかく、しばらくは身を隠しておかねぇとな。いつあの防寒野郎に襲われるか分からねぇし。





そうだねぇ。まぁ、いざとなったら私の力を使えばいいよぉ。





はっ。お断りだよ。





まぁ、嫌でも使うことになるよぉ。


ブラッドの予言めいた言葉を最後にノクトビションの意識は浮上し始めた。
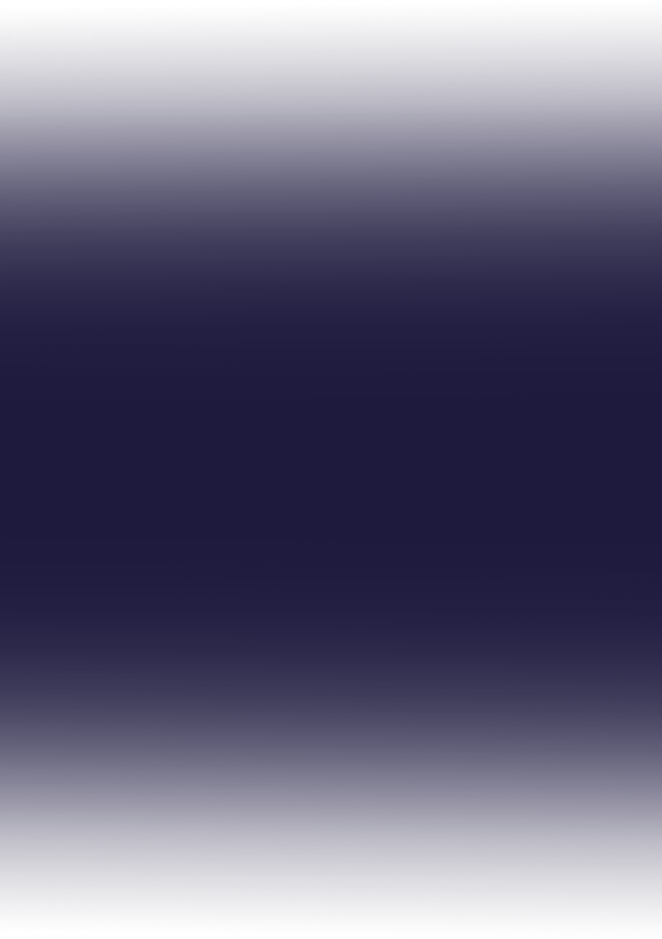



やれやれ。


ノクトビションはため息を一つついて、その赤いジャケットから小さな黒い書物を出した。

それは小さな英和辞典だった。
ページのところどころは汚く折れ曲がったり、血痕らしきものがシミになっていたりした。
そのみすぼらしい辞典を、ノクトビションはおもむろに開いた。
そこに載っているのは何かの暗号でもないし、魔術の使い方でもない。
ただアルファベット順に並べられた英単語とその説明だけだ。
その辞典はルック・ワールド・ノクトビションが、否、コードαが最初に覚醒したときに所持していたものであり、そして彼の名の名付け親であった。
覚醒したコードαはその無機質な呼称から自分を自由にしてやる必要があった。
ただ自分の名前を自分で自認するための手段である。
持っていた辞典をしばらく眺めていて目についた単語を並べただけである。
そもそも自分の出自など知らない。知りたくもない。
だが、こうしてこの世界に生きている以上、その生が死に向かっているだけのものだとしても、自分を自分と認める術が必要であり、「コードα」と言う言葉はそれを成し得なかったのだ。
理由などない。
気に入らない。それ以上の理由を求められてもノクトビションは答えられないし、答えない。
そして、あの牢獄のような実験室から脱走して時間があるときにはとにかくその辞典を読んだ。
別に知識欲でも勤勉でもない。
そうすること以外に時間を過ごす方法を知らないのだ。そしてそれ以外の時間の過ごし方を求めているわけでもない。
そして、辞典の「C」のところに来たとき、あの甘い香りをかすかに感じた。
そして軽やかな足音も聞こえる。
ノクトビションは辞典を閉じて懐にしまうと神経を張り詰めさせる。
コツ……コツ……コツ……。
そして時計塔の陰から現れたのは既視感のある少女だった。



泪さん、今日間に合ったのかな……?


