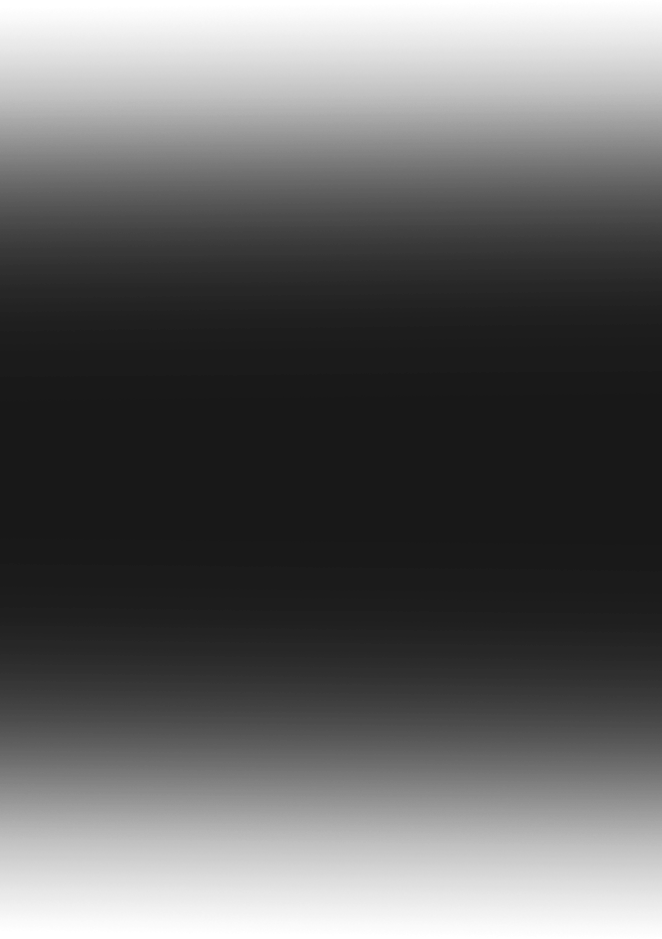――小学校の頃だった。酷く汚れた格好の兄が、どこかから一匹の子犬を拾ってきたのだ。「こいつの名前はポチだ!」なんて、その顔が凄く嬉しそうで、俺は何も言い出せなかった。
今思えば、両親は絶対飼うことを許してくれたと思う。けれど、何故かその時は親にバレたらいけないと二人してそう思っていた。だから、こっそり給食の余りを持って帰ったり、家から適当に食べられそうなものを持ってきたり、時々は自分達の少ない小遣いで餌を買って食べさせた。雨風の凌げる場所がいいだろうと、子犬を入れた段ボールは、いつも近所の高架下に置いておいた。
兄と二人で子犬を飼う。しかも、こっそりと。大したことではないのだが、その時の俺達にとってそれは、とても罪深い事だった。
ある日の帰り、いつもの通りに子犬の様子を見に行った俺は目を疑った。段ボールの中に、子犬がいなかったのだ。
その日はたまたま俺一人だけで子犬の様子を見に行っていて、兄はその場にいなかった。いつも兄の後ろに居た俺は、初めて一人でどうにかしなければいけない状態に立たされてしまった。俺は必死に子犬を探した。名前を呼んだ。けれど、子犬は見つからなかった。俺が諦めて家に帰ろうとした時、ふと傍にゴミ袋がいくつか固まっておいてあるのに気づいた。きっとこの辺のホームレス達が捨てたゴミだろう。そしてその袋の傍には、毛むくじゃらの塊が落ちていた。――それは、俺達の飼っていた子犬だった。どうして俺がすぐさまそれをいつもの子犬だと判断出来なかったのかは今でも覚えている。子犬は、子犬とは分からない形になっていたのだ。もうすっかり赤黒くなった血が、ほんの少しだけ子犬の周りに散っていた。きっと、ここじゃないどこかで、子犬は形を変えられたのだろう。「なぁ、ポチは元気だったか?」と、後で兄にそう聞かれ、俺は黙って頷くことしか出来なかった。
その翌日、近所で野良の動物を虐待していた男が逮捕されたと、ニュースでやっていた。兄は黙って俺の顔を見た。泣き出す俺に、兄は何も言わなかった。ただ黙って、俺の頭を撫でてくれた。