誰があなたの感受性を殺した?
昔の私は、そうやって感受性の泥棒ばかりを探していたのかもしれない。
昔はあんなにも小さなことに感動していたというのに!
あんなにも人と共感することができたのに!
でも、それでは埒があかない。結局のところ、感受性の泥棒の大半は、自分が撒いた種を刈る際に生じる傷なのだと知った。
感受性は死に向かうにつれて衰えるものではない。感受性は、自分自身を心から信じて、周囲へ優しさの種を投げかけた時に実る果実なのだと知った。
そう、彼のお陰で――。

誰があなたの感受性を殺した?
昔の私は、そうやって感受性の泥棒ばかりを探していたのかもしれない。
昔はあんなにも小さなことに感動していたというのに!
あんなにも人と共感することができたのに!
でも、それでは埒があかない。結局のところ、感受性の泥棒の大半は、自分が撒いた種を刈る際に生じる傷なのだと知った。
感受性は死に向かうにつれて衰えるものではない。感受性は、自分自身を心から信じて、周囲へ優しさの種を投げかけた時に実る果実なのだと知った。
そう、彼のお陰で――。
わたしは小さい頃から、人形として生きなければならなかった。
ギリシア神話のピグマリオンの話はご存知だろうか?
彫刻師のピグマリオンは、自身がつくった大理石の彫像に恋をした。それを哀れに思ったアフロディーテ様の御慈悲で、彫像を人間にしてもらったのだ。
「ガラテア」と名付けられたその元彫像とピグマリオンは結婚し、周囲からの祝福に満たされたという。
しかし、わたしにはそんな御慈悲などない。
所詮、人間になって愛された「ガラテア」のようになることはできないのだ、そう信じていた――。
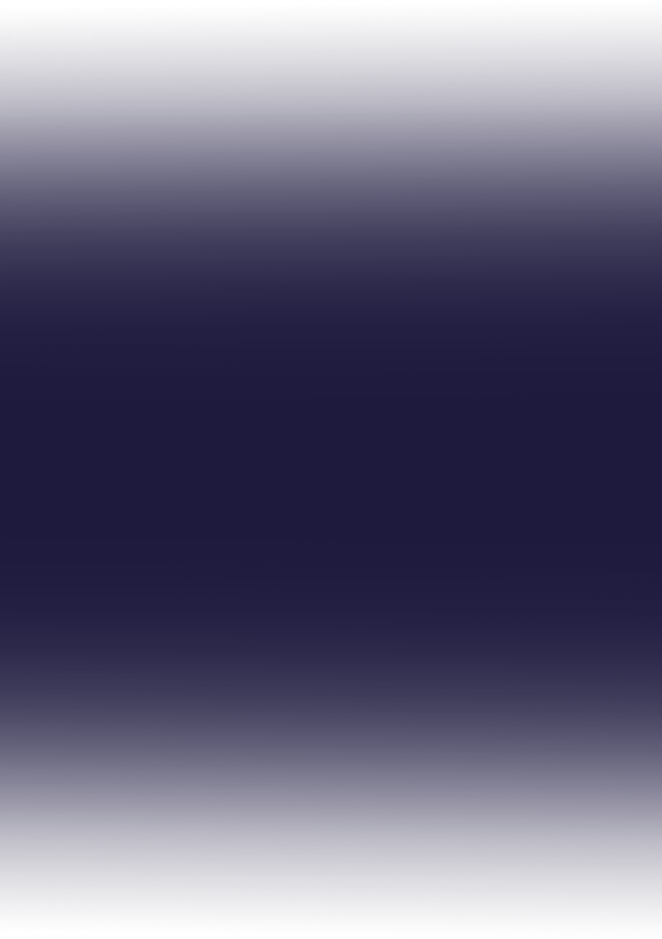
1871年 フランス
アルザス地方にある街、コルマール
コルマールはフランスの最東端にある街で、ドイツの国境付近でもある。

見わたせば余すところなく中世の街並み。
木骨造りの建物に、窓から垂れる花々。
わたしはそんな街の、「プチベニス(小さなベニス)」地区で生まれた。
ヴェネツィアほどの貫禄はないものの、中世、ルネッサンスの面影が残っている。
鼻腔を擽る、葡萄酒の香り。
時間の流れよりも穏やかに流れる、瑠璃色の小川。
極めつけに色とりどりの花々にあふれたメルヘンを体現した街だ。
お伽話の世界へのいざないを感じさせるこの街で、わたしの家だけは異様な雰囲気を放っていた。
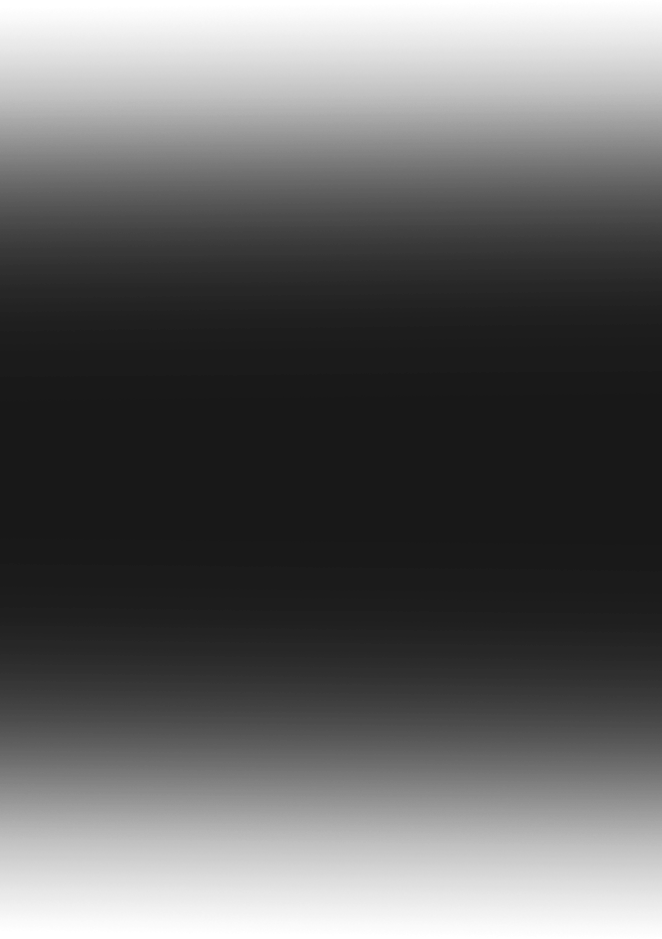
薄暗くて埃臭い部屋。
数多に存在する、所狭しと置かれた人形。
まだ昼間だというのに、この部屋はお化け屋敷のように暗くてじめじめしている。
小さな救いはカーテンの隙間から溢れる日光で、舞う埃を星屑のように煌めかせていた。
そんな中、この陰惨な部屋では耐え難い緊張感が流れていた。
わたしは瞬きを極力抑え、おばあちゃんの作った人形の列に混ざっておばあちゃんを見つめていた。
おばあちゃんはというと、窓辺の机についてふんふんと鼻歌を歌いながら人形の頭部をつくっている。



美しく仕上げてあげるからねぇ


――なんて言いながら、恍惚とした表情でさも愛しげに人形の頭部を撫でる。
素焼きを終えた人形の頭部は雪よりも白くて綺麗だが、ぽっかりと空いた眼孔が人を恐怖に誘う。
メデューサの目を見て石化するように、わたしもまたその眼窩を見て呪詛をかけられたように動けなくなってしまう。



だめ、考えないようにしなきゃ。


そう心に刻みつけても、やっぱり幼い子どもの空腹は耐え難いものだった。
カラカラの口腔内を十分に潤して、おばあちゃんの機嫌の良さそうなタイミングを見計らって唇をこじ開けた。



……おばあちゃん、お腹がすいた。


その言葉を聞いたおばあちゃんは、アイサイザーで研磨する手をとめた。
9歳のわたしには、おばあちゃんしか頼る人がいない。お父さんはとうの昔に戦死してしまったし、お母さんと双子の妹エリゼはパリへ行ってしまった。
しかし――唯一頼るべきおばあちゃんは、わたしのことなど邪魔者としか思っていない。それが現実だった。なぜかわたしは小さい頃の記憶が曖昧なため、おばあちゃんに嫌われる理由が分からずにいた。
ドールアイよりも乾いた目がこちらをじろりと見てきて、ひやりと肝が冷える。そこには微塵も愛情を感じることはできなかった。
おばあちゃんは机の上に置かれたガラス箱から何かを取り出すと、



適当に食べてきなさい。


と、投げつけてきた。それはなけなしのお金だった。それがわたしの頬に当たり、乾いた音がこだまする。
9歳のわたしにとってその振る舞いはとても傷つくものだったが、一時的に空腹がその悲しみをかき消してくれていた。
急いで拾い、立て付けの悪い木造の扉を開いて外へ出た。
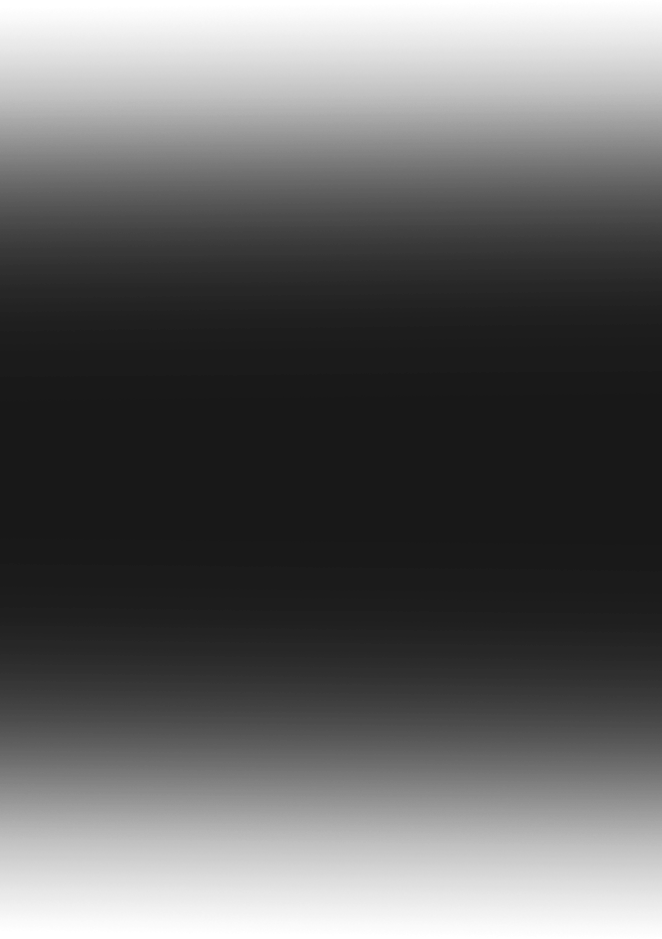
やっぱり、人形師のおばあちゃんは人間のわたしよりも、血の通わない人形を愛している。
その事実を脳裏から振り払いたかった。道中、こけて擦りむいた膝を眺めながら、



いいの、いつものことだから


妙に悟りきった態度でそう言い聞かせてみた。
すると、どうしたどうしたと近所の人びとや、コルマールの美術館を観にきた観光客が不躾にこちらを凝視してくる。
運が悪いことに、今日は木曜日だから訪問客が多い。コルマールでは、田舎家からの訪問客にご馳走をし、美術館へ案内するしきたりがある。
彼らにとって、わたしは見世物として格好の的であろう。



人形師のお孫さんよね。
ねぇ、あんた。助けてやんなよ。





いやよぉ。
あそこの家の人、皆頭おかしいんだもの。
呪われでもしたら。





ちょっと、言い過ぎよ……!
ああ、すみませんねぇ。
ささ、お気になさらず美術館へ案内しますわ。
偉大なショーンガウアー※の絵画などどうです?
採光の良い場所へご案内致しますわ!


※マルティン・ショーンガウアー
コルマール生まれの画家。
絵は生前から高く評価されていた。
そんな声が聞こえ、地面に視線を落としたまま走って小川へ向かった。
街の人たちも、こんな不気味な子どもなんて見向きもしないわよね。
――ええ、わかっている。
それなのに、喉までせり上がったこの感情はなんだろう。
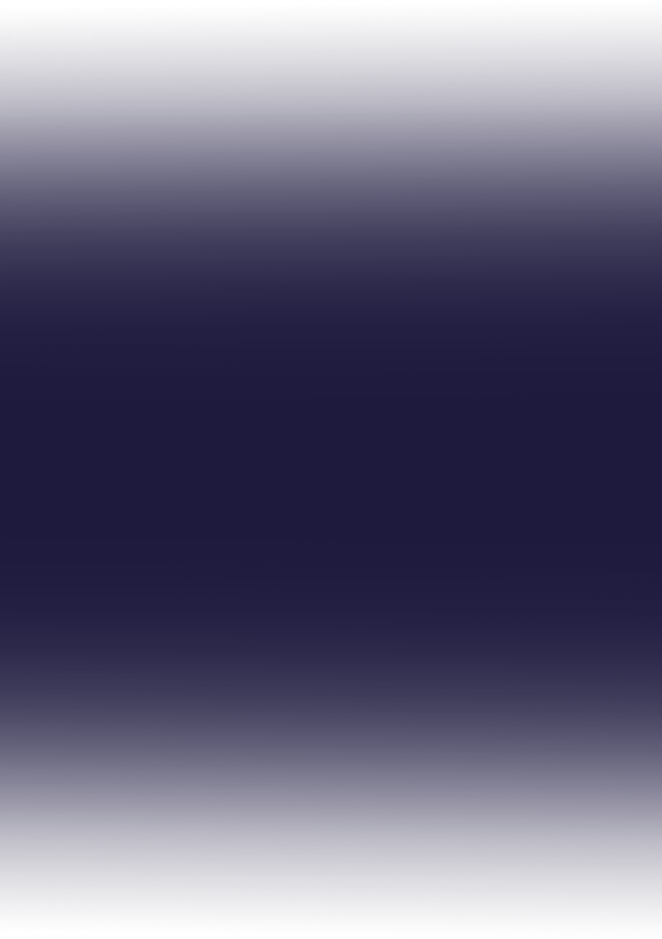
はぁはぁと息切れしながら橋の手すりにもたれ、濁った川の水を眺めていると、上流の方から柔らかい春風のような声が聞こえた。



アリシアやーい。またそんな仏頂面して、ばぁさんにいじわるされたんかい?
ほら、これあげるから元気だしな。


小舟から、花売りのおばさんが手招きする。
このコルマールで唯一、わたしに対して親切に接してくれる人だ。
急いで川岸へ回りこみ、小さな舟着場でおばさんの乗る小舟に乗り込んだ。小舟には溢れんばかりの花が積まれていて、ふわりと甘い香りが鼻腔をくすぐった。



いい香り


脳髄まで溶かしそうな花の香りにくらくらした。
この香りを一生忘れまいと必死に記憶に焼け付けようとするわたしを見て、おばさんは人の良さそうな顔をして微笑んだ。



花は人間より優しいからね


皺が顔の中心に集まったように笑うと、売り物であるはずの花をわたしの髪に差してくれた。
「いいねぇ、アリシアは将来べっぴんさんになるぞぇ」と大袈裟に褒めながら頭を撫でてくれる。水ぶくれだらけのその手は、誰よりも温かくて心地よかった。
おばさんから手渡されたタルトフランベを一心に頬張っていると、おばさんは表情を緩めながらも一瞬だけ憂いを含んだ表情を浮かべた。
※タルトフランベ…アルザス地方で愛されている郷土料理。
一見ピザに見えるが、トマトソースはない。
どうしたのだろう?
いつもとは少し違うおばさんの雰囲気に戸惑っていると、おばさんはこちらが聞き取れないほどの独り言を漏らし、何かを決心したように頷いた。



アリシア、おばさんはあんたを娘のように大切に思ってる。けど、ずっとあんたの元にいられないんだ。
だから、大切なこれをあんたにあげるよ



すると、首にかけてあった首飾りをはずし、わたしの手のひらにそっと置いた。
それはアール・ヌーヴォー調の花が刻まれた時計であった。年季が入っているのか、少し黄ばんでいるもののそれがまた味を出している。



おばさん、これは――?


おずおずと尋ねると、おばさんは物悲しい口調で



娘の形見だよ。私には、もう必要ないんでねぇ。もう一度だけ会いたかったわぁ……なんてね


とだけ言い、目を伏せた。
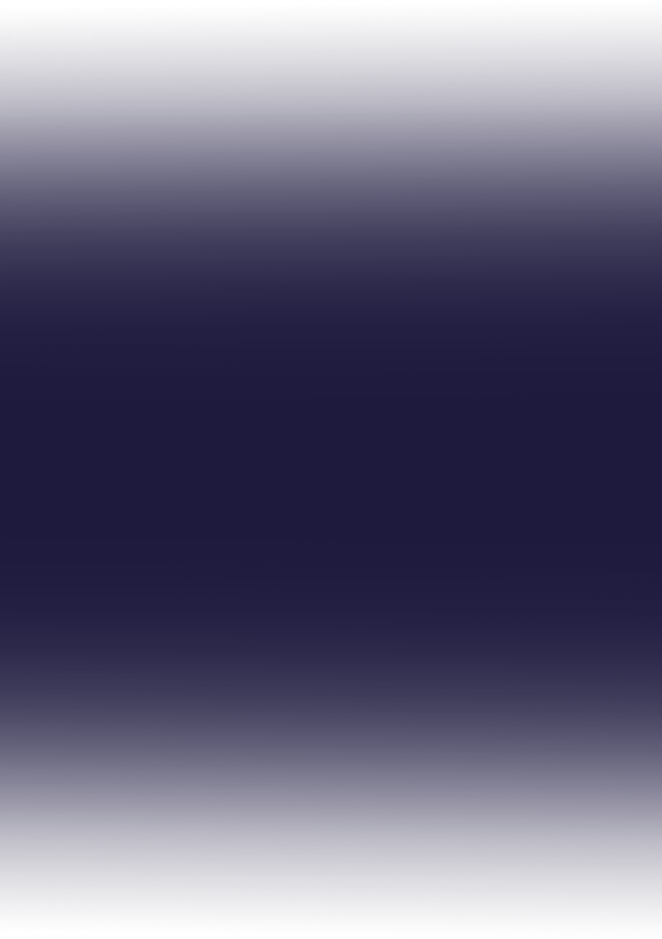
夕暮れ時、重い足取りで家に帰ると玄関前でおばあちゃんと見知らぬ老夫婦が立ち話をしていた。
老夫婦の腕の中には精巧に造られた人形があり、光を灯さないドールアイが老夫婦を見上げていた。



ああ、もう本当……あの子そっくりですわ。
なんとお礼をいえば良いことやら。





生き写しといっても過言じゃあない。
本当に、本当にありがとうございました。


妻、夫らしき人が順番におばあちゃんに心からお礼を言って涙を流している。
おばあちゃんはめったに動かさない表情を少しばかり動かし、口角を上げて彼らを見送った。
――おばあちゃんは、厳しいのか優しいのかわからない。



――ねぇ、カインもそう思わない?


人形にそう尋ねてみても、返ってきたのはメランコリーな美しい瞳から注がれる視線だけだった。
得体のしれない孤独感をたずさえつつ、僅かなオイルランプの灯りをたよりにおばあちゃんの作業場を掃除する。
完成品の人形はまだいい。
中途半端に腕や足だけが作られて天井から吊るされていたり、転がるドールアイは、禍々しいものの呼び水となりそうだ。
身を縮めて陶磁器の削り跡を箒ではいていると、箒が人形の足に当たる。



わ!


よろめいた人形に、慌てて手で支えながら定位置に戻してほっと息をつく。いけないいけない、よりによっておばあちゃんのお気に入り第二号を壊すところだった。
艶やかな栗色の髪とスカイブルーとゴールドのオッドアイが魅力的な人形で、名はカインという。この人形の列できっと一、二位を競い合うほど古い人形だ。
――が、最近のおばあちゃんはその横に佇んでいるシャルルになかんずく入れ込んでいる。これはわたしの偏見かもしれないけど、わたしはカインのほうが魅力的に映る。カインのほうが、どこか優しい眼差しを浮かべているように見えるから。
とはいっても、どちらもおばあちゃん好みの美形に仕上がっていて、一種の恐怖感すら感じてしまうことは否めない。



カイン、貴方は美しくていいわね


僻みにも似た言葉を投げかけつつも、カインの髪を丁寧に櫛で梳いた。
わたしは、カインやシャルルといったお気に入りの人形にも劣る存在なのだから、召使いのように人形にすらつかわれることがお似合いだ。
櫛を机の上に置いてもう一度カインを見た時、不思議なことが起こった。
錯覚だろうか。キラっと一瞬だけ、彼の瞳が光ったように空見した。他の人形の瞳は全く光を宿していないのにも関わらず、だ。
肌の上を走る震えと、背筋を駆け巡る悪寒に耐え切れず、いそいそと仕事場をあとにした。
――その翌日、わたしは花売りのおばさんの訃報を聞くことになる。
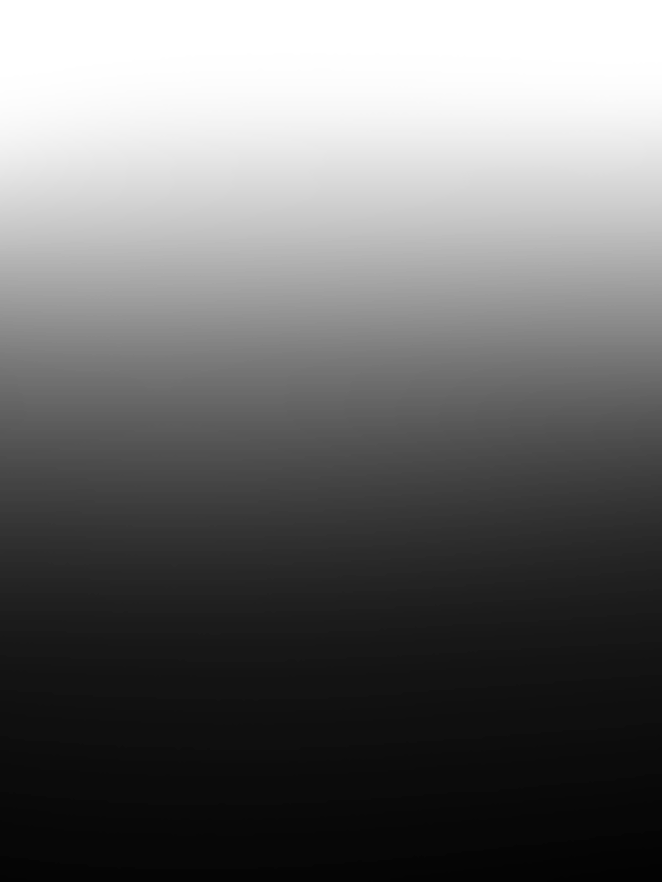
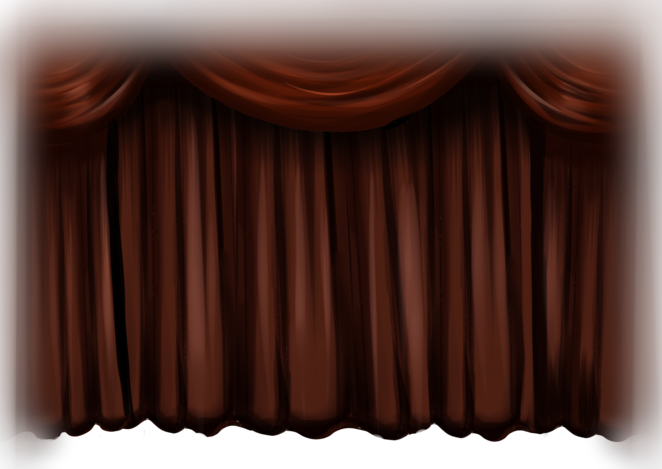

折角なので、始まりの1幕目にコメントさせていただきます。
私にもアリシアのような気分になる日があります。誰でもきっとそうなのだとは思うのですが。これを読むと思うのです。そんな時、アベルがいてくれたら、と。きっと冷たい言葉で突き放してくれるんだろうな、前に。そう思うのです。
さて、物語はまだまだ始まったばかりでしたね。これからが楽しみで楽しみで眠れない日々が続くと思うと、どうにもニヤニヤしてしまいます。
最後に、これからのアリシアと聖花さんに精一杯の頑張れ!を込めて。
連投、長文すみませんでした。
小さいアリシアたんが健気可愛くて、家族の愛に恵まれてないけど花売りのおばさんという唯一の存在が居たことにホッとしたけどそのおばさんさえも居なくなってしまってもう…!
おばさんはここで終らないと信じてた!