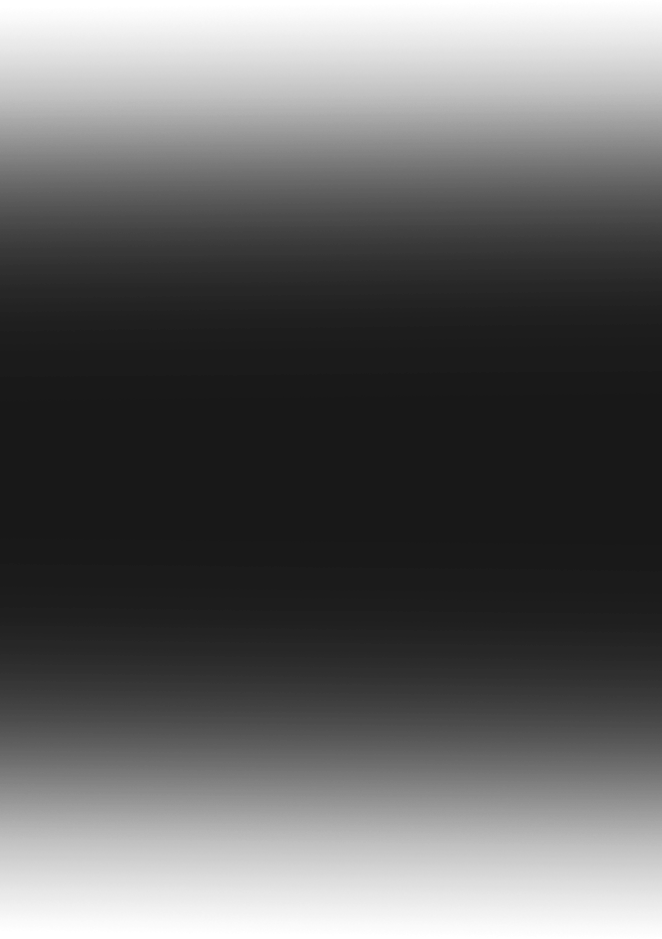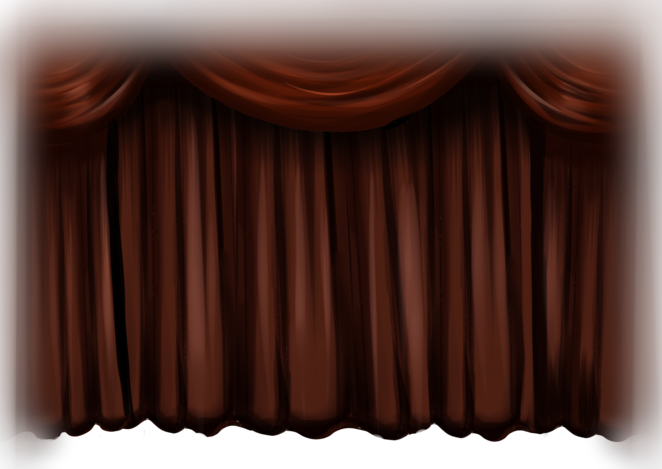人は常に孤独と闘わなくてはならない。
わたしがそのことに気づいたのは、9歳の時だった。

人は常に孤独と闘わなくてはならない。
わたしがそのことに気づいたのは、9歳の時だった。
唯一優しくしてくれた花売りのおばさんが亡くなってからというものの、わたしの感情は更に濃淡がなくなっていった。このまま、おばさんにもらった花時計のように色あせてしまうのかしら。
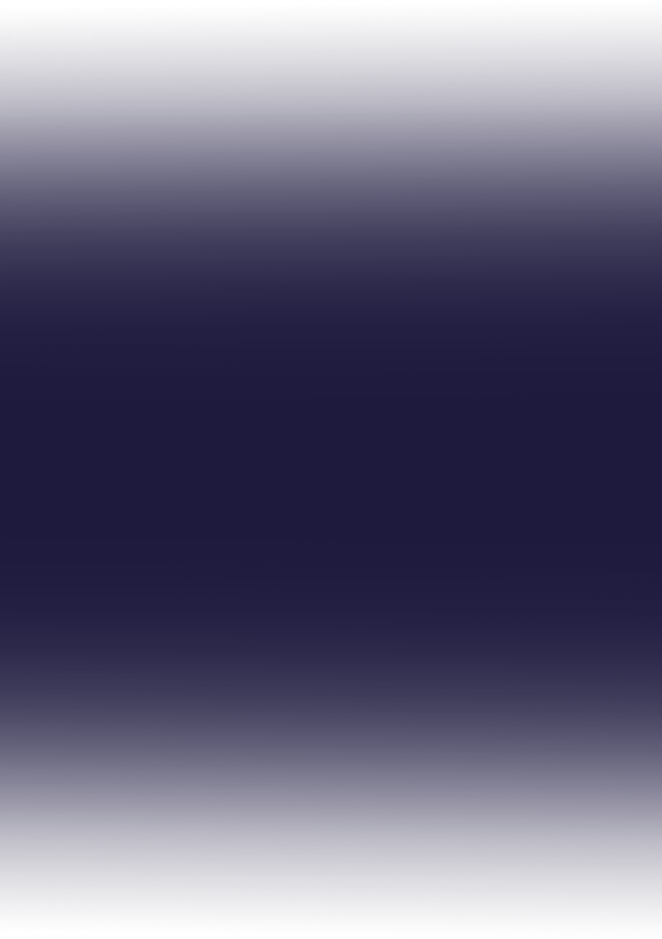



ま……けた?


震える声で問うと、



そう、フランスは負けたのよ。


とおばあちゃんはしゃがれた声で言い、自前の人形に縋り付いて泣いてしまった。
おんおんと泣き喚くおばあちゃんを見て、泣きたいのはこちらのほうだと思わないわけがなかった。
けれども、おばあちゃんの前で泣いてしまうと、



お人形らしくしていなさい!


と叱られ、暴力を振るわれてしまう。
痛いのが嫌いなわたしは言葉通り、お人形らしく無表情で見つめるほかなかった。
今日も今日とて、おばあちゃんのお気に入り第2号である人形カインの横に佇んで、狂気に満ち溢れるおばあちゃんを鑑賞する。



おうおう、シャルル。
フランスが負けてしまった!
ナポレオン様の御栄光がなくなってからは衰退するのみじゃ……。


それでもおばあちゃんは人形のふりをするわたしよりも、全く動かないビスクドールのシャルルがたいそう可愛いようだ。
シャルルは死人のような目をしているし、もちろんのこと瞬きはしない。
ぞくりとするような曇空のような目に、廃棄物のように黒い髪は、とんでもないグロテスクな芸術品で、どこがいいのかわたしには到底わからない美の境地であった。
それでも、おばあちゃんは人形を愛していた。
いつもそう……。わたしは居ても居なくても同じ。
人形師のおばあちゃんは血の通う人間よりも、陶器でできた人形を愛している。
これが、日常風景だけど。そう、日常風景だからそろそろ慣れないとね。
1871年。普仏戦争でフランスがプロイセン(※ドイツ)に敗北すると、生まれ故郷であるコルマールはプロイセン領となってしまった。

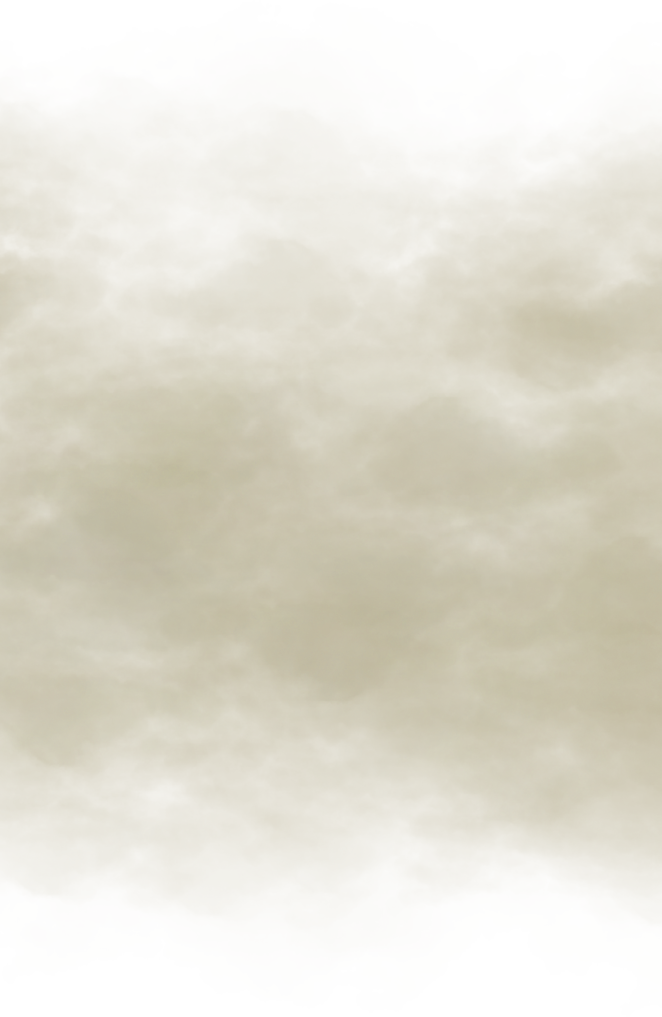
コルマール――出窓から顔をのぞけば、真下に流れる小川や、風と踊る花々の色鮮やかさに人々は感嘆するらしい。
わたしはもう、なにも感じないけど。
花売りのおばさんが亡くなった今、わたしはこの街に何の執着も持っていなかったのだ。
結局、若者を中心としてこのコルマールがプロイセン色に染まる前にパリへ移動することになった。
きっかけは、パリへ繋がる東部鉄道が切り離されることが決定されたからであった。
完全にプロイセン領となる前に脱出する算段だと聞いたが、当時のわたしはよく分からずに大人のいうことを鵜呑みにするほかなかった。
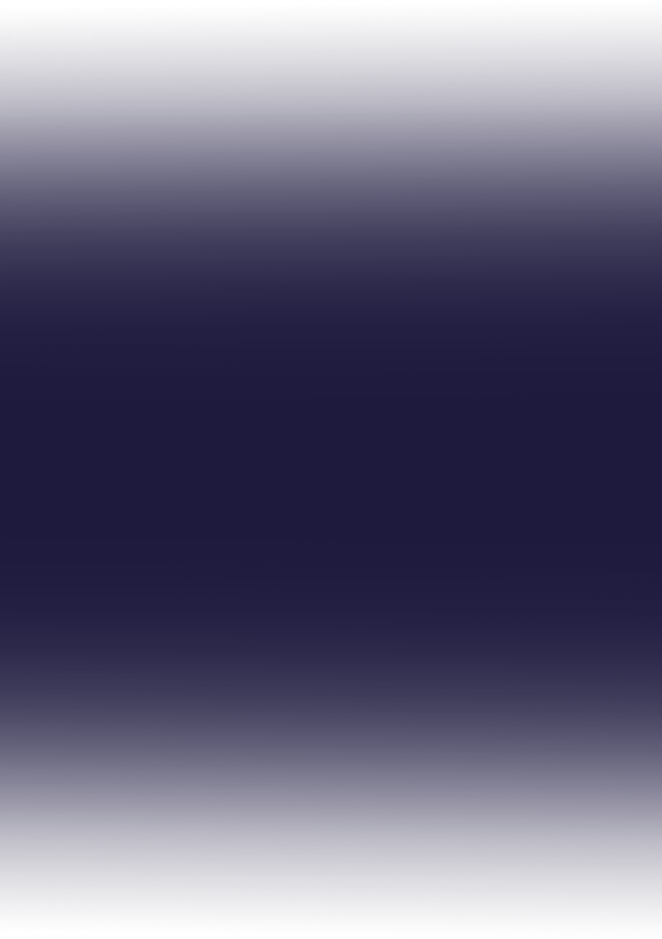
コルマールで過ごす最後の日、小川のほとりで過ごした。川のせせらぎが遠く聞こえてしまう。



あ……!


溢れんばかりの花をのせた小舟にのった人がおばさんに見えて声を漏らすものの、振り返った人物はもちろん赤の他人だった。
おばさん……わたし、本当にひとりぼっちになってしまったよ。この花時計を持っていても、心の穴を埋めることができない。どうしたら良いの?
瞼を閉じればおばさんの柔和な笑顔が語りかけてくれるのに、人間より優しい花の香りが慰めてくれるのに、心にあいた風穴をすり抜けていくばかりだ。
ぼうっと暗い水底を眺めていると、深緑色の水面に映る顔が揺れる。目からこぼれる水のせいだった。
これが涙だなんて、信じたくない。
だってわたしは、「お人形」なのだから。
水底を見つめていたはずが、自分の深淵を覗いているように思え、吐き気がした。
このまま落ちてしまえば、溺れてしまえば苦悶の呪縛から解き放たれるかもしれない。そんな悪魔のささやきが脳髄を駆け巡るが、それは出来なかった。
なぜか昔から水が怖いのだ。何もかもを飲み込み、時には原型を留めないほどに物体を溶かしてしまう水に畏怖を感じているのかもしれない。
それだけでない。わたしの姿を映し返し、孤独感をいっそう強くさせるのも水だからだ。
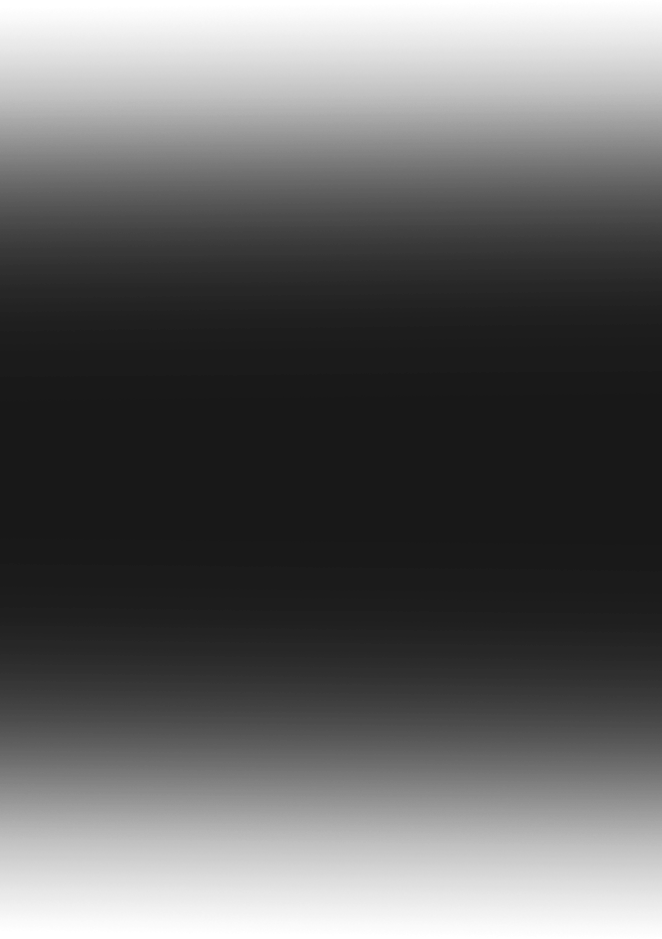
思い返してみれば、わたしはいつも独りだった。
お父さんはわたしが生まれる前に戦死して、お母さんはわたしが5歳の時にデザイナーの仕事でパリへ行ってしまった。双子の妹、エリゼを連れて。
もうエリゼの顔ははっきりと覚えていなかったけど、わたしと違って可愛くて、誰からも愛される子だったことは記憶の片隅にある。まるで将来の幸せを、花開く前の蕾のうちに約束されたような少女だった。
確か二人に、
行かないで!
ってすがりついたけど、鬱陶しそうに振り払われたっけ。
――わたしは誰からも愛されないんだ。
振り払われたその時、わたしと同じくコルマールに残されたおばあちゃんがわたしに見向きもせず、人形にのめりこむ背中を見て悟ってしまったっけ。

水面に映る歪んだ顔の自分が嫌いになり、右手で水面を叩いた。
かえってきた水しぶきが顔にかかり、その冷たさだけで生きている感覚を味わう。



アリシア、だいじょうぶ。
もともとアリシアはひとりでしょ。


最近となっては、口に出すときは自分のことを名前で話す。こうやって自分を自分だと感じないようにしたほうが、心が痛まないと知ったからだった。
どうせ独りなのだから、強く生きる。
そう決心し、着古した藍色のエプロンドレスの裾をつまんで立ち上がった。
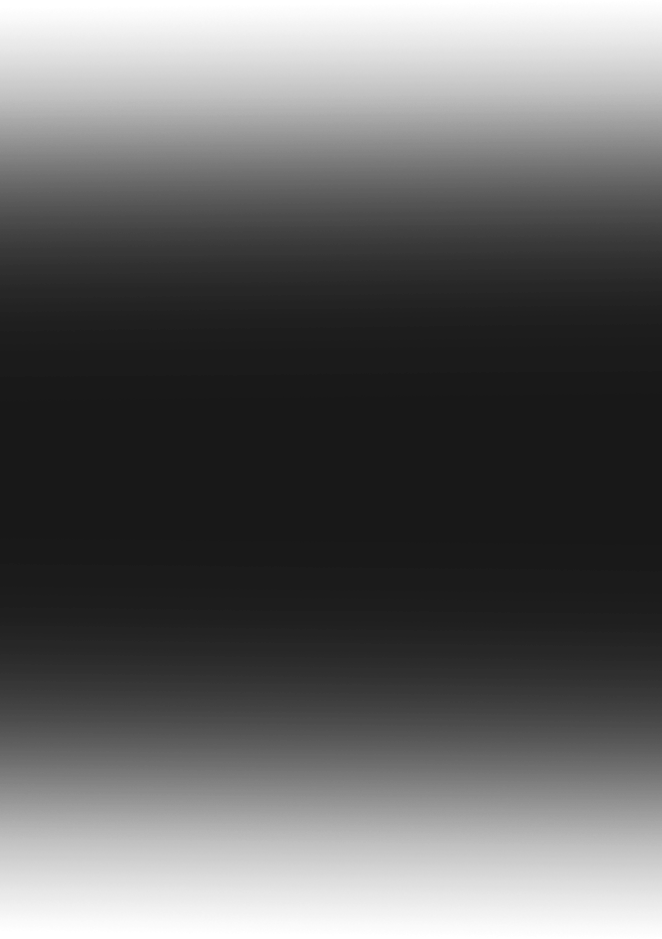
ちょうどその頃、パリでは普仏戦争で敗戦したことにより、動乱状態になっていた。
50億フラン(※5兆円)もの賠償金。
わたしの住む、アルザスおよびロレーヌ地方の一部割譲。
休戦の仮調印。
プロイセン――否、ドイツ軍のパリ入場。
相次ぎ起こる屈辱な仕打ちに、パリ民衆は憤り、政府の裏切りに立ち上がったのだ。
多くの死者を出したこの蜂起は、のちに「パリ・コミューン」と呼ばれることになる。
それはまだ、先の話――。