※注意!
本作品中には性的な描写が含まれています。
予めご了承くださいませ。

※注意!
本作品中には性的な描写が含まれています。
予めご了承くださいませ。
その日、男は歓喜にふるえていた。



…おわっっったぁぁぁ!!


北斎が版元(はんもと)に頼まれていた作品を仕上げたのは、深夜とも明け方ともとれる午前三時のことだった。
今の自分にできうる努力をしつくして、もうどう揺さぶっても何もでないという伽藍洞の境地で静かに横たわる。
煎餅布団はひんやりとしながらも北斎を受け入れてくれた。



はぁ


達成感と脱力感がさざ波のように行き来する。
次に何をするのかなど、今はもう考えたくもない。
いまの北斎には今しかなかった。
大の字になったまま板張りの天井を見つめる。
三度、瞬きをした。
一度目は自分への労いを込めて。
二度目は未来への殺伐とした不安を打ち消すように。
そして三度目で、逢いたい人を想った。
今すぐにでも逢いたかった。



ああ。
マジで“○こでもドア”欲しいわ


だが残念なことに、二十一世紀の今日に至ってもなお、そんな名器はこの世のどこにも存在しない。
ひと仕事を終えて、ここは仮眠をとるべきところなのだが、限界まで張り詰めた神経が邪魔をして眠れそうにもないため、このまま夜明け頃まで適当に時間を潰して起きていることにした。
体内時計がだいたい五時を告げるころ、北斎はそっと布団から起き出し二階の自分の部屋を出る。
言い忘れていたが北斎の家には電話もない。
不調法もここまでくると素敵な個性へと昇華するのだという誇大妄想を、北斎はわりと本気で信じている。
階段を降りて下駄に足を通す。
北斎の家は一階に水回りがまとめてあり、入り口を入っていきなり台所が地続きになって正面に、いる。
ある。というより、いる。
狭小な場所にあるというのに洗面代も焜炉も冷蔵庫も完備しているという存在感が尋常ではない。
これぞ究極の「みにまりすと」。
土間には簀の子が飛び石よろしく敷かれており、履物を要せずに辿り着けるというのが北斎の自慢だ。
格子戸の表戸を開けまだ暗い朝の路地へ出ると、電話を借りるため三軒隣の駄菓子屋へと向かう。
駄菓子屋の主であるご夫人は、いつでも使ってよいと勝手口の合鍵まで渡してくれていた。
こうして北斎は、親切な他人に支えられて生きていられるということを、一時たりとも忘れたためしはない。
合鍵を揺らしながら駄菓子屋の裏口へ行くと、予想に反して明かりがすでに灯っている。
勝手口を叩くと早起きのご夫人が気さくに話しかてくる。



おはよう





おはようございます


電話を貸してほしいと申し出ると快諾してくれたので、さっそく電話をかけて用件だけを手短に伝えた。
すぐに帰るつもりが夫人に引き止められる。朝食を勧められて他人の行為を無下にできない北斎は、遠慮なくご馳走になることにした。
世間話の延長から身内の話に及ぶ。なんでも夫人の家には今、春休み中の甥っ子が遊びに来ているそうで、夫人はその甥っ子の将来を大層心配しているのだとか。
このご時世では無理からぬことだと思った。
だが、職に就いているようないないような、不安定でしかない自分にはなんとも返す言葉が思いつかず、



はあ


と、曖昧な返事をしてしまった。
人生など、どうにかなるなどとは口が裂けても言えない。実際にはどうにかなってしまうものかもしれなくても。
それは大人になったから言えることだ。
何百、何千、あるいは何億もの不確定な未来を抱えて爆発寸前の精神状態で生きている少年少女に、それはあまりに酷な言葉だと、帰る道すがら北斎はひとりごちる。



やるしかないからな…


あるいは何かを積み重ねるか重ねないかの違いでしかないのかもしれない。
それが何なのか。
わからないからこそ辛く、しかしだからこそ面白いのかもしれない。
ただ、今の自分より少し先に、つま先を置くことでしか、前には進めない。
そして今の北斎にとってそれは、広重君に会うことだった。
そのはずだった…
…せーん
…ませーん
…すいませーん
…すいませーん!
すいませーん!!



…え?


家の外で声が聞こえる。
仕事漬けでろくに寝ていなかったせいか、目覚めても体が起きようとしない。
それでもなんとか起きて玄関に向かう。
ガラ



はい





あの、俺、そこの駄菓子屋の店番してて、





…はい





えと、北斎さんて





あ、おれです





あの、電話、かかってきてます





……え、あー、はい。
今行きます


ぼりぼりと頭を掻きながら青年の後についていく。



…もしもし





あ。北斎サン?





……


それは、いつも仕事を斡旋してくれる版元の女性からだった。今回の仕事もここに依頼されたもので、決定版との連絡はすでにもらっていた。
なぜ今、版元から電話が来るのか。



…お疲れさまです





寝てた? 寝てたよね?





え、ええ、まあ





ごめんね?





…?





急ぎで追加の仕事、お願いしたいんだけど、いい?


うわ~。ダメって言えないヤツだ



……はい


仕事の内容を手近な紙に書き終えると、気遣うように版元が云う。



仕事終わったばっかなのにごめんねー





いえ





この仕事ね、歌麿が蹴ったのよ


…え?
歌麿が蹴ったのよ
歌麿が蹴ったのよ
歌麿が蹴ったのよ
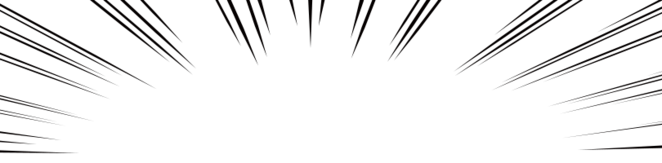
歌麿が蹴ったのよ
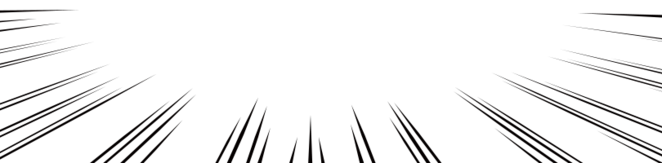
とぼとぼと部屋へ戻り、大の字で横たわる万年床の上で北斎は先ほどのやり取りを思い出す。
電話口で最後に版元は云った。



じゃ、明日までによろしくね





(サイアクだ)


北斎の腹時計(誤差±0.3秒)は午前十一時を示している。
ひび割れた椀のそこから染み出すように、次第に感情が込み上げてくる。



やだよぅ(泣)


そう思いながらも北斎は机に向かう。
それが己のすべきことだから。
三十分後…。



……


一時間後…。



……


二時間後…。



……腹、へったな


階下へ降りて小さな冷蔵庫を開けてみる。
ビール350ml 一缶
溶けた氷嚢 一つ
調味料 他
以上
ぐぅ。
この状況でぐうの音がなるのか。
俺って、はいせんす☆



……


仕方がないので商店街に買いに行くことにする。



毎度あり~!


卵を受け取ると、八百屋の主人にさっき彼氏が来てたぞと言われた。
だいたい想像がつくだけに心苦しいことこの上もない。
家へと向かいながらため息ばかりが生まれていく。



はぁ


せめて彼女と云ってほしかった…。
周囲のご婦人方の視線が今尚全身に突き刺さっているようで痛い。
だが相手は男なので彼は彼でしかなかった。
なんとなく、心が寒かった。
広重に、逢いたくなった。
昼食後、だらだらしながら仕事をなんとなく進めようとする。
三時間後。
依然として目の前には白いままの紙が。



明日までって…


“ムリです”と云えばよかったと、この時普通に北斎は後悔したのだった。
その後もぼんやり過ごしていると、駄菓子屋の青年の声が階下から聞こえた。
どんどんどんどんどんどん!!



すいませーん、北斎さーん


彼の名はたしか、一葉(かずは)とか云ったな、とこれまたぼんやりと思い出しながら駄菓子屋へ本日三度目の訪問。



もしもし、





もしもし、俺です


あ。広重君の声だー。



…んですけど、みそとしょうゆ、どっちにしますか?





……え?





だから、みそとしょうゆ、どっちにしますか?


このちょっと低く響く声がたまらく好きだ。
歯切れがいい。
ずうっと聞いていたい。
もっとしゃべって欲しい。
とぼけてみる。



……んあ?


ガチャン!
あれ? 切れた。
え? キレた?
ジリリリリリリリリリリンッ



!!?


受話器を置くと同時に電話が鳴った。
恐る恐る電話に出る。



…はい





あ、すいませーん。北斎さんを





あ、俺です





あ、丁度良かった。
どう? 進んだ??


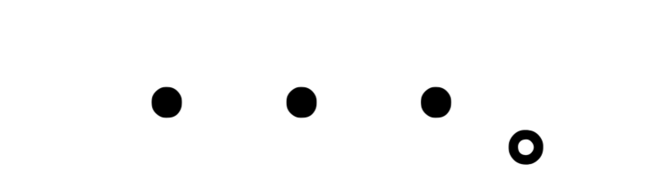



…ハア…


ぼりぼりぼりぼりぼりぼりぼり
なんとも言えない間から状況が切迫していることを察してくれたのか、版元は打開策を提示してきた。



…とりあえず簡単な下絵でいいからあげてくれる?





…ハイ…


正直それができるんなら苦労しない。
下絵ができるってことは頭の中では完成してるってことなわけで。
そこを知ってもたいたいわけで。
ていうーか版元はソコんトコを承知の上でワザといっている、わけで。
それもわかっている、わけで。
そしてそれができるんなら苦労しない、わけで。
もう、頭の中は広重君でいっぱいなわけで。
夕方を過ぎても万年床で悲観にくれていると、良策が降って湧いて飛び起きる。



うおお!?


すぐさま部屋の片隅に積まれた画材や資料の山をひっくり返し始める。
がさごそがさごそ…がさごそがさごそ…



あった!


天に掲げたそれは、この間珈琲を待ちながら描いたうたた寝広重君の絵であった。
逢いに行けないなら描けばいい。
至極簡単なことだった。



ふふ、ふふふ…


時間を忘れて上機嫌で描いていると腹時計が間もなく九時をお知らせするところだ。



やべぇ


あわてて駄菓子屋に走る。
どんどんどんどんどんどん!!



一葉くん!! 電話貸して!!





どうしたんですか血相変えて…





緊急じたい!!だ!!


トゥルルルルルルルルルルルル



はい





あ、北斎です。
ごめんやっぱムリ





…わかりました。じゃあ、また今度


駄菓子屋を出るとゆっくりとした足取りで部屋まで引き返す。

広重を下絵とした生々しい美人図の前で呆然と立ち尽くす。
絵筆を手に持ち、下絵と向き合いながら、けれどそれは北斎の頭の中に響く。
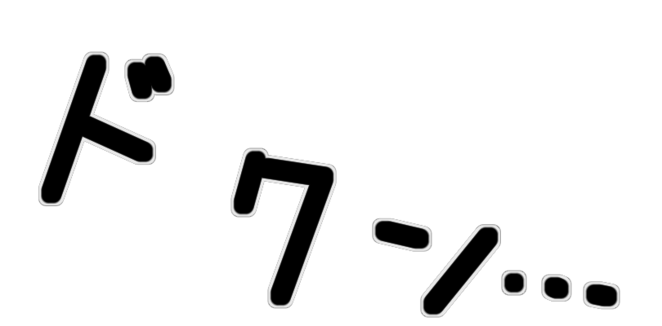
今度っていつ?
俺、今度はいつホントの広重君に逢えるの?



……


大人になったからといって、なんでも上手くいくわけじゃない。
逢いたい人にも逢えないなんて、しょっちゅうだ。
だけどやらなきゃならないことから逃げてまで逢えるほど、俺は絵が嫌いなわけじゃない。
つーか好きだし。
大好きだし。
だから辛いんだし。
心が、虚無になる一瞬を保持しようとする。
それは大きく口を開いて、いつでも堕ちてくるものを待ち構えている。
その矛盾と非常と無常を理解しながらも人は、その深淵に立っていようとする。
まるでそれが論証だとでもいうように。
それから数時間後。
”からんころん”が闇夜を進む。
俺はもう堕ちているのかもしれないと、北斎は思う。
虚ろな目は何処を見ているのか、自分でもわからなかった。
それでもこうして本物に逢いにきているからには、未だ堕ちてはいないのか。
それともこんな時間に逢いに行くのは堕ちた証拠なのか。
考えるのは止そう。疲れるだけだ。
普段見慣れた光景が暗いというだけでまったく別のものに見える。
門扉を抜けると、勝手口に回る。
懐からおもむろに合鍵を取り出し、(なんかのキャラクターが付いているけれど、これ何って聞くのいつも忘れるなってことを一瞬思い出してまたすぐに忘れながら)鍵穴にさす。
ガチャり。
扉を開けると音を立てぬようにそうっと中に入る。
台所に上がり、迷うことなく明かりを付ける。
綺麗に片付いたそこには、鍋が一つ。



……


ズキン、と何かがいった。
けれど、なんだか温かかった。
鍋の中は見ずに明かりを消し、そのまま寝室へ向かう。
廊下がひんやりと真夜中の訪問者を受け入れる。
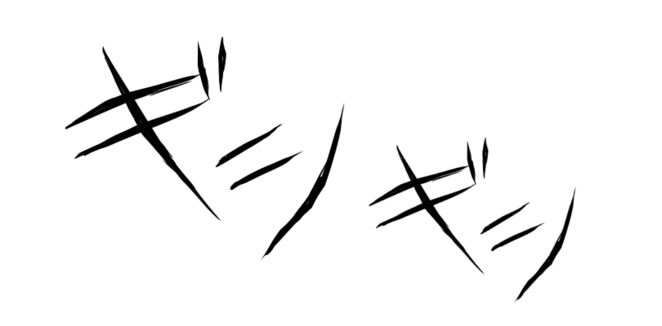
こんな広い屋敷では杞憂かもしれないが、主を起こさぬよう、足音に気をつけて歩く。
部屋へ辿り着くと、ゆっくりと障子戸を引き開ける。
そして北斎は無事、目指すお宝を発見する。
寝相よく布団に横たわる眠り姫は、規則的な寝息をたてている。
寝衣の浴衣が着崩れないのは見習うべきかと思いながら、枕元に立つ。
姫が目覚める気配はない。



ただいま


ぽつり、と庭の手水に雫が滴り落ちたときのような、微かな声で北斎は目の前の男に帰宅を知らせた。
そのまま布団に潜り込む。
「んん」
広重は寒いのか向こうを向いてしまった。



……


かまわずその背中にぴたりとくっついて、広重の温もりと匂いに包まれながら北斎は眠りに落ちた。



したいです


北斎は、自分の額に己のそれをぴたりと付けて懇願する広重の顔が近すぎて、事態を理解するのに少々時間を要した。
したい? したいってなんだっけ??
…ああ。そっちね。
ピントが合う位置まで離れた広重の頬にそっと触れる。



……


『うん』と云いたかったのに声が掠れていて息だけがでていった。
俺も。俺もそう思ってたよ
ちゃんと伝えたかった。どんなに逢いたかったか。どんなに想っているか。
北斎が口を開きかけた刹那に広重は応えた。
深い、口づけで。
「はぁ……はぁ……」
久々の挿入は思いのほかキツく、部屋中にバラの香が充満することとなった。
「動きますよ?」
「待って……動くなって」
「動いてませんよ」
「動いてんじゃん」
「え? どれ?」
「うあッ…」
「あ。スイマセン(笑)」
「……」
「も、いいよ。うごいて」
「ハイ」
「「……」」
「あ、…んんッ…ンあ…ああ…ハぁ、あんっ……」
後ろから何度も突かれていつの間にか北斎の髪はほどけてしまっていたが、そんなことはどうでも良かった。
あ~、きもちいぃ
愛しいものの温もりをいつまででも感じていたいと、ただただ北斎は純粋に願った。
ブォォォォォォォォォォォォォ



聞いてもいいですか


風呂上がりに広重がドライヤーで髪に風を送りながら話しかけてくる。



なに?


俺は美容院の客よろしく週刊誌に目を落としながら応じる。



遅くなった理由…って…





ああ


そんなことか
今となっては全くもって些末なことだった。
それこそ思い出すのに時間を要するほどに。



大きい仕事が片付いた直後に急ぎの仕事が入ったんだ


だから、北斎は地雷を踏ん付けた。

☟



歌麿が断わったらしくて


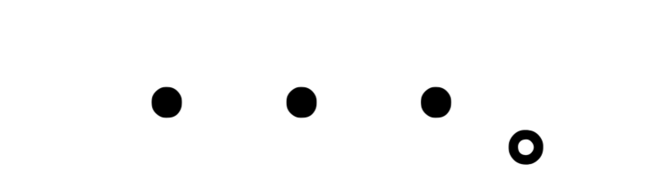



あ。やべぇ



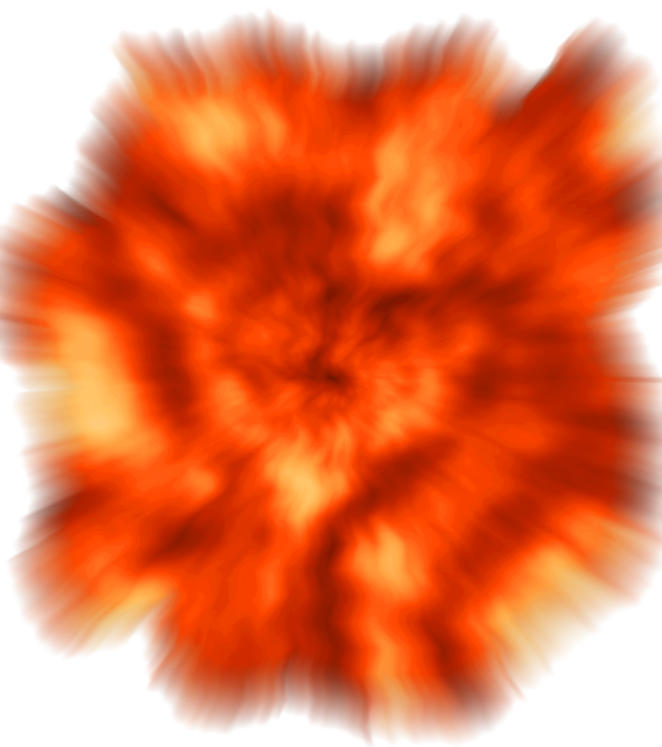

北斎が己の過ちに気づいて振り返ったときには、広重君はお伝えできないほどの怒気を纏って固まっていた。



やっちまった…


つづく、か?
