初めて口をきいた日から少しずつではあったが、ケンイチはアユミに心を開くようになった。
同じような境遇で同じ罪を背負った二人の悲しみは共鳴し、交じり合った。
初めて口をきいた日から少しずつではあったが、ケンイチはアユミに心を開くようになった。
同じような境遇で同じ罪を背負った二人の悲しみは共鳴し、交じり合った。
「……楽しかった?」───「何が?」
「子供の頃よ」───「いや……」
「ぜんぜん?」───「ぜんぜん」
「ひとつくらいあるでしょ?」───「……ない」
「あはは、可愛そう」
「アユミはあるのか」───「うーん、あるよ」
「お母さんがいた頃は楽しかった」───「そっか」
「あ、ごめんね」───「……いいよ」
アユミは自身の犯した父親殺害、その罪の重さに苛まれていた。
夢の中に現れる父親はその焼け爛れた顔でアユミに呪いの言葉を浴びせた。
目が覚めてからも逃れようがない罪悪感に押しつぶされそうになった。



お父さん…。ごめんなさい、でもそうするしかなかった……


アユミは父親の夢を見る度、贖罪の祈りを繰り返した。
ケンイチもまた母親を殺害した事による良心の呵責に苦しめられていた。



あの日雪の校庭で殴り殺されればよかったのに


ケンイチはそう思うようになっていった。
ケンイチはアユミと話してる時だけは穏やかになれた。
そのささくれ立った心が癒されていくのがわかった。
ずっと孤独だったケンイチにとってアユミは初めて出来た友達といえた。
「だれか待ってる人いる?」───「いない」
「ここでたらどうする」───「わからない」
じゃあ、一緒に暮らさない
似たもの同士一緒にいるのも悪くない
約束だからね・・・
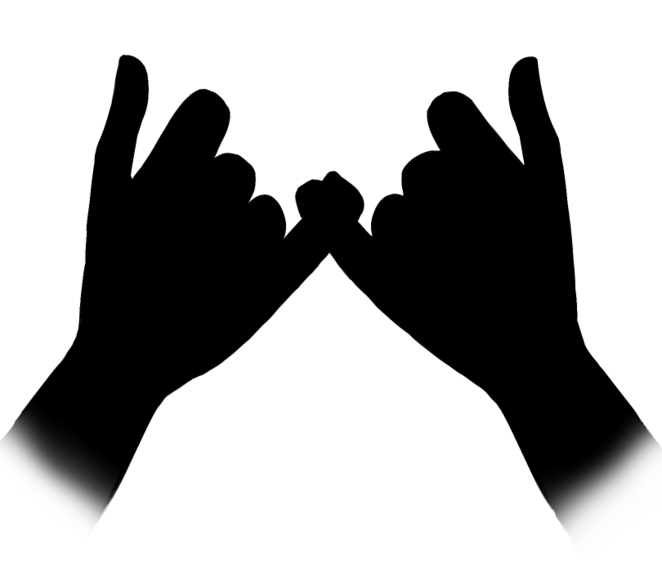
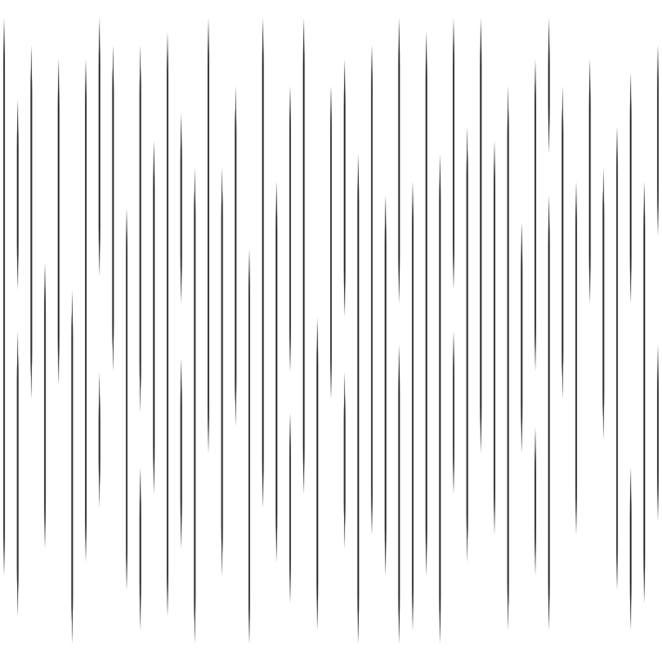
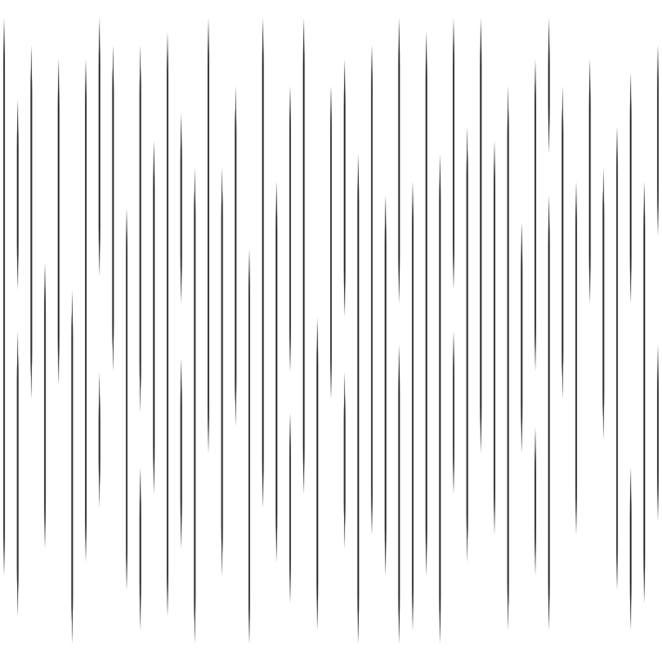
ある朝、院長のカリヤは二人を二階にある礼拝堂に呼び、ひざまずき神に祈るように命じた。



この祈りは、『私たちの負いめをお赦しください。私たちも、私たちに負いめのある人たちを赦しました』という事だ。
それでお前たちが罪を犯した者を赦したように、主はお前たちの罪も赦してくださる





でも、私は赦すことはできません


アユミはカリヤに向かっていった。



お前はどうだ?


カリヤはケンイチに向かっていう。



わかりません……


ケンイチは呟くようにいった。



そうか…… まあいい


そういうとカリヤは憮然として奥の部屋に姿を消した。
一階に下りて自分の部屋に戻ろうとしていたケンイチを施設職員のアライが呼び止めた。



ちょっとこい!


アライの手には竹刀が握られていた。
保健室にケンイチを押し込むとアライはいきなり竹刀でケンイチの太股の裏を叩いた。


たまらずケンイチは床に膝を付いた。
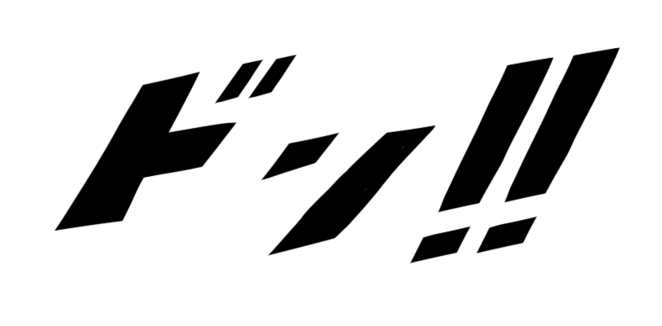
今度は竹刀の先でケンイチの腹を手加減なしに突いた。
激痛が腹部を貫き四肢が痺れた。

腹を押さえてうずくまるケンイチの頭めがけてアライの蹴りが飛んできた。


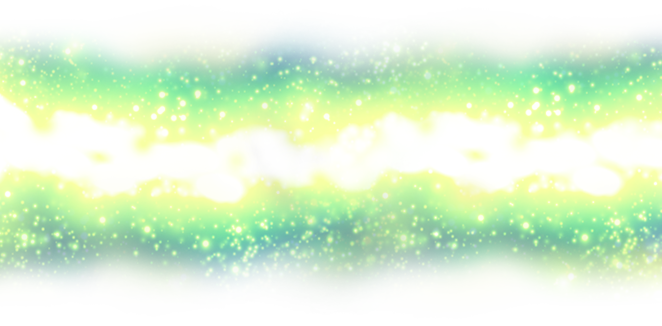
ケンイチの眼の裏に閃光が走った。
苦しむケンイチを見てアライは楽しむようにサディスティックな薄笑いを浮かべている。



これはお前の犯した罪に対する罰だ!


そういうとアライは倒れて呻き声をあげているケンイチの髪を掴んで顔を持ち上げ、両手につけていた軍手を外ずし、それを丸めて無理やりケンイチの口に押し込んだ。
そして更に殴る蹴るの暴行を続けた。
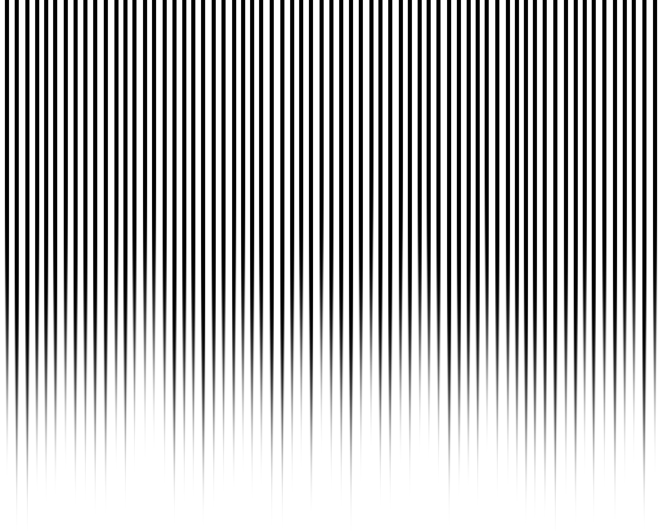
ケンイチは気がつくと自分の部屋のベッドで寝かされていた。
何時間たったのだろうか……。
遠くで野犬の遠吠えが聞こえた。窓の外はもう真っ暗だった。
時計を見ると真夜中だった。
ぼんやりと霞がかかった頭でアライがいった事について考えた。



これはお前の犯した罪に対する罰だ


ベッドから身を起こす、体中が痛んだ。
───お前の犯した罪……
母親を殺した……。
僕が殺した。
今でもあの感覚は忘れる事は出来ない。
だが夢の中の出来事のような気もしている。
死んでしまえば罪は消えるのか……。
わからなかった。
ケンイチは部屋を出ると食堂に向かった。
台所の包丁が入っている抽斗をあけると一番大きな牛刀を取り出した。
疲れた───
もうこれ以上生きていても意味がない。
ケンイチはここで死のうと思った。

