母親を殺害しクラスメイトの少年に重傷を負わせた罪でケンイチは逮捕された。
ケンイチは、当局による数週間の取調べを経て家庭裁判所の審判を受けた後、保護処分として地元から遠く離れた児童更生施設『国立のぞみの園学院』に送致された。
母親を殺害しクラスメイトの少年に重傷を負わせた罪でケンイチは逮捕された。
ケンイチは、当局による数週間の取調べを経て家庭裁判所の審判を受けた後、保護処分として地元から遠く離れた児童更生施設『国立のぞみの園学院』に送致された。

ここでは、政府発行の『重犯罪児童再教育プログラム』を遂行し管理されていて、重犯罪を犯した小中学生の少年少女が収容されている。
『国立のぞみの園学院』の方針は、院生の更正、矯正および社会復帰のため、家庭的な雰囲気で成長を促進させ、訓練し教育する事を目的とするとされていた。
しかしそれは全くの表向きであり、実際の院生の生活は悲惨極まりないものであった。
職員による子供たちに対する体罰は日常的であり、食事も汚染された食材で作られた料理が平然と出されていた。
当時院生はハルトを含め四人でその内、少年が三名、少女が一名であった。
皆、殺人の罪を背負ってここに送致されてきた子供たちである。
凶行に至った理由はそれぞれであったが、院生五人に共通するのは、親の愛情を全く受けずに育ったという事であった。
院長はカリヤといった。
宗教家でもあるカリヤは院生に自分の事を牧師様と呼ばせていた。
カリヤは五十代後半であったが、顔の色艶は良く見るからに健康そうであった。
背は低く腹が出て太っていた。
牧師といっても服装はいつも普通の会社員が着るようなスーツ姿あった。



……


ケンイチは、ここに到着してまず最初の手続きを済ますとアライという三十代の施設職員にバリカンで坊主にされた。
アライは体格の良い大男で半袖のシャツから出る日に焼けたその腕は太く毛深かった。



お前、お袋殺したんだってな?


刈られた毛を掃除させられてるケンイチに向かってアライがいった。



……





どんな気分なんだ? 自分のお袋を絞め殺すときは?





……





何とかいえよ、お前、しゃべれねえのか?



アライは、ケンイチの耳を掴むと力まかせに引っ張りあげた。



どうだ、痛いか? ここじゃあ、オレをなめるなよ!


黙って痛みを耐えるケンイチ。



強情なやつだな、思い知らせてやるからな



そういうとアライは、いきなりケンイチのみぞおちを殴りつけた。
ケンイチあまりの痛みで息が出来なかった。
たまらずうずくまり体を折って床に反吐を吐いた。

それからケンイチは保健室と呼ばれている独房に手錠とヘッドギア、拘束衣をかけられて二週間入れられた。
それは、新入りの収容者に課せられるここでの儀式でありこの施設の習慣であった。
これは新参の収容者の毒気を抜く事が目的の隔離であった。
院長のカリヤはここで静かに瞑想し自分の犯した罪の反省をする事をケンイチに命じた。

一人部屋の中ケンイチは母親の事を思った。
傷つけた少年の事を。
幼い頃の事を思った。
楽しい思い出などひとつもなかった。
ずっと一人だった。
暴力以外で人と繋がった事はなかった。
母親でさえもそうだった。
生まれてこなければよかった。
自分だけこんな目に……
一体何のため生まれてきたのか?
雪の中に現れた金魚、
それを見たときの抑えきれない憤怒、暴力衝動。
身体の中に入り込んで同化してしまったトカゲ。
いくら考えても答えはなかった。
どこにもなかった。
ただ空っぽになりたいと思った。
透明になりたかった。
この世界から消えてなくなればいいと思った。
いや、こんな世界なんかぶち壊してやりたいと思った。
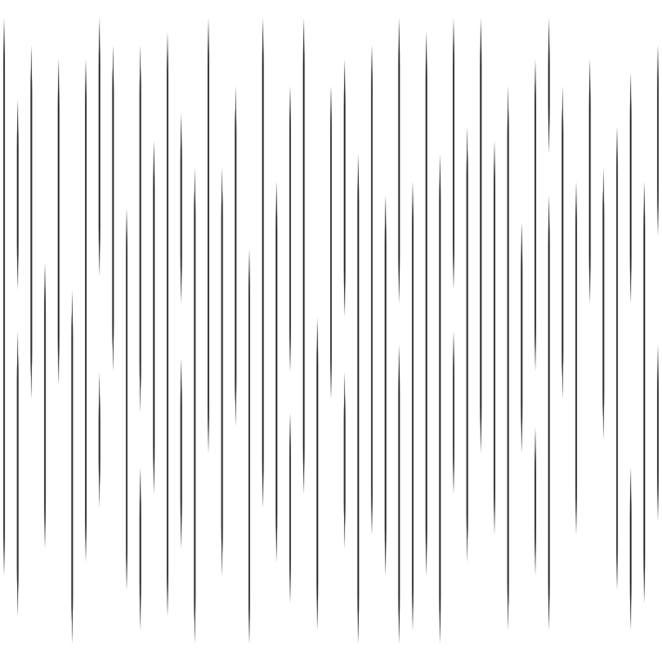
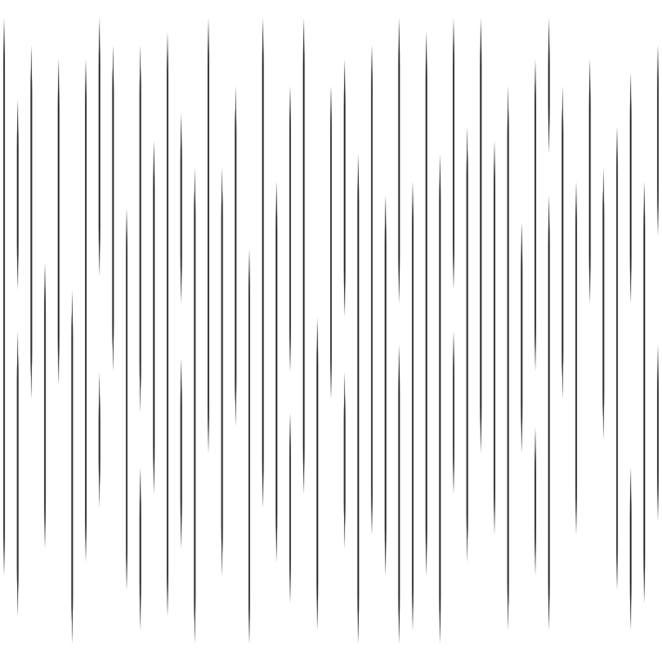
保健室から出されて数週間が過ぎた。
ケンイチは相変わらず誰とも喋らない日々が続いていた。
あれからアライはケンイチに絡んでくることはなかった。
ケンイチにとって穏やかな日々だった。
その日、昼食後の自由時間、窓の外の景色を一人ぼんやりと眺めているケンイチ。
その背後から少女が話しかけてきた。



何みてんの?


ケンイチは窓の外を見つめたまま振り向きもしない。
背中では平静を装っていたが内心は動揺していた。
通っていた小学校では、ケンイチに話しかけてくる子供なんて誰もいなかったからだ。



あんたまじ、口利けんの?


少女は、怒ったようにいうと、おどけてボクシングを真似た格好でケンイチの背中を軽く殴った。
ケンイチは、振り返り少女を見た。



……ヤメロ


不意の問いかけに対する躊躇いは隠し切れず、
ケンイチはやっとで答えた。



なんだ、ちゃんとしゃべれるやん!


少女はけらけらと笑うと



ケンイチっていい名前やね


といった。



今日はあったかくて、気持ちいいね───


少女は、ケンイチの肩越しに眩しそうな目をして窓から見える晴れ渡った空を見ている。
振り返りケンイチも窓の外を見る。何もない田舎の風景、南の方角のこないだまで雪化粧だった山に日が当たり緑が美しく輝いていた。
春が近づいていた。二人はしばらく並んだまま黙って外の景色を見ていた。
少女の名は、アユミといった。

