アイドルなのは、わたしだけじゃない。
グループの仲間も、他のグループの子達も、みんな誰かのアイドルなのだ。
今、リンちゃんの眼の前にいるのは、もちろんアイドルであるわたしなんだけれど。
アイドルなのは、わたしだけじゃない。
グループの仲間も、他のグループの子達も、みんな誰かのアイドルなのだ。
今、リンちゃんの眼の前にいるのは、もちろんアイドルであるわたしなんだけれど。



リンちゃん、あの……お願いが、あるんだけど


わたしは、少しだけ、アイドルとしての意識を薄めて、口を開いた。



お願いですか? はい、言ってください!





わたし達、もう、友達だよね





……そう想っていただけるのなら、嬉しいです


一瞬、ためらったようなリンちゃんの様子に、少し気落ちする。



硬いなぁ。
友達なんだから、もっと、柔らかくていいよ





でもでも……どうすればいいんでしょうか?


丁寧すぎても、こちらが複雑な気分になるのは、難しいなと想う。
そんなリンちゃんの素直な言葉に、わたしは、メンバー達と出会った頃を想い出す。
最初はぎこちなく、距離があったみんな。
動きもそうだし、心理的にも、今一つかみ合わない時期はあった。
合わない心と動きを、でも、あることを知ってから、一つにまとまり始めたのは驚きだった
不思議ではあったけれど、今でもあの日の感触を想い出せる。
それを心に浮かべただけで、今までよりも身近に、みんなを感じることができたことを。
今でも、懐かしい話として、みんなが話題にする。
みんなが、同じことを言っていた。そんな些細なことでね、って笑いながら。



なら、名前で……呼んでもらいたいな


――お互いを名前で呼び合うようになって、上手くいくなんて。
メンバーみんなで、不思議だねって、笑いあった記憶がよみがえる。



お名前……ぜひ!


満面の笑みを私に向けて、リンちゃんは答えてくれた。
ありがたいことに、わたしは、自分の名前をちゃんと覚えていることができた。



わたしの名前、相澤 沙耶っていうの。だから、サヤ、って呼んで欲しいな





サヤ……





サヤ……





サヤ!






ちょ、なんか、恥ずかしいってば


さすがに連呼されると、少し気恥ずかしい。
確信したように自信の笑みを浮かべるリンちゃんは、次いで、わたしの方へと詰め寄って明るい声を上げる。



あのあの、ですね!





ちょ、ちょっと、落ち着いて


嬉しそうなのはいいことなんだけれど、彼女の元気の良さにわたしは少し戸惑ってしまう。
そんなわたしの様子にかまわず、リンちゃんは口を開いた。



わたしのことも、ですね!





はい?





リン、って、同じように呼んで欲しいです!





……!


驚いて言葉を止めてしまったわたしの様子を見てか、リンちゃんが不安そうに見つめてくる。



わがまま、ですか?


わたしはすぐに、笑顔で彼女に言った。



ううん、全然。
リン、ありがとう


彼女の名前を呼んで、述べる感謝の言葉は、自分も嬉しくなる響きがあった。



こちらこそ、ありがとうございます!


お互いに名前で呼び合って、嬉しさを述べる。
ぐっと距離が縮まった気がして、笑顔も自然に浮かんでくる。
救助は来なかったし、暗闇の広さも全く変わらなくて、不安は消えなかったけれど。
わたしとリンは、それからも、たわいない話を続けていた。
その中でわたしは、リンが、あまり自分の話をしないことにだんだん気づき始めていた。



どちらかというと、リンは聞く方が好きなの?





そうですね。
みなさんのお話を聞くのが、リンにとって、とても嬉しいことなのです


わたしは、外見に似合わないことを言うなぁ、と感じてしまった。
見た目からは、わたしより上ということはないと想う。
他人の話を聞くのが好き、っていうことを否定する気はないけれど。



リンは、いつもなにをしていたの?


友達として、外見に似合わないことを言う彼女のことを、もっと知りたいと想ってしまった。
わたしの質問に、リンは視線をそらせる。答えに戸惑っているのが、すぐにわかった。




えっと、ですね……





リンのことも、知りたいの


わたしが念を押すと、リンはまた少しためらったけれど、口を開いて答えてくれた。



歩いています





え?





この暗闇の中を、ずっと、歩いているのです


――わたしは、質問の仕方を間違えたのかな、と想った。想いたかった。



散歩が趣味ってことかな?


周囲を覆うこの暗闇の世界で、リンがなにをしてきたか……それを想像するのも、想い出させるのも、まだ時間が欲しかった。
話したかったのは、いつか、戻れるはずの日常のこと。
だから、わたしと同じ日常を生きてきたと想う彼女に、かつての輝いていた日々を話してもらえればと想ったんだけど。
わたしなりの捉(とら)え方に、リンは頭を左右にふった。



リンは、目覚める前の記憶がないのです





記憶が、ない?


わたしは、ただ聞き返すことしかできなかった。
うまく脳に、リンの言葉の意味が入ってこない。



目覚める前って……この、世界で?





はい、そうです





……この世界が、リンが目覚めてから、見てきたものなの?





はい


わたしは、ずっしりと重いナニカが、胸にかかるのを感じた。
出会ってから、わずかな時間しか経っていない間のことをふりかえり、視線が揺れる。
――どうしてこの子は、そんなことを、微笑みを浮かべながら言えるのだろう。



じゃあ、リンは……この、暗闇の世界しか、知らないの?





ほとんど……そうかも、しれませんね





……そんな……


リンの笑顔を見るのがつらくて、眼をそらしてしまう。



あの、そんなに辛そうな顔を、しないでほしいのです


心配そうにわたしへ声をかけるリンに、わたしはもう一度視線を戻す。



リンには、この世界を歩くのが、普通なので……大丈夫ですよ


穏やかな笑みを浮かべて頷(うなず)くリンに、わたしは――そっと、手を重ねた。





やっぱり暖かいです、サヤの手


優しくわたしの手を握りかえしてくれるリンの手は、さっきと同じように冷たいものだったけれど。



本当に、輝かせてくれる手なんですね





リン……


その言葉は、わたしの心を暖かくしてくれる、優しいものだった。



ありがとうございます、サヤ。
サヤに出会えて……わたしも、嬉しいです





ううん、こっちこそ……ありがとう……


わたしはリンに感謝を言いながら、彼女の手をぎゅっと握った。



それに、サヤだけじゃないのです。
色々な方と出会って、リンは、暖かい言葉や時間を、いただきましたから





そっか、他にもリンのことを……大切にしてくれた人が……


リンの言葉に、わたしは安心する。わたしだけが、この暗闇で出会ったただ一人だったら、と、彼女のことを心配してしまったから。
感じ入ったせいか、いろいろな想い出が、わたしの頭によみがえってくる。
アイドルを目指し始めた日のこと。
養成所の扉をくぐった時のこと。
練習についていけなくて涙を流したこと。
グループのメンバーに選ばれた時のこと。
初のステージが大成功した時のこと。
――いろいろ、いろいろだ。
わたしも、一人では、あの日々を抜けられなかったと想う。
忙しく、苦しいけれど、充実した日々。
そんな記憶の最後に――ふっと、脳裏にある光景が浮かんできた。
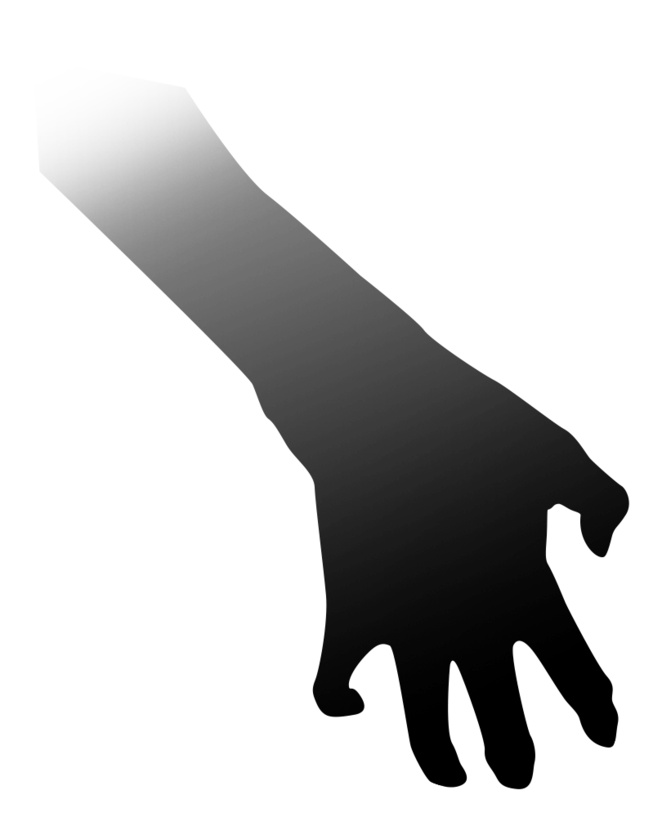



(――!)


――周囲の暗闇がわたしを覆った、あの日のことを想い出してしまう。



大丈夫ですか、サヤ





……え?





とても、怖い顔をされています


知らず、わたしはリンの手を強く握りしめていた。
よっぽど、暗い顔をしていたのだろう。
リンは、心配そうにわたしを見つめていた。
わたしは笑みを必死に作って、安心させようと明るくふるまう。



うん、大丈夫だよ





ですが……





ねえ、リン


わたしは、友達に話すことにした。



わたしが、グループに入っていたのは……言ったよね





はい


あの暗闇の日に、わたしが、どんなステージに立とうとしていたのかを。



みんなと踊って、歌って、ステージを輝かせる……とても、大切で、愛しいことなの


みんなで作る、新しい輝きの舞台。
わたしは、その輝きの一つであることに、支え合っていくことに、日々の喜びを感じていた。



『エターニティー』は、わたしにとって、大切な場所だった


そんな日々を過ごして、忙しいステージツアーが一段落した時だった。



ただ、わたしに……話があって


わたし一人だけが、個室に呼び出されて。
不安な気持ちを隠しながら、マネージャーから聞いた言葉は、予想しないものだった。



ソロでもやってみないか、って話


マネージャーが持ってきたその案件に、頭が真っ白になった。
『エターニティー』のことはもちろんだし、ソロの話がどうして出てくるのか、って、いろいろなことが頭を駆けめぐってしまったから。



グループを抜けるとかじゃなくて、表現の幅を広げるって意味での、お話だったんだけれどね


パニックになった頭が冷静になってくると――わたしは、幼い頃に見た、アイドルの姿を想い出していた。



憧れは、あったんだ。
子供の頃に見たアイドル――憧れの人は、たった一人で、みんなの夢になっていたから


でも、『エターニティー』のことも、気にかかっていた。
時間的な問題もあるし、生半可に両方やるのなら……止めた方がいい。
そう想って、みんなに相談した。



メンバーに相談したら、やってみた方がいいって、背中を押してくれた


みんなの言葉に、わたしも、新しいことに挑戦してみたくなった。
――それ以来、わたしのスケジュールは、分刻み。
レッスンや、グループとの兼ね合い、新曲に作詞に――わたしの時間は、詰めに詰めて大変なことになった。
疲れて意識を失ったり、死んだように眠っちゃったことも、何度もある。
レコーディングに、プロモーションに、会場となる場所でのステージングに。
わたしは、疲れ切った身体を自覚していたけれど。



でも、意識は、ずっとクリアだったんだ


周囲のみんなも応援してくれたし、わたしも、憧れだった人に近づけるようで、嬉しかった。
新たなソロ用の衣装を着て、わたしという個人の歌詞や曲を、ステージの上で輝かせる。
興奮する胸の動機を押さえながら、わたしは、でも喜んでいた。



だから、一生懸命に……ステージに、立とうとしたの


足を踏み出し、開かれるステージに出て、わたしが見た光景は――。



――真っ暗、だった


まるで、わたしを見に来た人達も、支えてくれたメンバーたちも、まるで、全てがなかったかのような、一面の黒。
その黒色は、まるで意志があるかのように、動いていた。
驚いて動けないわたしに、それは、まるで高波のように迫ってきて。
――わたしの意識は、そこで一度、途切れてしまった。
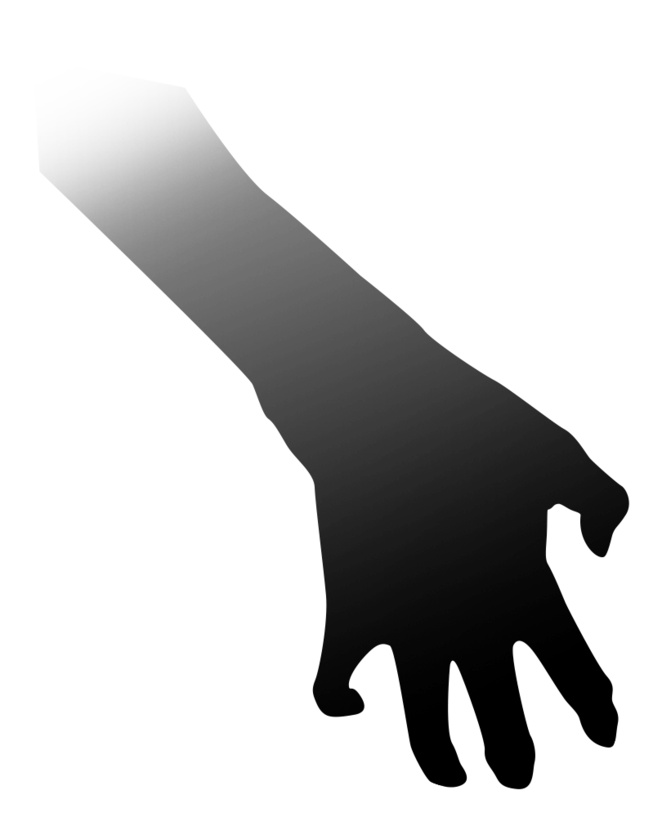



わたし……死んじゃった、のかな?


