――いったい、いつ我が生まれたのか、遠い記憶となりもう残ってはいない。
ただ、我は他の者達よりも知恵と力があり、自然とグループめいた存在の長となっていった。
静かに暮らしたかったのだ。自然と共生し、暴れる者を沈め、革新や変化は最小限に。
――だが、人間と呼ばれる者達は、革新と変化のみを求めるような種族だった。
我らは化け物と蔑(さげす)まれ、人間達に土地を追われ、命からがら逃げ延びた。




魔王を――演じようと想ったのだよ





魔王を……演じる?






人間が、我ら魔族の集団を、排除することを止めようとせぬからだ……


――いったい、いつ我が生まれたのか、遠い記憶となりもう残ってはいない。
ただ、我は他の者達よりも知恵と力があり、自然とグループめいた存在の長となっていった。
静かに暮らしたかったのだ。自然と共生し、暴れる者を沈め、革新や変化は最小限に。
――だが、人間と呼ばれる者達は、革新と変化のみを求めるような種族だった。
我らは化け物と蔑(さげす)まれ、人間達に土地を追われ、命からがら逃げ延びた。
その時、我はためらった。力をふるうことを。話し合いの余地があると信じていた。――だが、それは幻想だった。
何百年と争いをためらい、交渉し、裏切られ、惑わし、逃げ延びて、ようやく見つけた安住の地。
人間は、だが、なおも我らを付け狙う。魔族と魔王という、異名をつけて。
――みな、疲れていた。
何千年も前から共に社会を作り上げてきた幹部達――親友達――も、同じような言葉を言うばかり。
――なんで人間、ワシラを嫌うん……?
そう呟く者のなかには、抗戦派もいた。徹底的に人間と争い、自らの土地と恵みを取り戻すべきだと。
我の抑えもきかず、彼らの一部は人間と戦い散っていった。彼らの力は、我らの予想を上回るスピードで成長していた。
決断できずに逃げる我の元から、去る者も多かった。残ったのが、今の者達。
――戦うことも、逃げることもできない我ら……いや、我が選んだ、一つのこと。




我は、最後に好敵手と戦いたかったのだ……


ならば、と我らは考えた。
それが生まれた理由だとやつらが言うのならば、大規模な戦闘を仕掛け、我らが打ち倒される。
人間のなかに入りこみ、幻術をうまく駆使し、魔族を適度に配置して、勇者の物語を作り上げる。人間の偉大さ、勇敢さ、すばらしさを後世にたたえるための、偉大な歴史の一ページ。
それこそが――人間が我らに望む、理想の姿なのであろう?



……なるほどな。だが、そうして打ち倒されることで、あなたは満足なのか?






……





残された魔族達のことは、本当に考えていないのか?


勇者の言うことはもっともであり――だからこそ、我が倒される必要があったのだ。




魔王が消え、勇者が世界を平和にする――そうすれば、我らという存在が歴史に書き込まれる





ああ……






そうすれば――表向きは、魔族という存在は消える。ひっそりと暮らすことも、しやすくなっていくはずだ


とりまとめがいなくなれば、目立つことも減る。



……そんなにうまくいかないぞ。人間は、甘くない


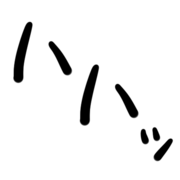




勇者よ、自分の言葉に気をつけた方がいいな


想わずわたしは、苦笑しながらそう注意してしまった。
我の言葉を聞いて、しかし勇者は話を続けず、話題を変えた。



もう一つ、教えてくれ。人間を滅ぼすことも、あなたは可能なのか?





……容易くはないが、可能ではあるかもな


それは、半分本当で、半分はわからない。



ならば、なぜ――殺さない?


勇者の答えは、問いかけだった。
彼はこう言いたいのだろう。滅ぼせるのであれば、なぜ、自らが滅ぶ道を選ぶのかと。その力をふるい、人間を滅ぼし、魔族の世界を作ろうとしないのか。
なぜ、本物の魔王になろうとしないのか――そう、聞くようになってしまったのだろう。




そう、だな……


迷ったが、その答えを与えるのもいいか、と、ふっと想った。
その答えで、彼らがなにを考えるのか――興味がわいたからだ。




……我の一部より生まれた子供達を、殺せるわけがなかろう?





な!?





え?





……!


驚愕に見開かれる、彼らの表情。
やはり、彼らはもう知らないのだ。
人間が神として崇める存在、それとは別に――我が、彼らを造ったのだということを。




はるかな、はるかな昔のことだがな……


かつて、種々多様な生物が我とともにあった時――我は、とある生物の姿を模倣して、人間を造った。その生物には、同じ種族が一人もいなかったからだ。
だが、彼は次第に自己意識を芽生えさせて自立し――そして、彼から生まれた人間達は、自分達が何者なのかを忘れていった。
世界は彼らに埋め尽くされ、満たされていった。
彼ら――人間でないものは、解体され、調べられ、名を変えられ、彼らが理解できない者は排除され、彼らは自分達だけの神を崇めるようになっていった。
我は、その一部始終を見て、その流れに抵抗しながらも――彼らを消すことが、出来なかった。




我についてきた者達には、本当に申し訳なかったが……


ふりかえれば、共に滅びる道を選ぶことが、一番だったのかもしれない。我にも、その程度の力は残されていたからだ。
だが、そう考え始めた時には、もう人間の数と勢力は、我の想像を超えていた。
我が愚かであったのは、人間の能力と増加を、まったく見誤っていたことだった。
我や魔族が扱う道術も、昔に比べればずっと弱くなってしまっていた。おそらく、人間達が精霊達になんらかのシステム化を施したため、力がうまく受け取れないためだろう。
もう、事態を変えることは――我には、できないこととなっていた。我につき従ってくれていた者達も、長い時の間で、自分達の行く末を受け入れ始めていた。




ならば、人間の造りだした物語にそって――我らは、滅びよう


もはやこの世界は、人間によって塗り替えられてしまった。
木々は口をつぐみ、動物達は各々の言葉しか語らなくなり、大地に根付いていた精霊達も姿を現さなくなってきた。
そして、人間達が我らを迫害し排除するというのなら――我らの存在を、なんらかの形で印象づけ、残す方法はないものか。




それが、我らを人間の記憶へと残し――この地を手に入れし人間達への、手向けかと考えたのだ


――魔王という存在を演じることで、我は、もう眠りたかったのだ。
そこまで言って、我は言葉を切った。語るべきことは、語ったからだ。
あとにあるのは……休戦の終わりだけだ。
勇者は、我の言葉を聞いてしばらく無言になった。他の二人も同様、どこか不安げな眼で我を見つめている。
だが、その視線は敵であるものに向ける視線というよりは、どこかすがるようなものであり、我は困惑した。



……すまないが、三人で少し話をしていいか?






かまわん。こうなっては、お前達の考えがまとまらないことには話が進まぬからな


――そう上から目線で言ってみるも、一番おろかなのが誰なのかは、我自身が一番良くわかっていた。
付いてきてくれた魔族に対しても、去っていった者達に対しても、失われた命に対しても――そして、勇者達に対しても。
世界がこうなってしまった原因は、我にある。なら、なにも言わずに討たれれば良かったのだろうに。



(……やはり、我もただの、こわがりなのだ)


覚悟を決めねばならない。我は、自身にそういい聞かせる。
勇者達は、我を討つしかない。
そうしなければ、彼らの旅の理由がなくなってしまうし、なにより人間達が勇者達の負けを許すはずがない。
我が彼らを鍛え上げるようにしたのは、我を倒した後のことを考えてのことだ。裏切られようが、彼らは今の力で生きていけるだろうから。



(だが、それもまた……勝手な小細工か)


想いを巡らせていると、勇者達はうなずきあって、我の方へ視線を戻してきた。
――いよいよ、この時がきた。
